このごろ、テレビ関係の人と会うと、決まって挨拶代わりにこんな会話になる。
「最近、TBSがいいね」
――事実、TBSは昨年から今年にかけて、総じて他局が視聴率を落とす中、唯一上昇傾向にあるのだ。近年、同局はずっと民放4位が定位置だったけど、2015年の年間視聴率では、ゴールデンとプライムタイムでフジテレビを抜いて年間3位に――。
その勢いは今年に入っても衰えない。
4月以降、遂に「全日」視聴率でもフジを上回るようになったのだ。
フジは近年、悪い悪いと言われながらも午前中だけは横並びトップだったんだけど、『めざましテレビ』からカトパンが抜けたあたりから日テレの『ZIP!』の後塵を拝すようになり、テレ朝もここへ来て朝帯の数字が上昇。相対的にフジが低下しつつあるのだ。
そんな中、TBSは『ひるおび!』が相変わらず好調。このままいけば、今年の年間視聴率はTBSが「全日」で3位になり、一方のフジは全日・ゴールデン・プライムの3部門で4位に沈んでしまう。わずか6年前は「三冠王」と言われていたフジが、である。
とかく話題になるTBSの番組
思えば、最近、テレビ界で話題になるのはTBSの番組が多い。
ベッキーの復帰回ということで話題となり、番組史上最高視聴率の24.0%(関東地区)を記録したのは、5月13日の『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』だったし、あの古舘伊知郎サンが3月末の『報道ステーション』の降板から2カ月間の充電期間を経て、復帰の場に選んだのも、6月10日放送のTBSの『ぴったんこカン・カン』だった。なんと同回の視聴率は16.6%(関東地区)と、前4週平均から4ポイント近くのアップ。

ちなみに、TBSはこの2つの番組に、『爆報!THEフライデー』を含めた金曜日のゴールデンタイムが、とにかく鉄板の強さを誇るんですね。
そうそう、火曜日の『マツコの知らない世界』も安定の二桁推移で横並びトップも珍しくないし、木曜日の『プレバト!!』と『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』も、いい時は軽く二桁に乗せる。何より、この2番組は子供たちに大人気だ。
土曜日の『ジョブチューン~アノ職業のヒミツぶっちゃけます!』だって、最近は二桁が板についてきたし、この4月にスタートしたばかりの日曜日の『珍種目No.1は誰だ!?ピラミッド・ダービー』なんて、裏が大河の『真田丸』と日テレの『世界の果てまでイッテQ!』の強力布陣だけど、6月12日放送で番組最高視聴率を更新した。まぁ、演出が過ぎて、先日、出演者に収録の内訳を暴露されていたけど――良くも悪くも、最近のTBSの番組が話題になるのは間違いない。
TBSはドラマも好調
ドラマだってTBSは好調だ。4月クールで平均15%超えを達成したのは、TBSの日曜劇場『99.9-刑事専門弁護士-』のみ。平均17.2%(関東地区)で、2位の日テレ『世界一難しい恋』を4ポイント以上も引き離す圧勝だ。
また、視聴率こそイマイチだったものの、データニュース社が行う「満足度ランキング」で、4月クールの全作品・全話を通じて最も高い満足度を叩き出したのが、『重版出来!』の第9話。「週刊バイブス」の人気作家、高畑一寸がライバル誌の「週刊エンペラー」から引き抜きを受ける話で、「作家が本当に描きたい作品とは何か?」の命題に迫った傑作回だった。脚本は『空飛ぶ広報室』や『掟上今日子の備忘録』の野木亜紀子サン。僕が今、最も信頼する脚本家の一人だ。
金ドラの『私 結婚できないんじゃなくて、しないんです』も、平均視聴率9.0%(関東地区)と、最近の同枠では健闘したほう。何より『夢をかなえるゾウ』の水野敬也サンの原作だけあって、誰に向けて、何を訴えたいのかがすごくハッキリしたドラマだったんですね。他局と比較するのはあまりよくないけど、その辺りが、何を見せたいのか最後まで曖昧だったフジの『早子先生、結婚するって本当ですか?』と違うところ。
――そんな具合で、ここへ来て、なんだか絶好調のTBS。
若い人たちの中には、「あのTBSが善戦してるなんて!」と意外に思う人もいるかもしれないけど、いえいえ、そもそもTBSという局は、かつて「民放の雄」と呼ばれ、テレビ界をリードするスタープレイヤーだったんですね。TBSの活躍なくして、日本のテレビ界の発展はなかったと言われるほど。
えっ、信じられない?
ならば、かつてのTBSがどれだけ凄かったか、少し振り返ってみることにしましょう。
TBSの誕生
日本の民放テレビの第1号と言えば、ご存知、1953年8月に開局した日本テレビだ。
テレビ黎明期の話題と言えば、大抵、新橋の駅前に置かれた街頭テレビに2万人もの群衆が押し寄せ、力道山の試合を観戦した映像が出てくるけど――まさにアレが日テレの武勇伝。
でも、そんな風に黎明期こそ日テレが先導した民放テレビ界だけど、間もなくその主役の座は奪われる。後に“民放の雄”と呼ばれるTBSである。
TBS――当初は『ラジオ東京』と名乗っていて、テレビ放送開始こそ日本テレビに2年遅れたけど、民間放送としては、1951年12月に首都圏初のラジオ局として開局しており、実は日テレの先輩だったんですね。
しかも、そのバックには、広告代理店の電通をはじめ、毎日・朝日・読売の三大紙。読売新聞一社で立ち上げた日テレと比べても、最初から強大な放送局だったんです。
開局に奔走したのは、広告の鬼と呼ばれた電通の4代目社長・吉田秀雄サン。日本テレビを作った読売新聞社社主の正力松太郎サンが“民間テレビの父”と呼ばれるのに対し、吉田サンはいわば“民間放送の父”と言ったところ。そう、日本の民放は電通が作ったのだ。
民放の雄
では、なぜTBSは日テレをあっさりと追い越せたのか?
それは、いわゆる“ネットワーク”の差なんですね。日本テレビは、正式名称を『日本テレビ放送網』と言うけど、当時は系列局なんてものはなく、割り当てられた放送エリアは関東地区に限られるので(これは今もそうだ)、実際は“放送網”でもなんでもなかった。
それに対し、TBS(当時はラジオ東京)がとった戦略は、地方のラジオ局と関係を結ぶこと。当時、全国各地には、愛知の中部日本放送(CBC)をはじめ、大阪の朝日放送や福岡のラジオ九州(現・RKB毎日放送)といったラジオ局が既に開局しており、TBSはまず、それら地方のラジオ局との業務提携を図ったんです。そして――各局がテレビ放送を開始すると、その関係は、そのままテレビの“ネットワーク”へスライドしたってワケ。今でも、TBS系列のネット局にテレビ・ラジオ兼営局が多いのは、そういう理由なんです。
そのアドバンテージは、すぐに広告費に表れたんですね。広告主にとって、全国ネットは大いに魅力。自然、日本テレビより、TBSに出稿する回数が増えていった。
テレビ放送を始めたばかりのTBSが日本テレビを広告予算で追い越し、“民放の雄”と呼ばれるまで、そう時間はかからなかった。
報道のTBSへ
ちなみに、今日では当たり前の民放の全国ニュースネットワークも、最初に構築したのはTBSなんです。時に1959年。『JNN(Japan News Network)』と名付けられたそれは、TBSと各地方局とがニュースを相互に補完する協定。その目的は、全国組織のNHKに対抗するものだった。
というのも、当時、事件現場にはマスメディアの“士農工商”とも言うべき厳しいヒエラルキーが存在していて、取材で優先されるのは通信社、新聞社、NHKの順で、その遥か後方に民放テレビ局がいたってワケ。何せ、民放はキー局と言えどもローカル局に過ぎないからだ。
そこでTBSは、ニュースを相互に補完し合う全国ネットワークを構築することで、全国規模のNHKと対抗しようとした。
かくして「報道のTBS」の異名が生まれる。
今日、事件現場で民放の記者たちは、朝日新聞やNHKの記者たちと同様、最前線でバリバリ取材できる。その陰に、TBSの先人たちの苦労があったことは忘れてはいけないんです。
ドラマのTBS
TBSを語る際に、もう一つ忘れはいけないのが、「ドラマのTBS」の異名である。
先行してテレビ放送を開始した日本テレビは、プロレスやプロ野球などのスポーツ中継で人気を上げ、また、名物プロデューサーの井原高忠サンがアメリカのバラエティ・ショーを模した番組をいち早く取り入れていたことから、バラエティの分野でも日テレが先んじていた。
これに対し、TBSがとった戦略は、赤坂の局舎に東洋一のマンモススタジオを設置し、本格的テレビドラマを作ること。そこで生まれたのがTBS最初の連ドラ『日真名氏飛び出す』である。カメラマン・日真名進介と、助手の泡手大作が事件を解決するミステリードラマで、たちまち人気番組となり、TBSとしては幸先のいいスタートとなった。
そして――「ドラマのTBS」を決定付けた、あの作品が登場する。1958年放送の『私は貝になりたい』である。平凡な理髪店の主人が、戦時中に上官の命令で米兵を殺害した罪を問われ、絞首刑を執行される話。今の若い人たちは、中居正広サンのリメイクで見たことがあるかもしれない。
当時、放映されるや、たちまち社会現象になり、フランキー堺演ずる理髪店主人の「私は貝になりたい」の台詞は流行語になった。ドラマもその年の芸術祭賞を受賞する。
ホームドラマ全盛期
1958年、「東芝日曜劇場」のプロデューサーに石井ふく子サンが就いた。そう、後にドラマ界の一大ブランド「石井ファミリー」を作り上げる、あの御仁だ。
彼女の功績と言えば、平岩弓枝サンをはじめ、橋田壽賀子サンや向田邦子サンといった稀代の女性脚本家たちを育て上げたこと。そして、彼女たちと共に60年代から70年代にかけてテレビ界を席巻する一大ジャンルのドラマを生み出す。
ホームドラマだ。
1960年代半ば、石井サンは『七人の孫』や『ただいま11人』、『女と味噌汁』といった一連のホームドラマで爆発的な人気を博し、一躍ヒットプロデューサーになる。
そして1970年――いよいよ、あの2つの大型ホームドラマが登場する。
『時間ですよ』と『ありがとう』である。
『時間ですよ』は、久世光彦演出・向田邦子脚本のライトコメディの傑作。銭湯を舞台にした遊び心ある久世演出が評判を呼び、最高視聴率36.2%(関東地区)と大ヒット。一方の『ありがとう』は、石井ふく子プロデュース・平岩弓枝脚本の王道路線。主演に当時人気絶頂の歌手・水前寺清子を起用し、第2シリーズでは驚異の最高視聴率56.3%(関東地区)を記録する。この数字は、今も民放連ドラ最高視聴率だ。
テレビ局の財産は人
そうそう、僕は、テレビ局の財産は“人”だと思ってる。
実際、TBSが元気だった時代、かの局には綺羅星のごとく、名物社員たちが数多く在籍した。先の石井ふく子サンをはじめ、演出家の久世光彦サン、山田太一サンや倉本聰サンらが書くドラマを数多くプロデュースした大山勝美サン、『ウルトラセブン』の演出家でも知られる奇才・実相寺昭雄サン、『岸辺のアルバム』や『ふぞろいの林檎たち』の神演出で知られる鴨下信一サン、『JNNニュースコープ』の初代キャスター・田英夫サン、『輝く!日本レコード大賞』や『東京音楽祭』をプロデュースした“ギョロナベ”こと渡辺正文サン、『8時だョ!全員集合!』の居作昌果サン、『ザ・ベストテン』の山田修爾サン――etc.
また、名前は知られていないが、例えば『ザ・ベストテン』で新幹線からの中継を可能にしたり、羽田空港の滑走路からの中継を可能にしたのは、当時の国鉄や運輸省に特別なパイプを持つTBS社員がいたからである。
そう、まさに社員こそがTBSの財産だった。
面白い社員なくして、面白い番組は作れないのである。
TBS全盛期
60年代から70年代にかけて、TBSは19年間にわたり、ゴールデンタイムの視聴率トップの座に君臨する。人気番組と言えば、全てTBSと言っていいくらいの無双状態だった。
例えば――
〇バラエティ/『8時だヨ!全員集合』『ぴったしカン・カン』『ぎんざNOW!』
〇歌番組/『ロッテ 歌のアルバム』『ザ・ベストテン』
〇ドラマ/『ありがとう』『時間ですよ』『Gメン’75』『赤いシリーズ』『3年B組金八先生』
〇報道/『JNNニュースコープ』『報道特集』
〇クイズ/『クイズダービー』『クイズ100人に聞きました』
〇子供番組/『ウルトラシリーズ』『ケンちゃんシリーズ』
〇ドキュメンタリー/『兼高かおる世界の旅』
〇料理番組/『料理天国』
――ほら、すごいラインナップでしょ?
実際、今のテレビマンで、55歳以上(要するに幹部クラスですね)なら、ほぼ例外なく、TBS志望だったと思って間違いない。しかし、彼らはその願い叶わず、仕方なく他局へ行った人たちなのだ。現在、30代~40代のテレビマンが一様にフジテレビ志望だったのと同じ現象である。
ザ・ベストテンの時代
さて、綺羅星のごとく輝いた60年代から70年代のTBSの番組。
中でも――『ザ・ベストテン』ほど光り輝いた番組はないと思う。
司会はご存知、黒柳徹子サンと久米宏サン。この番組が画期的だったのは、それまでテレビ局のプロデューサーと芸能プロダクションの都合で出場歌手が決められていた歌番組の体質を一新。完全なるデータ主義で、生放送でランキングを発表したことに尽きる。

だが、いきなり初回、その試金石がやってくる。
放送前日、ランキングを集計すると、時の大スター山口百恵の『赤い絆』が11位。このままでは出演できない。そこへ、TBSの歌番組の天皇とも言える“ギョロナベ”こと渡辺正文サンが口を出す。
「新番組の初回に山口百恵が出ないとはどういうことだ!」
ランキングの入れ替えを主張するギョロナベさん。しかし、これに担当ディレクターの山田修爾サンは頑なに拒否する。というのも、司会に黒柳徹子サンをキャスティングする際、黒柳サンから固く約束させられていたからだ。
「絶対にランキングは操作しないでくださいね。それが、私が出演する条件です――」
かくして、初回に大スター山口百恵を出さなかった『ザ・ベストテン』。しかし、その英断が番組に“リアリティ”という箔を付け、瞬く間に高視聴率番組へと成長する。ちなみに、最高視聴率は41.9%(関東地区)。この数字、レギュラーの音楽番組で今もって歴代最高だ。
80年代のフジテレビの時代へ
だが、そんな「民放の雄」も、80年代にフジテレビが台頭してくると、次第にその勢いを低下させていく。
1980年、フジは鹿内春雄サンが副社長に就任。外部プロダクションを社内に戻して、“大編成局”を立ち上げた。そして「楽しくなければテレビじゃない」のスローガンのもと、若者をターゲットにバラエティからニュースまで、フジテレビのカラーに刷新する。
82年、フジは開局以来、初めて年間視聴率三冠王に輝き、以後これを12年間にわたり維持する。そう、フジテレビ時代の幕開けだ。
一方、TBSはフジに業界の盟主の座を奪われると、自らのアイデンティティーを失い、迷走を始める。かつての家族をターゲットにした王道の番組作りも、フジの後追いから、慣れない若者向きへとシフト。
87年には、テレ朝の『ニュースステーション』に対抗しようと、伝統の金ドラ枠を廃止してまでニュース番組『JNNニュース22プライムタイム』を始めるが、結果は惨敗。2年で同枠から撤退し、「報道のTBS」の看板まで下ろすことになる。
だが――本当の苦難は90年代に入ってからだった。
秋山さん、宇宙へ
1990年、TBSは創立40周年事業として「宇宙特派員計画」をぶち上げる。ソ連(当時)と協力して、TBSの社員を“宇宙飛行士”に仕立てるという遠大な計画だ。
それに先だって、社内に宇宙飛行士の募集がかけられる。162名の候補者が語学・医学・体力測定などの難関に挑み、記者の秋山豊寛サンとカメラマンの菊地涼子サンが選ばれる。2人はソ連のスターシティで1年間(!)にわたり、宇宙飛行士としての訓練を受け、最終的に秋山サンが飛行メンバーに決まった。
90年12月2日、秋山サンを乗せたソユーズTM-11がカザフスタンの宇宙基地から打ち上げられる。その模様は特番『日本人初!宇宙へ』で中継され、軌道に乗った瞬間、最高視聴率36.2%(関東地区)を記録する。
同計画では、国際宇宙ステーションミールとTBSを結んでの中継も行われ、そこで秋山サンが発した第一声が「これ、本番ですか?」だった。
遂には宇宙にまで進出したTBS。
だが、皮肉にもその“宇宙”が、転落への引き金になる。

ミクロコスモスの黒歴史
1991年9月、TBSは長年親しまれた筆記体のロゴを廃止し、“宇宙”をイメージした「ミクロコスモス」なる新ロゴを発表する。
仕掛け人は、経理畑出身の田中和泉社長だった。彼は、経営面にコンサルタント会社のマッキンゼーを参画させるなど、次々にドラスティックな経営改革を進める。しかし、番組の内容を鑑みず、いたずらに制作費の削減を優先する施策は、現場の士気を低下させた。
さらに、91年10月には、野村證券からの損失補てん問題が発覚。TBSは世間から大いに非難を受け、田中社長は責任をとって辞任する。
だが、TBSの迷走は終わらなかった。後を継いだ磯崎洋三社長は、またも現場を省みないドラスティックな改革を断行する。
92年秋、TBSが誇る数々の人気番組を一斉に打ち切ったのだ。『クイズ100人に聞きました』、『クイズダービー』、『わくわく動物ランド』、『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』、『そこが知りたい』――etc.
さもありなん、相次ぐ人気番組の終了で視聴率は激減。さらに94年には、一向に回復しない視聴率を受け、新ロゴのミクロコスモスもわずか3年で廃止される。
TBSが死んだ日
だが――それでもTBSの斜陽化は終わらない。
96年には、坂本弁護士を取材したテープを放送前にオウム真理教の幹部に見せたことが一家の殺人を誘発したとされる「坂本弁護士オウムビデオ事件」が起きる。加えて、TBSはこの事実を隠ぺい・偽証するという二重の罪を犯す。
TBSが偽証を認めた夜、『NEWS23』で筑紫哲也サンはこう発言した。
「TBSは死んだ」
一連の責任をとり、磯崎社長は辞任する。
宇宙特派員計画で華々しく幕開けたはずの90年代のTBS――。
しかし、その“宇宙”が仇となり、ミクロコスモス時代の黒歴史に端を発する数々の失策で、以後、長くて暗い「失われた20年」に突入したのである。
復活の年、2009年
そして時代は一気に飛んで、2009年10月11日。
この日、TBSの歴史を大きく変える1つのドラマが始まった。日曜劇場の『JIN-仁-』である。
主演は大沢たかお。共演に綾瀬はるか、内野聖陽ほか。このドラマ、現代の医師が幕末にタイムスリップする話だけど、そんな荒唐無稽な設定に反して、その内容は実にリアリティあふれるものだった。結果、平均視聴率は19.0%、最終回は25.3%(いずれも関東地区)と大ヒット。何より、その高いクオリティが評価され、テレビ界の権威であるギャラクシー賞をはじめ、国内外で33もの賞を受賞する――。
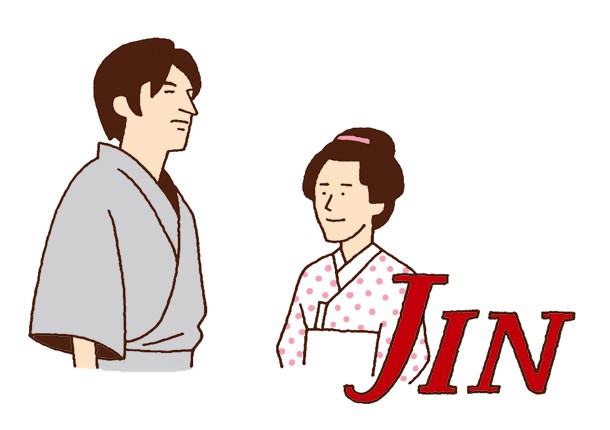
そう、歴史は1日で変わる。
『JIN-仁-』の大ヒットを機に、TBSは久々に「ドラマのTBS」と言われるようになり、以後、日曜劇場は、『新参者』、『JIN-仁-完結編』、『とんび』、『空飛ぶ広報室』、『天皇の料理番』、『下町ロケット』と次々に秀作を発表する。
中でも、2013年に放映された『半沢直樹』は、最終回が42.2%(関東地区)と驚異の視聴率を獲得。社会現象と呼ばれるまでになる。
思うに――同枠の強さの要因は、作り手の切磋琢磨にあるのではないだろうか。
『JIN-仁-』は、プロデューサー・石丸彰彦と演出・平川雄一郎らのチーム。一方、『半沢直樹』はプロデューサー・伊與田英徳と演出・福澤克雄らのチーム。両チームが互いに競い合いながら、良作を作り続けているんですね。
そして最も大事なのは、これらドラマの復活が刺激となって、2010年代に入ると、バラエティも徐々に復活を遂げたってこと。
ここで冒頭の話に繋がる。『JIN-仁-』から始まった同局の潮流の変化が、TBS全体に波及していったのだ。
――「最近、TBSがいいね」と。
「エンタメのTBS」へ
来年――2017年春、東京・豊洲に新しい劇場「IHI STAGE AROUND TOKYO」が開場する。
それは、世界で2番目となる、1300人もの観客を乗せたまま客席が360°回転する円形劇場。周囲をステージとスクリーンが取り囲み、全方位型の劇空間を創出する。
この劇場を作るのが、TBSである。
こけら落とし公演は、劇団☆新感線の『髑髏城の七人』。既に1年3ヶ月のロングラン公演が決まっている。出演は、古田新太率いる劇団メンバーを始め、小栗旬に山本耕史、りょう、青木崇高、清野菜名、近藤芳正といった個性豊かな顔ぶれたち――。
演目自体は、劇団☆新感線の代表作だ。だが、今作は360°のセットとプロジェクター、さらに客席も360°回転することから、全く新しい演出が期待される。これまで見たこともないエンタテインメントが繰り広げられるのだ。
テレビ局のビジネスモデルは基本、広告収入である。この先、テレビ界全体を視聴率の下落が襲い続けると、広告費の削減は避けては通れない。
そうなると、業界全体としても、新たなビジネスモデルの構築が急がれる。その最大の可能性を秘めるのはネットだと思うけど、このTBSが仕掛ける新劇場のように、エンタテインメント産業としてのすそ野を広げる施策もありだ。
そう、大事なのは、テレビの世界で培った“本分”を忘れないこと。
かつての「報道のTBS」、「ドラマのTBS」に続く異名――僕はそれを勝手に「エンタメのTBS」と信じているのだけど、テレビ界の新たなる潮流を作るのは、案外、TBSかもしれない。
例えばそれは――テレビに限らず、街そのものをメディア化する事業だったりする。その試金石が、先の豊洲の360°回転劇場だ。
TBSサン、期待してまっせ。
(文:指南役 イラスト:高田真弓)




