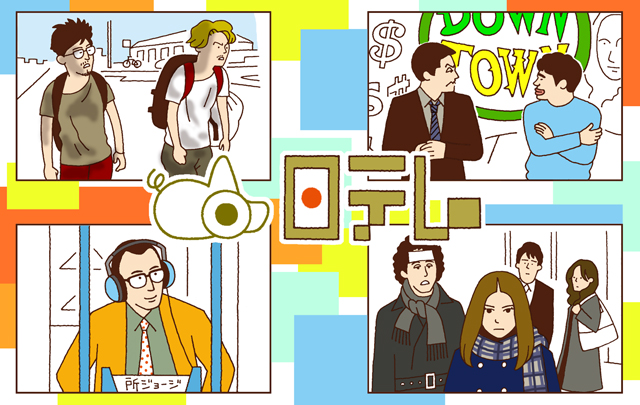刺客は後ろからやってきた。
1970年代、東京キー局は「2強2弱1番外地」と呼ばれ、長らく日テレはTBSに次ぐ2位の座に安住していた。ところが80年代に入り、様相が一変する。競馬でいうところの――突如、後ろから“まくられた”のだ。
フジテレビだった。
1980年5月、「ジュニア」こと鹿内春雄サンが34歳で副社長に就任すると、フジは社外にあった制作部門を戻し、“大制作局”を立ち上げる。フジの社内は自由闊達な空気であふれ、「楽しくなければテレビじゃない」を旗印に、様々な画期的な新番組が生まれた。『THE MANZAI』、『北の国から』、『オレたちひょうきん族』、『笑っていいとも!』、『なるほど!ザ・ワールド』――etc.
1982年には、フジはTBSを抜いて、開局以来初の年間視聴率三冠王となる。その後もフジとTBSとの間で激しいデッドヒートが繰り広げられ、一方、両局の間に埋もれるように日テレは徐々に存在感を落としていった。
名物番組の相次ぐ終焉
1980年代半ば、日テレの名物番組が相次いで終了する。『テレビ三面記事ウィークエンダー』が84年5月をもって9年の歴史に幕を下ろしたのを皮切りに、『久米宏のTVスクランブル』は85年3月、『びっくり日本新記録』は85年10月、『カックラキン大放送!!』は86年3月、『お笑いスター誕生!!』は86年9月、『太陽にほえろ!』は86年11月――と、かつて一世を風靡した番組たちが次々と姿を消した。
要因の1つとして、日テレが合理化のために1971年から75年までの5年間、新卒の採用を控えたことが影響したと言われた。世代交代が進まず、番組の金属疲労を招いたのだ。皮肉にも、フジテレビも同時期に採用を控えたが、その間、外に出した制作プロダクションで新人を採用し、80年の改革で彼らを社内に吸収した。その結果、フジは新陳代謝が進んだのである。
振り向けばテレ朝
気が付けば、日テレは視聴率でフジとTBSに大きく離されていた。両局がゴールデンタイムで平均15~16%で競っているころ、日テレは13%台。巨人戦でなんとか体面を保っているという状況だった。
辛うじて人気番組といえば、『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』とドラマの『あぶない刑事』くらい。ちなみに、『元気~』の総合演出は、制作会社のIVS時代のテリー伊藤さんだった。
もはや日テレは、「振り向けばテレ朝」という状況にあった。そこで、局の上層部は開局35周年にあたり、ある決断をする。
1988年の転換
1980年代後半、日テレは開局以来のどん底期にあった。
かつて井原高忠サンが築いた「ヴァラエティ・ショーの日テレ」の看板はタモリさんがホストを務める『今夜は最高!』に残すくらい。もはやバラエティといえば、アドリブと楽屋オチを得意とするフジテレビの全盛期にあった。『お笑いスター誕生!!』で発掘し、井原サンが名付け親となったとんねるずも、すっかり活躍の場をフジテレビに移していた。
88年、事態を打開するために、日テレの上層部は開局35周年のこの年、「SI35」なるプロジェクトを立ち上げる。SIとはソフト・イノベーションの頭文字のこと。つまり、ソフトの改革である。組織・人事・編成・番組企画――あらゆる面での改革案が打ち出された。
その1つに、30代の若手チームにゴールデンのレギュラー番組を作らせる話があった。そして、あの男が登場する。
登場、五味一男
五味一男――この連載を読んでる方なら、名前くらいは目にしたことがあるだろう。『マジカル頭脳パワー!!』や『投稿!特ホウ王国』、『速報!歌の大辞テン!!』や『エンタの神様』など、日テレの数々のヒット番組を手掛けた稀代のヒットメーカーである。
だが、この時点では、まだ前年の87年にCMディレクターから中途入社した、一介の新人に過ぎない。
「SI35」の試みの1つに、当時「魔の水曜日」といわれた水曜夜8時台を30代の若手4人に委ねるというプロジェクトがあった。縛りは1つ、「新しいクイズ番組を立ち上げよ」――。
クイズ番組の意味
かつて、週刊文春に『テレビ消灯時間』を連載したエッセイストの故・ナンシー関さんがクイズ番組について語った、こんな名言がある。
「このクイズ番組というのは便利だったのだ。番組改編期の特番が各局軒並みクイズ番組形式なのは、新番組の宣伝だろうと自社主催のイベントだろうと、何でもクイズ番組にしてしまえば無理矢理つっこめるからだ。」
――けだし名言である。そう、レギュラーのクイズ番組は、ただ毎週放送されるだけの代物じゃない。春と秋の改編期に、新番組の番宣を兼ねたスペシャル番組のフォーマットとしても活用されるのだ。いわばバラエティ番組の要。
だが、当時の日テレにはレギュラーのクイズ番組がなかった。そこで上層部は「新しいクイズ番組を立ち上げよ」と、30代の4人の若手に企画を委ねたのである。その中の一人が、前年に中途入社したばかりの五味サンだった。
五味サンは他局のクイズ番組を徹底的に研究した。そして生まれたのが――“職業”をテーマにした、あの番組だった。
誕生、SHOW by ショーバイ!!
1988年10月、新タイプのクイズ番組『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』が始まった。司会は、同年3月にフジを退職してフリーになったばかりの逸見政孝サン。レギュラー回答者は山城新伍サンである。
番組は、毎週1つの仕事にスポットライトを当て、それにまつわる国内外のネタをクイズにしたもの。ちなみに、第1回は「世界のタクシードライバー」だった。この時、逸見サンの発した「さぁ~みんなで考えよー!」の掛け声が番組の名物となる。
視聴率は開始当初こそ伸び悩むが、逸見サンと山城サンの掛け合いが番組名物となり、徐々に上昇。途中から、早押しクイズの「何を作っているのでしょうか?」もブレイクし、やがて20%を超えるようになる。
頭の中に1000万人を住まわせる
五味サンは、ヒット番組を生み出すコツを、著書で次のように述べている。
「頭の中に1000万人を住まわせる」――。
どういうことか。実は、普段よく聞こえてくる視聴者の声は少数派なのだ。ジャニーズのファンだったり、女子高生だったり――。彼らはノイジー・マイノリティといって、その意見を聞きすぎると、大局を見誤りかねない。
対して、五味サンが求めるのは“サイレント・マジョリティ”――物言わぬ大衆。彼らのニーズを掴まないと、視聴率は取れないのだ。
そこで、五味サンが重視するのが「毎分視聴率」である。毎分視聴率とは1分毎の視聴率を表した指標で、視聴者がどのコーナーで番組に流入し、どういう展開で番組を離れたかが一目で分かる。五味サンはそれを丹念に分析することで、1000万人の嗜好を嗅ぎ取るという。
そして――五味サンのこの分析が、次に、あの伝説の番組を生み出すことになる。
「マジカル頭脳パワー!!」で30%に
『マジカル頭脳パワー!!』は、1990年10月に始まった。司会は板東英二サン、レギュラー回答者は所ジョージさんに俵孝太郎サン、間寛平サン等々。
それは、知識ではなく、発想力や思考の柔軟性を問う新手のクイズ番組だった。そこで類い稀なる頭の回転の速さで評価されたのが所ジョージさんである。また、彼と板東サンとのやりとりも評判となった。
番組は瞬く間に高視聴率となり、20%台半ばを安定飛行。さらに95年に登場した新コーナー「マジカルバナナ」で社会現象になった。96年5月には最高視聴率31.6%を記録するまでに――。
五味サンの頭の中に、1000万人が宿った瞬間だった。

88年入社組
一旦、話を1988年に戻そう。創立35周年の「SI35」プロジェクトは、人事の面でも大きな成果を生んだ。この年、新入社員で入ったアナウンサーが、福澤朗サンや永井美奈子サンだったのだ。さらに、後にダウンタウンの番組を手掛ける菅賢治サンもこの年、中途入社を果たしている。
最初にブレイクしたのは永井美奈子アナだった。入社1年目にして、いきなり『アメリカ横断ウルトラクイズ』のコンピュータ予想の担当に抜擢され、アイドルアナとしてブレイク。丁度、フジテレビの同期入社が八木亜希子・有賀さつき・河野景子の三人娘で、そのライバルとしても脚光を浴びた。
次に人気を博したのが福澤アナだった。入社翌年の89年、全日本プロレス中継の実況に抜擢され、あの「ジャストミート!」の名文句が生まれる。
そして――同年10月、中途入社の菅賢治サンもまた、名物番組を生み出した。もたらしたのは、あの2人だった。
ガキの使いやあらへんで!
――そう、ダウンタウンだ。言わずと知れたお笑い界の大スター。今、40代以下のお笑い芸人はほぼ全員、ダウンタウンを目指してこの世界に入ったと言っても過言じゃない。
そんな2人は80年代後半、まず大阪でブレイク。88年10月にはフジテレビの深夜番組『夢で逢えたら』、89年4月には同局の『笑っていいとも!』の火曜日レギュラーとして東京進出を果たす。
そして、日テレもその波に乗り遅れまいと、東京における彼らの最初の冠番組をスタートさせる。今日も続く『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』である。
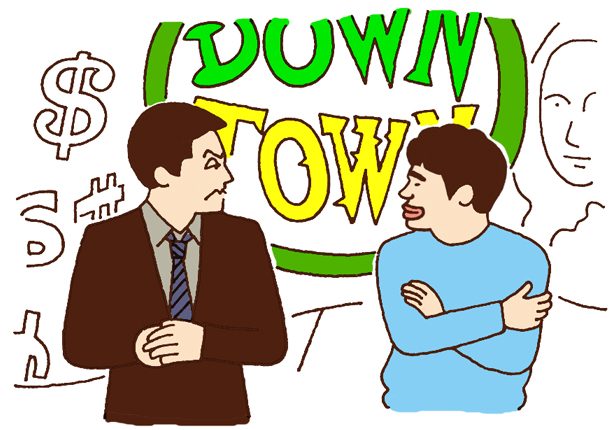
この時、編成担当だったのが、後にTプロデューサーと呼ばれる土屋敏男サンで、番組の総監督が菅賢治サンだった。だが、初回視聴率は0.9%――。
菅サンは動じなかった。彼には確信があったのだ。実際、番組は少しずつ形を変え、やがて後半のフリートークが名物となる。それと共に徐々に数字が上昇、91年10月からは時間帯が深夜からプライムタイムへ上がり、間もなく視聴率20%台の人気番組となった。
24時間テレビの復活
日テレの毎年恒例の特番といえば、言わずと知れた『24時間テレビ』である。
かつてアメリカのチャリティー番組『レイバー・デイ・テレソン』にヒントを得た都築忠彦サンが立案し、上司である井原高忠サンに相談したところ、「色々難しいが、面白そうだからやろう!」という話になった。第1回は1978年に行われ、24時間の平均視聴率15.6%、募金総額11億9000万円――大成功だった。
だが、それから毎年続けるうちに、徐々にマンネリとなり、話題性も減少する。91年には平均視聴率が6.6%にまで落ち込んだ。
そこで、日テレの上層部は番組の打ち切りも検討するが、最後の賭けとして、あの男に全てを託す――五味一男サンである。
92年、五味サンは番組の方向性を“チャリティーをエンタテインメントにする”――と大きく方針転換する。そして、司会にダウンタウンの2人を起用し、キャッチフレーズを「チャリティーやで」とした。今日に繋がる「チャリティーマラソン」やエンディングの『サライ』が生まれたのも、この回だった。
平均視聴率は17.2%。それは、第1回を上回る過去最高値であり、見事に復活を遂げた同番組は、今日まで続く日テレの名物となるのである。
TBSを抜いて2位に
80年代後半、絶不調に陥っていた日テレ。だが、88年に打ち出したプロジェクト「SI35」によって、五味一男サンの『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』や『マジカル頭脳パワー!!』が人気を博したり、88年に中途で入った菅賢治サンによる『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』が若者の心を捉えたり、88年入社の永井美奈子アナが女子アナブームをけん引したり、同じく88年入社の福澤朗アナが「ジャストミート!」で話題となったり――と、一連の番組改革は全て88年を起点に進んだ。
そして90年代に入ると、日テレはプライムタイムでTBSを抜いて視聴率で2位となった。
だが、その上を目指すとなると、当時の日テレはもう一つ要素を欠いていた。それは、全社一丸となれる強力なリーダーシップの存在である。かつてテレビ朝日が教育専門局のNETから脱却した際の三浦甲子二サンや、フジテレビの80年改革の旗振り役となった鹿内春雄サンのような存在である。
そんな折、時代は日テレに味方する。あの男が帰ってきたのである。
復活、氏家齊一郎
時に1991年4月、一つの巨星が墜ちた。読売新聞の「販売の神様」こと、務台光雄会長がその94年の生涯を閉じたのである。
それを機に、読売新聞は“ナベツネ”こと渡邊恒雄サンが社長となり、日テレには、かつて務台サンから追放された氏家齊一郎サンが帰ってきた。ちなみに、渡邊サンと氏家サンは同期の仲である。
氏家齊一郎――。かつて読売新聞の名物記者としてキューバのカストロ議長やベトナムのホー・チ・ミン首相と親交があり、82年には50代の若さで日テレの副社長となる。しかし、務台会長と衝突して失脚。その後、東京大学時代からの朋友・堤清二セゾングループ代表(当時)の元に6年間ほど身を寄せ、復活の機会を窺っていた。
92年6月、日テレの副社長に復帰した氏家サンは、幹部らを前に、こう高らかに宣言する。
「2年以内に視聴率ナンバー1を達成せよ――」
フォーマット大改革
時を同じくして、「CMフォーマットプロジェクト」が始まった。
それは、視聴率を落とさないためのCMの入れ方や番組フォーマットを考察するミッションである。
局内を横断して13名の精鋭たちが集められ、その中に、広告代理店の博報堂から中途入社した、元コピーライターの岩崎達也サンもいた。リーダーは編成部の高田真治サンだった。
だが、その作業は辛辣を極めた。それは、フジテレビと日テレの番組を2週間分、手分けして秒単位で比較・分析するという地味で泥臭いものだったのだ。その辺りの苦闘は、岩崎サンの著書『日本テレビの「1秒戦略」』に詳しい。
そして生まれた秘策が、次のようなものだった。
①「フライングスタート」
定時より5分早くスタートして、他局がCMを流している間に視聴者を呼び込む。
②「提供スポンサーCMずらし」
通常、番組冒頭に入る提供スポンサーのCMを少し後ろにずらし、早く番組の内容に入る。
③「CMまたぎ」
例えば、クイズ番組などでクイズの出題をCM前に行ない、「答えはCMの後で!」と煽ってザッピングを防ぐ。
④「エンドロール早送り」
視聴者はエンドロールが始まるとチャンネルを変えるので、極力短く編集し、ロールも早送りする。
⑤「終了直後に次の番組予告」
番組終了直後に次の番組の予告を15秒間流し、視聴者の流出を繋ぎとめる。
――等々である。これらはほんの一部だが、いずれも今日では当たり前の手法である。そこには、テレビマンでは思いつかない、広告代理店出身の岩崎サンならではの“視点”もあった。
三冠王へ
1993年1月、「CMフォーマットプロジェクト」の報告書が、前年11月に社長となった氏家サンに報告される。そして氏家社長から全社員に「細大漏らさず全てやりきれ」との大号令が下る。
同年4月、フォーマット改革を受けた番組改編が始まった。まさに全社一丸の取組だった。そして狙い通り――多くの番組の視聴率が上昇したのである。この年、遂に日テレは「全日」の部門でフジテレビと並んでトップに立つ。
改革は続く。翌94年4月には19時台の30分の帯番組『追跡』を終了し、1時間枠にする編成の大手術を行う。その結果、プライムタイムでもフジテレビと視聴率のデッドヒートを繰り広げることになる。
両局の戦いは大晦日にまでもつれた。日テレは最終兵器として、NHK『紅白歌合戦』の裏に5時間を超える生放送『ダウンタウンの裏番組をブッ飛ばせ!!』をぶつける。じゃんけんに負けた女性が服を1枚ずつ脱いでいく番組だ。もはや恥も外聞もなかった。ちなみに、プロデューサーは菅賢治サンである。
そして、年が明けた1月2日、視聴率が発表された。日テレはゴールデンとプライムでフジと同率首位となり、既に1位が確定していた全日視聴率と合わせ、開局以来初の「視聴率三冠王」を達成する。
その瞬間、日テレの社内は歓喜に沸いたという。
日テレとジブリの関係
ここで、日テレとジブリの関係についても記しておきたい。
両社の関係は、1985年の『風の谷のナウシカ』のテレビ放映に端を発する。同映画の製作総指揮を務める徳間書店の徳間康快社長(後の初代スタジオジブリ社長)が失脚前の氏家副社長に話を持ってきて、それを二つ返事で氏家サンがテレビ放映権を買ったからである。
当時、ジブリ映画は未知数だったが、徳間社長がかつて読売新聞社に在籍したこともあり、氏家サンとは旧知の間柄だった上に、氏家サンが直感で「これはイケる!」と感じたからである。彼のリーダーとしての資質は、まさにその判断力にあった。
その後、氏家サンが一時失脚しても両社の関係は続き、92年に氏家サンが日テレに戻ると、日テレの開局40周年のロゴマークをジブリの宮崎駿監督と鈴木敏夫プロデューサーに依頼することになった。責任者は前述の岩崎達也サンである。そして生まれたのが――映画『紅の豚』のオープニングに登場するブタのマーク「なんだろう」だった。
電波少年とTプロデューサー
90年代半ば、遂に視聴率でトップに立った日テレ。その原動力はバラエティだった。ここで、五味一男サンや菅賢治サンと並ぶ日テレの“バラエティ三銃士”の最後の一人にも触れないといけない。
Tプロデューサーこと、土屋敏男サンである。2人と違い、新卒で日テレに入ったプロパー社員だ。20代の頃に『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』のディレクターを務め、この時に総合演出のテリー伊藤サンに師事。いわゆる“ドキュメント・バラエティ”の手法を身に付ける。
その後、一時編成に異動になるが、この時に菅賢治サンと共に手掛けたのが『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』である。
そして再び制作に戻り、そこで立ち上げた番組が――『進め!電波少年』だった。
アポなしからヒッチハイクへ
かの番組のスタートは、1992年7月。司会は、松村邦洋サンと松本明子サンである。
当初は2カ月だけの“つなぎ”番組の予定だったが、「アポなし」企画が評判を呼び、たちまち人気番組となる。中でも、「村山富市の長い眉毛を切ってあげたい!」や「アラファト議長とデュエットしたい!」などは伝説となった。
同番組の特徴は、「イラン人AD募集」と称してペルシャ語だけの映像を流すなどのナンセンス性にある。それこそ、土屋サンがかつて学んだ『元気が出るテレビ!!』の手法だった。
だが、番組が真に社会現象化するのは、96年4月に始まった猿岩石の「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」からである。当時、無名の若手芸人だった2人の旅は、単なる無謀な一企画として始まるも、土屋サン自身も予想もしなかった視聴者の感動を呼び、高い視聴率を記録する。
番組はそれを機に、アポなしからリアリティ・ショーへと路線転換。その後も「電波少年的懸賞生活」などのヒット企画を連発し、遂には視聴率30%台を記録する。

『電波少年』の功績は、単に番組としての成功にとどまらない。後のバラエティに大きな影響を与えたこともある。それは、テロップの演出的活用だったり、木村匡也サンのナレーションの遊びだったり、ハイエイトの小型カメラでディレクター兼カメラマンが一人でタレントのロケに随行する撮影手法だったり――。
そして何より、その“ドキュメント・バラエティ”の手法こそ、20世紀後半から21世紀初頭にかけて、世界的ブームとなる“リアリティ・ショー”の先駆けだったのだ。
90年代の日テレドラマ
ここで、90年代の日テレのドラマについても記しておきたい。
1994年から2003年までの10年間、三冠王を謳歌した日テレだが、その主たる要因はバラエティだったことは既に述べた。
一方、ドラマはフジテレビやTBSの後塵を拝していた。当時よく指摘されたのが、同局のキャスティングと企画力の弱さである。
だが、そんな中でも、評判になったドラマは少なからずある。94年の『家なき子』は、野島伸司サンの企画。安達祐実演ずるヒロインすずの台詞「同情するなら金をくれ!」が流行語大賞に選ばれるなど、社会現象になった。最終回の視聴率は37.2%。中島みゆきが歌う主題歌『空と君のあいだに』もミリオンセラーとなり、翌年には続編も作られた。
95年の『星の金貨』も聴覚を失ったヒロインを酒井法子が好演。初回視聴率7.2%から最終回23.9%と驚異の伸びを見せ、こちらも主題歌の『碧いうさぎ』が大ヒット。同じく翌年、続編が作られた。
90年代、氏家社長の強力なリーダーシップのもと、視聴率トップを快走する日テレ。だが、そんな栄華は長くは続かない。引き金は、あのヒットコンテンツだった。
巨人戦の落日と三冠の終わり
2001年はプロ野球にとって、大きな転換点となった。
この年、イチロー選手がMLBのシアトル・マリナーズへ移籍。1年目から首位打者と新人王、そしてMVP受賞と大活躍を見せる。一方、日本では巨人の長嶋茂雄監督がシーズン終了後に勇退。それは、プロ野球からメジャーリーグへ野球の重心が移ったことを人々に印象付けた。
事実、この年の巨人戦の平均視聴率は前年の18.5%から15.1%と急落。過去最低だった。そして、翌年以降も巨人戦は数字を落とし続け、06年には遂に一桁となる。
気が付けば、日テレも視聴率を落としていた。90年代に栄華を誇ったバラエティは金属疲労を起こし、新番組もパッとしないまま、2004年、日テレは三冠王から陥落する。その座を再びフジテレビに譲ったのである。
日テレドラマの考察
ここから先の話はあまり長くない。
ご存じの通り、2000年代半ばに日テレは一時低迷するも、今日では磐石の強さを誇っている。
しかも、90年代よりも強力なのだ。それは、かつての日テレの弱点だった「ドラマ」の克服に起因する。
90年代、日テレでヒットしたドラマは『家なき子』にしろ、『星の金貨』にしろ、その設定や世界観はいわば“変化球”だった。2000年代に入っても、その傾向は変わらず、最高視聴率32.5%を記録した『ごくせん』シリーズも、任侠一家の跡取りである女性教師がヒロインだった。
そこで、同局の櫨山裕子プロデューサーは一計を案じる。
水曜10時は女性たちへの応援歌
どんなにヒットしたドラマも、それは1クールの命である。それを回避するために、テレ朝のようにシリーズ化する手もあるが、日テレの櫨山裕子サンは枠に色をつけようと考えた。
それは、同局の水曜10時のドラマ枠を、女性を主人公に、女性をターゲットに、女性への応援歌的な位置づけにする――というもの。一般に、ドラマの主要視聴者は20代から40代の女性である。彼女たちが枠に定着すれば、作品が変わっても、継続して見てもらえる。
そうして2005年、篠原涼子主演で『anego(アネゴ)』が作られた。仕事や結婚に悩みを抱えながらも、ナチュラルに生きる30代のOLを好演。世の女性たちの共感を誘い、スマッシュヒットする。その路線は07年の『ハケンの品格』へと受け継がれ、同じく篠原涼子がマイペースだが有能な派遣社員のヒロインを演じ、最終回の視聴率は26.0%――。
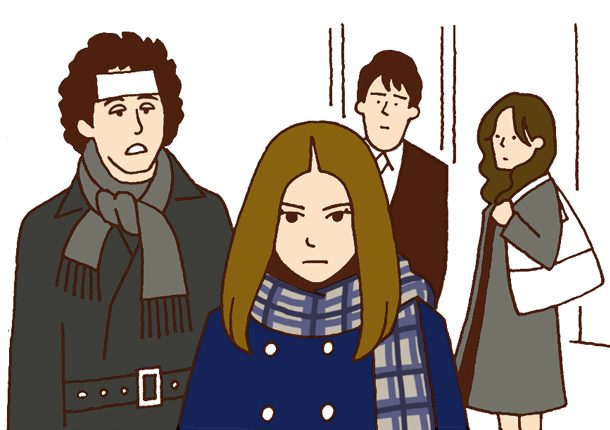
以後、同枠は『ホタルノヒカリ』や『アイシテル〜海容〜』、『Mother』、『家政婦のミタ』、『Woman』、『花咲舞が黙ってない』など、女性視聴者をターゲットに次々とヒット作を連発する。気が付けば、「水10」枠に女性視聴者が定着していたのである。
バラエティの復活、そして三冠復活へ
一方、バラエティも2000年代の半ば以降、徐々に復活の兆しを見せる。
特に顕著なのが日曜日だった。『ザ!鉄腕!DASH!!』は、「DASH村」のコーナーが起爆剤となり、アイドルなのに真剣に農業に打ち込むTOKIOの姿が世間の共感を得て、高視聴率番組へ――。
また、07年スタートの『世界の果てまでイッテQ!』も、イモトアヤコの「イッテQ登山部」や、宮川大輔の「世界で一番盛り上がるのは何祭り?」などの“ドキュメント”路線が人気を博し、番組10年目の今も視聴率20%台は珍しくない。
2011年、日テレはドラマとバラエティの両輪が機能し、8年ぶりにフジテレビから三冠を奪取した。そして14年からは3年連続三冠王を続け、17年の今年も死角は見えない。
日テレのDNA
元をただせば、『DASH!!』も『イッテQ!』も、そのドキュメントスタイルは、1977年スタートの同局の『アメリカ横断ウルトラクイズ』に端を発するものだ。それは85年スタートの『元気が出るテレビ!!』にも通じる、日テレのオリジナルのスタイルである。
思えば、井原高忠サンは渡辺プロダクションとの“仲違い事件”を起こした際、こんなことを言っていた。
「出演者とテレビ局の関係は、こっちが『出ていただいている』って言うと、向こうが『出していただいている』っていうのが理想。そのバランスが悪いのが一番よくない。お互い様なんだから。『出てやる』のだったらそれは変だし、昔みたいに『出してやる』って言うのも変だ。ぼくはどっちも同じだと思う」
――実際、井原サンはこの後、既存のスターへのアンチテーゼとも取れる『スター誕生!』で、自分の番組からスターを生み出すことに成功する。その思想は、素人がクイズ王となる『ウルトラクイズ』へと受け継がれ、『元気が出るテレビ!!』や『電波少年』を経て、今は『イッテQ!』がイモトアヤコというスターを生み出している。
そう、無名の新人(素人)を番組の中でドキュメントに掘り下げ、新たなスターにする。井原サンの時代から続くそのスタイルこそ、日テレのDNAなのだ。
その伝統が息づく限り、日テレの時代は当分、続きそうである。
(文:指南役 イラスト:高田真弓)