始めに断っておくけど、今回、新しい話は出てこない。
激変するテレビ業界とか、ネット配信事業とか、SNSとの連動とか――そんな今っぽい話題は一切登場しない。
今回の話は、昨今、何かと話題のフジテレビである。そう、ここ数年、とんと良い話を聞かない、あのフジテレビだ。2010年の三冠王を最後に、同局の視聴率は右肩下がり。今じゃTBSにも抜かれ、キー局4位である。
かつてテレビドラマのカルチャーを牽引した「月9」は視聴率も内容もパッとしないし、長らくバラエティの一丁目一番地だった『めちゃイケ』もすっかり影が薄くなってしまった。
なんだか、フジテレビのあるお台場の街までパッとしない印象だ。皆さん、最近、お台場に行かれました?
テレビ局に歴史あり
さて、今回はそんなフジテレビの物語。フジの歴史の話だ。
人に歴史あり――じゃないけど、テレビ局にも歴史あり。フジテレビがあれこれ言われる今だからこそ、ここらで一度、その歴史を振り返ってみましょうという趣旨である。
皆さん、フジと聞いて、どんなイメージを抱きます?
恐らく――「楽しくなければテレビじゃない」に代表されるイケイケドンドンな社風じゃないでしょうか。でも、アレは80年代以降の話なんですね。それ以前のフジは、『ママとあそぼう!ピンポンパン』や『ひらけ!ポンキッキ』、『世界名作劇場』などの子供向け番組を持つ、「母と子のフジテレビ」と呼ばれる局だった。
70年代以前、テレビ界は長らく「2強2弱1番外地」と呼ばれる時代が続いたんですね。その中でフジは、NET(現・テレビ朝日)と並び、万年3位が定位置の比較的マイナーな局だった。80年代以降の躍進しか知らない世代からすると、ちょっと意外かもしれない。でも、温故知新じゃないけど、過去を振り返ることで未来への指針が見えることもある。
今回は、その前編。まずは「母と子のフジテレビ」の物語である。
フジテレビの誕生
フジの開局は、1959年3月1日。昭和でいえば34年。そう、テレビが普及するキッカケになった、あの皇太子(現・天皇陛下)ご成婚の年だ。皇居から東宮仮御所までパレードが行われる40日前に、新宿区の河田町で産声を上げたのである。
民放キー局としては、日本テレビ、TBS、NET(現・テレビ朝日)に次ぐ4番目の開局。とはいえ、NETとはわずか1カ月しか違わず、しかもNETは開局当初、教育専門局(放送の50%は教育番組でなければならない)だったので、フジは実質的には第3のキー局という位置づけだった。
当初は富士テレビジョンと漢字表記だったが、「富」の文字が当時のテレビの解像度では映りが悪く、間もなく簡素な「フジテレビ」となった。
主な出資元は、ラジオ局のニッポン放送と文化放送である。元々、別々にテレビ免許を申請していたんだけど、郵政省の行政指導で一本化したってワケ。ちなみに、時の郵政大臣は、戦後最年少の39歳で大臣になった田中角栄である。
角栄の大量免許交付
そう、田中角栄――。
彼が郵政大臣に就任した当初、民放テレビ局は全国に5局しかなかった。それを彼は、わずか3カ月で39局まで増やすという離れ業をやってのける。世に言う「角栄の大量免許交付」である。
田中が並の政治家と違ったのは、100を超えるテレビ局の申請に対して、なるべく、その希望に応えようとしたこと。自ら県ごとに複数の申請者を一本化する超めんどくさい調整を行い、例えば、A社から社長を出したら、B社からは専務を、そして各社の持ち株比率はこう――といった具合に。
その甲斐あって、彼は申請者をただの一社も見捨てることなく、全てにテレビ免許を交付した。
この気配りが、後に自民党・田中派のテレビ局支配に繋がる。
母と子のフジテレビ
さて、そんなこんなで船出したフジテレビ。2つのラジオ局がベースになったので、社員は全員、両局からの出向者と移籍組だった。ラジオとテレビの違いこそあれ、“放送”という点では皆、開局時から経験者だった。
とはいえ、日テレから遅れること6年、TBSから遅れること4年のハンディキャップは大きい。既にTBSは「ドラマのTBS」の地位を確立しており、日テレもプロレス中継やプロ野球中継で固定客を掴んでいた。そこへ新参者が割り込むのは容易ではない。
フジは考えた。先行する2局とは違う、何か編成に独自色を出そうと。そして冒頭でも述べた、あの有名なキャッチフレーズが生まれる。
――「母と子のフジテレビ」である。
発案者は、当時の編成部長で、後に関西テレビの社長となる村上七郎サン。ここで特筆すべきは、「ドラマのTBS」や「プロレス中継の日テレ」が、あくまで局側の視点(要するに川上の発想)だったのに対して、フジは視聴者目線(川下の発想)に立ったこと。まだマーケティングという用語が一般化する前の時代の話である。
フジは、開局当初から視聴者に近づこうとしていたのだ。
日本初の昼ドラ
その編成方針は、翌年、意外な形で早くも成果を見せる。
1960年7月。日本初の昼ドラ『日日の背信』の大ヒットである。
本来、「母と子のフジテレビ」の方針は、親子で楽しめる健全な番組編成を意味していた。例えば、日本フィルハーモニー交響楽団のコンサートを流したり、海外の文化や風習を紹介する良質なドキュメンタリーを放送したり――。だが、その種のマジメな番組はともすれば視聴率がとれず、苦戦を強いられがちだ。
その時、一人の男が新番組の企画を提出する。当時、不毛地帯といわれた昼の時間帯に、主婦向けのメロドラマを流すという。亭主も子供もいない昼間に、禁断のラブシーンを放映したいという。
彼の名は岡田太郎。女優・吉永小百合と結婚する13年前の話である。

昼ドラ「日日の背信」は、丹羽文雄の小説が原作である。お妾さんが他人の亭主と禁断の愛欲を重ねる話で、当時、カムバックを果たしたばかりの池内淳子サンは「よろめき女優」と呼ばれ、一躍時の人になった。
また、当の岡田太郎サンも本作で演出を担当し、そのアップを多用するカメラワークが評判を呼び、「アップの太郎」の異名を取る。
この大ヒットを機に、フジの昼ドラは定番となり、2016年3月に昼ドラ枠が廃止されるまで、長らく主婦たちに親しまれたのは承知の通りである。
五社協定から生まれた2つの副産物
そうそう、テレビ草創期の話題で避けては通れないのが、「五社協定」である。
それは、1956年に松竹・東宝・新東宝・東映・大映の5社からなる日本映画連合会が、テレビへの映画作品の提供打ち切りと、専属俳優の出演を制限した申し合わせだ。翌年、これに日活も加わった。
要は、映画会社はテレビ局に一切協力しないという通告。作品も貸さないし、スターも出演しない。当時、スターといえば、ほぼ“銀幕のスター”を意味していたので、今でいえば、人気の芸能人が一切テレビに出ないことを意味する。これは大変だ。まだフジテレビが開局する前の話である。
その打開策として、TBSや日テレは、外国(主にアメリカ)ドラマを輸入する措置をとる。当時、日本のドラマ制作能力は未熟だったから、これはこれで功を奏した。日テレが輸入した『ヒッチコック劇場』はヒッチコック自ら案内役を務めるスタイルが人気を呼んだし、TBSが輸入した医療ドラマの『ベン・ケーシー』も、最高視聴率50.6%を獲得する社会現象になった。五社協定の思わぬ副産物だった。
もう1つの副産物は、舞台俳優の活躍である。映画俳優がドラマに出てくれないのなら、役者を演劇界から連れてくるしかない。
これが想定以上の評判を生んだ。というのも、草創期のドラマはVTRが高価なため、多くが生放送だった。舞台で鍛えられた彼らの芝居に大いに助けられたのだ。むしろ、1カットずつ撮影する映画俳優では務まりにくい世界だった。
かくして、文学座・俳優座・民藝の御三家をはじめ、新劇や新派から多くの無名俳優がテレビドラマの担い手になり、テレビ時代の新たなスターになった。
『スター千一夜』というウルトラC
外国ドラマ人気と舞台俳優の活躍――「五社協定」に対抗してTBSや日テレが編み出した路線は、開局したばかりのフジテレビも踏襲した。だが、フジは“銀幕のスター”の出演も諦めなかった。
そこで生まれた番組が、映画俳優たちをトーク番組のゲストに呼ぶ『スター千一夜』である。番組開始は1959年3月1日。そう、フジの開局の目玉番組だったのだ。
そのカラクリはこうだ。確かに五社協定は、映画俳優がテレビドラマへ出演するのを禁じている。だが、役を演じない素のままの俳優なら、この協定に抵触しない。要は、時事ネタを扱うトーク番組へ出演してもらうのだ。まさにウルトラC。今でいう、テレビのバラエティ番組に出ない大物俳優を、映画やドラマの番宣の名目で引っ張り出すニュアンスに近い。
かくして、開局の日に出演した長門裕之・津川雅彦兄弟を皮切りに、以後、勝新太郎、市川雷蔵、長谷川一夫、山本富士子、三船敏郎、京マチ子、岩下志麻、吉永小百合、石原裕次郎、高倉健――と、そうそうたる銀幕のスターたちが同番組に出演、最盛期には20~30%の高視聴率を獲得する。
そして1981年まで22年間も続く、大長寿番組となるのである。
『三匹の侍』の発明
そうそう、“五社”協定で思い出したけど、草創期のフジテレビには、五社英雄という一風変わった名前の名物演出家がいた。そう、後に独立して映画『鬼龍院花子の生涯』や『極道の妻たち』を監督する、あの五社英雄サンだ。
彼のフジテレビ時代の代表作といえば、自ら企画した時代劇『三匹の侍』である。主演は、丹波哲郎。新東宝時代は芽が出ず、その後フリーになったところに五社監督から声がかかった。“三匹”の残り2人は、俳優座の平幹二朗と浅草・ロック座の長門勇である。どちらも当時は無名だったが、このドラマで人気俳優になった。
実は当初、同ドラマは「五匹の紳士たち」なる探偵ドラマの企画だった。だが、五社監督が企画書を入社2年目の編成マン・白川文造サンに見せたところ、白川サンから「私立探偵が銃を放つのはダメです」とNGが出る。
しかし、この白川サン、なかなかのアイデアマンだった。どうしても「殺しをやりたい」と訴える五社監督に対して、「ならば時代劇はどうです?」と逆提案する。かくして『三匹の侍』が生まれたのである。
同ドラマの功績は、何といってもその“効果音”だ。今では当たり前の殺陣シーンで刀が当たる金属音やビュンとうなる刀の音、人を斬る時の「ブズーッ」といった擬音は、全て『三匹の侍』で五社監督が発明したもの。彼はニッポン放送の出身だったので、効果音には長けていたのだ。
日本のアニメの扉を開いた『鉄腕アトム』
実は、草創期のフジの話を語る際に、しばしば黒子のように登場する名前が、前述の編成の白川文造サンである。
彼は、あの国民的アニメの誕生にも一役買っている。日本初の本格的連続アニメ『鉄腕アトム』がそう。
時に1962年9月下旬。手塚治虫サン率いる虫プロダクションが制作した『鉄腕アトム』のパイロットフィルムの試写会が、内々で行われた。テレビ局へ売り込むために作られたサンプルである。
その日、かつて手塚サンとアニメ映画『西遊記』を作った東映動画の白川大作サンが、弟を連れて虫プロを訪れた。弟は名を文造といった。そう、フジテレビの白川サンである。
白川文造サンは15分のフィルムを見て、そのクオリティの高さに驚愕したという。そして「1日、時間をください」と言い残し、翌日にはフジの社内を説得して回り、その足でスポンサーの明治製菓の了解も取り付けたのだ。
かくして、『鉄腕アトム』のフジテレビでの放送が決まった。第1回放送は1963年1月1日。初回視聴率は29.5%と大成功だった。
その後も人気はうなぎのぼり。春先には40%の大台に乗る。そして1クールの予定が都合4年間、全210回も放送されたのだ。
かの作品が日本のテレビアニメの扉を開けたのは、承知の通りである。
異色ホームドラマ『若者たち』
いや、白川文造サンの活躍はまだまだ続く。
時に1965年。当時のテレビドラマ界は、圧倒的に「ドラマのTBS」の時代だった。以前にこのコラムでも紹介したが、その中心にいたのは同局の石井ふく子プロデューサーが牽引するホームドラマである。
その余波はフジテレビにも波及した。月曜8時のドラマ枠(今風に言えば「月8」)で、一社提供のYKKから「ホームドラマにしてほしい」という要望が寄せられたのだ。それまで同枠は青春ドラマやコメディが放映されていたが、視聴率も低迷し、スポンサーの評判もあまりよくなかった。
そこで、新ドラマの企画に、フジの賞取り男として知られていた森川時久サンに白羽の矢が立った。彼はある日、毎日新聞紙上で「大阪で両親を亡くした5人兄弟が仲良く助け合って、健気に生活している」という記事を目にする。
「いいオヤジといいオフクロがいて、子供たちと晩飯を食って、お説教をして万事メデタシメデタシという家庭なんて日本にあるかい」
常々、通り一遍のホームドラマに批判的だった森川サンは、これぞ自分の求めるリアリティだと確信し、記事の切り抜きを編成の白川文造サンに見せる。半ば、NGを出されることを覚悟しての提案だった。だが、白川サンの答えは意外なものだった。
「私の学生時代がこれとそっくりでした。立派なホームドラマです」
なんと、白川サンは学生時代に両親を亡くし、6人兄妹のうち受験生の次女を親戚宅に預け、残る5人で共同生活をしていたという。まさに記事の内容と同じである。その話に森川サンが目を輝かせる。
かくして、5人兄妹の青春ホームドラマ『若者たち』が誕生した。

放送開始は1966年2月7日。前ドラマが打ち切りとなったため、変則的な時期のスタートとなった。
ドラマは建設現場で働く長男を筆頭に、トラック運転手の次男、大学生の三男、一家の母親代わりで事務員の長女、それに受験生の四男からなる5人兄妹が、ひとつ屋根の下で助け合いながら、時に悩み、時にぶつかり、ひたむきに生きる姿を描いた物語である。
そう、後に野島伸司サンが書いて大ヒットする『ひとつ屋根の下』の元ネタだ。
主題歌がドラマ人気をけん引
リアリティを重視する森川サンの姿勢は、配役にも表れた。名の知れた俳優は田中邦衛サンだけ。あとは、橋本功サンや山本圭サンなど、当時は無名の俳優座の役者ばかりを起用した。ドラマを俳優の顔で見せるのではなく、彼らの等身大の演技に期待したのである。
開始当初、同ドラマは「暗い」「怒鳴りあいが多い」などと言われ、視聴率も5~6%台と低迷する。しかし、回を追うごとにそんな逆風は和らぐ。けん引役は主題歌だった。今もテレビドラマ史に残る名主題歌『若者たち -空にまた陽が昇るとき」である。
主題歌のヒットと共に、視聴者がドラマの内容にも共感するようになったのだ。「暗い」は「真面目」に、「怒鳴りあい」は「ディスカッション・ドラマ」へと評価を変え、気がつけば最高視聴率18%の人気ドラマとなっていた。
ドラマから映画へ
その後、同ドラマはギャラクシー賞を受賞するなど高い評価を得て、33回をもって9月末に終了した。
だが――同ドラマはここから意外な展開を見せる。終了を惜しむ投書がフジテレビに殺到したのだ。その数、10万通。反響の大きさに、独立系の新星映画社からフジに『若者たち』の映画化の話が持ち掛けられる。
今でこそ、フジは映画製作を手掛け、『踊る大捜査線THE MOVIE』シリーズをはじめとする数々のヒット作があるが、当時は「五社協定」の壁の前に、テレビ局が映画を製作するのはタブーであった。
そこで、同ドラマを影で支えた俳優座がこの企画を肩代わりする。だが、映画の配給も五社協定に阻まれ、仕方なく自主上映の形をとることに。大博打だった。しかし――1967年12月、映画『若者たち』が封切られると、150万人もの観客を動員。映画は大ヒットしたのである。
時に日本映画は斜陽にあり、映画とテレビの主役交代を予感させる象徴的な出来事となった。
ドラマ『男はつらいよ』の誕生
そして、この『若者たち』の映画の成功が、あの国民的映画を生むことにも繋がる――『男はつらいよ』である。同映画が、フジテレビのドラマが発端であることはあまり知られていない。
時に1968年夏。東京・赤坂にある旅館・近源には、売り出し中の喜劇俳優・渥美清とフジテレビの小林俊一プロデューサー、そして松竹の山田洋次監督らが集っていた。新ドラマの企画の打ち合わせである。
その日、渥美は生まれ育った浅草や上野で覚えたテキヤの口上を、立て板に水の名調子で延々3時間も披露した。その様子を笑い転げながら見ていた山田監督は、「下町のとらやの店を舞台に、おいちゃん・おばちゃんの夫婦に腹違いの妹がおり、寅さんがヘマをやっては妹の結婚を邪魔する」というドラマのシノプシスを着想する。
なぜ寅さんを殺したのか
かくして68年10月、ドラマ『男はつらいよ』が始まった。脚本は山田洋二監督、演出とプロデューサーを小林俊一サンが兼任した。枠は現在の「木曜劇場」――“木10”枠である。ホームドラマ全盛期に、家(ホーム)を捨てる寅さんの自由な生き方は視聴者の目に新鮮に映り、視聴率も上々だった。
ドラマは2クール放映され、最終回で寅さんは奄美大島でハブに咬まれ、あえない最期を遂げる。ところが――この後が大変だった。放送が終わるや否や、フジに「なぜ寅さんを殺したのか」と、苦情の電話が殺到したのである。
その話を小林俊一プロデューサーから聞かされた山田洋二監督は、寅さんを勝手に殺してしまったお詫びの気持ちから映画化を思いつく。そして早速、松竹に企画を提出する。当初、テレビドラマの映画化に松竹の上層部は難色を示すが、山田監督の強い思いもあり、同年8月、映画『男はつらいよ』が封切られる。
そう、後にシリーズ全48回を数える国民的映画は、フジテレビのドラマが発端だったのである。
『いいとも』の元ネタになった番組
ここで、フジのバラエティにも目を向けたいと思う。
近年のフジテレビを象徴するバラエティといえば、長らく『笑っていいとも!』がその顔だったと思う。
だが、あの月~金の帯でお昼休みの1時間に公開生放送のバラエティを流すフォーマットは、『いいとも!』が始まる14年前に、既に存在したのである。『お昼のゴールデンショー』がそう。
時に1968年4月。場所は有楽町の「東京ヴィデオ・ホール」。司会は放送作家出身のマエタケこと前田武彦サン。アシスタントは、同番組がテレビ初出演となるコント55号(萩本欽一・坂上二郎)だった。
同番組には日替わりで人気のお笑い芸人や流行歌手らが出演して、フルバンドをバックに歌やコントを披露した。そのフォーマットは、まさに『笑っていいとも!』の先駆けだった。たちまち人気を博し、主婦向けのワイドショーが定番だった昼の時間帯に、一大旋風を巻き起こす。そして、新人のコント55号を一躍人気者に仕立てたのである。
フリートークの天才、前田武彦
それら一連のヒット街道の最大の功労者こそ、時に毒舌を交えつつ、軽妙洒脱に生放送を回した、当代きってのフリートークの天才、前田武彦サンだった。
まさにマエタケさんのアドリブ力と、フジテレビの持つ自由な空気がマッチしたのである。
面白い話がある。翌69年、マエタケさんは日テレの『巨泉×前武ゲバゲバ90分!』に大橋巨泉サンと並び、メイン司会者として起用される。2人は洪水のように流れるショートコントの合間に登場し、生放送でトークしつつ、番組を交通整理するのが役割だった。
その記念すべき第1回の放送でのこと。2人のトークにはあらかじめ台本があり、セリフでは最後に巨泉サンのひと言でマエタケさんがギャフンとなる形だった。だが、これにマエタケさんはアドリブで切り返す。
スタジオに笑いが起きた。だが、次の瞬間、副調整室のスピーカーからプロデューサーの井原高忠サンの怒鳴り声が飛ぶ。
「勝手な真似はやめろ! ここはフジテレビじゃない!」
――日テレのバラエティは、アメリカ仕込みのショーがベースにある。そこには台本があり、出演者はあたかも自分の言葉のように喋るテクニックが求められる。井原プロデューサーが求めたのはそういうことだった。
当時から日テレとフジの社風の違いが、このエピソードからも読み取れる。
社会現象となった『夜ヒット』
さて、そのマエタケさん。68年の11月からは、同じくフジで音楽番組の司会を務めることになった。――『夜のヒットスタジオ』である。
芳村真理サンとの名コンビは評判を呼び、マエタケさんの歯に衣着せぬ毒舌や、出演歌手に即興であだ名をつけるアドリブが評判を呼び、瞬く間に人気番組となる。ちなみに、菅原洋一サンのあだ名は「三日前のハンバーグ」、都はるみサンが「海坊主」、布施明サンが「ピノキオ」だった。
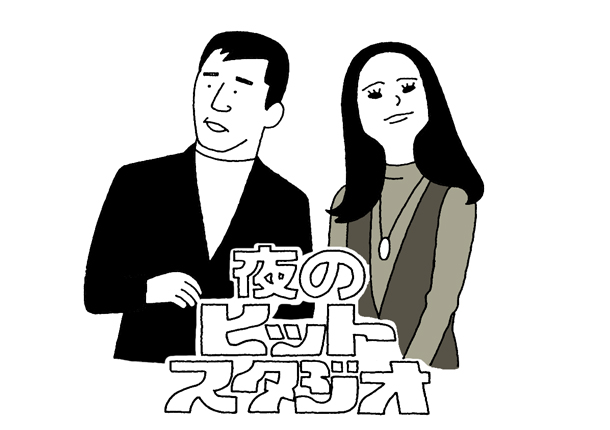
中でも、同番組の一番の人気コーナーが、コンピューターによる「恋人選び」だった。中村晃子サンの回では意中のマエタケさんの名前が出て彼女が号泣したり、いしだあゆみサンの回も同じく意中の森進一サンの名前が出て、こちらも「ブルー・ライト・ヨコハマ」を歌い出すと共に号泣。森進一サンが彼女の横に寄り添い、ハンカチで涙を拭いてあげるシーンが印象的だった。
いつしか同番組は「泣きの夜ヒット」と呼ばれるようになった。
極め付きは小川知子サンが出演した回。その月、彼女は当時恋人だったレーサーの福澤幸雄を事故で亡くし、歌い出すタイミングで、以前、番組で2人が電話で会話した録音テープがマエタケさんから手渡された。イントロが流れた時点で、既に彼女は大号泣。助け舟で親友の中村晃子サンといしだあゆみサンが前に出て歌おうとするが、こちらも貰い泣き。やがて涙の連鎖は出演者全員に伝播した。
『夜ヒット』は社会現象になった。そして69年3月には最高視聴率42.2%を記録する。この記録は今もってレギュラー歌番組の最高視聴率である。
制作プロダクションの設立
1960年代後半、『若者たち』の映画化や、社会現象となった『夜ヒット』で存在感を増しつつあったフジテレビ。だが、そこに暗雲が立ち込めようとしていた。
1970年――後に「暗黒の10年」と呼ばれるキッカケになる、制作プロダクションの設立である。
事の顛末はこうだ。その動きは民放の雄、まずはTBSから始まった。
かねてより同局は、映画監督の木下恵介サンと博報堂との共同出資で「木下恵介プロダクション」を設立していたが、70年2月、これに続いて渡辺プロダクションや電通との共同出資で「テレパック」、さらには退職したディレクターらと「テレビマンユニオン」を設立したのである。
そして、この3つの制作プロダクションに、番組の発注や、スタジオと中継車の優先使用などの支援体制で育成を図る。その結果、同局は局内の制作部とも併せ、競争原理による番組の質の向上を実現する。ちなみに、今も民放ドラマの最高視聴率56.3%を誇る『ありがとう』は、設立されたばかりのテレパックの制作だった。
フジテレビ、暗黒の10年へ
このTBSの動きにいち早く反応したのが、時のフジテレビの鹿内信隆社長だった。
当時、民放各局はカラー化による設備投資を進め、経営的に厳しい状況にあった。そこで鹿内社長もTBSに倣い、制作部門を分離することで経費削減を図ろうと考えたのである。
かくして、フジポニー、ワイドプロモーション、フジプロダクション、新制作なる4つの制作プロダクションが設立され、この4社にフジの制作から150人の社員が出向する。そして71年4月、フジは制作局を廃止したのである。社内に制作部門を残したTBSに比べ、徹底的な合理化だった。
しかし――この措置はフジにとって裏目に出る。独立志向が強く、自ら外に飛び出したTBSのディレクター陣と比べ、フジの社員たちは会社の意向で出向させられた身。「守り」の姿勢に入ってしまい、以後10年間、フジは暗黒の低迷期を迎えるのである。
伝説になった『白い巨塔』
1970年代、フジテレビは視聴率が低迷し、不遇の時代を送った。制作部門を分離したことによる社員の士気の低下が原因だった。フジの持ち味である“自由闊達な空気”が薄れたのである。
この時代、フジで話題になった番組といえば、市川崑監督の斬新な演出と、上条恒彦サンが歌うフォークソング調の主題歌が評判を呼んだ、1972年放送の時代劇『木枯し紋次郎』くらいだった。
74年に放送された、テレビ業界の内幕を描いた倉本聰サン脚本の『6羽のかもめ』も、時のスター美空ひばりも見ているなど業界内では評判になるも――視聴率は7%台と低迷した。
そして、1978年6月に始まった『白い巨塔』も、かつて大映専属の映画スターとしてならし、その後、テレビに転じてTBSの「白いシリーズ」で人気を博した田宮二郎を担ぎ出すも――視聴率は思うように伸びず、夏のナイター時期には一桁台と低迷した。

同ドラマのプロデュースと演出は、かつて『男はつらいよ』も担当したベテラン小林俊一サン。しかし、大学の医学部を舞台にした権力闘争と、当時まだタブー視されていた医療裁判という硬派なテーマは、お茶の間の共感を十分には得られなかった。
また、密かに「躁うつ病」の病に苦しむ田宮二郎のケアも、小林俊一プロデューサーを悩ませた。ドラマの終盤、病に冒される天才医師・財前五郎の苦悶以上に、時に感情の起伏が抑えられない主演俳優を抱える制作現場の戦いは壮絶だった。
11月15日、財前五郎の最期となるシーンが撮影された。自らの死を前にし、初めて財前が医者としての良心に目覚めるシーンである。その思いを綴った友人・里見への遺書は、代筆を断り、田宮自らがしたためたという。
そしてドラマはクランク・アップ。その年の暮れの12月28日――田宮は自室で猟銃自殺を遂げた。
皮肉にも、彼の死後放映された『白い巨塔』は、密葬の行われた夜の30話が26.3%、年が明けた1月6日の最終話が31.4%と、異例の高視聴率を記録した。だが、小林俊一プロデューサーは手放しでは喜べなかった。
夜明け前――
1979年6月、フジテレビはそれまで万年4位だったテレビ朝日にも抜かれ、遂に月間視聴率が民放キー局で4位となった。
社内の空気はどん底だった。評判になる番組も皆無だった。
そんなある日、草創期のフジテレビを支えた、あの白川文造サンの元へ、旧知の脚本家の倉本聰サンが訪ねてくる。白川サンは一時、編成局からネットワーク局へ異動となり、再び企画担当として戻ったタイミングだった。倉本サンが問いかける。
「ネットワークに何年いたの?」
「丸4年ちょっとかな」
「そんなに長く休んでいたのなら、少しはいい企画を考えてきたろ?」
「まあね」
白川サンは、かねてから温めていた企画を話した。それは、日本版『大草原の小さな家』ともいえる物語。富士の裾野に建てた丸木小屋を舞台に、自然の中で親子が暮らし、知恵と技術を学んでいくドラマである。
それを聞いて、不意に倉本サンが立ち上がった。そして白川サンに向かって最敬礼する。
「それを富良野でやらせてよ! 文ちゃん」
「富良野って何?」
倉本サンはテーブルの上にあったコースターの裏に北海道の地図を描いて、その真ん中に印を入れた。
「富良野ってのは、いま俺が住んでいるところ」
この数年前、倉本サンは脚本を手掛けていたNHK大河ドラマ『勝海舟』を演出陣とのトラブルから途中降板し、それがきっかけで東京を離れ、北海道に移り住んでいた。
「とにかく富良野を見にきてよ」
――時に、鹿内春雄サンがフジテレビの副社長に就任し、プロダクション制度を廃止して“大制作局”を復活させる、1年前の話である。
(中編へつづく)
(文:指南役 イラスト:高田真弓)




