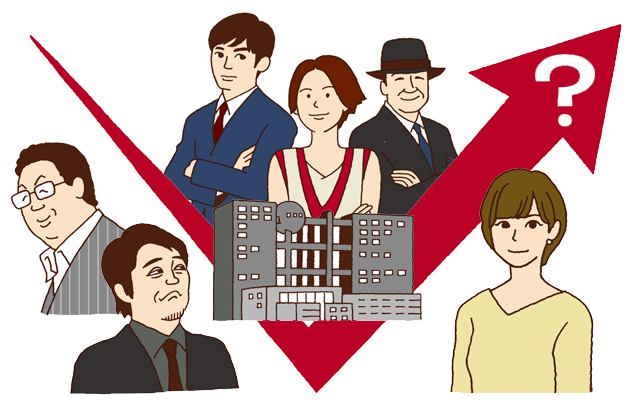少し前の話題で恐縮だが、フジテレビの4月クールのドラマ『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』の最終回(第9話)が2時間スペシャルで放映され、視聴率6.8%で幕を閉じた。最終回が2時間だったのは、評判がよかったから――ということではなく、単に次の週からロシア・ワールドカップが始まるからである。つまり、終盤の2話を1話にまとめた形だ。
ちなみに、全話通した平均視聴率は6.2%。これは最近のフジの木曜劇場――通称“木10”枠としては、ごくごく平均的な数値。高くも低くもない。実質全10話というのも平常運転。低視聴率で打ち切られたワケでも、評判がよくて最終回を延長したワケでもない。数字上は極めて平凡なドラマだった。
TLは“モンクリロス”の声一色に
――こう書くと、『モンテ・クリスト伯』は、最近のフジのパッとしない一連のドラマの1つと思われるかもしれない。いやいや、そうじゃないのだ。特筆すべきはSNSである。最終回の放映直後のTwitterでは、トレンドのベスト10の半分が――1位「#モンクリ」、2位「#モンテクリスト伯」、4位「#モンテ・クリスト伯」、8位「#モンクリロス」、10位「#ディーンフジオカ」――と、同ドラマ関連で占められたのだ。さらに、タイムラインは“モンクリロス”を叫ぶ声一色に――。こんなことは、久しくフジのドラマでは見られなかった。
そう、『モンテ・クリスト伯』は視聴率以上の爪痕を残したのである。

ゴールデンでテレ東に敗れたフジ
その一方で、最近、フジにとって不名誉な話もあった。
それは、『モンテ・クリスト伯』の最終回が放映された翌週――6月18日週のこと。このところ、2年連続で年間視聴率の「全日」「ゴールデン」「プライム」の3部門で、キー局4位に低迷しているフジテレビ。「振り向けばテレビ東京」と揶揄されているが、遂にそれが現実になったのだ。
その週――フジはゴールデンタイムで、テレ東に0.1ポイントの差をつけられ、民放5位に沈んだのである。これまでテレ東がゴールデンの週平均で他局に勝ったのは、毎年中継する『世界卓球』の期間中のみだったが、この週のテレ東は平常運転。しかも、W杯の中継を1つも持たないテレ東に対して、フジは2つのW杯のゲームを中継したにもかかわらずである。
フジの敗因は?
――それは、あの人の存在が大きなカギを握る。
カギを握る人物
その人物とは、ドラマ『古畑任三郎』や『踊る大捜査線』などの企画を立ち上げた、フジテレビきってのアイデアマン――石原隆サンである。
昨年6月、宮内正喜新社長の体制になって、新たに設けられた役職「編成統括局長」に就任した石原サン。それは、編成局・制作局・映画事業局・広報局の4つの局をひとまとめにして、よりダイナミックな環境で積極的にコンテンツを発信していこうという、アグレッシブな試みだった。
あれから1年――フジの改革はそれなりに進み、石原サンは一つのメドがついたとして、先日、その任を後進に譲っている。とはいえ、改革は道半ばという話もある。
一体、石原サンのもとで何が変わり、そして――何が道半ばなのか。
3つの成果
この1年、「編成統括局長」の役職にあった石原サンは、3つの“大改革”を成し遂げた。
1つ目の成果は、ご存知の通り、フジを長年支えた2つの長寿バラエティ――『とんねるずのみなさんのおかげでした』と『めちゃ×2イケてるッ!』の終了である。賛否あったが、やはり新しいことを始めるには、古い殻を破らないといけない。その意味では前向きな終了だったと思う。
ただ、スクラップ&ビルドの視点で言えば、次の番組を当てないことには、改革は終わらない。現状、新番組は『みなおか』の後が、坂上忍司会のトークバラエティ『直撃!シンソウ坂上』で、『めちゃイケ』の後が、紀行バラエティの『世界!極タウンに住んでみる』――。正直、両番組とも特段目新しくもなく、視聴率で苦戦中である。
ドラマに変化の兆し
2つ目の成果は、先の4月クールの2つのドラマ『コンフィデンスマンJP』と『モンテ・クリスト伯』である。
前者は、『リーガル・ハイ』でお馴染みの人気脚本家の古沢良太サンを起用してのコンゲームもの。脚本を1年前から準備し、初回の放映前には全話の撮影が終了していたという、盤石の体制で作られた。おまけに映画化まで決まっているという。
全10話の平均視聴率は8.88%。まるでフジを象徴するような数字だが、これも先の『モンクリ』同様、視聴率以上に毎回SNSで盛り上がったのは記憶に新しい。大スター長澤まさみの振り切った演技も話題になった。
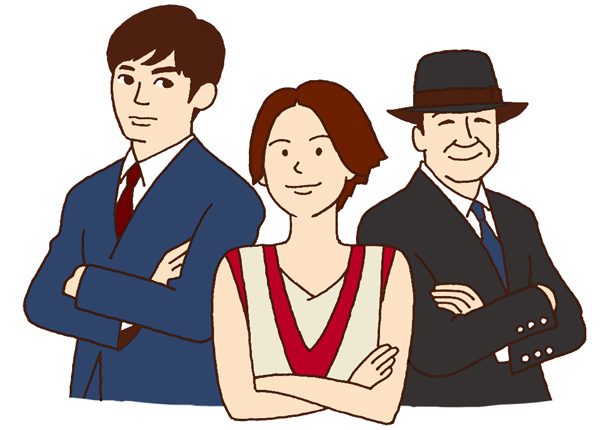
そして、『モンテ・クリスト伯』は、かの有名なデュマの書いた名作『巌窟王』を、現代日本を舞台にアレンジしたもの。題材といい、設定といい、かなりチャレンジングな企画だったのには違いない。とはいえ、こちらもSNSで視聴率以上の反響を得たのは、先に書いた通りである。
まぁ、SNSで盛り上がったからといって、すぐに視聴率に反映されるとは限らない。以前、本連載の「視聴率の正体」の回でも書いたが、SNSによって動かされる視聴率はせいぜい全体の5~10%。一方で、視聴率を構成する“幹”の部分――90~95%は、“なんとなく”テレビをつけて、チャンネルを合わせている人たち。とはいえ、その幹を動かすには、やはり5~10%の“積極視聴者”の存在は欠かせないのだ。
カンヌのパルムドール
そして3つ目の成果が――先のカンヌ国際映画祭で最高栄誉となるパルムドールを受賞した映画『万引き家族』である。知らない人もいるかもしれないが、同映画の製作には、フジテレビが幹事会社として関わっている。
元々、フジと是枝裕和監督は、監督がドキュメンタリーのディレクターだった時代からの付き合いで、『NONFIX』で数々の秀逸なドキュメンタリーを世に送り出した。
そして、映画は2013年の『そして父になる』以降、『海街diary』(2015年)、『海よりもまだ深く』(2016年)、『三度目の殺人』(2017年)、そして今回の『万引き家族』と、5作連続で両者は組んでいる。『万引き~』が当初『声に出して呼んで』というタイトルだったのを、現行タイトルに変えるようアドバイスしたのは、フジの松崎薫プロデューサーである。そして石原隆サン自身も、是枝作品にはアドバイザー的な立場でずっと関わっている。
正直、フジと組む以前の是枝作品は海外で高い評価を得るも、興行的には今ひとつだった。それがフジと組んで以降は全国ロードショー公開となり、興行収入も10倍以上に。それまでの作家性に加え、大衆性も身に着け、メジャー作品へと昇華させたのはフジの功績だった。今回の『万引き~』のパルムドール受賞も、長年にわたる監督とフジとのパートナーシップが実を結んだ側面もあった。
天才プロデューサーの死角
――以上3点が、「編成統括局長」時代の石原サンの3つの成果である。映画で1つの歴史的結果を残し、ドラマでは反転攻勢のキッカケを作り、バラエティでは長年の懸案だった2つの伝説の番組を終了させた。
だが、そこが石原サンの限界でもあった。彼はフジテレビ入社以来、ずっと映画とドラマ畑しか経験していない。ゆえに、『コンフィデンスマンJP』や『モンテ・クリスト伯』のような、世の中の時流とは関係なく、シンプルに自分が面白いと思うドラマを見抜き、推す目は持っていた。しかし――バラエティでは何が面白いのか、多分、分からなかったと思う。天才プロデューサーにも死角があったのだ。
現状、フジに足りないもの
ゆえに、石原サンにできることは、他の民放で評判になっていたり、自局で数字を取っている番組の焼き直しという“後ろ向き”の方策しかなかったと推察する。
タレントではなくディレクターが海外で体当たりリポートする『世界!極タウンに住んでみる』は、テレ朝のナスDの『陸海空 地球征服するなんて』を彷彿とさせるし、坂上忍司会の『直撃!シンソウ坂上』は、やはり同局の『バイキング』の焼き直しに見えてしまう。『梅沢富美男のズバッと聞きます!』にしても、申し訳ないが巷のバラエティの既視感は否めない。
かくして、作り手が今ひとつ面白がっていないであろう番組を、お茶の間が面白がるワケもなく――。
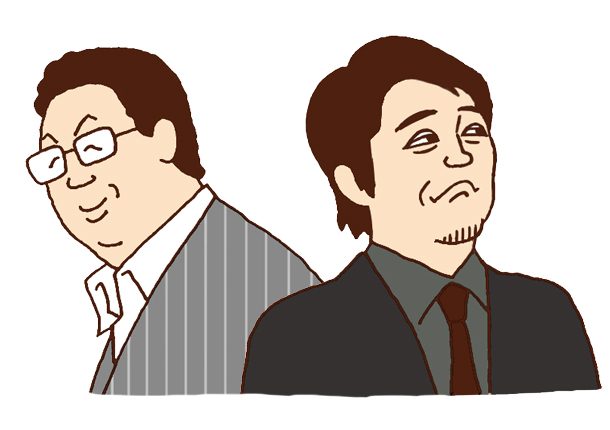
そう、現状のフジに足りないのは、作り手が自ら面白がって作るバラエティである。今や、ゴールデンタイムの8割の番組が、バラエティで構成される。日テレを見れば分かるが、バラエティを制す局が、視聴率を制す時代。先のテレ東にゴールデンの週平均で敗れた話も、そういう事情である。
フジテレビがこれからやるべきこと
いかがだろう。
フジテレビの復活に必要な手順がなんとなく見えてきたのではないだろうか。多分、この先――ドラマは少しずつ持ち直すと思われる。石原隆サンが道筋をつけた“自分たちが面白いと思うドラマを作る”路線に従い、昔のようにフジテレビらしいドラマが増えるだろう。幸い、優秀な作り手やブレーンは、社内外に大勢いる。軌道に乗るまで、もう少し時間がかかるかもしれないが、SNSに引きずられる形で、徐々に視聴率も回復すると思う。
問題はバラエティである。
自分たちが面白いと思うバラエティを作るのは当然として、何か道筋になりそうなヒントはないのか?
――ある。僕は、それはフジテレビの“DNA”だと思う。
フジテレビのDNA
一般に、フジは1959年の開局から70年代までは「母と子のフジテレビ」の時代で、“第二の開局”と言われた80年代以降は「楽しくなければテレビじゃない」の時代だと思われていてる。
でも――実のところ、2つの時代は多くの点で連続している。「母と子」の看板を下ろした以降も、日曜夜7時半の『世界名作劇場』は1997年まで地上波で続いたし、『ひらけ!ポンキッキ』の後継番組の『ポンキッキーズ』も、BSフジに場所を移して、今年の3月まで続いた。ガチャピンとムックの再就職先が取りざたされたのは、ついこの間の話だ。何より、『ちびまる子ちゃん』や『サザエさん』といった国民的な家族アニメは今も続いている。
一方、80年代以降の「楽しくなければ~」の看板も、フジは開局の年から既に、クレージーキャッツの『おとなの漫画』という帯のコメディ番組を生放送していたし、長らくお正月の風物詩と言われた『新春かくし芸大会』も、1964年から2010年まで放送していた。あの『笑っていいとも!』も、その源流を辿ると、68年にスタートした前田武彦とコント55号司会の『お昼のゴールデンショー』に行きつく。
そう、「母と子」も「楽しくなければ~」も――図らずも開局から今日まで、フジのDNAとして連綿と続いているのである。
ここはフジテレビじゃない!
以前、本連載の「フジテレビ物語(前編)」の回でも紹介したが、1969年、日テレの伝説的バラエティ番組『巨泉×前武ゲバゲバ90分!』の初回収録時に、こんなエピソードがあった。

それは、司会の前田武彦サンと大橋巨泉サンのトークのシーン。2人のやりとりには台本があり、最後に巨泉サンのひと言でマエタケさんがギャフンとなるはずだった。だが、これにマエタケさんがとっさのアドリブで切り返したのだ。スタジオに笑いが起きる。その時である。突然、副調整室のスピーカーからプロデューサーの井原高忠サンの怒鳴り声が鳴り響いたのだ。
「勝手な真似はやめろ! ここはフジテレビじゃない!」
フジテレビの持ち味
日テレのバラエティは、アメリカ仕込みの“ヴァラエティ・ショー”がベースにある。そこには台本があり、出演者はあたかも自分の言葉のように喋るテクニックが求められる。井原プロデューサーが演者に求めたのは、そういうことである。
一方、前武サンは当時、フジテレビで『お昼のゴールデンショー』と『夜のヒットスタジオ』という2つのヒット番組を持つ売れっ子司会者。フリートークとアドリブの名手と呼ばれた。そう、当時のフジは生放送で演者が自分の言葉を発し、アドリブを繰り出せる自由な空気で満ちていたのだ。
思えば、そんな局をまたいだ対比のパターンは、80年代にも再び繰り返された。それは、土曜夜8時の「土8戦争」である。台本通りにコントを演じる王者、TBSの『8時だョ!全員集合』に対し、挑戦者のフジの『オレたちひょうきん族』は、アドリブの宝庫。当初はトリプルスコアを付けられていた『ひょうきん族』だったが、じりじりと差を詰め、遂には『全員集合』を抜き去り、終了へと追い込んだのだ。

カギは非・予定調和
そう――思うに、フジの強み(DNA)とは、昔から一貫して、演者のフリートークとアドリブだと思う。その際、作り手に求められるのは、演者をリラックスさせて、自由な発言が飛び出す空気を作ること。これに関しては、フジは昔から他局に長けている。日テレもTBSも、この自由な空気感はマネできない。
これだ。フジがバラエティで復活する道は、この持って生まれたDNAを生かさない手はない。要はそれを21世紀にアップデートするのだ。コンプライアンスが叫ばれる今だからこそ、挑戦しがいがあるのではないか。
しょせん、日テレ流の作り込んだバラエティで勝負しても、フジに勝ち目はない。それは、日テレのDNAだから。『世界の果てまでイッテQ!』はその集大成なのだ。だったら、フジはフジのやり方で勝負するしかない。そう、何が飛び出すか分からない“非・予定調和”だ。
ターゲットは女性と若者
それともう一つ――フジテレビならではのターゲットの特性にも留意したい。
「母と子のフジテレビ」の昔から、フジは他局に比べて女性と若年層の視聴者が多い傾向にある。これは今も変わらない。各種データを見ても、NHKと民放キー局を通して、フジの視聴者層が最も若い。そして女性が多い。
現状、視聴率を稼ぐには、高齢者を狙えと言われる。日テレとテレ朝の視聴率が比較的高いのは、要は視聴者の年齢層が高いからである。だから、その線で勝負しても、フジに勝ち目はない。
だったら、ここは割り切って、女性と若者にターゲットを絞り、新しいバラエティを仕掛けるのだ。考えたら、『あいのり』や、その発展形の『テラスハウス』(現在は『TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS』)は今も人気だし、やはり餅は餅屋なのだ。
それに、本当に面白い番組を作れば、例えメインターゲットが女性と若者でも、幅広い層が見てくれる。全盛期の『みなおか』や『めちゃイケ』が20%から30%の視聴率を稼いだのは、そういうことである。
面白い番組は面白い社員が作る
そして、面白い番組を作るにあたって、忘れてはいけないこと――それは、つまるところ、“面白い番組は、面白い社員が作る”ということだ。
思えば、80年代にフジがバラエティで一世を風靡した時は、いわゆる“ひょうきんディレクターズ”らにもスポットが当たった。90年代にフジが連ドラブームをけん引した時は、大多亮プロデューサーや亀山千広プロデューサーも注目を浴びた。2000年代に入り、フジが再び三冠王に就いた時は、『めちゃイケ』の片岡飛鳥総監督が脚光を浴びた。
それは、他局も同様である。90年代に日テレがバラエティで視聴率を伸ばした時代は、Tプロデューサーこと土屋敏男サンや五味一男サンが注目を浴びたし、今、バラエティで良くも悪くも物議を醸している『水曜日のダウンタウン』は、TBSの藤井健太郎Dの存在抜きには語れない。テレビ朝日なら『アメトーーク!』の加地倫三サンに、『陸海空 地球征服するなんて』のナスDこと友寄隆英Dが目立っているし、テレ東なら『池の水ぜんぶ抜く』をはじめ、面白い企画は大抵、伊藤隆行プロデューサーの影がちらつく。
そう、フジテレビ復活のカギは、面白い社員がどんどんオモテに出ることだ。もう、「裏方に徹する」なんて謙遜しなくていい。幸い、フジには面白い社員がまだまだ大勢いる。積極的に露出していこう。
フジテレビ復活の顔
最後に、フジテレビ復活を期待して、その顔になってほしい一人の女子アナを紹介して、このコラムを〆たいと思う。
その人物とは――宮司愛海アナである。

思えば、先日、物議を醸したサッカーロシアW杯予選リーグ最終戦の「日本対ポーランド」。フジテレビはその中継局だったが、あの時、スタジオにいたのが宮司アナだった。例の「フェアプレーポイント」で日本が決勝へ進む微妙な空気の中、そんな戸惑う空気をあえて隠さず、さりとてしっかりとした口調で進行する宮司アナが、気になった視聴者も多かっただろう。
彼女は福岡出身で、僕の同郷だから推すワケじゃないけど――似たようなミディアムヘアーの女子アナが多い中、そのショートカットの美貌は抜群の存在感を放っている。何より、アナウンス力・アドリブ・キャラと、その才能は申し分ない。この4月から週末のスポーツニュース『S-PARK』のメインMCに抜擢されたのが、彼女の実力を物語る。いや、それだけじゃない。ここ一番の大舞台のMC――最近では、先の衆院選の開票速報特番や今回のW杯など――は、決まって宮司アナが指名されることが多いのだ。それは図らずも、上層部からの信頼を伺わせる。つまり、彼女なら安心して任せられるのだ。
過去、フジテレビの調子がいい時は、必ず“顔”となる女子アナがいた。古くは80年代前半のひょうきんアナの3人に、80年代後半の『プロ野球ニュース』の中井美穂アナ。90年代に入ると、有賀さつき・河野景子・八木亜希子の三人娘が注目を浴び、2000年代に入ると、『めざましテレビ』発でアヤパン・ショーパン・カトパンらが脚光を浴びた。
そして今――その顔は、宮司愛海アナが担うべきだと僕は思う。
彼女がフジテレビの顔と世間から認知されたその時、フジは不死鳥のごとくV字回復を遂げていると確信する。
(文:指南役 イラスト:高田真弓)