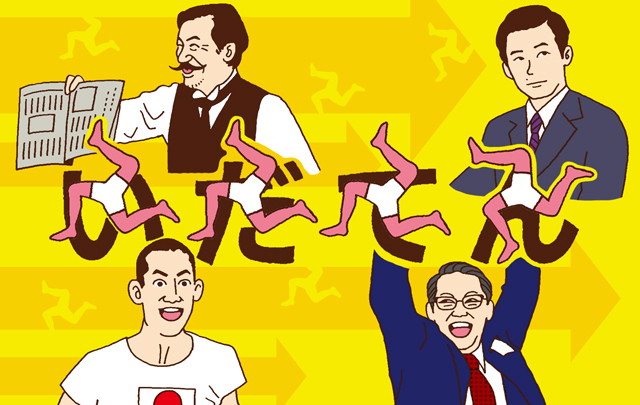皆さん、ご承知の通り――先の3月31日、脚本家の宮藤官九郎サンが新型コロナウイルスに感染したことが、所属事務所の大人計画から発表された。幸い、今のところ症状は発熱のみで、少しずつ快方に向かわれているそう。一日も早いご回復をお祈りします。
さて、そんな中――奇しくも、この4月6日から、彼が脚本を書いた昨年のNHK大河ドラマ『いだてん』の再放送がNHK-BSプレミアムで始まった。となれば、クドカンさんへのエールも込めて、改めてこのタイミングで同ドラマを振り返るのもありかもしれない。再放送を機に、途中脱落した人が戻ってくるかもしれないし、初めて視聴する人もいるかもしれない。何せ、今や僕らは毎日、家にいるのだから。
というワケで、今更ながら『いだてん』を“考察”したいと思います。それは、どんなドラマだったのか。何がよくて、何がイマイチだったのか――改めて分析した上で再放送を見返せば、また違った風景が見えてくるというもの。
『麒麟がくる』好調の影に沢尻砲あり
――と、その前に、現在絶賛放映中の大河『麒麟がくる』についても少々。初回視聴率は19.1%と、16年の『真田丸』以来の高い水準となったのは、ご承知の通り。その後は下がったり、上がったりしながら、まずまずの出足だろうか。個人的には、久々の王道大河の匂いがして、割と楽しんでいる。
とはいえ、一般にドラマの序盤の数字って、内容云々よりも期待値の高さを表しているんですね。つまり、現段階での『麒麟がくる』の健闘ぶりは、舞台である「戦国時代」人気と、多少なりとも「沢尻砲」のお蔭でしょう。
そう、沢尻砲――。
俗に「100の番宣より、1本のニュース」と言われるように、沢尻エリカさんが同ドラマの告知に果たした役割は、やはり大きいのです。普通、マックで女子高生は大河ドラマの話をしないけど、「沢尻エリカ、麒麟惜しいことしたね~」とは言ってそうでしょ。
正直、撮影済みの分はそのまま放映して、新撮分から川口春奈サンに代わればよかったのに、とも思う。川口・帰蝶も魅力的だけど、沢尻・帰蝶がどんな風だったのか、個人的に両者を見比べてみたかったし――。
出演者の不祥事にテレビ局が対処する理由
まぁ、これが民放なら、まだ分かる。あちらはスポンサーの広告費で番組が制作されているので、いざコトが起きたら、スポンサーのイメージを損ねることがあってはいけない。だから、テレビ局の営業担当と広告代理店がスポンサーのところへすっ飛んで平謝りしつつ、代役なり差し替え放送なり、次善の策を提案しないといけないんです。
それに対して、NHKは国民の受信料で賄われる公共放送だ。何かコトが起きても、NHKのイメージを損ねることはあっても、国民のイメージが下がることはない(当たり前だ)。それに、大河ドラマがかなり前倒しで収録されていることは視聴者の誰もが知っている。ちゃんとテロップでお断りを入れたら、「まぁ、予算も時間もかかっているし、仕方ないよね」と、お茶の間は分かってくれたと思う。
1分短縮は『いだてん』チームの作戦勝ち?
現に、前作の『いだてん』は、巨額の税金の申告漏れなどが報じられたチュートリアル徳井サンに代役を立てることなく、テロップで対処して、表向きは編集で1分削った体で放送した。そして――お茶の間はそれを受け入れたのだ。いや、むしろ制作側の英断(徳井サンの出番が意外と多かった)を称賛する声すらあった。
実際、編集前の内容を僕らは見ていないので、本当に彼が演じた大松監督のシーンが削られたのか、真実は誰にも分からない。個人的には、僕は『いだてん』チームの作戦勝ちだと見ている(ニヤリ)。
それに、だ。NHKはかつて同じ大河の『勝海舟』(1974)で、前代未聞の主演俳優の途中交代劇すら経験している。言っとくが、主演の交代だ。渡哲也サンが病気のために9話で途中降板し、10話から松方弘樹サンが代わって主役の海舟を演じたのだ。それでも、お茶の間は何事もなかったかのように視聴を続け、同ドラマは最高視聴率30%超えの成功を収めている。
そう、代役なんて、作り手が思ってるほど、お茶の間は気にしてないんです。『麒麟がくる』の途中で、帰蝶(濃姫)が沢尻サンから川口サンに代わったところで、お茶の間は「だよね」くらいにしか思わなかったはず。ちなみに『勝海舟』は、脚本の倉本聰サンも途中降板して、それを機に東京から北海道へ移住するんだけど――それはまた、別の話。
大河史上最短の全44話に
なんにせよ、撮り直しで得する人間なんて、誰もいない。川口春奈サンだって、新撮分から登場した方が、どれだけ気が楽だったか。まぁ、今のところ川口サンの演技は好評で、彼女がメインで登場した第7回「帰蝶の願い」なんて、前週から1.2ポイントも視聴率を上げて、15%に乗せたほど。
とはいえ、今回の措置でお金と時間が余計にかかり、既に放送開始が2週遅れたのは事実。今年1月、NHKから『麒麟がくる』が大河史上最短の全44話になるのが発表されたけど、2週遅れのしわ寄せが、多少なりとも総回数に影響を与えたのは間違いない。ただでさえ、今年は「東京オリンピック・パラリンピック」の中継で、当初から5週間の休止が決まっていたワケだから――。
――と、思っていたところに、よもやの新型コロナウイルス騒動で、そのオリ・パラの延期である。となると、逆にその空いた5週間の穴埋めをどうするのだろうと心配していたら、今度は「緊急事態宣言」で収録自体が休止に。結果的に、空いた5回分が収録スケジュールを調整する“緩衝材”になりそうで、なんやかんやで結果オーライか。
『いだてん』とは何だったのか
そんな次第で、ちょっと話が横道に逸れてしまったが(長すぎる!)、ここからは『いだてん』の考察に移りたいと思います、ハイ。
さて、ご存知の通り、同ドラマは1年間の平均視聴率が大河ドラマ史上最低となる8.2%。それまでの最低が『平清盛』(2012)と『花燃ゆ』(2015)の12.0%だったから、これはダントツである。しかも、初の一桁。しかし一方で、SNSでは終盤、かつてない盛り上がりを見せたのも、また事実である。
一体、『いだてん』とはどういうドラマだったのか。良作だったのか、駄作だったのか、それとも――。その辺りについて、なるべく客観的な目線から考察したいと思う。
僕が『いだてん』を語る理由
おっと、その前に、まずは僕の立ち位置の説明から。
僕は以前、もう10年以上前になるが――『幻の1940年計画』(アスペクト)なる本を出したことがある。その本では、戦前の1940年(昭和15年)に行われる予定だった東京オリンピックと日本万国博覧会、それにテレビ放送と弾丸列車計画を“幻の4大偉業”として紹介した。
よく、戦後日本の4大偉業として、比較的短期間で成し遂げられた「東京オリンピック・大阪万博・新幹線・テレビ放送」の4つの事業が語られるが、それらのルーツは戦前にあり、コトの真相は戦前から戦後へ計画が分断されることなく続いていた――というのが、この本の趣旨だった。
それって、『いだてん』が描いた、1940年の“幻の東京オリンピック”を招致した嘉納治五郎の志が、戦後に田畑政治や東龍太郎たちへと受け継がれ、1964年に花開いた――とするプロットと基本、似ていると思いません? そんな次第で、僕には少しばかり、『いだてん』に物申す権利があると勝手に自負している。
歌舞伎座で大人計画が上演したのが『いだてん』
さて、まずは視聴率の話から始めたいと思う。
――と言うと、「視聴率なんて関係ない! 大事なのは中身だ!」と憤る『いだてん』ファンの方もいるかもしれないけど、まぁ、落ち着いて。何も、そこを責めようって話じゃない。
なぜ、かくも『いだてん』が歴史的低視聴率に終わったのか。これはシンプルな話、いわゆる“大河ドラマ”じゃなかったからだと思います。要は、クドカンのドラマだったと。それを「大河」の枠で放送したから、客とのミスマッチが起きた――たった、それだけの話なんです。ドラマのクオリティどうこうではなく。
こう考えたらどうだろう。
『いだてん』とは、東銀座の歌舞伎座で、大人計画が上演した演劇だったと。それだと、普段、歌舞伎を見慣れている常連客たちにとっては、相当違和感のある舞台に映っただろう。台詞は早口だし、場面転換も早いし、コメディ色もかなり強い。正直、何をやっているのかよく分からない、というところか。だから、幕間に一人帰り、また一人帰り――。
これが、下北沢の本多劇場で上演していたら、大入り満員でドッカンドッカンとウケたに違いない。SNSで絶賛した人たちは、要は本多劇場の常連客たちだったと。つまり、『いだてん』とは、枠(ハコ)と演目のミスマッチが招いたドラマだったんです。
芥川賞=大河に対する、直木賞=金曜時代劇
個人的には――僕は、『いだてん』は別の枠でやった方がよかったと思う。単刀直入に言えば、大河とは別の“娯楽時代劇”の枠だ。
思い返せば、NHKには昔、総合テレビのプライムタイム(夜8時)に、「金曜時代劇」や「水曜時代劇」と称する娯楽時代劇の枠があったんですね。要は、正統派の歴史ドラマの“大河”と対を成す存在として、エンターテインメント路線の時代劇の枠があったと。いわば芥川賞に対する直木賞のようなもの。
ちなみに、その枠――紆余曲折あって、今では、週末の夕方6時台に放送している、近代劇も扱う「土曜時代ドラマ(40分枠)」と、BSで放送される、昔ながらの娯楽時代劇枠の「BS時代劇(45分枠)」の2つに分かれて、一応存続はしている。ただ、ここ1年くらいは、「BS~」で放送したものを再編集(5分短縮)して「土曜~」で再放送するという同一化が進んでいる。
地上波20時台に「大型娯楽時代(近代)劇」枠の復活を
まぁ、こういう言い方をしたらなんだけど――ぶっちゃけ、夕方6時台の放送にしろ、BSのドラマにしろ、地上波のプライムタイムのドラマに比べて、どうしても“格落ち”感は拭えない。予算も大河と比べて相当低いし、出演者もそれに順ずる。やはり、地上波のプライムタイムで放送してこそ、“大作感”を醸成できるし、予算も増えるというもの。
NHKに1つ提案。
僕は、NHKの娯楽時代(近代)劇枠は、かつてのように地上波(総合テレビ)の夜8時台に戻すべきだと思う。つまり、局の「看板枠」だ。それなら、『いだてん』をやるのに丁度よかったのではないか。視聴者もエンタメ路線に慣れているので何の違和感も抱かなかっただろうし、視聴率も大河でやるより2倍は取れたかもしれない。
大河の視聴率を上回った『天下御免』
実際、かつて「金曜時代劇」時代に放送された、早坂暁サン脚本の『天下御免』(1971-)なんて、平賀源内が主人公で、江戸時代のごみ問題や受験戦争を描くなど、かなりアグレッシブな娯楽時代劇(ちなみに、三谷幸喜サンがこのドラマのファン)だったんだけど――全46話(一年間)の放送で、平均視聴率が30%を超えたんですね。なんと、同じ年に放映された大河ドラマの『春の坂道』の年間平均を10%近く上回ったんです。
僕は、近年、スイーツ路線など迷走しがちだった大河ドラマを立て直す意味でも、大河と同格の大型娯楽時代(近代)劇の枠を、地上波のプライムタイム(夜8時台)に復活させるべきだと思う。それも、半年から1年間の放送に拡大して。それが叶えば、大河は大河で迷わず王道路線を貫けるし、一方の大型娯楽時代(近代)劇枠も、よりチャレンジングな作風に挑めるというもの。NHKさん、どうでしょう?
『いだてん』が犯した2つのミス
では、いよいよ肝心の『いだてん』の内容面の検証に移ることにする。
なんだか、SNSでは終盤、『いだてん』を褒める声ばかりになり、「いだてんを褒めるワタシが好き」「いだてんを褒めるワタシはインテリ」状態になってるきらいもなくはなかったけど――そりゃ、最後まで見続けた人たちは、『いだてん』が好きで見ている人たちだから、そうなるのは当たり前。いわゆる視聴者の“純化”ですね。視聴率6%の世界とはそういうもの。
ただ、全く批判のない世界も、作り手にとっては味気ないし、ドラマ界にとってもあまりいいことじゃないので、このコラムでは前向きな意味で、忌憚のない感想を述べたいと思います。
単刀直入に言いましょう。
僕は、『いだてん』は、2つのミスを犯したと思う。1つは、古今亭志ん生のパートを入れたこと。もう1つは、嘉納治五郎を主人公にしなかったことである。
最初は「古今亭志ん生物語」だった
順を追って説明しましょう。
まず、古今亭志ん生のパートだけど、これはクドカンさん自身がインタビューでも再三語っているように、当初は大河とは関係なしに、「志ん生」のドラマを書こうとしたんですね。
クドカンさん自身、昔から落語好きを公言してるし、かつてTBSで落語を題材にしたドラマ『タイガー&ドラゴン』(2005)を書いて、これは視聴率・内容とも評価され、ギャラクシー賞にも輝いた。だから、タラレバの話になっちゃうけど、どこか別の枠で、シンプルに古今亭志ん生の一代記を書いていれば――普通に傑作として評価されたと思う。
これは僕の推測だけど、恐らくクドカンさんは、志ん生物語を『タイガー&ドラゴン』のフォーマットで書こうとしたのではないか。
「本歌取り」というプロット
そう、『タイガー&ドラゴン』のフォーマット――いわゆる各回のサブタイトルを落語の演目にするってやつですね。例えば『志ん生物語』なら、冒頭、高座で晩年の志ん生が「黄金餅」や「鈴振り」など得意の演目を一席やっている。その語りの途中から回想シーンに乗り変わり、志ん生の青年期のドラマが始まる。で、そのストーリーが、冒頭の演目とリンクする、いわゆる「本歌取り」のプロットになっている――ほら、面白そうでしょ?
実際、そのフォーマットに近い回が、『いだてん』の第39回「懐かしの満州」だったと思う。残念ながら、ラグビーW杯「日本VSスコットランド」戦の真裏に当たり、大河最低視聴率となる3.7%に沈んだけど――志ん生が慰問先の満州で、終戦直後のソ連が侵攻してくる史実を背景に、持ちネタの「富久」を、浅草と日本橋をちょいと往復する話から、“浅草と芝”という遠距離をガムシャラに往復する話へと大転換するエピソードが描かれた。クドカンさん曰く「最も描きたかった回」だったそうで――。
イメージは『フォレスト・ガンプ』
思うに、志ん生の青年期は自著以外の資料がほとんどないので、志ん生物語のベースは、この満州の回のように、史実としての時代を描きつつ、そこにフィクションとしての志ん生のエピソードを乗せる展開になったと思う。そう――イメージは、トム・ハンクスの『フォレスト・ガンプ/一期一会』だ。歴史の重要場面に、ことごとくガンプ=若き志ん生が居合わせるパターン。これなら、明治・大正・昭和の近代史を、志ん生らしい“下町の庶民目線”で描けるというもの。
多分、この段階で、クドカンさんの頭の中には、既にビートたけしサンのキャスティングがあったと思う。彼にとって、たけしサンは中学時代に『オールナイトニッポン』を聴いて以来の憧れの人だし、晩年の志ん生を演じるのに、年齢的にも丁度いい(どちらも70代前半)。何より――晩年の志ん生は、1961年に脳出血で倒れて以来、全盛期の立て板に水の語り口が影を潜めた。ある意味、これはバイク事故で生死を彷徨い、奇跡的に助かった現在のたけしサンとも重なる。
再度、タラレバになっちゃうけど――僕は、この『古今亭志ん生物語』を「土曜時代ドラマ」枠(多分、当初はこの枠で話が進んでいたと思う)で、2クール(半年)くらいやるのが一番よかったと思う。間違いなく、傑作になっていただろう。
だが、そこにNHKの政治力学が働く。そう、“夕方6時台”問題だ。
大河ドラマへの誘い
ここから先は、完全に僕の推測になる。
NHKとクドカンさんの間で、この『古今亭志ん生物語』を話し合ううち、どこかの段階で、「果たして、土曜時代ドラマはクドカン作品を放送する枠として相応しいのだろうか」というNHKの政治力学が働いたのではないか。まぁ、クドカンさん自身は、そういうのにこだわらない人だけど、NHKサイドとしては、『あまちゃん』で朝ドラを盛り上げた功労者でもあるし、もっと大きい枠で扱いたい――という野心が芽生えたのかもしれない。
そうして、色々と話し合ううちに、「大河」の話が出てきたのではないか。ただ、そうなると古今亭志ん生の話だけでは資料も少ないし、さすがに1年間はもたない。そこで――恐らくNHKサイドの提案だろうけど、2020年の東京オリンピックと絡めて、志ん生の話と並行して、日本と近代オリンピックの歴史を紐解く物語のアイデアが出たと推察する。
オリンピックは平和の祭典
日本の近代史というと、戦争の連続で、どうしてもきな臭いイメージが付きまとう。クドカンさん自身もインタビューで、権力者たちの近代史をストレートに描くのには抵抗があるが、志ん生を通してなら「下町の庶民」目線で近代史を語れるからいいと答えている。同様に、NHKサイドは、オリンピックは平和の祭典だから、「スポーツ」目線で近代史を語れば、これも権力者目線とは違う、新たな近代史を描けると説いたのではないか。
そう、「庶民」と「スポーツ」――いわゆる権力者ではない、2つの目線による日本の近代史だ。ある意味、サブカル好きのクドカンさんらしい大河ドラマとも言える。この時点では、そんなに悪くない企画に見える。
だが、そうなると、鍵となる人物をもう一人登場させないといけない。
嘉納治五郎である。
大きすぎた嘉納治五郎
そう、嘉納治五郎――。
ご存知、講道館柔道の創設者であり、アジア初のIOC(国際オリンピック委員会)委員であり、日本がオリンピックに参加する道を開拓し、1940年の幻の東京オリンピックを招致した偉人である。だが、彼自身は戦争への足音が聞こえる中、最後まで「平和の祭典」を唱え続けながらも、志半ばで没した。

そして、そんな治五郎が抱いた「東京オリンピック」への夢は、戦後、田畑政治や東龍太郎らに引き継がれ、やがて1964年に花開いた。そう、オリンピック目線の日本の近代史とは、要するに嘉納治五郎の物語でもある。
――となると、この物語は、古今亭志ん生と嘉納治五郎という2人の人物を主人公に据えるのが順当だろう。
だが、ここで新たな問題が持ち上がる。自著以外、ほとんど資料らしい資料が残されていない青年期の古今亭志ん生に対し、嘉納治五郎は22歳で「講道館」を設立して以来、資料が山のようにある。加えて、IOCの委員になって以降は、世界を股にかけて活躍しており、歴史の表舞台の人物になった。
そう、嘉納治五郎が大きすぎたのだ。志ん生と対を成す主人公として描くには、あまりにバランスが悪いのだ。
浮かび上がった金栗四三
恐らく――打ち合わせ早々、嘉納治五郎の存在感の大きさを悟ったクドカンさんは、日本の近代オリンピック史の物語の案に賛成しつつも、嘉納に代わる、新たなオリンピック関係者を探し始めたのではないか。このままでは志ん生が呑まれてしまうと――。
そうして色々と調べるうち、日本人初のオリンピック選手である金栗四三に行き着いたと。年齢を調べると、志ん生と一つ違いでバランスもいい。しかも、初めて出場したストックホルム大会では、マラソン競技の途中で気を失って、知らない人の家の庭で倒れていたという人間くさい一面もある。更には、それから半世紀以上を経た1967年には、そのストックホルム市に招待され、55年かけてマラソンをゴールしたという感動的な逸話まである。
そう――金栗四三の人生そのものが、壮大なマラソンなのだ。あまつさえ、戦前で生涯を閉じた嘉納治五郎に対して、四三は戦後も生き延び、1964年の東京オリンピックも目撃している。彼こそ、半世紀に渡る日本の近代オリンピック史の語り部に相応しいだろう――クドカンさんは会心の人物の発掘に、きっと心を躍らせたに違いない。

四三のもう一つの顔・駅伝走者
加えて、金栗四三にはもう一つの顔がある。それは、日本発祥の「駅伝」競技の発展に寄与したキーマンであること。
実際、四三は日本で初めて開催された駅伝で、栄えあるアンカーを務めており、また、あの「箱根駅伝」の創設者の一人でもある。四三なくして、今日の「駅伝」の隆盛はなかったと言っていい。
そんな駅伝の醍醐味と言えば、「襷(たすき)」である。そう、襷を繋ぐところに人間ドラマが生まれる。ならば――金栗四三から始まる「日本の近代オリンピック史」の物語も、襷を繋ぐように主人公をバトンタッチできないか。つまり、時代が進むごとに主人公をリレー方式で繋いでいけないか――そんなアイデアをクドカンさんが思いつくのに、そう時間はかからなかったと推察する。恐らく、『いだてん』というタイトルは、この段階で考案されたと思う。
主人公をリレー方式で繋ぐ
例えば、それはこういうプロットだ。
物語の序盤、まず金栗四三が主人公として物語が展開する。彼は日本人初のオリンピック出場を果たすが、思うような結果を残せず、主人公の“襷”を次の時代の水泳選手・前畑秀子へ引き渡す。そして彼女は、あの河西アナウンサーの「前畑ガンバレ」の実況もあり、日本人女性初の金メダルに輝く――。
その後、日本は悲願の1940年のオリンピック招致を成し遂げる。だが一転、戦争の影が近づき、無念の返上へ。そのまま日本は敗戦をも経験する。戦後、もはやオリンピックの“襷”は途切れたと思われたが――そこへ現れたのが「フジヤマのトビウオ」こと古橋廣之進。襷は蘇った。
そして時代は進み、1964年――日本は、一度は潰えた東京オリンピックを成し遂げる。この時、襷は「東洋の魔女」こと女子バレーボールチームの手に渡り、宿敵・ソ連を破って金メダル。その後、襷は再び金栗四三に引き継がれる。アンカーだ。彼は思い出の地、ストックホルムを訪れ、55年かけてマラソンをゴール――。
なるほど、四三に始まり、四三に終わる。これはこれで壮大な大河ドラマだ。企画書面(ヅラ)では、とてもよくできたプロットに見える。
連続ドラマにとって一番大事なもの
ところが、そのプロットには1つ大きな欠陥があったんですね。
連続ドラマにとって一番大切なものって、何だかわかります?
これは、あらゆる連ドラに共通する要素だけど、ずばり――「視聴者はこの続きを見たいか?」――この一点。とあるドラマを見始めた視聴者が、翌週も同じドラマを見続けるのは、シンプルに「この続きを見たい」から。
つまり、連続ドラマにとって欠かすことのできない要素とは、物語を強力に前に進める推進力なんです。ラブストーリーなら、2人の愛は成就するか? ミステリーなら、真犯人は誰か? 医療ドラマなら、患者の命は救われるか? 戦争ドラマなら――死ぬか、生きるか?
その考えに立てば、先の金栗四三に始まり、時代が進むごとに“主人公”をリレーしていくプロットは、一見、スター選手ばかりできらびやかには見えるけど、彼らはそれぞれの時代の象徴に過ぎず、物語を前に進める推進力に欠けるんですね。残念ながら、それだと日本の近代オリンピック史の“ドキュメンタリー”にしかならない。
オリンピックを日本で開催するまでの物語
では、原点に戻って、日本の近代オリンピック史にとって、物語を強力に前に進める推進力は何かと考えると――やはり、それは「オリンピックを日本で開催する」に尽きるんですね。
そう、嘉納治五郎が1909年にアジア初のIOC委員に就任して以来、そのゴールは、いつの日かオリンピックを日本で開催することだった。ならば、やはり嘉納を軸に物語を作るしかない。しかし、彼自身は戦前の1938年に志半ばで没する。そこで物語の後半は、そんな嘉納の遺志を受け継いだ者たちの群像劇になる。ゴールは1964年の東京オリンピックだ。
――これだ。これぞドラマのカタルシス。物語の中盤で一旦、奈落の底へと突き落され(東京オリンピック返上)、そこから這い上がり(戦後の復興)、幾多の苦難を乗り越え(招致活動)、ハッピーエンド(オリンピック開催)。そんなカタルシスたっぷりなドラマのキーパーソンの一人が、偶然にも氷川丸で嘉納治五郎の死を看取り、後にIOC総会で1964年の東京オリンピック招致を決定づける、名スピーチを披露した元外交官・平沢和重、その人である。
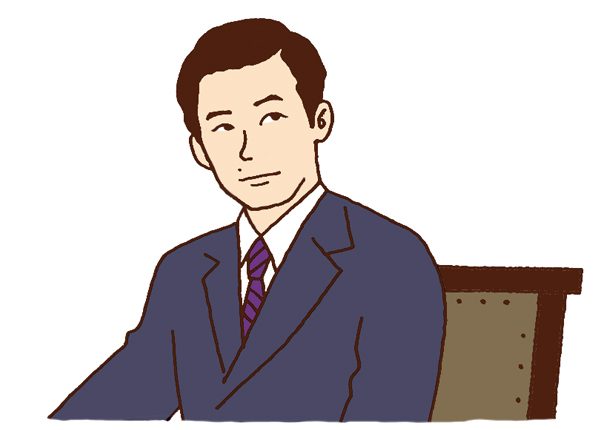
平沢氏の名スピーチ
そう、平沢和重。
時に1959年5月――ミュンヘンで開かれたIOC総会で、日本側の最終スピーチのプレゼンターとして登壇した彼は、こう紹介された。
「ただいま登壇した平沢和重氏は、かの嘉納治五郎先生の最期をみとった人物です」――その瞬間、各国のIOC委員たちは身を乗り出したという。IOCはいわば欧州の貴族たちのサロン。多くのメンバーは戦前から変わっておらず(←ここ重要)、嘉納は彼らにとって、かけがえのない友人だったからだ。
彼らを前に、平沢は流ちょうな英語でスピーチした。
「東京は極東(Far east)に位置しております。航空機の発達により“極”という文字は抹消されました。しかし、国際的な理解や人間関係については、この距離感は解消されておりません。IOC委員会の皆様、今こそオリンピック大会を、この五輪の紋章に表された第五の大陸、アジアに導くべきときじゃないでしょうか!」
沸き起こる拍手と喝さい――この瞬間、事実上、1964年の東京オリンピック招致は決まったと言っていい。そう、1940年に一度は潰えた夢を再び引き寄せたのは、平沢の名スピーチもさることながら、やはり彼の後ろに見え隠れする、嘉納治五郎の圧倒的な存在感だった。
東京オリンピックは戦後の奇跡ではなく“戦前からの悲願”
そう、『いだてん』で最も鍵となる部分は、この1940年の幻の東京オリンピックと、1964年の東京オリンピックを繋ぐ“ミッシングリンク”なんです。
一般に、僕ら戦後世代は、東京オリンピックを「戦後の奇跡」と教えられてきた。1945年の敗戦から、わずか19年で成し遂げた奇跡と――。
でも、本当は1909年の嘉納治五郎のIOC委員就任から掲げてきた「半世紀にも及ぶ悲願」だったんですね。その根底にあるのは、平和の祭典であるオリンピックを、いつの日か日本(東京)で開きたいという“志”――。
本来、『いだてん』が最も強調すべきポイントは、そこだったんです。それが、1909年から1964年までの半世紀にも及ぶ“大河”ドラマを描く理由だった。でも、残念ながら後述する諸般の事情で第1部の主人公が金栗四三になり、その辺りの物語の軸=カタルシスが希薄になったんです。
なぜ、金栗四三が主人公になったのか
大河ドラマとして、ストーリーテリング上の理想を言えば、主人公は嘉納治五郎を置いて他にない。でも、結果として一選手である金栗四三がその大役を務めることになった。なぜか?
――答えは、女優。
昨今の大河ドラマは、女性視聴者を意識して、またジェンダーへの配慮もあり、女性を主人公にしたり、あるいは主演男優と同格の女優(多くは妻役)を出すことがアンリトン・ルール(暗黙の了解)になっている。
それに従えば、第1話の時点で、50手前の初老で既婚者の嘉納治五郎が主人公だと、華のある20~30代の人気女優をキャスティングしにくいんです。
そう、大河の主人公は、若く、未婚であることが何より求められる。ある意味、国民的人気女優・綾瀬はるかを四三の妻・春野スヤにキャスティングするために、金栗四三が主人公に抜擢されたと言っても過言ではないのである。
遺志を受け継いだ者たち
話を嘉納治五郎の遺志を受け継いだ者たちに戻そう。もちろん、それは平沢だけじゃない。
戦後、日本体育協会会長やIOC委員などを歴任し、東京都知事として最前線で東京オリンピックの招致に尽力した東龍太郎は元より、『いだてん』では描かれなかったものの――私財を投じて中南米を歴訪し、各国IOC委員たちを“東京招致”へと説得して回った日系アメリカ人実業家、フレッド・イサム・ワダの功績も忘れてはならない。
政治家では、自民党の大物代議士・河野一郎が、戦前には1940年の東京オリンピック反対の急先鋒に立ちながら、戦後は一転、建設大臣として1964年の東京オリンピックの成功に尽力するという、ドラマチックなエピソードもある。
そして、なんと言っても『いだてん』第2部の主人公――朝日新聞記者の田畑政治の存在だろう。彼の場合、1932年のロス・オリンピックで水泳日本代表チームの総監督を務めており、戦前からオリンピックとの関りは深い。事実上、嘉納治五郎の遺志を継いだ筆頭格と言っていい。

第2部は群像劇が理想だった
ただ、理想を言えば、第2部の主人公は田畑に限定せず、フレッド・イサム・ワダも含めた、上記の複数人による群像劇がよかったと、個人的には思う。なぜなら、『いだてん』全体のバランスを眺めた時、あまりに戦前の話が長く、戦後が短すぎるからだ。
実際、放送では10月27日の第40回から、やっと戦後である。ここから最終回のオリンピック本番まで、わずか8話。この間、戦後の焼け野原からの復興があり、“フジヤマのトビウオ”こと古橋廣之進の登場があり、ロンドン五輪に対抗した“裏オリンピック”があり、東京五輪招致活動があり、鬼の大松の「東洋の魔女」引退騒動があり、平沢和重の名スピーチあり――etc
なぜ、これほどのエピソードがあるのに、戦後の話数が短かったか。
これはもう、主人公を田畑一人に特化したからですね。もちろん、彼はこの壮大な物語の最重要人物(キーマン)の1人だけど、彼自身が最も活躍したのは、弱冠33歳で水泳総監督に就任した1932年のロサンゼルス五輪。この時、日本競泳陣が獲得した金5・銀5・銅2の計12個のメダルは、当時の国別1位。そして、今なお日本が参加したオリンピック史上最多である。まーちゃん、凄い!
田畑主人公の副作用
――しかし、そこには副作用もあった。
田畑が主人公の『いだてん』第2部は、先の通り、このロス五輪が最も厚く作られた。第27話から31話までの計5話がそう。一方、田畑が本部役員に昇格して現場を離れたベルリン五輪は、わずか2話である。
その結果、何が起きたかと言うと、あの有名なベルリン五輪の「前畑がんばれ」が、本来なら83年前に金メダルを取ったのと同じ日――8月11日(2019年は日曜日だった)にオンエアできる千載一遇の機会だったのに――それを逸したのだ。せっかく、番宣等で盛り上がれるチャンスだったのに、オンエアされたのは、ロス五輪の男子・競泳陣だった。
オリンピックの政治利用の是非
また、1964年の東京オリンピックの聖火最終ランナーのエピソードも、田畑主人公の副作用か、若干ニュアンスが変えられた。
史実では、聖火最終ランナーを金栗四三や三段跳びの織田幹雄らレジェンドではなく、昭和20年8月6日に広島県で生まれた坂井義則青年にするプランは、自民党の河野一郎のアイデアだった。田畑は朝日新聞時代の同僚のよしみで、これをアシストしたのである。
だが、一方でこのプランは、当時マスコミから「オリンピックを政治利用するのか」と批判されたのも事実。ドラマでは田畑の発案とされ、彼の台詞「アメリカにおもねって、原爆に対する憎しみを口にしえない者は、世界平和に背を向ける卑怯者だ!」と美談仕立てにされたけど、コトはそう単純ではなかったのである。
本来なら、それは1940年の東京オリンピックの時から再三、田畑自身を悩ませてきたテーマ。もっと深く語られてもよかったと、個人的には思う。
『いだてん』の理想的なプロット
さて――色々と語ってきたが、ここらで僕の思う『いだてん』の理想的なプロットを示したいと思う。こうすれば、『いだてん』はもっと面白くなるはず――。
まず、スタートは1909年だ。物語は、嘉納治五郎がアジア初のIOC委員になるところから始まる。この辺りは、オリジナルの『いだてん』と変わらない。但し、主人公は金栗四三ではなく、嘉納治五郎である。そして、古今亭志ん生も登場しない。
翌年、嘉納は近代オリンピックの創始者にしてIOC会長であるクーベルタン男爵から、1912年に開催されるストックホルム五輪に日本も参加するよう、招待状を受け取る。そこで彼は思う――「いつの日か日本でもオリンピックを開催したい」と。壮大な大河ドラマの幕開けである。
嘉納目線+スター選手のリレー方式
そこからは、嘉納治五郎目線で物語が進みつつ、大会毎にその時々のスター選手にもスポットライトが当たる二重構造だ。
当然、ストックホルム大会では、日本人初のオリンピック選手である金栗四三が脚光を浴びる。続く1928年のアムステルダム大会では、日本人で初めて金メダルに輝いた陸上三段跳びの織田幹雄と、日本人初の女性オリンピック選手、人見絹江がクローズアップされる。36年のベルリン大会では、あの「前畑がんばれ」の前畑秀子のサクセス・ストーリーが描かれる。
そして同年――日本が初めてオリンピックに出場してから24年目、遂に嘉納治五郎悲願の1940年開催の「東京オリンピック」招致が実現する。それが第1部のクライマックスだ。しかし、不運にも時勢が悪化。嘉納は最後まで「平和の祭典」を願い続けながら、その77年に渡る生涯を閉じる。
本当の第2部
第2部は戦後のスタートだ。この部分は、オリジナルの『いだてん』とかなり異なる(オリジナルの2部は1924年のパリ五輪から)。そして、主人公は田畑政治に限定しない。田畑を筆頭に、東龍太郎、フレッド・イサム・ワダ、河野一郎、そして平沢和重――嘉納治五郎の遺志を受け継いだ者たちの群像劇となる。
そのフィナーレは、1964年の東京オリンピックの閉会式だ。今なお「史上最高の閉会式」の呼び声高い、五輪史上初めて選手たちが国籍や性別を越え、肩や腕を組んで国立競技場へ雪崩れ込んだという、あの閉会式。それまで整然と並んで入場するのが慣例だったオリンピックの閉会式が、いい意味で打ち破られた瞬間だった。
実はあれ、競技場の外で待ちくたびれた海外の選手たちの一部がお酒を飲んだ上でのハプニング。もしかしたら、終生オリンピックを「平和の祭典」と位置づけて疑わなかった、嘉納治五郎の魂が呼び寄せたイタズラだったのかもしれない――。
――ほら、嘉納治五郎を軸にすると、とてもシンプルなプロットに見えるでしょ? 「いつの日か、日本でオリンピックを開催する」という壮大なゴールに向かって、ひたすら人々が尽力する物語。これこそ、大きな歴史の流れ=いわゆる“大河”ドラマなんです。
『いだてん』の敗因は第1部
先に僕は、『いだてん』が犯した2つのミスとして、古今亭志ん生のパートを入れたこと、そして嘉納治五郎を主人公にしなかったことを挙げた。その2つを改善したのが、先に記したプロットである。
おっと、“ミス”という言い方は、あまりよくないかもしれない。「古今亭志ん生物語」の企画から始まって、様々な大人の事情や政治的な駆け引きもあり、現行の『いだてん』に落ち着いたのだ。それはそれで素晴らしい仕事だし、評価したい。ただ、僕が言いたいのは、返す返すも『いだてん』は、もっと面白くできたということ。少なくとも、第1部は――。
そう、第1部。金栗四三のパートですね。
思い起こせば、『いだてん』がSNS上で評価され始めたのって、第2部からなんです。阿部サダヲ演じる田畑政治編から。さもありなん、田畑編は先に示した理想のプロットと基本的なベクトルは同じ。嘉納治五郎の遺志を継いで、日本(東京)でオリンピックを開催するために関係者たちが尽力する物語。その構造は至ってシンプル。話をグイグイと前に進める推進力もあった。
第2部で減った志ん生パート
もっと言えば、第2部って、実は「古今亭志ん生パート」が第1部に比べて、相当減ったんですね。五輪パートと落語パートの比率は、第1部では3:2くらいだったのが、第2部では4:1くらいに差が開いた。それゆえ、ドラマとして、かなり見やすくなったんです。
もちろん、誤解してほしくないのは、何も「落語パートがつまらない」という話ではないこと。『いだてん』というドラマの理想のプロットとして、五輪と落語を並行して描くのは、やはり無理があった――それだけの話。現に、今でも僕は、クドカンさんの描く純粋な「古今亭志ん生物語」を心の底から見たいと思っている。
4つの話が“入れ子構造”になった第1部
実は、『いだてん』を絶賛してやまない映画評論家の町山智浩サンも、第1部で一度視聴を脱落したと、正直な心境を告白している。
仕方ない。だって第1部って、4つの話が入れ子構造になっていたのだもの。それは――
〇昭和30年代のオリンピック(田畑政治)の話
〇明治から大正にかけての金栗四三の話
〇昭和30年代の古今亭志ん生の話
〇明治から大正にかけての若き古今亭志ん生(孝蔵)の話
――と、まあ、これら4つの話が時空を超えて、行ったり来たりするものだから、熟練のクドカンファンでも、理解するのに相当苦労したはず。ましてや、お茶の間が理解するのは至難の業。「面白い・面白くない」以前に、僕はこの“入れ子構造”に、大半の視聴者はついていけなかったと思う。
予兆は『監獄のお姫さま』にあった
実はこれ、クドカンさんが『いだてん』を書く直前、TBSで書かれた連ドラ『監獄のお姫さま』に、既に予兆があったんですね。
あの話も過去と現在を行ったり来たりする話で、正直――分かりづらかった。視聴率もそれを裏付けるように、初回の9.8%が最高で、後は一度も上がることなく、全話一桁。まぁ、クドカンドラマは視聴率よりSNSで盛り上がると言うけど、正直、SNSもあまり盛り上がらなかった。
やっぱり、2つの時間を行き来する構造って、連ドラ向きじゃないんです。密閉空間で2時間集中して見続ける映画ならまだしも、スマホ片手に、生活音のするお茶の間で見るテレビドラマには向いていない。ましてや『いだてん・第1部』は、その時間軸の移動に加えて、「オリンピック」と「落語」という2つの物語の移動もあったワケで――混乱しないで見ろという方が、無理からぬ話である。
ディレクターズカット版を
NHKに1つ、お願いがある。
来年、1年延期された東京オリンピック・パラリンピックが成功裏に終わった暁には――よきタイミングで、『いだてん』のディレクターズカット版「オリンピック編」を放送してほしい。なぜなら、このまま埋もれさせるには、『いだてん・オリンピック編』はあまりに惜しいドラマだから。
それは、古今亭志ん生絡みの「落語」パートをそっくり削り、第1部をもう少し嘉納治五郎目線に寄せて、2クール――全20話くらいに再編集するというもの。
そもそも、『いだてん』に落語パートを入れたまま、最後まで貫き通したのは、「オリンピックのプロパガンダと思われたくない」というクドカンさんなりの意思表示だったと思うし、終わった後なら、気兼ねなく「オリンピック編」を再編集できるというもの。賭けてもいいけど、かなり面白くなると思う。
考えてくれませんかね、NHKさん。