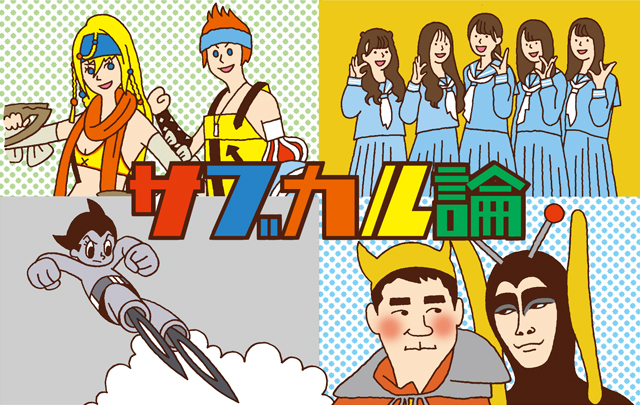例年2月に行われる世界最大の映画の祭典「アカデミー賞授賞式」。今年は新型コロナウイルスの影響で2ヶ月遅れの4月下旬の開催となった。
作品賞の栄冠は下馬評通り『ノマドランド』の頭上に輝いた。不況で家を失った一人の女性が家財道具を車に積み込み、ノマド(遊牧民)のように働き口を求めて全米を放浪するロードムービーだ。監督は中国出身のクロエ・ジャオ。彼女はアジア系女性として初の監督賞も受賞した。
他に目立った作品の1つに、ユン・ヨジョンが韓国の俳優で初めて助演女優賞を受賞した『ミナリ』もあった。韓国系アメリカ移民2世のリー・アイザック・チョン監督による自伝的作品で、1980年代、家族を連れて米アーカンソー州に移住した韓国系移民の苦難が描かれている。
そう、この2つとも「アジア系」の監督の作品である。アメリカは今、アジア系住民へのヘイトクライム問題があり、両作品がオスカーでフィーチャーされたのは、それなりに意味のあることかもしれない。近年、ハリウッドは“白すぎるオスカー”と、受賞者の白人偏重への批判回避から投票権を持つアカデミー会員の非白人率を増やしており、そうした多様性を求める流れも追い風になったのだろう。
外国作品で初めて作品賞を受賞した『パラサイト』
思えば、昨年の作品賞もアジア系監督の作品だった。そう、オスカー初の外国作品の受賞となった韓国映画の『パラサイト 半地下の家族』だ。監督は、韓国映画界のレジェンド、ポン・ジュノ。カンヌ映画祭でパルム・ドールを受賞し、その勢いのままオスカーもゲットした。韓国の社会問題に切り込みながら、物語にエンタテインメント性を持たせ、観客の間口を広げるのがポン・ジュノ監督のやり口である(褒めてます)。その辺り、“見られてナンボ”の韓国映画のスタンスが見えて、面白い。

国家ぐるみで「映画」を輸出する韓国
もっとも、『パラサイト』のカンヌやオスカーの受賞には、韓国の国家ぐるみの支援体制も働いたと聞く。韓国には「韓国映画振興委員会(略称:KOFIC)」なる国内の映画製作をサポートする国の機関があり、年間約4,000ウォン(日本円で約400億円)もの予算が組まれている。特筆すべきは、制作費の助成だけでなく、脚本作りから配給、海外への広報活動まで国家ぐるみで手厚くサポートしてくれること。海外の映画祭における受賞は、そうした国の支援抜きには語れないという。
ちなみに、韓国では韓流ドラマやK-POPにも国家ぐるみの助成制度がある。そちらは「韓国コンテンツ振興院(略称:KOCCA)」が担当し、映画の支援と同様、制作費の助成や海外への売り込みもサポートしてくれる。背景に、人口約5,000万人の韓国はどうしても国内市場が小さく、日本や北米、東南アジアなど海外で稼がざるを得ない切実な状況もある(かつての『冬のソナタ』に代表される日本における韓流ドラマブームもそうした成果の1つ)。
そこでカギになるのが、海外でもウケる、普遍的かつ高いクオリティのコンテンツ作りである。例えば、今や世界的に活躍するBTS を始めとするK-POP グループ――彼らは、そのためにデビュー前に長期に渡る厳しい選考やレッスンが課せられる。しかし、投資から回収まで相当な時間がかかるため、一プロダクションの財力では賄いきれず、国の支援を受ける。そう、K-POPの卓越したパフォーマンスは、国家の手厚いサポートあってのものなのだ。
日本のコンテンツは世界で戦えない?
――という話をすると、「じゃあ日本はどうなんだ」という声が上がる。今回のアカデミー賞でもそうだったが、よく話題になる。日本の映画やドラマ、音楽が世界市場で戦えないのは、国の支援が足りないからでは?――と。
結論から言えば、映画に限れば日本も国からの助成はあるにはある。是枝裕和監督が『万引き家族』でカンヌのパルム・ドールを受賞した際にも明かしたように、文化庁が毎年20作品ほどに、約10億円の年間予算から制作費を助成している。とはいえ、韓国のように海外の映画祭に売り込むなどのサポート体制はない。お金を出して終わり。
あと、海外へ売り込む国の施策としては、官民ファンドで設立された「クールジャパン機構」も一応ある。ただ、あれはエンタメ分野に限らず、商品や地方自治体の観光事業など扱う対象が幅広く、それも個別の案件を売り込むというよりは、外国における日本の観光・商業施設などのプラットフォーム支援がメイン。過度な期待はできない。
もっとも、助成制度があるだけ映画はマシ。他方、テレビドラマや音楽業界にその種の国の支援はない。現状、日本の民放ドラマはスポンサーの広告費で作られ、放送もネット配信も、国内の流通がメイン。海外展開はあくまでオプション。なので、制作費のバジェットが限られ、大作が生まれにくい。結果的に、海外展開も難しいという負の連鎖に陥っている。
また、音楽業界で言えば、日本のアイドル市場は初めから完成品を提供する韓国のK-POPと異なり、その成長過程もファンに楽しんでもらうビジネスモデルになっている。これは、70年代に日本にアイドルビジネスが確立された時からそう。つまり、ある種の育成型のロールプレイングゲーム感が、日本のアイドル市場の特徴である。そのために、ファンとの繋がりも握手会などの“会いに行ける”ローカライズが基本。遠く離れた海外展開は難しい。唯一、AKB48グループが「フォーマット」を海外へ輸出しているくらい――。
でも、僕は、日本はそれでいいと思う。少々前置きが長くなったが、その理由が、これから述べる今回のテーマ「サブカル論」である。まずはその前編から進めていこう。
フランスの“オタク”たちが集結するイベント
フランスのパリでは毎年7月、「ジャパン・エキスポ」なる日本のポップカルチャー(漫画・アニメ・ゲーム・アイドル・音楽・ファッション、グルメなど)を紹介する見本市が開催される。2000年に日本のアニメ好きの3人のフランスの若者によって創設され、回を重ねるごとに規模を拡大。今や4日間で25万人もの来場者を集めるビッグ・イベントに成長した。
元々は、日本のコミケのような同好の士のための催しだったが、そのうち日本の出版社やレコード会社、ゲーム会社、ファッションブランドなどの企業も参加するようになり、今では日本から漫画家やアイドル、ミュージシャンやモデルらが渡仏し、サイン会やライブ、ファッションショーなどが頻繁に開かれている。
ちなみに、YOSHIKIは同イベントの常連ゲストで、アイドル枠ではAKB48や乃木坂46も過去に参加したことがある。面白いのは、ゲストの中でも漫画家やアニメ作家、声優陣らは特に反響が大きく、これまで永井豪や浦沢直樹、富野由悠季監督、声優の岩男潤子ら多くのレジェンドたちが招かれ、トークショーやサイン会で大いに盛り上がったという。
そんなお祭りには、フランスの“オタク”たちが集結する。彼らの中には、日本のコミケ同様、アニメやゲームのキャラに扮したコスプレイヤーも少なくない。会場のそこかしこに、ナルトやジョジョ、綾波レイやキキが普通にいて、そのクオリティも相当高い。むしろ普段着でいる方が違和感を覚えるほど――。

フランスのキッズたちがハマったジャパニメーション
それにしても、なぜフランスに日本のポップカルチャーのマーケットが普通に存在しているのか?
――実は、かつて1970年代後半から80年代にかけて、ヨーロッパに日本のアニメが大量に輸出されたという歴史的背景があるんですね。その際、最大の輸入元だったのがフランス。国営放送では毎週、ゴールデンタイムに『UFOロボ・グレンダイザー』を始め、『キャンディキャンディ』、『ドラゴンボール』、『聖闘士星矢』、『シティーハンター』、『セーラームーン』等々が放送されたんです。
そして、それらの作品は“ジャパニメーション”と呼ばれ、フランスのキッズたちの間で大人気を博したと。中には、視聴率が70%(!)を超える作品もあったとか。それを起点に、フランスの少年少女たちは日本のマンガやゲーム、アイドル、ファッションなどにも興味を持ち、やがて彼らが大人になり、日本のポップカルチャー好きの“オタク”を大量に輩出したという次第――。
かくして、「OTAKU」は今や国際用語となり、先に記したジャパン・エキスポを創設した3人の若者も、そうしたムーブメントから出てきたんです。
『ハイジ』をスイス製と勘違いした欧州人たち
いや、何も“オタク”の存在は、フランスに止まらない。アメリカではもっと昔、1960年代後半から日本のアニメ――『鉄腕アトム』や『エイトマン』、『マッハGoGoGo』などが輸出され、一定のオタク市場を形成してきた歴史を持つ。彼らが80年代半ば、タカラ(現・タカラトミー)の商品から派生した変形ロボット『トランスフォーマー』に熱狂し、米国でアニメ化した作品を日本に逆輸入させたという武勇伝もあるほどだ。そうそう、子供時代に『マッハGoGoGo』にハマったウォシャウスキー姉妹が、大人になって映画『スピード・レーサー』を作ったのも有名な話――。
また、欧州各国も先に記した通り、70年代後半から日本のアニメが大量に輸入された歴史を持つ。中でも、『アルプスの少女ハイジ』は欧州が舞台ということもあり、各国で大人気。面白いのは、あちらの人々はハイジを舞台となったスイス本国で作られたアニメと勘違いしたんですね。つまり、それくらいディテールがリアルだったと。実際、かつて高畑勲サンや宮崎駿サンらは制作に入る前、一ヶ月に渡ってスイスやドイツをロケハンして回ったそうで、その努力は無駄ではなかったのである。
世界のスーパープレイを生んだ『キャプ翼』
もっと驚く話がある。
80年代半ば、欧州各国で『キャプテン翼』が放映されたんだけど、各国のキッズたちが同作に影響を受け、サッカーを始めたんですね。まぁ、それ自体はよくある話だけど、その後、大人になった彼らがどうなったかというと――フランスでジダンになり、アンリになり、イタリアでデル・ピエロになり、トッティになり、スペインでイニエスタになったんです。
もっと言えば、アルゼンチンのメッシも、コロンビアのロドリゲスも、ブラジルのカカもロナウジーニョもネイマールも、子供の頃に見た『キャプ翼』に影響を受け、サッカーを始めたと公言しており、つまり――世界のスーパープレイは、『キャプテン翼』が生んだとも言えるんですね(ドヤ顔)。
日本とサウジアラビアを橋渡しした『グレンダイザー』
そうそう、世界に影響を与えた日本のアニメと言えば、もう1つ『UFOロボ・グレンダイザー』もある。少し前、サウジアラビアに日本の大使として赴任した外務省の岩井文男サンが、ツイッターで自身の奥さんを『ウム・コウジ』と紹介したところ、現地の人々から喝さいを浴びたニュースって、覚えてません?
ちなみに、アラビア語で「ウム」とは母親のことで、「コウジ」は岩井大使の息子さんの名前。つまり、岩井大使は奥さんを「コウジの母」と紹介したんだけど、この一見、なんてことない言葉がサウジアラビアでは特別な意味を持つんですね。
種を明かすと、サウジアラビアを始めとする中東諸国でも日本のアニメは80年代から盛んに放送され、中でも人気を博したのが『UFOロボ・グレンダイザー』だったんです。日本では『マジンガーZ』から始まるシリーズ3作目で、若干影が薄い印象だけど、海外では絶大な人気。で、その登場人物の1人が、かつてマジンガーZを操縦した兜甲児だったというワケ。つまり、「コウジ」はサウジの人々にとって親しみ深い日本人の名前。要は、アニメを通じて日本とサウジの外交関係が良好になったという、そんな話なんです。
世界で戦える日本のアニメの強みとは?
つまり――ここまで長々と語ってきたが、何が言いたいのかというと、よく日本の映画やドラマ、音楽は世界市場で戦えないと言われるけど、こと「アニメ」に限っては、1970年代の終わりから世界中に輸出され、かなり爪あとを残したんですね。それも、国のバックアップなどなく、アニメ制作会社やテレビ局が独力でやって――。
ちなみに、一般社団法人日本動画協会が毎年発表している「アニメ産業レポート」の最新版(2020年版)によると、日本の2019年のアニメ市場は約2兆5,000億円と、過去最高を更新したそう。このうち海外で稼いだ分は約1兆2000億円と、全体のおよそ半分。そう、今も日本のアニメは世界市場で絶好調なんです。それにしても――なぜ日本のアニメは海外でこんなにも強いのか?
理由は大きく2つあります。1つは、海外へ輸出し始めた1970~80年代当時、とにかく日本のアニメは放映権料が安かったんです。だから、コンテンツ不足に悩む海外のテレビ局が飛びついたと。彼らは「日本のアニメだから」ではなく、単純に安かったから放映権を買ったんですね。
まぁ、これは功罪両面あって、後で詳しく述べるけど、漫画の神様・手塚治虫先生のせいでもあるんです(笑)。ただ、安いお陰で、結果的に大量の日本のアニメが海外に拡散されたワケで、それはそれで一定の効果があったのは確か。
もう1つは――実はこっちの方が大事なんだけど、日本のアニメはバリエーションが豊か、つまり作品に多様性があるんですね。おまけにクオリティも高く、表現も自由。要するに、海外の人たちから見て、シンプルに“面白い”んです。
世界のアニメと日本のアニメの違い
そう、バリエーションが豊かで、面白い。これが日本のアニメの最大の強み。で、ここからの話が、いよいよ今回のテーマ「サブカル論」の根幹に関わってきます。
先に僕は、韓国は国内市場が小さいから、世界市場を見据えて、映画も音楽も普遍的でクオリティの高いコンテンツを作っていると書いた。それは、マーケット的に極めて正しい方法論だし、現にアメリカのハリウッド作品も同じ戦略で作られている。ディズニーやピクサーが作るアニメ映画もそう。だから国境や宗教を越えて、世界中でヒットする。
でも――それは反面、極めて高い表現のハードルも課せられるんですね。人種や宗教への配慮はもちろん(例えば、ハリウッドのチームものの作品なら、黒人やアジア人も登場させないといけないとか)、今ならLGBTにも目を配らないといけないだろう。過激な性描写や暴力シーンもNG。ストーリーも自ずと全世界が共感できるシンプルなものになりがちで、時に戦争や政治への骨太なメッセージも要求される。
一方、日本のアニメは、その真逆の方法論で作られる。まず、日本のアニメは漫画原作が多いため、基本的には「少年ジャンプ」を頂点とする巨大な漫画市場のユーザー向けに制作される。つまり、国内向けだ。馴染み客がメインなので、人種やLGBTへの配慮もそこまで気にしなくていいし(もちろん差別的な表現はNG)、良くも悪くも性描写や暴力シーンの規制もユルい。『鬼滅の刃』にしても、あれだけ子供たちの間でヒットしながら、意外と残酷なシーンが多かったりする。実際、劇場版は北米公開の際、「R指定(17歳未満の観賞は保護者の同伴が必要)」を受けたほど。
そうした日本の現状を「ガラパゴス」と批判する識者たちもいる。日本のアニメはもっと世界市場を見据えて、表現やテーマをグローバル化すべきだと。まぁ、言わんとするところは分からないではないけど、その種の意見に対して、当の海外の日本のアニメオタクたちはどう反応しているかというと「冗談じゃない。日本のアニメは日本国内向けに作っているから面白いんだ。余計なことをするな」と一蹴してるんですね(笑)。
これは一体、どういうことか。
メイド・イン・ジャパンの強み
要するに――日本のアニメの強さは、国内向けに作られるゆえに規制がユルく、作り手が純粋に「面白さ」を追求できるところにあるんです。結果、多様な作品が育まれ、冒険モノから、学園ラブコメ、スポ根、ギャグ、アクション、SF、ロボット、刑事、時代劇、医者、料理人、もののけ――と、何でもあり。この多様さは、ディズニーもピクサーも真似できない。
つまり、日本のローカライズなルールで作られたものが、たまたま海外に輸出され、ジャンルの多様性とシンプルな面白さに現地の人々がハマった。これが日本のアニメが海外で支持される構図なんです。例えて言えば、混沌とした陳列と、掘り出し物を探す楽しみがある雑貨書店「ヴィレッジヴァンガード」みたいなもの。一方のディズニー作品は、国際規格を満たした商品が整然と並ぶショッピングモールと言えば、分かりやすいだろうか。
そう、メイド・イン・ジャパンの強みは、サブカル――。堂々と世界に打って出るメインカルチャーではなく、いわば肉屋の片隅で売られるコロッケみたいなもの。一見、脇役の扱いだけど、実はそれ目当てに来店するファンも少なくないというアレである。
日本のアイドルを愛でる海外のオタクたち
そんな構図は、日本のアイドル市場にも当てはまる。
実は、日本は世界に誇るアイドル先進国。海外でアイドルと言えば、2002年に始まり、各国にフォーマットが輸出されたことでも知られるリアリティショー『アメリカン・アイドル』が有名だけど、素人の歌手志望者がオーディションにエントリーして、審査を勝ち抜いてデビューするフォーマットは、日本では1971年に日本テレビが『スター誕生!』として、とっくに番組化していたんですね。なんとアメリカより30年も早かった。
その後も、1985年にフジテレビが『夕やけニャンニャン』の番組内オーディションから「おニャン子クラブ」を結成したり、1997年にはテレビ東京の『ASAYAN』のオーディション企画の落選者から「モーニング娘。」がデビューしたり、2005年には秋葉原を拠点とした究極のローカルアイドル「AKB48」が誕生したり――と、日本のアイドルは着実に進化してきた。
先に僕は、日本のアイドルはローカライズが売りなので、海外展開は不利と書いた。でも、一方でテレ東の『YOUは何しに日本へ?』には、しばしば欧米からAKB48の握手会に参加するために来日した熱心な外国人ファンが登場する。ネットの時代になり、国内外の情報格差がなくなったのと、ローカライズゆえの日本のアイドルの“深み”に、逆に外国人ファンがハマったのである。
意外なところでは、香港の民主活動家の周庭サンも、そんな日本のアニメやアイドルに惹かれ、「オタク」を自称する一人。彼女は、昨年秋に収監された際も、欅坂46の『不協和音』の歌詞に励まされたと語っていたほど。現在、再び収監中で、1日も早い釈放を願うばかりである。
日本のアイドルには“ストーリー”がある
では、日本のアイドルの何が、外国人をそれほどハマらせるのか。僕は――それは“ストーリー”の力だと思う。
分かりやすい例に、あのモーニング娘。がいる。先にも述べた通り、彼女たちは、『ASAYAN』のオーディション企画「シャ乱Qロックヴォーカリストオーディション」の落選者から選ばれた。この“落選者”がミソで、オーディション自体は平家みちよがグランプリを獲り、武道館デビューを果たした。いきなり武道館だ。それは凄い。でも――お客はそっちよりも、“敗者復活戦”の方に惹かれたんですね。
そう、平家みちよが武道館デビューする一方、モーニング娘。の5人に課せられたのは、インディーズのCDシングル「愛の種」を5日間で5万枚、手売りで完売すれば、メジャーデビューできるというミッション。彼女たちは年齢も容姿もバラバラ(最年長の中澤裕子が24歳、最年少の福田明日香が12歳)。いかにも寄せ集めの感じがしたが、逆にそれが非予定調和に映り、日本人の判官贔屓も働いて課題をクリア。メジャーデビューを勝ち取り、今日に至るのである。
一方の平家サンは、新人離れした歌唱力と表現力を持ちながら、人気がハネることなく、次第にフェードアウト。教訓、日本のアイドルが成功するために大事なのは、パフォーマンスの完成度よりも、ストーリーなのだ。
二軍からワンチャンスで駆け上がった日向坂46
今なら、あの「日向坂46」にも、同様のストーリーを感じる。
元々、彼女たちは、先輩グループの「欅坂46」に遅れて加入した長濱ねるのために作られたアンダーグループ(早い話が二軍)だった。それゆえ「けやき坂46(ひらがなけやき)」と呼ばれ、ほとんど活躍の場が与えられなかった。握手会を催しても、長蛇の列の「欅坂」の隣で閑古鳥状態――。
だが、好機は意外なところからやってくる。2018年1月、平手友梨奈のケガで欅坂46の武道館公演に穴が開くピンチが訪れた際、急遽、その穴埋めに「ひらがなけやき」の武道館3DAYSが決定する。デビュー前のグループには荷が重すぎる大役だったが、彼女たちは見事にこのミッションを成功させる。それを機にデビューアルバムのリリースも決まり、欅坂46の2軍から独立して正式なグループへ昇格する。そして2019年2月には「日向坂46」へ改名し、今に至るのである。

もちろん、日向坂46は実力の上でも申し分ない。例えば、オードリーがMCを務めるテレビ東京の『日向坂で会いましょう』で見せるトークスキルの高さは、アイドル界随一と、他局のテレビマンたちからも賞賛されるほど。しかし、やはり彼女たちの現在の地位を作り上げたのは、二軍のどん底から這い上がったサクセスストーリーに「おひさま」と呼ばれるファンがどハマりしたからである。
ひろゆきの「アイドル=キャラクター」論
そうそう、あの「2ちゃんねる」開設者のひろゆき(西村博之)サンが、かつてアイドルについて論じた定義が面白かったので、この場を借りて紹介したいと思う。
「僕はアイドルに恋人がいるって許せない派です。アーティストとかであれば恋人がいようが全然いいんだけど、能力がある人って『歌手』とか『ダンサー』とか『役者』とか能力に対する肩書きがつく。一方、アイドルって能力ではなくてキャラクターに対する肩書きで、アイドルというキャラクターは恋人がいないのが前提だと僕は思っている。なので、恋人を持つんだったらその肩書きは使っちゃダメですよ、って思っています」。
――どうだろう、「アイドルとはキャラクターに対する肩書き」。なかなか的を射た考察だと思いません? これ、先に述べた「ストーリー」ともリンクする話なんですね。要は、魅力的なキャラクターって、背後にストーリーがあるんです。なぜ、ディズニーランドのキャラクターに日本人が感情移入できるかというと、ちゃんとバックストーリーがあるからなんですね。日本のアイドルもこれと同じ。
そう――つまり、音楽におけるメインカルチャーを“世界で戦えるパフォーマンス力や高い歌唱力”とするなら、たとえばK-POPは純粋にその線上で勝負している。評価の基準は技巧の優劣や芸術性だ。一方、日本のアイドルは、ストーリーやキャラクターといった、いわば“サブカル”をウリにする。人気の指標は、どれだけ共感を集められるか。その点において、日本のアイドルは世界で唯一無二の存在なんです。
日本のサブカルを支える潤沢な国内市場
さて――この「サブカル論・前編」も、いよいよ佳境に入ってきた。ここからは、そんなサブカル天国・日本がいかにして生まれ、育まれたか。そんな核心部分に迫りたいと思います。
まず、日本の“サブカル”を支えるのは、圧倒的に分厚い国内マーケットなんですね。ここが、韓国との分岐点でもあるところ。ちなみに、日本の総人口は1億2600万人だけど、俗に世界には人口1億人以上の国を指す「1億人クラブ」が12ヶ国ある。多い方から順に、中国、インド、アメリカ、インドネシア、ブラジル、パキスタン、ナイジェリア、バングラディシュ、ロシア、日本、メキシコ、そしてフィリピン――。
お気づきだろうか。この12ヶ国のうち、IMF(国際通貨基金)の定める「先進国」に該当するのは、アメリカと日本の2ヶ国だけ。後は「中所得国」か「発展途上国」なんですね。つまり、日本はアメリカと並んで、そこそこ裕福な国民を1億人以上も抱える、極めて恵まれた国内市場を持つんです。
ただ、ことエンタメ事業に関しては、日米の戦略は分かれます。アメリカは国内市場をベースとしつつも、世界で商売する道を選択。一方、日本は国内で賄う道を選んだと。つまり、前者は国際規格という非常に高いハードルが課せられる反面、リターンも大きい。ゆえに作品に巨額の制作費を投じることが可能に。対する後者は、作品の自由度は高いが、ローリスクローリタンゆえに制作費も大きくハネないと。
かくして、アメリカではハリウッド映画やネットフリックスのドラマなどの“大作”が世界を席巻、一方の日本は比較的低予算で回せるアニメやアイドル市場で国内外のオタクたちのハートを掴むと――。
サブカルの扉を開けた『鉄腕アトム』
ここから先の話は長くない。
そんなサブカル天国・日本が生まれるエポックメーキングとなった作品をご存知です? そう、言わずと知れた漫画の神様――手塚治虫が手掛けた日本初の本格的連続テレビアニメ『鉄腕アトム』である。

時に1963年1月1日――漫画の神様が経営するアニメ制作会社「虫プロダクション」により、その扉は開かれたんです。初回視聴率は29.5%。春には40%の大台に乗り、アトムは日本中に大旋風を巻き起こした。あまりの人気に、当初予定の26話を大幅延長し、4年間に渡って全210話も放送されたほど――。
いや、アトムの登場は、何も日本のテレビアニメの扉を開けたことに止まらない。今日、繁栄を誇る日本のサブカル史においても、エポックメーキングな事件として記憶されるんです。そう、アニメ版のアトムは日本初のサブカル作品とも言えるのだ。
なぜ、アトムがサブカル?
それは、手塚先生がアトムをアニメ化する際に語った言葉に表れている。「僕は、ディズニーを目標にしていません」――幼少期からずっとディズニーに憧れてきた先生が、目標はディズニーではないという。どういうことか。
その答えが、「リミテッド・アニメーション」なんですね。リミテッドとは「限定」の意。要は、滑らかな動きを見せるフル・アニメーションのディズニー作品が1秒あたり12枚のセル画を使用するのに対して、8枚のセル画で済ます簡易版のアニメのこと。滑らかさは若干劣るが、不自然ではない。
いや、それだけじゃない。キャラクターを固定して、口や目だけを動かしたり、大きな背景を描いて、その中でキャラクターを動かしたり――。極端な話、カメラさえ動かせば、止まっている絵でも画面上は動いているように見える。それら全てを総称して、漫画の神様は「リミテッド・アニメーション」とうそぶいたんですね。
「ディズニーの作品は、一言でいえば、絵ばなしです。あまりに児童文学的です。僕はディズニーを足場にして、内容的に、もう一歩超える自信がある」
――とはいえ、それは手塚先生一流のレトリックだったんです。要は、現実問題として、毎週30分のアニメを放送するには、ディズニーのような丁寧な仕事をやってたら、スケジュールが追い付かない。そこで、「リミテッド・アニメーション」と大上段に構えつつ、その実、作業の簡素化を図ったんですね。でも、その分、ストーリーや人物描写、構図などでクリエイティブを見せるという、手塚先生なりの勝算があったのは確かなんです。
実際、アニメ版のアトムはスピーディーな動きや斬新な構図、そして人類に警鐘を与えるストーリーの深みなど、子供だけでなく、大人も虜にしたんですね。だから視聴率が40%も取れたし、アメリカに輸出されて、あちらでも大人気を博したんです。まさに、フル・アニメーションに引けを取らない、リミテッド・アニメーション=サブカルの本領発揮と。
60~70年代に日本のアニメが量産された理由
そして、アトムが開いた日本流のリミテッド・アニメーション(サブカル)の扉は、60~70年代、カンブリア紀の大爆発のごとく、多様な作品を輩出するんです。――『鉄人28号』、『エイトマン』、『ジャングル大帝』、『オバケのQ太郎』、『魔法使いサリー』、『おそ松くん』、『黄金バット』、『マッハGoGoGo』、『リボンの騎士』、『巨人の星』、『ひみつのアッコちゃん』、『サザエさん』、『ムーミン』、『みなしごハッチ』、『あしたのジョー』、『いなかっぺ大将』、『ルパン三世』、『天才バカボン』、『科学忍者隊ガッチャマン』、『デビルマン』、『ど根性ガエル』、『マジンガーZ』、『エースをねらえ』、『宇宙戦艦ヤマト』、『アルプスの少女ハイジ』、『銀河鉄道999』、『ドラえもん』、『機動戦士ガンダム』――etc…
壮観だ。なぜ、こんなにも多様な名作が、アニメ黎明期に次々と生まれたのか? 皆、手塚先生の敷いたレールに乗ったからなんですね。それはレール同様、2つあって、1つが前述の「リミテッド・アニメーション」。絵の完成度はフル・アニメーションに劣るものの、その分、構図やストーリー、キャラの造詣などにクオリティを発揮し、作品を面白く仕上げるというもの。そして、もう1つが――なんと「低予算」だったんです。
そう、低予算――アニメ史における手塚先生の“功罪”である。アトムの放映時、先生は広告代理店が示した1話あたりの制作費150万円を断り、なんと「55万円でいい」と自ら値切ってみせたんですね。代わりに、虫プロが著作権を持ち、赤字分はグッズなどのロイヤリティーや海外への輸出で補うというのが先生なりの算段だった。単価を下げることで、虫プロが受注する仕事を増やす狙いもあったと言われる。
だが――これは悪しき前例となり、その後のアニメ業界を長く苦しめることになったのも事実。実際、あの宮崎駿監督は、手塚サンが亡くなった時の追悼文でこの件に触れるなど、相当根に持っていたほど。
とはいえ、その一方でアニメは低予算だから企画が通りやすいという副作用も、この時代に生まれたんですね。多くの名作が日の目を見たのは、そういう背景もあったんです。そう、先にも触れたように70年代後半、海外へ安く輸出できたのも、低予算で作られたお陰――。結果的に、世界中に日本のアニメが拡散され、今日のジャパニメーションブームを育んだ歴史を思えば、制作費を値切った手塚先生の判断は、功罪相半ばするとしか言いようがないんです。
バラエティの覚醒
さて、ここまで長らくアニメとアイドルを軸に、日本のサブカル史について解説してきたが、実はもう1つ、日本のサブカルを語る際に外せないジャンルがある。――「バラエティ番組」だ。
よく「日本ほど、テレビでバラエティ番組が放映される国もない」と言われる。事実、バラエティテイストの情報番組まで含めると、日本の地上波のテレビ番組の実に7割近くがバラエティになる。
また、これもよく言われることだけど、「日本のバラエティ番組は海外では通用しない」と言われる。ある意味、正しいだろう。フォーマットがしっかりしている海外のリアリティショーと異なり、日本の場合、『アメトーーク』(テレビ朝日系)や『水曜日のダウンタウン』(TBS系)、『有吉の壁』(日本テレビ系)など、お笑い芸人のパーソナリティーで成り立っている番組が多く、フォーマットを売るという概念から遠い。
――とはいえ、こちらもアニメ同様、日本のバラエティがたまらなく好きという外国人がいるのも事実なんですね。実際、先に紹介した香港の民主活動家の周庭サンも、日本のアニメとアイドル好きに加えて、日本のバラエティ番組好きを公言する一人。なんと彼女は「日本のバラエティから多くの日本語を学んだ」とまで言ってのけるんです。
日本のバラエティの特徴は、お笑い芸人の層の厚さと、彼らのトークスキルの高さ、そしてネタの繊細さである。売れている芸人の多くは、アドリブに長けている。どんな番組でも、芸人さえ仕込んでおけば、彼らがなんとかしてくれる。そんな変幻自在なトークスキルを持ったコメディアンは、海外ではなかなか見かけないんですね。
だが――日本の芸人が、昔からアドリブに優れていたワケではない。そこにも、禁断の扉を開けた偉大なるレジェンドがいるんです。思うに――それは、1981年から89年まで放送された、日本のバラエティ史に燦然と輝く『オレたちひょうきん族』(フジテレビ系)ではないだろうか。

かの番組の登場で、日本のバラエティ番組やお笑い芸人がどう進化したのか。ひいては1990年代以降、NHKを含む日本のテレビ局全体がフジテレビ化し、あらゆる番組がバラエティ化に進んだ背景に何があったのか――。
この続きは、次回の「サブカル論・後編」で存分に語りたいと思います。それまで、しばしお待ちを――。
(イラスト:高田真弓)