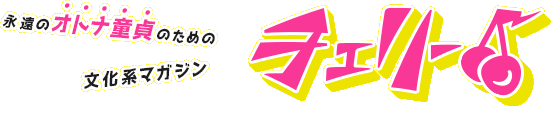世界のコンテンツ市場の話にはじまり、日本のアニメ・アイドルなどの“強み”を存分に論じた『サブカル論(前編)』。あれから4年。待望の後編は、バラエティ番組の歴史を遡ります。指南役さんの指摘する「日本のテレビ局全体のフジテレビ化」とは――!? 前編はこちら
以前、日本テレビ系で『おしゃれイズム』が放映されていた頃の話である。
その日のゲストは、お笑いコンビのジャルジャル(後藤淳平・福徳秀介)だった。意外なことに――終始、2人は緊張していた。ふと僕は、こんな風に2人が平場(フリートークの場)で話すシチュエーションをあまり見たことがないのに気が付いた。大体、テレビで見かけるジャルジャルは、ネタ見せ番組でコントを演じているか――かつての『めちゃイケ』だった(ちなみに、めちゃイケは99%台本である)。ひな壇に座り、他の芸人たちと気ままにトークに興じる姿は正直、あまり記憶にない。
よく、お笑い芸人は2度売れないといけないと言われる。1度目は、『M-1グランプリ』(テレビ朝日系)等、いわゆるコンテストもので爪あとを残すこと。2度目は、テレビのバラエティ番組でトーク芸人としてハネることである。サンドウィッチマンはM-1の覇者だけど、今も彼らがテレビの第一線で活躍し続けるのは、トーク芸人としてハネたからである。かまいたちも同様だ。M-1では惜しくも最終決戦でミルクボーイに敗れたけど、それをキッカケに様々な番組に呼ばれるうち――トークで売れたからである。反対に、優勝したミルクボーイは今のところ、少なくともトーク芸人としてはハネていない(もちろん、ステージでは大人気。テレビが主戦場じゃないだけ)。
冒頭の話に戻るけど、ジャルジャルはお笑いコンビとして、実力は誰もが認めるところ。要は、テレビでトーク芸人としてハネる道を選択しなかったというだけの話。その分、ライブやYouTubeで“コント芸”を磨き続けた結果、そっち方面の評価はすごく高い。とはいえ、ファン以外に彼らの活躍が見えにくいのも事実である。
実は、“トーク芸人”というカテゴリーは日本独自のもの。外国には存在しない。あちらのコメディアンは、映画やドラマで“喜劇”(芝居)を演じるか、舞台でスタンドアップコメディ(話芸)を披露するのが一般的。どちらも台本があり、いかにそれをアドリブっぽく演じられるかが、プロのテクニックとされる。台本も専業の作家が書くことが多い(←ココ重要)。
こんな話がある。
その昔、日本テレビで『巨泉×前武ゲバゲバ90分!』というバラエティ番組があった。もう半世紀以上前の番組だ。90分間に150本ものショートコントのVTRを流し、その幕間に2人の司会者――大橋巨泉と前田武彦が生放送でトークに興じる構成だった。実は、この番組には元ネタがあり、米NBCの番組『ローワンとマーティンのラフ・イン』がそう。矢継ぎ早にショートコントを流して、その幕間にダン・ローワンとディック・マーティンの司会者2人による軽妙な生トーク。フォーマットはまるで同じだった。今なら、『ゲバゲバ』はパクリと言われちゃうけど、草創期の日本のテレビ界は結構、この手の話が多かったんです。良くも悪くもユルい時代だった。
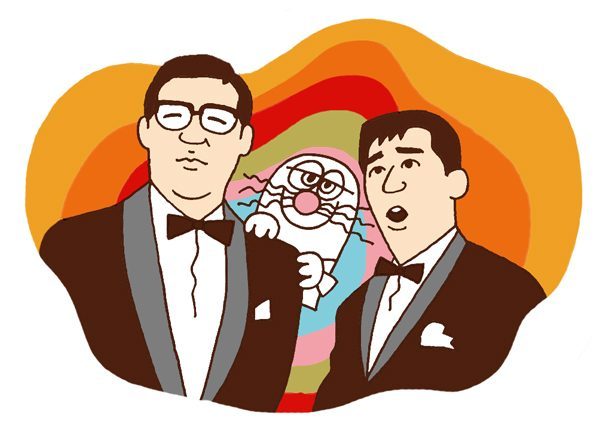
そんな『ゲバゲバ90分』の記念すべき第1回放送――。数本のショートコントのVTRが流れ、突然カメラが生放送のスタジオに切り替わった。大橋巨泉と前田武彦が生でトークに興じるパートである。とはいえ、実は2人のやりとりには台本があり、この時は巨泉サンのひと言で前武サンがギャフンとなるオチだった。だが、これに前武サンが咄嗟のアドリブでやり返す。スタジオは大爆笑。そのままCMへ――。その時である。CM中に副調整室(ディレクターのいる部屋)からスピーカーを通じて、スタジオ全体に怒鳴り声が鳴り響いた。
「バカ野郎!ここはフジテレビじゃない!」
声の主は、同番組の総合演出(よーするに番組で一番偉い人)の井原高忠サン。知る人ぞ知る、日本のバラエティ番組の礎を築いたレジェンドである。井原サンが怒ったのは、前武サンがアドリブを入れたから。前武サンは当時、フジテレビの『夜のヒットスタジオ』の司会が好評で、生放送の同番組はアドリブが自由だった。軽妙洒脱なフリートークは彼の真骨頂。平常運転のつもりだった(※日本のテレビ史における元祖フリートークタレントが前武サンである)。
だが、アメリカのバラエティショーを手本にする井原サンからすれば、プロの司会者とは台本に沿って、いかに今、思いついたかのように面白おかしく話すテクニックこそ一流の証し。ウケるかウケないか分からない丁半ばくちのアドリブではなく、確実に笑いの取れる台本を巨泉・前武の2人に求めたのである。
まぁ、今でこそ、芸人たちのフリートークをメインに見せるバラエティ番組は珍しくない。というか、バラエティに限らず、情報番組やワイドショー、ドキュメンタリーなど、あらゆるテレビ番組は芸人のトーク(アドリブ)なしでは成り立たないほど。今や報道番組ですら、選挙開票などの特番で芸人が呼ばれることは珍しくない。
しかし――1970年代の終わりまで、日本のバラエティ番組は台本通りにキッチリ進行するのが当たり前だったんですね。60年代に一世を風靡したハナ肇とクレージーキャッツの『シャボン玉ホリデー』(日本テレビ系)しかり、70年代にバラエティの王様として君臨したザ・ドリフターズの『8時だョ! 全員集合』(TBS系)しかり――。全て台本があり、彼らはそれを面白おかしく、まるでアドリブのように演じるプロの集団だった。
しかし、である。
80年代に入ると、その流れを大きく変える革命的番組が登場する。時に1981年5月16日にスタートした、フジテレビ系の『オレたちひょうきん族』である。
テレビの笑いを変えた『ひょうきん族』
そう、『ひょうきん族』――。
同番組の何が革命的だったかというと、看板コーナーの「タケちゃんマン」は、大まかなストーリーはありつつも、見せ場であるビートたけしサン演じるタケちゃんマンと、明石家さんまサン演じる敵役(「ブラックデビル」や「アミダばばあ」等々)との対決シーンは大雑把な台本しかなく、ほとんどがアドリブだったこと。それも、いわゆる楽屋オチと呼ばれる、芸人仲間やスタッフたちとの内輪ネタが大半。さんまサンの女性スキャンダルがネタにされることも多かった。
しかし――これが抜群に面白かったのだ。まぁ、お笑い芸人として最高に尖っていた頃のたけしサンとさんまサンの丁々発止のやりとりが面白くないワケがない。いわゆる“フリートーク”がテレビのゴールデンタイムの見せもの(商品)になったのは、この時が初めてである。

そんな『ひょうきん族』は、瞬く間に若者たちの支持を集めた。ほどなくして、それは数字となって表れる。同番組の裏番組である王者――TBSの『8時だョ! 全員集合』を、じわじわと視聴率で追い詰め始めたのだ。かの有名なTBS対フジの「土8戦争」である。
思えば、長らく土曜8時は、『全員集合』の天下だった。全盛期の最高視聴率は1973年に記録したバラエティ番組史上最高となる50.5%(!)。その後も志村けんサンのブームもあり、1980年代初頭まで40%台の高い視聴率をキープする。なんと81年2月の時点でも、視聴率47.6%を叩き出していたんですね。ところが、同年5月にフジで『オレたちひょうきん族』が始まると、にわかにその地位が揺るぎ始める。
とはいえ、当初は『全員集合』が30%台、『ひょうきん族』が10%そこそこと、それでもトリプルスコアだった両番組。それが翌82年になると次第に視聴率が接近して、83年には、抜きつ抜かれつの攻防となり、84年には完全に『ひょうきん族』が逆転する。そして1985年9月28日――王者『全員集合』は遂に力尽き、16年間もの歴史に幕を下ろしたのである。
なぜ、『全員集合』は『ひょうきん族』に敗れたのか。――“フリートーク”である。要はその時代、お茶の間が予定調和の台本の笑いより、非予定調和のアドリブの笑いを求めたんですね。
当時、よく明石家さんまサンがフジテレビのバラエティの「台本」をネタにしていたのを覚えている。「ページをめくっても、『あとはよろしく』しか書いてないんや(笑)」と。要はアレ、芸人たちのアドリブを引き出すフジのディレクター陣の確信犯だったんです。実際、さんまサンは、当時の『ひょうきん族』の収録現場について、こう回想する。
「1日撮るわけですよ。朝の10時くらいから夜中のてっぺん(深夜0時)まで。何時間もカメラを回して、(オンエアで)使うのが24分やからな。そういう戦い」。
そう、今でこそ芸人たちにフリートークをさせて、カメラを長時間回して、編集で面白いシーンをピックアップするやり方は、バラエティ番組を作る基本フォーマットになっている。業界用語の“撮れ高”がネタにされる時代である。それを最初にやったのが『ひょうきん族』だった。
そして現在――お笑い芸人に求められるスキルは、もっぱらアドリブやフリートークの面白さになった。本コラムの冒頭でも述べたように、いくらネタ見せ番組やコンテストもので爪あとを残しても、その先もテレビで生き残るには、アドリブやフリートークの能力がマストになった。その意味で、テレビにおけるバラエティ番組の歴史は、『ひょうきん族』以前と、以降とに分かれると言っても過言じゃない。
お笑い芸人がテレビ界の主役に
お笑い評論家のラリー遠田さんも、著書『お笑い世代論~ドリフから霜降り明星まで~』(光文社新書)の中で、こう述べている。「現代のバラエティ番組の最前線にいるような芸人たちは、ほぼ例外なくアドリブ能力が高く、1つ1つのやり取りの中で即興で話にオチをつけて笑いを生み出すことができる者ばかりである。逆に言うと、その能力がなければ生き残れない時代になった。」
――まさにコレ。実際、今や華大(博多華丸・大吉)の2人や麒麟の川島明サン、南海キャンディーズの山ちゃん(山里亮太)らが、午前の帯番組でメインMCを張れるのも、彼らの極めて高いアドリブ能力が買われたからである。そして見逃せないのが、彼らのように第一線で活躍している芸人たちは、近年、コンプライアンスが厳しくなるテレビ界に上手に順応(アップデート)して、人を傷つけることなく笑いを取れる面々なのだ。
かつて“毒舌”で鳴らした有吉弘行サンもアップデートを繰り返して、面白さのエッジを損なわずして、毒舌をTPOで使い分けている。テレビ東京系の『日向坂で会いましょう』で、MCとしてアイドルグループの日向坂46と共演するオードリーの2人(若林正恭・春日俊彰)もまた、絶対に日向坂のメンバーの容姿いじりをしない。コンプラ的なNGワードを回避しつつ、表向きは面白さのエッジを損なわず、極めて高度なトークをアドリブで見せる。
かくして――今やテレビ界は、そんな風にコンプラ面でも安心安全な(でも面白さは損なわない)、極めて器用な芸人(褒めてます)抜きでは成り立たなくなった。彼らはMCだけでなく、コメンテーターやひな壇要員としても登場し、業界用語でいうところの「裏回し」(MCを補佐しながら、アドリブで進行を司る)の役を担うことも珍しくない。
裏回しの例を1つ。NHKに『あしたが変わるトリセツショー』という生活科学番組がある。毎回1つの暮らし回りのテーマ(ex.餃子、枕、腰痛等々)を科学的に深掘りする内容だ。MCは石原さとみサンで、番組は彼女が“トリセツ”を語り、ゲストたち(お笑い芸人等)がリアクションする体で進行する。要は、前に同局で放送されていた『ためしてガッテン』の後継番組だ。ただ、『トリセツ』と『ガッテン』で大きく異なる点が1つ――MCとゲストの役割である。
『ガッテン』のMCは落語家の立川志の輔師匠だった。喋りのプロである。だから番組を進行しつつ、ゲストとのフリートークも自在にこなした。対して、『トリセツ』の石原さとみサンは役者である。なので、彼女の仕事は台本にある台詞を艶っぽく言う役回りになる。似たような立ち位置として、かつての『料理の鉄人』(フジテレビ系)で“主宰”を演じた鹿賀丈史サンの役回りと言えば、わかりやすいだろう。
で、大事なのはココから。多分この番組、石原サンのパートとゲストたちのパートは別撮りなんですね。石原サンのパートを先に撮影しておいて、その後でゲストパートを撮っている。だからオンエア上は石原サンの発言にゲストたちはリアクションするけど、ゲストの喋りに石原サンが返すことはない。そう、この番組はゲストのお笑い芸人たちが「裏回し」をしている。石原サンをフォローしつつ、番組を面白おかしく盛り上げているのだ。
まぁ、役者である石原サンに、志の輔師匠のような、番組の進行とゲストとのフリートークの両方を同時に求めるのは無理である。それは石原サンの個人の能力の問題ではなく、俳優がMCを務めるという構造的な問題。そう考えると、僕らが普段、何気なく見ている情報バラエティって、MCが進行しながら、時おりパネラーたちと面白おかしくやり取りしているけど、アレ――MCに芸人を起用して初めて成立するフォーマットなんですね。一見簡単なようで、実は高いアドリブ能力が求められる。
思えば、昭和の時代のMCはもっとラクだった。俳優の田宮二郎サンが『クイズタイムショック』(テレビ朝日系)、同じく柳生博サンが『100万円クイズハンター』(同)と、役者がMCを務めることができたのは、回答者が芸能人ではなく視聴者で、番組をトークで面白く見せる必要がなかったからである。
そう、いつから日本のテレビ界は、純然たるバラエティに限らず、クイズや情報番組でも“フリートーク”や“笑い”の要素がマストになった。その結果、アドリブに長けたお笑い芸人の活躍の場が増え、下世話な言い方になるけど――現在、彼らは稼いでる。昭和の時代、長者番付(2004年で廃止)の芸能人部門の上位は映画スターや大物歌手が占めたけど、今、再開したら、お笑い芸人が多数ランクインするだろう。そして、これも下世話な言い方になるけど――今や彼らが女優や女性アナウンサーを射止める時代になったのも、かように芸人の“地位”が上がったからである。
思えば、2024年の年末、『M-1グランプリ』で優勝した令和ロマンや同最終決戦に残った真空ジェシカなど、“高学歴”芸人の活躍が話題になった。まぁ、冷静に考えれば、今やテレビ界でバラエティ番組に限らず幅広く活躍し、高額のギャラを稼ぎ、時には女優を射止める“芸人”という職業を、高学歴の若い人たちが目指さないワケはない。
さて――先に僕は、日本のバラエティ番組のエポックメーキングは、“フリートーク”(アドリブ)を商品にした、1981年スタートの『オレたちひょうきん族』と説いた。ただ、厳密に言うと、そこでお茶の間の“嗜好”が突然変わったワケじゃない。実は、その下地として70年代後半から、テレビ界では“非予定調和”を見せる番組がじわじわと存在感を増していたんですね。その上で満を持して放たれたのが『ひょうきん族』だったと。で、その下地を作った番組こそ、日本のテレビ史において輝きを放つ2つの名番組である。1つは『アメリカ横断ウルトラクイズ』(日本テレビ系)、もう1つが『ザ・ベストテン』(TBS系)だ。
お茶の間に“非予定調和”の面白さを伝えた2つの番組
「ニューヨークへ行きたいかー!」――日本テレビの福留功男アナウンサー(当時)の名台詞でお馴染みの史上最大のクイズ番組が始まったのは、1977年10月20日である。国内予選会場は、今は亡き後楽園球場。実は同予選の模様が収録された9月4日は、その前日に巨人の王貞治選手が756号のホームラン世界記録を樹立した日。偶然だけど、その余韻が残る同球場で、かの歴史的番組が幕開けたのは、何かの運命を感じる。
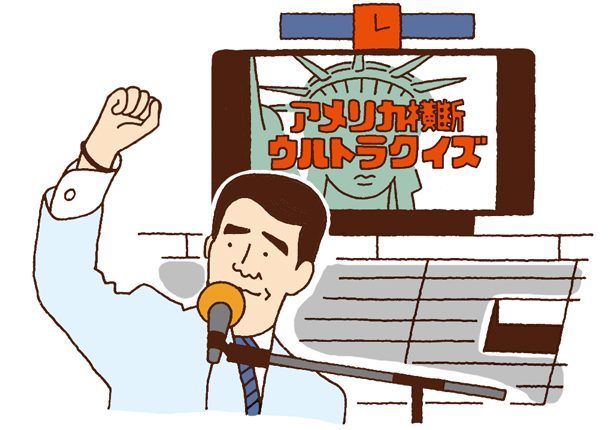
記念すべき第1回の出場者は404人。そこから回を重ねるごとに倍々ゲームのように参加者が増え、第7回には1万人を突破した。改めて番組を説明すると、後楽園球場(後に東京ドーム)を起点に、まず○×クイズで100名程度に絞られ、次の成田空港の「じゃんけん」で更に半分になり、日本を出国して、グアム、ハワイ、北米大陸を横断しながら、チェックポイントごとにクイズで脱落者を出しつつ、決勝のニューヨークを目指すというもの。参加人数・移動距離・予算と、世界一のクイズ番組である(※実際、ギネスブックに「世界で最も制作費のかかったクイズ番組」として登録されている)。
とはいえ、同番組の真の見どころは、実はクイズそのものじゃない。番組のキャッチフレーズ「知力・体力・時の運」の通り、成田空港のじゃんけん大会の悲喜こもごもだったり、グアム島の「○×どろんこクイズ」で全身泥まみれになっての雄叫びだったり、アメリカ本土で空から問題がばら撒かれる「バラマキクイズ」で疲労困憊になりながらの珍解答だったり――と、白日の下にさらされる人間ドラマ“非・予定調和”の方にあった。
ゆえに、司会の福留功男アナは、出場者のプライベートを掘り起こすのに余念がなかった。クイズに入る前に他愛もない世間話をしたり、パーソナリティを深掘りしたり、あだ名をつけたり――。すべてはお茶の間を、一般人である彼らに感情移入させるため。また福留アナが、局アナには珍しくフリートークに長け、場の回しがバツグンに上手かったのも幸いした。
今思えば、出場者のパーソナリティをクローズアップして、ある特殊な環境下における人間ドラマを白日の下にさらす――それは、1990年代後半から世界的に隆盛を誇る“リアリティショー”そのものである。そう、『ウルトラクイズ』は世界のテレビの潮流を20年くらい先取りしていたのだ。だから、同番組に元ネタはない。正真正銘、日本テレビのオリジナルの企画である。
ちなみに、番組は1977年から98年まで全17回(※途中休止あり)放送され、平均視聴率は20%超えと高い人気を誇った。1983年の第7回なんてシリーズ最高視聴率34.5%を叩き出したほど。同番組の成功が、後に『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』(85年~96年)や『電波少年』シリーズ(92年~02年)など、同局のドキュメント・バラエティ路線の礎となったのは間違いない。
そして――“非・予定調和”を売りにした、もう1つの歴史的番組が、1978年1月スタートのTBS系『ザ・ベストテン』である。同番組が新しかったのは、それまで音楽番組の出場歌手はプロデューサーの裁量に委ねられていた慣例(だから音楽番組を担当すると、ゴニョゴニョあって、プロデューサーの家が一軒建ったとも)を、マーケットのランキングをもとに出演をオファーする仕様に変えたこと。

そして、毎週生放送で10位から順に発表して、スタジオで歌ってもらったが、その際――仕事その他の理由でスタジオに来れなくても、その歌手が日本のどこにいても(例え、他局にいても)、TBSの系列局の協力のもと、現場に撮影クルーが出張して、生中継で歌ってもらった。時に、それは移動中の新幹線にも及んだ。例えば、中森明菜サンの場合、ホームから窓越しに車内で歌う明菜サンを映してたら、途中で発車ベルが鳴り、歌の後半は遠ざかる新幹線の外観をカメラが望遠レンズで捉える映像に――なんてことも。だが、そんな非・予定調和感こそ、『ザ・ベストテン』の真骨頂だった。
番組MCは、TBSの局アナだった久米宏サン(※番組途中からフリーに)と黒柳徹子サン。もともと喋りのプロである黒柳サンはもとより、久米サンの類い稀なるフリートークの才能が一気に爆発。ハプニングが起きる度に、彼の回しで番組はどんどん面白くなった。後に久米サンは、自身がアンカーを務めた『ニュースステーション』(テレビ朝日系)と比較して、同番組をこう回想した。――「『ニュースステーション』はニュース番組の形を借りたバラエティで、『ザ・ベストテン』はバラエティの形を借りたニュース番組でした」。
そう、『ザ・ベストテン』は単なる音楽番組に留まらず、時代の“今”をお茶の間に届ける番組だった。その意味では、ハプニングも含めてニュース性にあふれていた。だから、お茶の間の高い支持を得た。実際、同番組の年平均視聴率は、1979年から83年にかけて30%前後で推移。最盛期の81年なんて、年平均33.6%もあったのである。
――かように、これら2つの番組を振り返るに、80年代の『ひょうきん族』が売りにした“アドリブ=ドキュメンタリー”的な番組作りは、既に70年代後半にはお茶の間の支持を得ていたのが分かる。日本人のエンタメの嗜好が、かつての台本に基づく王道(メインカルチャー)から、アドリブありの変化球(サブカル)へと移行していた過渡期である。
サブカルの革命児・ビートたけし
かくして80年代、日本にフリートークやアドリブが時代の主役となる“サブカル革命”が起きる。それを象徴する時代のカリスマこそ――かのビートたけし、その人だった。先にも記した通り、番組単体では“サブカル”に移行しつつあった時代の流れを、メインストリームに押し上げるには、やはりカリスマの登場が必然だった。その扉を開けたのは、意外にもラジオである。時に1981年1月1日木曜深夜――1本の番組が産声を上げた。ニッポン放送の『ビートたけしのオールナイトニッポン』だ。
当時の時代背景を軽く説明すると、前年の1980年は、『花王名人劇場』や『THE MANZAI』(いずれもフジテレビ系)から火が着いた「漫才ブーム」全盛期。当初、人気を博した漫才コンビは、星セント・ルイス、B&B、紳助・竜介、ザ・ぼんち等々。たけしサンのツービートは5、6番手といった印象だった。実際、同年10月にお昼の帯番組として始まった『笑ってる場合ですよ!』(フジテレビ系/※後の『笑っていいとも!』の枠)の月~金通しのメインMCには、B&B(※その頃にはセント・ルイスの人気は失速)が起用された。ところが、翌81年5月に始まる『オレたちひょうきん族』になると、座長に指名されたのは、たけしサンだった。その7ヶ月の間に何があったのか?
それが、先の『オールナイトニッポン』だったんですね。同番組の何が革命的って、それまでのラジオはDJとリスナーとの関係性、つまりハガキを介したやりとりがメインだったのに対し、同番組はDJのフリートークがメイン。2時間のオンエアのうち、冒頭1時間はたけしサンの独演会だった。実際、番組の第1回で、たけしサンはリスナーに、こうぶちかましたほど。「この番組はナウな君たちの 番組ではなく、完全にオレの番組です」――。
まぁ、肝心のトークは身内ネタがほとんどだったけど、聞き役の放送作家の高田文夫サンの“受け”の上手さもあって、これが面白いのなんの。その評判は瞬く間に中高生の間に浸透し(僕もその1人だった)、ラジオ開始4ヶ月後の『ひょうきん族』の開始のころには、たけしサンはすっかり時代のカリスマに。かくして――そんな“革命児”の登場で、80年代のサブカル時代が幕開けたのである。
タモリの復権とさんまの覚醒
そんなたけしサンのブレイクは、波状効果のように周囲に多大なる影響力をもたらした。中でも――この2人を同じステージに引き上げたことが、最大の功績と言ってだろう。2人とは、タモリさんと明石家さんまサン――そう、“ビッグ3”のそろい踏みだ。
この3人の関係はちょっと面白い。芸歴はたけしサンが一番古くて(1972年)、さんまサン(74年)、タモリさん(75年)の順だが、年齢はタモリ→たけし→さんまとなり、『オールナイトニッポン』に起用されたのはタモリ→さんま→たけしの順で、テレビで売れたのもこの順番。ただ、漫才ブームの追い風もあり、突出してブレイクしたのは、たけしサンが一番乗りだった。
で、この時にカギとなるのは、前述の『オレたちひょうきん族』(フジテレビ系)である。同番組の看板コーナー『タケちゃんマン』で2代目ブラックデビルを演じたのが、さんまサンだった。初代を演じた高田純次サンがおたふく風邪になり、その代役で出演したところ、たけしサンとの掛け合い(フリートーク)が好評を博し、そのままレギュラーに定着。そればかりか、後にたけしサンをして「喋りじゃアイツには敵わない」と言わしめるまでに覚醒する。
一方、タモリさんは、『ひょうきん族』の横澤彪プロデューサー(当時)が暗躍した。彼の指揮するお昼の帯番組『笑ってる場合ですよ!』が終了して、引き続き横澤Pが82年10月スタートの後継番組を託されるが、そこで『笑っていいとも!』のMCにタモリさんを抜擢する。それまで夜のイ メージが強かった“密室芸人”を昼の帯番組に起用する大英断だったが――これが大当たり。看板コーナー「テレフォンショッキング」でタモリさんはフリートークの才を開花させる。
そして翌83年になると、たけし・タモリ・さんまの“ビッグ3”がテレビ界に定着。タモリさんに至っては、なんと同年暮れの『NHK紅白歌合戦』の総合司会に抜擢される。同司会にNHKのアナウンサー以外の人物が起用されたのは初めての快挙だった。早くもサブカル時代の1つの到達点と言っていい。
更に、翌84年10月――『笑っていいとも!』に、あの名物コーナーが誕生する。後に「タモリ・さんまの日本一の最低男」のタイトルで呼ばれる、日本のテレビ番組史上初の100%のフリートークのコーナーだ。さんまサンが横澤Pに企画を直訴して誕生したコーナーだった。セットは2人の間に小さなスタンドテーブルが1つ。互いにノープランで15分間、雑談するだけのコーナーだが、これが大人気を博す。そして95年9月にさんまサンが『いいとも』を降板するまで、実に11年間も続くのである。
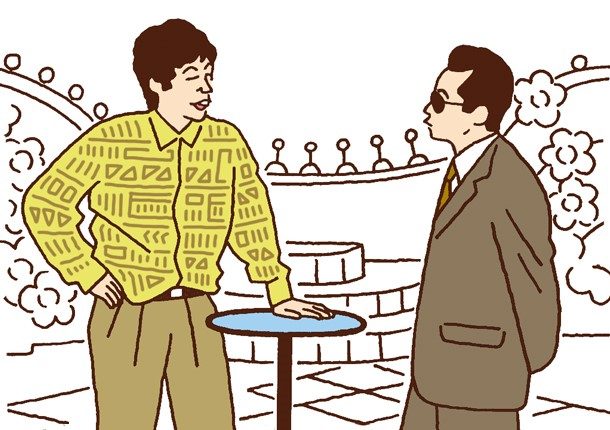
『ニュースステーション』で久米宏2度目の覚醒
さて、話は変わって1985年10月、日本の報道番組史上、かつてないニュース番組が生まれた。『ニュースステーション』(テレビ朝日系/以下、Nステ)である。番組の要となるアンカーに久米宏サン。同年3月に7年間務めた『ザ・ベストテン』(TBS系)の司会を卒業し、半年間の充電を経た彼は、なんとニュースキャスターとしてテレビに帰ってきた。

今や、ニュース番組でキャスターが私見を述べるのはごく普通の光景になっている。でも、かつて日本のテレビ界では、ニュースとはアナウンサーが原稿を正しく読む“ストレートニュース”(余計な演出のない正統派のニュース番組)のことだった。その慣例をあっさり破ったのが、先のNステだった。
ただ、Nステは開始当初、“ニュースショー”という位置づけだった。金曜日は更にカジュアルな演出で「金曜版」が放送された。制作陣に、テレビ朝日以外に久米サンの所属事務所のオフィス・トゥー・ワンも関わり、従来のニュース番組とは一線を画していた。
久米サンとしては、ストレートニュースばかりの中、1つくらいソフトなニュース番組があってもいいだろう……くらいの思いだったそう。事実、Nステのコンセプトは「中学生でもわかるニュース番組」。だから、自らを欧米風にアンカーとか、日本風にキャスターとは呼ばずに、「僕はニュース番組の司会者です」と謙遜した。
ちなみに、欧米のニュース番組は、今でも多くがストレートニュースである。そしてアンカーは私見を述べない。また、賛否の分かれるニュースは両論併記して、双方の専門家の意見を紹介する。そして結論は視聴者に委ねる――それが欧米流の報道の矜持である。つまり、世界的に見れば、キャスターが私見を述べる日本のニュース番組は異端なのだ。ただ、久米サンのコメントが許されたのは、あくまで“自分たちのニュース番組はサブカルです”という自覚があったから。そして何より――久米サンのコメントがバツグンに面白かったからである。
なお、今の“私見”だらけの日本のニュース番組を俯瞰して、近年、久米サンはこんなコメントを残している。「もし、僕が今、再びニュース番組を引き受けることになったら、キャスターが私見を述べないストレートニュースを目指します」――どこまでも“サブカル”を貫く久米サンなのだ(褒めてます)。
永遠のアマチュアリズム「とんねるず」という奇跡
80年代、フジテレビは「楽しくなければテレビじゃない」を旗印に、すべての番組にバラエティ的な匂いを施した。例えば報道では、タイトルから“ニュース”を外して『FNNスーパータイム』と称し、逸見政孝サンと幸田シャーミンさんをキャスターに、少し軟らかめのニュースを始めた(番組開始は前述の『Nステ』の1年前である)。ドキュメンタリーでは、タレントを入れ、敷居を低くした。その代表格が、ムツゴロウこと畑正憲さんが案内する『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』だった。そして、それらの集大成が『FNS27時間テレビ』である。何より、その要であるバラエティ部門が絶好調だった。その背景に、横澤彪・王東順・疋田拓・石田弘という4人の大物プロデューサーが互いに切磋琢磨し合う構図があった。そう、ライバルは外にいるより、内にいる方が組織は伸びる――。
そのトップに君臨する“横澤班”は、ビッグ3(ビートたけし・タモリ・明石家さんま)を擁し、『オレたちひょうきん族』や『笑っていいとも』など最新の笑いをお茶の間に届けた。“王班”は、『なるほど・ザ・ワールド』(※ちなみに、クイズ番組にフリートークの概念を持ち込んだのが同番組である)や『クイズ・ドレミファドン!』など、家族に見てもらえる番組作りを心掛けた。“疋田班”は、『夜のヒットスタジオ』に命を懸けた。石田班は、『オールナイトフジ』や『夕やけニャンニャン』、『とんねるずのみなさんのおかげです』など、若者目線のバラエティ番組を開拓した。
で、ここで取り上げるのは、その中でもキング・横澤班と並ぶ存在感を示した、“ダーイシ”こと石田プロデューサー率いる石田班である。同班が生んだ最大のスターが、とんねるずだった。『オールナイトフジ』で800万円もするカメラを倒し、『夕やけニャンニャン』ではおニャン子相手にガチ喧嘩をして、そして冠番組の『みなおか』では松田聖子、小泉今日子、渡辺満里奈、宮沢りえなど当代一流のアイドルたちと堂々と共演した。
とんねるずの芸風は、いわば高校の“部室芸”だった。仲間内で先生のモノマネをするあのノリだ。彼らに師匠はおらず、芸能プロダクションの養成所などで修行を積んだ経験もなかった。一貫して我流を貫き、アマチュアの感性のままプロになった。ただ、何事も振り切れば面白い。
例えば、『みなさん~』の1コーナーから、今や独立した特番になった『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』なんて、彼らの“部室芸”の真骨頂だろう。元ネタがマニアックすぎて、正直、似ているかどうか分からない。ただ、マニアックとクローズド(閉鎖性)こそ、彼らのレーゾンデートル。2人が時々やる“ダーイシ”と“小港”のモノマネも、正直、お茶の間は元ネタの人(何せフジの社員である)をよく知らない。それでも面白いとお茶の間に感じさせる、とんねるずのパワーこそ“サブカル”の極みだった。
90年代、“ダウンタウン以降”という世界
90年代、日本のテレビ界に2つの革命が起きた。NHKとオール民放のフジテレビ化と、ダウンタウンのブレイクである。
前者は、80年代に「楽しくなければテレビじゃない」を旗印に、すべての番組をバラエティに寄せて成功したフジテレビに倣えとばかりに、他の民放やNHKまでもが、一斉に“フジテレビ化”に舵を切った。ドラマは若者向けの作品が増え、ニュース番組は軟らかくなり、ドキュメンタリーや情報番組もタレントを入れてエンタメ色が濃くなった。各局の女性アナウンサーがアイドル化するのもこの時代である。
そして後者は――世に言う“ダウンタウン以降”という世界線を生んだ2人の登場だ。ブレイクのキッカケは1991年、共に全国ネットでレギュラー化した2つの冠番組――『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』(日本テレビ系)と『ダウンタウンのごっつええ感じ』(フジ系)だった。
そこから翌92年――2人は日本テレビ系の『24時間テレビ「愛の歌声は地球を救う」』でメインパーソナリティーに起用され、視聴率を前年の6.6%から一気に17.2%に押し上げる。更に、94年には松ちゃん(松本人志)の初の単行本『遺書』(朝日新聞社)が250万部のメガヒット。一方、95年には、今度は浜ちゃん(浜田雅功)が歌う「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント」がWミリオン――と、90年代前半のダウンタウンの“成り上がり”っぷりは壮絶だった。
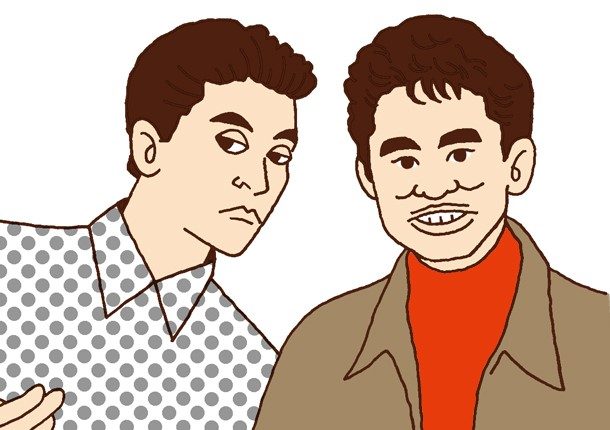
一体、2人の何が凄かったのか。テレビに映る、彼らのトークがすべて面白かったのだ。考えたら、先のビッグ3は、普段は1人で番組に出演する。それゆえ、絡む相手次第では、時に抑えたトークになることも。それに対して、ダウンタウンは常に2人で出演する。よく関西人は「2人揃えば漫才になる」と言われるが、ダウンタウンの2人もテレビで口を開けば、すべて漫才に聞こえた。ある意味、発明だった。
2人は率先して前に出ていく タイプじゃない。声も張らない。ただ、口を開けば必ず笑いを起こす。そして相手が誰であろうと、臆せず絡む――そして面白い。そんな2人に10代の少年少女たちは共感し、自らもお笑い芸人の道を志す。それが――いわゆる“ダウンタウンキッズ”である。後に彼らは、2000年代の『M-1グランプリ』で活躍する面々となる。
そう、ここへ至り、日本のフリートーク芸は完成の域を見たのではないか。本来、コメディアンとは、欧米流に言えば、台本に沿って喜劇を演じるか、同じく台本に沿ってスタンドアップコメディを演じるか――いずれも専業作家が台本を書き、コメディアンはいかにそれを今思いついたように喋れるかが、プロのテクニックとされる。それに対して、日本の芸人のフリートーク芸は、本人自らその場で考え、瞬時にアウトプットする。
日本が世界に誇る“大喜利”の存在
個人的には、僕はそんなフリートーク=アドリブを生み出せる日本の“笑い”を世界一だと思っている。例えば、「大喜利」というジャンルがある。あるお題に対して、回答者が気の利いた答えをその場でひねり出して、時間を置かずに発表するというもの。実はアレ、世界広しと言えども、日本にしか存在しないジャンルの笑いなんですね。
日本では、『笑点』(日本テレビ系)が大喜利を普及させた元祖として知られるけど、近年では松ちゃんが企画した『IPPONグランプリ』(フジテレビ系/2009年スタート)が最も有名だろう。あの番組の歴代の優勝者たちこそ、今の日本のお笑い界を牽引するレジェンドたちと言っても過言じゃない。バカリズム、千原ジュニア、設楽統、有吉弘行、博多大吉、若林正恭、秋山竜次、川島明、大吾――皆、笑いの天才、笑いのアスリートたちである。
そして、今やX(旧ツイッター)では、一般のユーザーたちも日々、誰かが発する大喜利のお題に答えてる。こう言っては何だが、素人ながら、みんな面白い。日本は世界的にも珍しく、今もSNSでXが隆盛を誇っている。僕は、その一因に大喜利文化があると思っている。

日本が生んだ、独自の笑い“大喜利”。その背景にあるフリートークとアドリブの文化。そんな“サブカル”の笑いが日本で独自に発展し、今や隆盛を極めている。僕はそんな日本の笑いを誇りに思うし、そこで育まれた日本の芸人を心底尊敬するし、個人的には世界一面白いカルチャーだと思っている。
なぜ、日本の笑いは“サブカル”に向かったのか
最後に――。
何ゆえ、日本の笑いは、かつてアメリカのテレビなどから学んだ“王道”の笑い(台本があり、芸人はそれを今思いついたように面白おかしく演じるプロフェッショナル)を脱し、“サブカル”の笑い(フリートーク=アドリブ)へと向かったのか。
時々「笑いは権力への風刺。政治をネタにしない日本の笑いは、欧米よりレベルが低い」などの意見を見かける。確かに、アメリカのスタンドアップコメディなどを見ると、大抵、政治の風刺ネタがある。でも――それは本当に面白いのだろうか。
アメリカは移民社会で、欧州は階級社会である。人種も宗教も言語も歴史観も多様。1つの価値観に収まらない。そんなとき、政治ネタは共通の話題になりやすい。一方、日本人はよくも悪くも島国ゆえに閉鎖的で、宗教観も薄く(何せクリスマスを祝った一週間後にお寺で除夜の鐘を突き、その翌日に神社に初詣に行く国民だ)、言葉も地域性もそこまで差がない。
――となると、日本人の笑いの原点は、似たような価値観を持つ人々の中で共有する笑いになり(ある意味、広義の“部室芸”とも)、例えば「あるある」ネタ(その代表格がテレビ朝日系の『アメトーーク!』である)や「大喜利」などの繊細で、ひねりの利いたものになるか、今この瞬間、一番面白い返し――気の利いた「アドリブ」が喝さいを浴びる。つまり、極めて高度な笑いのテクニックが求められるとも。前述の『アメトーーク!』の「くくりトーク」なんて、あるジャンルの“好き”の熱量を競い合うという、誰も攻撃しない、やさしい笑いだ。そんな平和なトーク番組は世界中を見渡しても日本くらいしかない。そうしたハイレベルなトークが飛び交う中で、わざわざベタな政治の風刺をして笑えるだろうか。
それと、戦後80年――日本が平和で豊かになり、僕らがそこそこ幸せに暮らせているのも「政治ネタをやらない」一因だと思う。なんのかんので、戦後80年、日本は先進国で唯一戦争をしていない。経済力だって敗戦国から立ち上がって、一時はGDP世界2位まで上り詰めた(現在は4位。それでも高い)。「笑いは権力への風刺」の意図は分かるが、正直そこまで“現状”に差し迫った不満がないというのが、僕ら日本人の本音では――。
日本史において、“娯楽”が著しく発展した時代が2つある。1つは平安時代中期、もう1つは江戸時代である。前者は、先の大河ドラマ『光る君へ』でも描かれた、紫式部の「源氏物語」や清少納言の「枕草子」などを生んだ“国風文化”華やかりし時代。後者は、今年の大河『べらぼう』でも描かれている浮世絵や歌舞伎などに代表される“江戸文化”の時代だ。
なぜ、それらの時代に娯楽が発達したのか?
――概ね、平和だったからである。その時代、外国との目立った争いもなく、国内の内乱もほとんどなかった。ゆえに、人々は明日を生きるための心配をせずに済み、どうすれば今日をもっと楽しく過ごせるかに関心が向いた。心が平穏になり、他人にやさしくなった。その結果、武力よりもエンタメが求められ、著しく進化したのである。
そう、戦後80年――少なくとも今の日本は歴史上、稀にみる平和な時代である。そんな時代を背景に生まれた、人を傷つけない、日本独自のやさしい笑い――“サブカル”に、僕らはもっと自信を持っていいのかもしれない。
ビバ・サブカル!