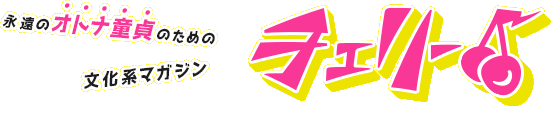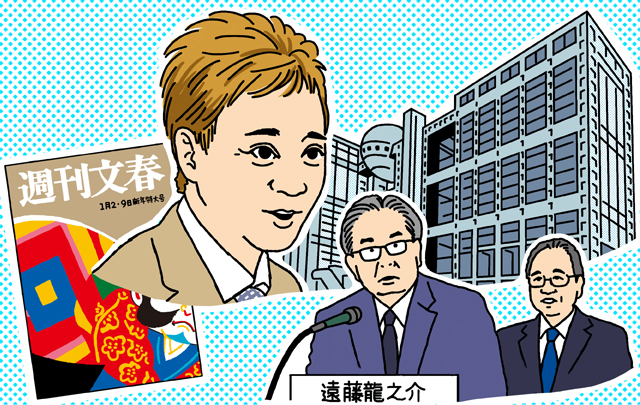「皆さんが静かになるまで××分、かかりました」
――学校の先生がよく口にするセリフである。生徒たちが騒いでる教室であえて制止せず、彼らが自ら気づいて、自然と静まるのをひたすら待つ戦略だ。そして、おもむろに先生は語り始める――。
まぁ、それと重ねるワケじゃないけど、先の3月31日のフジテレビの第三者委員会の報告と、その直後に行われた同社の清水賢治社長の記者会見から、早やひと月半――。一時は山火事のごとく炎上していた“案件”も、まだ鎮火とは言えないまでも、ようやく声を張り上げなくても会話できるくらいには収まってきた。今なら、少しクールダウンした環境で、よりフラットな目線で、一連の案件を冷静に検証できそうだ。
――と思っていたら、5月12日の夕方、突然、朝日新聞(デジタル版)の速報が飛び込んできた。「中居正広氏側、フジ第三者委の報告書に反論 性暴力認定は『問題』」――と。まぁ、その件も含めて、今回、敢えて“あの日”からインターバルを置いて、このコラムを書かせてもらった次第です。少々長くなりますが、最後までお付き合いのほどを。

えーっと、本案件の今後の注目点としては、ことフジテレビにおいては、6月に開かれる同社の親会社――フジ・メディア・ホールディングス(FMH)の株主総会で、例の“アクティビスト(物言う株主)”のアメリカの投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」が提案する新たな取締役候補の行方と、いまだCM出稿を差し控えるナショナルクライアントたちがいつ戻ってくるのか?――ざっくり、この2点だと思う。ただ、これらの事案はかなり“政治的”な話でもあり、正直、僕のテリトリーじゃないので、ここでは触れないでおく。そのスジの専門家の皆さんにお任せします。
世紀の大誤報を“ミニマム”と表現した第三者委員会
じゃあ今回、このコラム(コラムです)は、何を語るのかと言うと――キッカケは、例の第三者委員会の報告書でした。一点、ちょい気になる記述がありまして――。それは、弁護士の橋下徹サンから指摘され、「週刊文春」(文藝春秋)が渋々“誤報”を認めた、あの一件。文春の初報では“被害女性はフジ編成幹部A氏に誘われた”と報じていたのに、年をまたいだ次の号では、「あの日、X子さん(※被害女性)は中居さんからA氏を含めた大人数で食事をしようと誘われていました」と、橋下サン曰く“しれっと上書き”した、あの一件――。
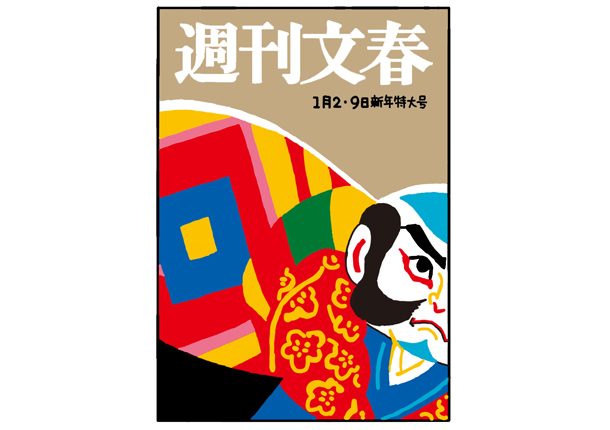
そんな“世紀の大誤報”を、第三者委員会はどう捉えたかというと――「当委員会としては、当時の報道の状況からすれば、本事案での中心的な問題は、当日(2023 年 6 月 2 日)の食事会に B 氏(※編成幹部。文春の記事ではA氏)が関与していたかどうかというミニマムに切り取った事実ではなく……」
――おっと、“ミニマム”と。これには驚いた。第三者委員会は文春の誤報をミニマムと。いやいや、あの誤報は、とてもミニマムで済ませられるものじゃないでしょう。こうなると、俄然こちらとしては、なぜソコまで同委員会が過少に評価したがるのか――と疑問がフツフツと湧いてきまして。で、調べました。考えました。そして導き出されたのが、以下の3つの仮説です。第三者委員会は、世論がこれらの真相に近づくのを恐れ、敢えて例の“誤報”を過少に評価したのではないかと――。
①ナショナルクライアント(大手企業)による“一斉CM差し止め”の本当の理由
②『業務の延長線上』なるワードの違和感と、その真意
③結局、中居正広さんは何をした?
――そう、本コラムはこれら3つの仮説に迫る、渾身のリポート。いえ、何も声高に自説をがなり立てようってワケじゃありません。できるだけ私情や思い込みを排除し、可能な限り客観的な資料を用い、冷静に、知的に考察したつもりです。ま、あくまでコラムですから。
一ヶ月も放置された世紀の大誤報
――と、その前に。まずは、僕がこの4ヶ月半にも及ぶ一連の騒動に対して、ず~っと思っていたコト。つくづく皆さん――それは記者も含めての話だけど、“記事”や“公式声明”、“報告書”の類いを読んでいない。言っちゃなんだけど、まるでACジャパンのCMの「決めつけデカ」のごとく、SNSで拡散される“表層”のみを鵜呑みにして、全部理解した気になってません? 今回の一連の騒動は、特にその傾向が強いと思う。
では、改めてコトの経緯のおさらいから。結局――文春が先の“誤報”を公式に認め、謝罪したのが、あの1月27日の“10時間半”にも及んだフジテレビの記者会見の翌日。そう、初報(昨年の12月26日)から実に一ヶ月もの間、誤報が放置されていたんですね。ちなみに、フジは初報の翌日には、早々に公式サイトに「当該社員は会の設定を含め一切関与しておりません」と声明を発表。だが、既に世間は“被害女性はA氏(※編成幹部)に仕組まれた!”と大炎上――。年を越して1月9日、今度は中居正広サン自身が公式サイトに“お詫び”と称して「このトラブルについては、当事者以外の者の関与といった事実はありません」と重ねて表明するも――こちらも焼け石に水だった。
かくして、文春の初報の空気感のまま、例の10時間半の会見へと雪崩れ込み、記者らは“編成幹部が被害女性を食事会に誘った”体で、延々とフジテレビの幹部を吊し上げたのである。結果的に、この会見は10時間半も浪費しながら、記者らはただの1つも(本当にただの1つも!)新事実を引き出せなかった。現に、翌日の朝日新聞の一面の見出しは「フジテレビ会長・社長辞任」と、会見前にフジがリリースしたものだった。
ふと思う。記者会見って本当に必要だろうか。江戸時代の「市中引き回しの刑」じゃないが、エンタメとしての“生け贄ショー”以外に、やる意味があるのだろうか。あの日、壇上にいたフジの幹部5人の心労は察して余りある。その一挙手一投足が衆目に晒され、表情一つ崩せず、満足に水も飲めず、ひたすら低姿勢に終始するしかなく、わずか10分程度のトイレ休憩を1回挟んだのみで、いつ終わるともしれぬ会見にひたすら耐え続けた体力と精神力は――こう言っちゃなんだけど、テレビマンとしての矜持だったと思う。
1つだけ収穫があるとすれば、作家・遠藤周作のご子息、フジテレビ副会長(当時)の遠藤龍之介サンがお茶の間に見つかったコトくらいか。あの過酷な状況でも冷静さを失わず、かといって質問者を煙に巻くこともなく、やさしく、真摯に語り続けた彼に救われた場面がどれだけあったか。素顔はお父様に似た知的なユーモリスト。フジでは広報畑を歩み、その人あたりの良さとスマートな身のこなしで社内外にファンも多い。
龍之介サン、当初は会見に出る予定はなかったらしいが、会見4日前に開かれた社内説明会で、港浩一社長と嘉納修治会長が度々答えに窮する姿を見て「2人だけに任せておけない」と急遽、金光修FMH会長を誘って出席へ。そんな“火中の栗を拾う”気骨も備えた方。彼がいなかったら、あの会見はどうなっていただろうと、今更ながら思う。

CM差し止めは1月17日の会見前に決まっていた
お待たせしました。いよいよ本題に入ります。まず、第1の仮説――「ナショナルクライアント(大手企業)による“一斉CM差し止め”の本当の理由」から参りましょう。おっと、例の中居サンの“真相”は3番目の仮説で取り上げるので、今しばらくお待ちを。
さて、第三者委員会の報告書によると、フジテレビへの一斉CM差し止めの原因は、あのテレビカメラを入れず、週刊誌やウェブメディアの記者も入れず、記者クラブのみの参加で、港浩一社長(当時)がひたすら質問に「調査委員会の調査に委ねる」と繰り返した、今年1月17日のクローズドな会見が発端だという。あの“惨状”を見て、日本生命やトヨタを皮切りに、雪崩のごとく多くの企業が一斉にCM差し止め(ACジャパンのCMに差し替え)に舵を切ったと。主要なメディアも概ねその論調である。要は、フジテレビの企業ガバナンスが問われたと――。
ただ、ちょっと待ってほしい。特定の番組の提供を見合わせるならまだしも、フジテレビ全体のCMを見合わせるなど前代未聞である。これまでの長い長い、日本のテレビの歴史において、昭和天皇崩御や東日本大震災など、特別な事情で全局のCMが控えられたコトはあったが、一局のCMのみを控えるなど前例がない。思い返せば、刑事事件として社員が逮捕されたテレビ朝日の『アフタヌーンショー』の「やらせリンチ事件」の際も、惨忍な坂本一家殺害事件に発展した「TBSビデオ問題」の際も、一局のCMが控えられるまでには至っていない。それに対して、刑事事件でもなく、そもそも示談で解決済みの本案件で、そんなオオゴトを大企業が即断できるものだろうか――。
――僕がそう思っていたら、TBSの「調査情報デジタル」の記者の方も同じ疑問を感じたらしい。先の3月22日に配信された「フジテレビにスポンサーは戻るのか?企業広報担当者が明かす“CM一斉撤退”に至った本音や今後」と題した記事によると、同記者がスポンサー各社に問い合わせたところ、多くの企業はフジの1月17日の会見前に、既に水面下でCM停止を決めていたという。曰く、“港社長の会見は、最後の一押しに過ぎなかった”と。
ちなみに、TBSの「調査情報デジタル」とは、1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだウェブマガジン。テレビ、メディア等に関する多彩な論考で知られ、放送業界で最も古く、最も権威ある業界メディア誌として一目置かれている。
同記事は、CM差し止めに関して、様々な大手企業の広報担当者の声も紹介している。
「フジテレビの最初の会見の数日前には、弊社の人権方針に照らして差し止めの方向で社内の協議はほぼ終わっていました。フジテレビの会見はダメ押し程度。広告会社とも方向性は共有していましたし、他の企業も差し止め方向で動いていると聞いていました」
「業界的な横並びですよ。対応が遅れると、批判されますから」
「経団連のトップを輩出する日本生命の動きは気にしていました」
「トヨタさんがやるならうちも――」
――etc
要は、業界特有の横並び意識、同調圧力である。では、なぜ彼らナショナルクライアントはそんな前代未聞の決断に至ったのか。思い出してほしい。あの最初の会見前、フジテレビに対して、どれだけ猛烈なアゲンスト(逆風)が世間で吹き荒れていたか。それを検証するには、昨年末の文春の初報に続いて、年をまたいで、会見のあった1月17日までの間に放たれた第2弾、第3弾の“文春砲”を改めて検証するのが妥当だろう。
“3悪人”と名指しされた佐々木アナ
文春砲の第2弾は、初報の次の号、1月8日発売の1月16日号である。見出しは「X子さんの訴えを握り潰した『フジの3悪人』」――。そう、この号で佐々木恭子アナが、被害女性を守らなかった“3悪人”の一人として名指しで批判される。記事は被害女性の語りで進む。“すぐに佐々木さんには事件のことを相談しました。それを聞いた彼女は「大変だったね。しばらく休もうね」と言うだけ……。守ってもらったという感じではありませんでした”――。
この記事をキッカケに、佐々木アナはSNSで猛バッシングされ、大炎上した。それはそれは、酷い有様だった。ちなみに、この号には先の“しれっと上書き”の記述もあるが、SNS民はそんな細かいトコロまでは読んでいない。本案件に対する世論は、この時点で、いちタレントの中居正広サンのゴシップから、フジの編成幹部が関与し、被害女性の訴えを佐々木アナら“3悪人”が握り潰した“組織的犯罪の疑い”へと新たなステージに入ったのである。
ところが、第三者委員会の報告書を読むと、全く違う風景が見えてくる。少なくともアナウンス室の2人――男性の室長と先の女性のFアナ(同報告書は原則匿名表記なので、お察しください)は被害女性に終始寄り添う姿が見受けられる。文春に“3悪人”と書かれる心証はない。特にFアナは、被害女性との連絡窓口として、心身両面から彼女を懸命にケアする様子が綴られている。先の文春の被害女性の証言も、報告書では、Fアナが医師から女性の即入院の必要性を知らされ、「少し休もう、仕事を休むことを全く迷惑だと思う必要はないので、ずっと待っている」と、むしろ彼女を気遣った発言として記されている。
また、Fアナが入院中の被害女性から収入面の不安を打ち明けられた際も、心置きなく治療に専念してほしいとの思いから、人事に相談して、退院後も満額の給与が支給されるように取り計らっている。Fアナについては、第三者委員会のアンケートでも、多くの同僚たちが「週刊誌報道の内容が誤りである」「週刊誌報道の内容に納得がいかない」などと回答しており、当の第三者委員会もその名誉回復に言及している。
文春砲第3弾が報じた“上納文化”
そして――僕が最も問題視する文春砲第3弾、1月16日発売の1月23日号である。本号こそ、あらゆる客観的な事象を繋ぎ合わせるに、“一斉CM差し止め”の最大の原因になったと思われる。その見出しは「新たな被害者(フジ女性アナ)が爆弾告白『私もAさん(フジ編成幹部)に“献上”されました』」――。そう、本号で初めて“上納文化”なるワードが登場する。記事は、それに該当する3つの会食を紹介している。
〇2021年冬(12月)、フジのアナウンサーの水谷愛子さん(仮名)がA氏(※編成幹部)に誘われ、飲み会に参加。場所は、東京・六本木のグランドハイアット東京のスイートルーム。ゲストは中居正広さんと男性タレント1名。水谷さんの他に2人の女性アナも参加。
〇上記と同じ時期、件の被害女性もA氏に誘われ、飲み会に参加。場所は、同じく六本木のグランドハイアット東京のスイートルーム。ゲストは上記と同じタレント(※中居さんの記述はなし)。被害女性の他に2人の女性アナも参加。
〇2019年12月26日、東京・赤坂の高級日本料理屋「古母里」で、井澤健社長(イザワオフィス)や周防郁雄社長(バーニングプロダクション)ほか4人の芸能事務所社長との大忘年会。フジテレビ側からBSフジの亀山千広社長や共同テレビの港浩一社長(当時)をはじめ、幹部多数が参加。ほかに女性アナも3名参加。
――そして、これらの記述の前後に、ブリッジ的に様々な人物の“証言”も入り、文春も随所に交通整理的に私見を述べている。
〇「女性アナをいかがわしい接待の道具として使い、二人きりにして『あとはご自由に』。(中略)性的行為を断るとき、無言の圧力を感じました」(水谷アナ)
〇「この数年間、Aさん(編成幹部)はずっとそんなことばかりしてきた。上司である港社長を含め、彼らは二十年以上ずっと同じような遊び方をして…」(水谷アナ)
〇「中居さんとダウンタウンの松本人志さんの二人に可愛がられていたA氏は、彼らの鶴の一声でプロデューサーになり、さらには編成部長という役職を手に入れた。彼は、女性アナや女性局員をタレントに“上納”し、出世を遂げてきた」(フジ関係者)
〇このように、A氏とその部下によるグランドハイアットを舞台にした接待は、フジ社内で常習的に行われてきたのだ。(文春編集部)
〇なぜ、A氏や港氏は時代錯誤な考え方を持ち続けているのか。その背景には、フジテレビの悪しき“上納文化”が横たわっている。(文春編集部)
〇「港社長は常務時代、月一回、女性アナを手配した上で(中略)イザワオフィスの井澤健氏を囲む会を催していました。『港会』と呼ばれたこの会合には、当時を代表する女性アナが多い時で8人ほど集められていた」(元フジ幹部)
〇「港社長は、こうした女性アナ接待の常習者。そのため、彼は自身のDNAを受け継ぎ、みずから編成部長に抜擢したA氏を処分することができないのです」(元フジ幹部)
――とまぁ、普通にサラッと読んでいると、もはやフジテレビがとんでもない会社にしか見えてこない。なんと、タレントや芸能事務所らとの会食で、常習的に女性アナを“いかがわしい接待”の道具として“上納”(!)していたという。編成幹部も港社長も、それでタレントや芸能事務所の信頼を得て、今の地位に出世したらしい……。
“性上納”が海外に報じられる
――って、そんなアホなことあるかいっ(笑)。だが、そこは“文章”を生業とする天下の文藝春秋社。実に巧妙なロジックで記事が構成されており、サラッと読んでいると、まんまと、その筆使いに“洗脳”されそうになる。以下がそのロジックである。
①編成幹部が被害女性を誘い、中居正広サンに“上納”した。
②彼は女性アナをタレントに上納する常習犯。同様の接待をホテルのスイートルームで常習的に行っていた。
③そうしてタレントたちの信頼を得て、彼は編成幹部に出世した。
④彼に限らず、フジテレビには“上納文化”のDNAがある。その先駆者が港社長である。
⑤港社長は常務時代から芸能事務所との会食で、女性アナを上納してきた。(そして社長になれた)。
――とまぁ、実に見事なロジック。そして本号が発売される前日(1月15日)には、件の記事が一足先にスクープとして「週刊文春 電子版」から配信され――まぁ、SNSは大騒ぎになった。もはや中居さんの案件は氷山の一角となり、フジテレビは会社ぐるみで自社の女性アナをタレントや芸能事務所に“性上納”するトンでもない会社と、大炎上した。そう、“性上納”なるワードがSNSで飛び交うのは、この日からである。
ほどなくして、SNS上で「フジテレビの放送免許をはく奪せよ」の声が上がった。同時にスポンサー各社への不買運動(キャンセルカルチャー)も囁かれ、事態はただならぬ様相を呈してきた。「性上納されたらしい」と同社の女性アナにも好奇の目が向けられた。そして――恐れていたコトが起きる。この週刊文春の記事を引用したニュースが海外へ配信され、アメリカ4大ネットワークの1つ、ABCが“性上納”を匂わせる文脈で報じたのだ。「フジテレビは中居のようなスターを喜ばせるために、長年、同局の女性アナウンサーを利用してきた」――。
推測するに、ここへ至り、スポンサー各社は一斉に水面下でCM差し止めに動いたのではないか。今やナショナルクライアントにとって、海外市場は売り上げの半分近くを占める重要なマーケット。それが、日本で女性社員を“性上納”するテレビ局をスポンサードしていると見られたら、国際的に性加害に加担する企業と烙印を押されかねない。
もはや“性上納”が本当かどうかという話ではない。そのニュースが海外のメジャーなテレビ局が報じた時点で、世界からどう見られるかという話になった。日本のナショナルクライアントたちが、“CM差し止め”という前代未聞の英断を下しても不思議じゃない。それくらい、米4大ネットワークのABCが報じたニュースのインパクトは大きかった。
かくして――1月18日に報じられた日本生命とトヨタのフジテレビへのCM差し止め(ACへのCM差し替え)を皮切りに、同月末にかけて雪崩を打つように他の大手企業たちも同調する。第三者委員会の報告書によると、その総数は1月だけで330社に上ったという。日本アドバタイザーズ協会(かつて“主協”と呼ばれた日本広告主協会)に加盟する大手企業の数は264。そのすべてがCM差し止めに動いたと見て間違いないだろう。
一方、国内の視点に立つと、この“雪崩化”の要因の1つに、昨今のSNSに見られるキャンセルカルチャーが影響したのは否めない。こちらも“性上納”が本当かどうかなど関係ない。その真偽が確定するまでフジのスポンサーにとどまり、SNS民の餌食になるくらいなら、取る物も取り敢えず一目散に逃げだしたほうが賢明と、ナショナルクライアントたちは判断したのである。
世紀の大誤報その2“スイートルームの2つの飲み会”
今現在(5月上旬)、フジテレビにまだ彼らナショナルクライアントは戻ってきていない。民間放送の同社の収益の6割はCM収入である。このままの状態が続けば、経営は成り立たないだろう。実際、今年3月までの同社の2024年度の決算は、201億円の赤字だったそう。1月半ばから2ヶ月半のCM差し止めで、その前の9ヶ月半で稼いだ黒字を食いつぶした形だ。これが1年続けば――もはやフジテレビはテレビ局として存続できないだろう。

かような事態を招いた責任は誰にあるのか?
もちろんフジテレビ? ――いえいえ、僕はある意味、週刊文春にもかなりの責任があると見ている。ぶっちゃけ、先の文春砲第3弾にある“上納文化”なるワードが、すべての引き金になったと言っても過言じゃない、と。そして――そのワードの起点に当たるのが、本コラムの冒頭でも記した“編成幹部が被害女性を誘った”とする同誌の“誤報”である。第三者委員会が“ミニマム”と評した、あの誤報だ。
実は、当の文春は記事内で“性上納”なるワードは一度も用いていない。性的な行為を匂わせつつも、頑なに「上納」表記で抑えている。それは、図らずも同誌が、フジの女性アナらが参加する会食が“性的な目的”を含んでいないと知っていたからではないか。業界一、法務部が厳しいとされる文藝春秋社である。ただ、結果的にSNSでは、より過激な“性上納”なるワードが拡散した。それは同誌が言葉には出さずとも、読み手にそう取られるよう、巧みにロジックを重ねて読者をミスリード(誘導)したからである。
ところが――3月31日の第三者委員会の報告書を読んで、僕らはこの文春砲第3弾が、もっと酷いミスリードをしていた事実を知る。記事には別々の事例として書かれたスイートルームの2つの飲み会が、実際には一度しか開かれていなかったのだ。その会には水谷アナ(仮名)と被害女性が共に参加しており、文春は2人それぞれの視点から記事を書き、あたかも2件(!)の飲み会のように仕立てていたのである――。
もはや、これはミスリードでは済まされないでしょう。個人的には“誤報”だと思います。先の“編成幹部の関与”に続く、第2の誤報とも。こうなると、先に記した文春のすべてのロジックが崩れてくる。まず、第三者委員会があれだけ詳細に調べても、過去10年間で“スイートルーム飲み会”は一度しか開かれていなかった。これで、「編成幹部が常習的にスイートルームで接待を行っていた」という“常習性”が崩れた。
しかも、その一度だけのスイートルーム飲み会も、時期を見ると、コロナ禍に開かれている(2021年12月)。当時は東京都から「基本的対策徹底期間における対応(第2期)」が要請されていた時期。飲食店の酒類提供は原則21時まで、同一グループは4人までという“ルール”があり、事実上、ホテルの部屋飲みしかできない状況だった。参加人数を考えれば、スイートルームを使うのが妥当だろう。ソコに特段の意図はなかったとも考えられるのである。
実際、僕自身も経験あるけど、テレビ局ではドラマの脚本や番組台本を作る際、時間がない時は、いわゆる“カンヅメ”と称して、作家をホテルに入れるコトが多々ある。バラエティなど大人数の作家が共同で作業する場合は、普通にスイートルームが手配される。打合せをしたり、軽食をとったり、たまに仮眠もとりながら、各々分担して台本を書き上げる。だからテレビ局が仕事でスイートルームを使うのは、別に珍しい話じゃない。
崩れた文春のロジック
更に言えば、文春砲第3弾の記事の後半では、フジの港社長が常務時代に女性アナを伴い、某芸能事務所の社長をもてなす「港会」なる懇親会を頻繁に開いていたと書かれている。2019年の年末には、複数の芸能事務所の社長とフジテレビの幹部らが集い、赤坂の日本料理屋で忘年会が行われ、共同テレビ時代の港社長や女性アナも3名参加した。記事では、これら一連の会食を「フジテレビの悪しき“上納文化”」と断罪していた。
ところが――第三者委員会の報告書によると、港社長が女性アナを伴った、これら一連の会食等で、不快な思いをした旨を述べる女性アナは一人もいなかったという。となれば、単に会食に女性アナが参加しただけの話に過ぎない。ココでも“上納文化”の存在が否定されたのである。そう、フジテレビが編成幹部以外にも組織的に女性アナを上納していたという“組織性”も崩れたコトになる。
つまり、先に示した一連のロジック――
①編成幹部が被害女性を誘い、中居正広サンに“上納”した。
②彼は女性アナをタレントに上納する常習犯。同様の接待をホテルのスイートルームで常習的に行っていた。
③そうしてタレントの信頼を得て、彼は編成幹部に出世した。
④彼に限らず、フジテレビには“上納文化”のDNAがある。その先駆者が港社長である。
⑤港社長は常務時代から芸能事務所との会食で、女性アナを上納してきた。(そして社長になれた)。
――という“常習性”と“組織性”に主眼を置いたロジックは、もろくも崩れ去ったのである。
この文春砲第3弾が出た週末の1月18日、TBS系『情報7daysニュースキャスター』では、MCの安住紳一郎アナが同案件を報じて、こう私見を述べている。「私もこの業界で仕事をしてますけど、当然、打ち上げ、飲み会、懇親会のようなものに、女性スタッフや女性アナウンサーが参加するということは、ごくごく普通にあります。そこで信頼を得て、自分の仕事に将来、繋げるということは、ビジネスとして決して間違ったことではないと思います」――。
実際、第三者委員会の報告書でも、会食・飲み会への参加について問われたアンケートで、多数の女性社員から「女性社員が飲み会に参加できないような結果にはなってほしくない」との声が寄せられている。それは、取りも直さず、それら仕事絡みの会食等への参加が、自身の人脈や知見を広げ、先方の信頼を得る機会になると考える女性社員(女性アナ)が少なくないコトを証明する。また、先の文春等で報じられた接待文化・上納文化についても、大多数の社員が否定する旨の回答を寄せている。
現代の女性アナは局専属のタレント
そもそも――僕は、男女問わず局のアナウンサーとは、ある意味、局専属のタレント、スターだと思っている。かつて、映画会社は自社専属の看板スターを抱え、毎年入る新人を“ニューフェイス”と呼んだが、まさにアレと同じ構図。局の看板アナに、毎年脚光を浴びる新人アナ――今や彼らは単なる原稿を読む存在にとどまらず、報道からバラエティまで幅広くこなす、局をあげての(いわば)スターなのだ。
ゆえに、一般社員が(男女問わず)アナウンサーを会食等に誘う場合も、文春に書かれた“接待要員”などの不当な扱いはありえず、“ゲスト・スター”的な立ち位置になる。とはいえ、当の彼らは謙虚で、場を和ませるのが上手く、更に言えば“聞き上手”である。もちろん、最終的に参加するか否かの判断は、アナウンサー自身に委ねられる。その会食が自身のスキルアップに繋がると思えば参加する――それだけの話だ。
そして――かつて人気を博した映画俳優たちが、更なる活躍の場を求めてフリーに転じた(※俳優間の引き抜きを禁じた五社協定はやがて崩壊した)ように、アナウンサーの世界でも、人気の局アナともなると、いつからか30代で退職してフリーアナウンサーになるケースが増えてきた。フジテレビで言えば、八木亜希子サン、高島彩サン、加藤綾子サンらは、その先駆者だろう。男性の場合は40代でフリーに転じるケースも多く、古くは同局の逸見政孝サンや芸能事務所のタイタンに移籍した山中秀樹サンの例もある。
もちろん、現在、『めざましテレビ』で3代目総合司会を務める伊藤利尋アナや、夕方の『Live News イット!』でメインキャスターを務める宮司愛海アナのように、高い人気と実力を誇りながら、局一筋で頑張っている人たちもいる。どちらが正解という話ではない。それぞれが自分の実力を最も発揮できる場で、研鑽を積んでいるというコト。応援したい。
ちなみに、個人的な話をさせてもらうと、僕は少なからずフジテレビに知人がいるが、常々思うのは、同局の社員の仲間意識の強さである。それも、どこか同好会的な温かさを感じる。アナウンス室も同様で、他局よりもアットホームな空気がある。実際、アナウンサーのOBで、退職後も元の職場と仲良くしているのは、圧倒的にフジテレビの出身者が多い。
先にも記した1月18日のTBS系『情報7daysニュースキャスター』で、その日のゲストの弁護士の菊間千乃サンは、件の案件で、MCの安住紳一郎アナから(かなり気遣われつつ)元フジテレビアナウンサーとしての感想を求められ、こう答えた。少し長くなるが、とても大切なコトを語られたので、すべて紹介したい。
「誰かと食事に行ったことでレギュラーを取るとか、そんな仕事じゃないんですよ、アナウンサーって。やっぱり、皆さん一生懸命努力して、アナウンサー技術を磨いて、取材先の信頼を勝ち得て、視聴者の方々から指示を受けながら、すべてのアナウンサーは画面に出て、活動しているワケだから…。そこをヘンに今、誤解してる風潮がすごくイヤだなぁと思うのと、アナウンサーの皆さんは、そこは真摯に、仕事にしっかり向き合っていただいて、自信を持って、画面に出ていてほしいなと思います」
朝日新聞が指摘したナショナルクライアントの責任
ここで、かの朝日新聞が同案件をどう報じてきたかという話をしたい。もちろん、他のメディア同様、フジテレビに対する厳しい論調が目立つが、朝日ならではの“視点”もある。意外にも、識者を起用しながら、例のナショナルクライアントの“一斉CM差し止め”の責任や問題点に言及している。かいつまんで、引用させてもらう。
■スポンサー「判断」説明を
鹿毛康司さん(元エステー宣伝部長・クリエーティブディレクター)
「今回はフジという組織人格への大きな疑念が生じました。自社のCMを出していいメディアなのか。そういう根本的な不安が生じてしまった。ただ、広告主の対応は私も理解できる半面、かなり疑問も感じています。CMを降りる理由をきちんと説明せず『総合的な判断』などとコメントする企業が散見されたからです。総合的な判断とはいったいなんなのか。(中略)ドミノ倒しのようにACジャパンのCMだらけになったのを見て怖さも感じました。影響力が落ちたといってもフジはまだ大きなメディアです。それがこれほどたやすく追い詰められてしまうわけですから」
■社会の意識変化、見誤った
ベンジャミン・クリッツァーさん(批評家・哲学者)
「番組の内容を問題視してCMを中止するのは、表現の自由の侵害になる可能性があります。しかし、いま問われているのは、フジの企業としての体質です。(中略)一方で、スポンサー企業が黙ってメディアへの広告を中止するというのは好ましくありません。番組や記事の内容、政治的な姿勢を理由に、恣意(しい)的に広告を取りやめるといったことが常態化する恐れがあるからです。広告を止めたり、あるいは再開したりする場合には、その理由を明確に示すべきでしょう」
■広告だから、できる表現も
水野由多加さん(関西大名誉教授)
「この状況はフジの経営には痛手ですが、視聴者にとっては大きな問題ではないと思う人もいるかもしれません。(中略)しかし広告には公共性があることも忘れてはなりません。(中略)自分はどういう社会に生きているのか。この社会ではいま多くの人がどんなことを気にしているのか。そうしたことを考えさせる多様な情報を、広告にしかできないやり方で視聴者に伝えているわけです。(中略)CMが一斉に消えても社会に大した影響はない、とは言えないでしょう」
――いかがだろう。フジテレビと同様、ナショナルクライアントの各社もまた、説明責任が問われているのである。
“会の延長”なる謎ワード
おっと、ここまで随分とページを割いてしまったが、次の2番目の仮説――「『業務の延長線上』なるワードの違和感と、その真意」に移りたいと思う。安心してほしい。ここから先は、そう長くない。
週刊文春に、「会の延長」なる謎ワードが初めて登場するのは、文春砲第2弾の1月8日発売の1月16日号である。会の延長――なんとも不思議なコトバである。実生活で聞いたり、自ら口にしたコトのある人がどれだけいるのだろうか。そんな謎ワードが突如登場したのは、とりもなおさず、文春が先の“誤報”をなんとしても誤魔化そうとしたからである。
それが効いたのだろうか。第三者委員会の報告書でも「業務の延長線上」なる謎ワードが登場する。まぁ、言いたいコトはわかる。仕事場以外の場所――例えば、飲食店における取引先との会食であっても、広く業務の一環として認められる。ゆえに、支払われる費用は会社の経費として精算される。だから、タレントが自宅に客人を招いて食事を振舞うケースも――。
おっと、待った。本案件で、中居サンがご自宅にタレント仲間やフジや他局のスタッフらを招いたバーベキューと、その2日後に同じくご自宅に被害女性を招き入れた2つのケースにかかった費用は、すべて中居サンの手出しである。これも業務の一環なのだろうか。
一般論だけど、タレントとテレビ局の局員が懇意になり、プライベートで食事するコトは珍しくない。2人してレストランで会食して、その際、局員が支払い、会社の経費として落とすコトもままある(実際、仕事の話をしていたりする)。ただ、互いの自宅を行き交うくらいの仲になって、部屋で食事するケースも業務の一環かと問われたら、ちょっと疑問に思う。
第三者委員会も“グレーゾーン”と認識?
このあたり、第三者委員会の報告書も自信なさげである。被害女性が中居サンのご自宅に招かれた本案件に対するフジテレビの対応に、こうコメントしている。「少なくとも本事案を『プライベートの問題』と即断するのではなく、業務の延長線上の行為である可能性を認識して本事案について必要な事実確認をしたうえで対応を検討し、意思決定を行うことが適切であった」――。
どうだろう。“業務の延長線上の行為である可能性を認識して”――このまどろっこしい表現。本当に業務の一環と思うなら、素直に“業務”と書けば済む話。それが、“業務の延長線上の行為である可能性を認識して”――それは果たして業務を指しているのだろうか。少なくとも、かなりグレーゾーンであるコトを、当の第三者委員会も認めているようにも見える。
実際、文春が被害女性に「会の延長」と言わせた(と想像します)、その基になった2日前のバーベキューにしても、報告書では「本事案が(BBQ の会の延長ではないとしても)……」と、あっさり“延長ではない”と却下している。とすれば、フジテレビが本案件を当初から“プライベートな案件”と位置付け、一連の対応を取ってきたコトも、グレーゾーンを考慮すれば、全くありえない判断ではなかったとも。同社が本案件をコンプライアンス推進室に伝えなかったのも、中居サンを番組から降板させるよう強く働きかけなかったのも、“プライベートな案件”を前提とすれば、“誰にも知られずに復帰したい”という(当初の)被害女性の思いとの整合性も付く。
一方で、被害女性の心身のケアについては、第三者委員会の報告書を読む限り、アナウンス室の人たちは真摯に、懸命に寄り添ってきたように見える。文春の記事にある“(フジが)何一つ味方になってくれない”は、まるで当てはまらない。おそらく、フジ側は、3月31日に第三者委員会の報告書が上がってくるまで、本案件を“プライベートな案件”と認識しており、その判断は当の第三者委員会自身もかなりグレーゾーンにおける判断だったのではないだろうか――。
特ダネを発信し続ける小学館
お待たせしました。いよいよ、冒頭の朝日新聞の記事にも関わってくる、最後の仮説――「結局、中居正広さんは何をした?」に移りたいと思います。もちろん、既に2人の間で示談が成立して解決済みの案件。守秘義務があり、基本的には、その真相が当事者から語られるコトはないと思います。
ただ、朝日新聞の記事によると、新たに中居正広サンの代理人に就任した弁護士チームが、かの第三者委員会に対して、報告書にある「性暴力」認定を「極めて大きな問題がある」と反論した上で、関連する証拠の開示を求めたという。
実際、代理人らは、中居サンに詳細な聞き取りを行い、関連資料を精査した結果、「『性暴力』という日本語から一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されなかった」と。またWHOの広義な定義を使用したことで、「中立性・公正性に欠け、一個人の名誉・社会的地位を著しく損なった」とも。まぁ、その展開次第では、この先どうなるか――ですね。
一方で、示談が成立する以前に、何らかのカタチで、あの日の出来事が(正確性は別として)外部に語られた形跡があるのも事実。俗に“芸能界の噂は光よりも速い”と言われる通り、一度漏れたら、間違いなく拡散します。なので、本コラムでは、これまで方々で語られた記事等をベースに、中居サンの“真相”に近づきたいと思います。
この案件、最初からずーっと俯瞰して見ていると、要所要所で特ダネを発信しているのは、文春ではなく、女性セブンや週刊ポストを発行する小学館なんですね。昨年12月19日発売の女性セブン(1月2・9日号)で本案件を最初に独占スクープしたのもそうだし、各誌の報道が一巡した後、1月17日発売の週刊ポスト(1月31日号)で被害女性に「私はそんなにたくさんのお金(解決金9000万円)をもらってません!」と梯子を外させたのもそう。
かと思えば、1月23日発売の女性セブン(2月6日号)では、自宅に引き込もる中居正広サンの部屋の中の様子を“どのチャンネルに変えても自身についての報道が繰り返し流れる大画面のテレビを見るともなしに見つめていた”と詳細に報じている。被害女性、中居サンともに、小学館に太いパイプがあるのは事実だろう。
中居正広さんが反撃の狼煙?
そして――4月24日発売の女性セブン(5月8・15日号)では、「中居正広『黙ってられるか』反撃準備」と題して、これまた他誌が掴んでいないスクープを報じた。記事によると、中居サンは件の第三者委員会が下した“性暴力者”の烙印に強い抵抗があり、新たに強力な弁護団を結成し、同委員会に異議を唱える準備を検討しているという。そう、これが冒頭の朝日新聞の記事へと繋がる。恐るべし、小学館である。
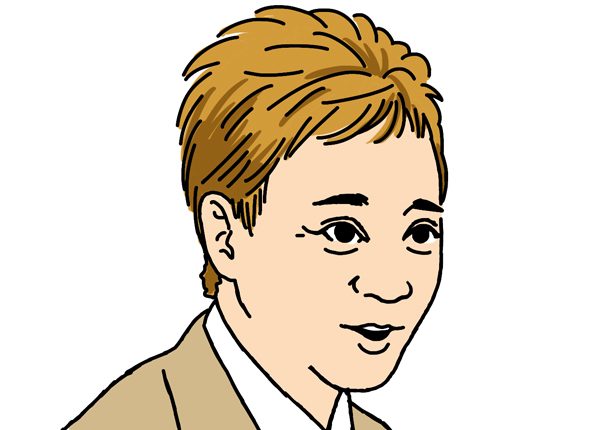
ここで注目したいのは、それは被害女性に対するアクションではなく、あくまで“第三者委員会”への反証というコト。中居サンの性格を思えば、被害女性への“二次加害”に繋がりかねない行動は避けるだろうし、そもそも守秘義務を解除しなかった(※朝日の記事によると、当初、中居サンから解除が提案されたが、同委員会から“直接の調査対象ではない”と言われ、引っ込めたとも)のも、彼女を二次加害から“守る”ためだったと推察される。それがファンのイメージする「中居正広」像の近似値じゃないだろうか。そう、“保身のために女性を売らない”男と。
改めて、第三者委員会が中居正広サンに対して行なった「認定」のくだりを読んでみよう。そこには、こう書かれてある。「女性 A が中居氏によって性暴力 による被害を受けた」――。同委員会は、その根拠として、世界保健機構(WHO)の「性暴力」の定義を挙げる。以下がそう。
“強制力を用いたあらゆる性的な行為、性的な行為を求める試み、望まない性的な発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為をいい、被害者との関係性を問わず、家庭や職場を含むあらゆる環境で起こり得るものである。また、この定義における「強制力」とは、有形力に限らず、心理的な威圧、ゆすり、その他脅しが含まれるもので、その強制力の程度は問題とならない。”
――これだけを読むと、定義が広すぎて、今一つピンとこない。だが、これを受けて第三者委員会が補足した文章のほうに、実は重要なヒントがある。報道や識者たちはWHOの定義ばかりをクローズアップするが、第三者委員会がわざわざ付け足したほうに、あの日、2人の間に何があったのかの重要なヒントが隠されている。それが、以下の一文である。
“「性暴力」には「同意のない性的な行為」が広く含まれており、「性を使った暴力」全般を意味する。”
そう、わざわざ第三者委員会が付け足したというコトは、2人の間に「同意のない性的な行為」があった(と推察される)と、半ば明かしたようなものではないだろうか。性暴力と聞くと、力ずくで行為に及ぶ姿を想像しがちだけど、そうじゃない。一見、同意のように見えても、被害者が“内心”拒んでいれば、「同意のない性的な行為」=広義の性暴力が成立するのである。
これまでも“暴力”は否定されていた
一方、2人の間に、目に見える“暴力(脅迫)”がなかったコトは、1月9日に中居正広サンが自身の公式サイトで発表したお詫びコメントでも明かされている。「このトラブルにおいて、一部報道にあるような手を上げる等の暴力は一切ございません」――。
この声明文、公開にあたり“守秘義務”にも関わるので、事前に被害女性側の弁護士に確認を取り、了承を得た上で公開されている。ちなみに、よく批判される「なお、示談が成立したことにより、今後の芸能活動についても支障なく続けられることになりました」も、被害女性側の了承が得られたコトを指しており、中居サンが勝手にそう思い込んでいるという意味じゃない。
それと、業界一法務部が厳しいとされる週刊文春も、あれだけ本案件を報じながら、これまで、ただの一度も記事内で“性加害”という文言を使っていない。それは、取りも直さず、2人の間に“暴力(脅迫)”に値する行為はなかったと、(被害女性の知人らを介して)文春が掴んでいたからではないか。
また、昨年12月19日に独占スクープした女性セブンの記事には、芸能関係者の話として、本案件が報じられる以前の民放他局の“判断”も記されている。件の噂が業界内に広まり始めた2024年10月上旬ごろの話だろう。“中居さんがトラブルを抱えているという話は、フジテレビ以外の局にも伝わり、各局が水面下で調査する事態に発展しました。(中略)問題は『解決済み』とみなされ、いまのところフジテレビ以外では番組終了などの対応は出ていません”――。そう、おそらく各局ともそれなりに精度の高い情報を仕入れたものの、明らかな暴力行為は認められず、示談済みの案件でもあり、中居サンの番組を続行したのだろう。
何より――当のフジテレビが、本案件を3月31日に第三者委員会から報告書が上がってくるまで“プライベートな案件”と認識しており、仮に暴力行為が伴うものであれば、とてもそんな判断はできなかっただろう。図らずも、第三者委員会から批判された一連のフジテレビの対応が、中居正広サンが暴力を振るっていない、何よりの“状況証拠”になったのではないだろうか。
結局、中居正広サンは何をしたのか?
このコラムもいよいよ終わりが見えてきた。結局、中居正広サンは何をしたのか――。
まぁ、本当のトコロは当事者2人にしか分からない。一応、状況証拠として言えるコトは、暴力や脅迫行為はなかったものの、第三者委員会曰く「同意のない性的な行為」が行われた、と。一方、中居サン側の認識としては、週刊文春(3月6日号)の記事によると、彼の知人曰く「中居くんは周囲に『合意(の上)だったんだけどな』と話していた。その根拠として、事件直後にX子さん(※被害女性)が中居くんに感謝を述べるショートメールを送ってきたことなどを挙げていました」と――。
これに関連して、4月6日の『Mr.サンデー』(フジテレビ系)で、社会学者の古市憲寿サンが興味深いコトを指摘していた。「この(第三者委員会の)報告書って、書かれていないことがいくつかあるなと思っていて。(中略)6月2日に事案があって、(その次は)6月6日に飛んでいるんですね。6月3日、4日、5日のことが空白になってる」――そう、同報告書には、案件の翌日から3日間の記述がスッポリ抜け落ちている。いきなり6日に被害女性がフジテレビの産業医に泣きながら電話する場面に飛んでいる。いわゆる“空白の3日間”である。
報告書によると、第三者委員会が認定した、当事者2人の守秘義務の範囲は、「2023 年 6 月 2 日に女性 A が 中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの事実」および「示談契約の内容」である。そこで2人には、それ以外の部分のヒアリングをしたという。また、中居サンからは個人使用のスマホが提出され、削除済みのショートメールがすべて復元された。実際、案件当日に中居サンがショートメールで女性を誘う様子は、同報告書に記されている。
だが、空白の3日間については、2人にヒアリングをした内容も、先に中居サンの知人が明かしたショートメールの記述もない。2人の間でやりとりがなかったとも書かれていない。ただ、状況証拠として――案件当日は“中居サンは合意と思って”おり、それを証明するように、(おそらく)翌日に“女性から中居サンに感謝を述べるショートメールが送られた”。しかし、案件から3日後、突如“被害女性がフジテレビの産業医に泣きながら電話した”のである。
第三者委員会の報告書には、こう書かれている。「当該事実(案件当日の守秘義務に関する部分)は、女性 A の人権及びプライバシーに関わる事項を含むものであることから、女性 A の人権及びプライバシーを尊重し、女性 A から同意が得られた範囲で調査報告書に事実を記載した」――つまり、“空白の3日間”に、2人の間で交わされたショートメールのやりとりは、守秘義務に関する内容を含んでおり、被害女性の同意が得られず、記載できなかった可能性が高い。ただ、その結果、案件前に中居正広サンの被害女性への“誘い文句”ばかりがクローズアップされ、案件の前後でバランスを欠く報告書になった感は否めない。ちなみに、件の誘い文句に登場するのは、フジの編成幹部の名前である。
被害女性がフジテレビの産業医に泣きながら電話してから、およそ1ヶ月後の7月10日、女性は都内病院の消化器内科に入院する。そして同月末、精神科に転移し、「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」と診断される。その後の経過は、承知の通りである。入院中、被害女性が心身ともに衰弱し、筆舌に尽くし難い苦しみにさいなまれたのは事実である。心より、ご心情を察します。
第三者委員会の意味
――以上が、僕がこのコラムの冒頭で提示した3つの仮説の、僕なりの答えである。
①ナショナルクライアント(大手企業)による“一斉CM差し止め”の本当の理由
②『業務の延長線上』なるワードの違和感と、その真意
③結局、中居正広さんは何をした?
これら3つの仮説は、第三者委員会の報告書が、週刊文春の“世紀の誤報”を「ミニマム」のひと言で済ませてしまったコトから始まった。結論として、今に至るフジテレビへの一斉CM差し止めの直接の原因は、やはり、あの誤報に端を発する“上納”報道にあったと思うし、同報告書で「業務の延長線上」なる謎ワードを用いたのも、文春の誤報が元になったのは明らか。そして、肝心の「結局、中居正広さんは何をした?」も――最大の鍵を握る“空白の3日間”のやりとりが握り潰され、一方で案件当日の中居サンの被害女性への誘い文句のみがクローズアップされる、著しくバランスを欠いたものに。ソコにあったのが、渦中の編成幹部の名前だった。
まぁ、生け贄とは言いたくないが、第三者委員会がことさら文春の誤報を「ミニマム」で済ませたかった背景にあるのは、件の“編成幹部”に責任を過重に押し付けたかったからではと、個人的には想像する。ちなみに、273ページにも及ぶ同報告書は、以下の一文でしめられている。
foxcale による削除データの調査の結果、特に B 氏(※編成幹部)は、2022 年 5 月 9 日から 2025 年 1 月 10 日までに、有力出演者タレント U 氏、中居氏、K 弁護士との間でやりとりしたショート メールチャットデータ 325 件を 2025 年 1 月 9 日から 2025 年 2 月 1 日にかけて削除していることが認められた。
以 上
ちなみに、本案件の関係者の削除されたデータの総数は1950。編成幹部はそのうちの16%に過ぎない。なのに、膨大なページ数の報告書のトリを“一社員”が飾ってしまった。もちろん、彼がやったコトは褒められたもんじゃない。過去2件あった“置き去り案件”に共に関与しているし、少なくとも案件後の中居正広サンとの接し方は、自重すべきだったろう。
ただ、今回の一連の案件は、誰か1人に責任を負わせて解決するものじゃない。また、誰か1人が引き起こしたものでもない。第三者委員会は中立・公正を原則とする。ゆえに報告書は原則匿名表記となり、裁く対象は“ヒトではなくコト”でなければならない。そこが裁判所と決定的に異なる。守るべきは人権であり、示すべきは再発防止への道筋と――。
被害女性は2020年4月に念願の仕事に就いたが、そこから3ヶ月間――突如、世界を襲った新型コロナウイルスの影響により、自宅待機とリモート研修を強いられた。更に入社から3年間、未だ社内外のコミュニケーションはままならず、同期との飲み会も自粛させられ、当初思い描いた社会人生活を満足に送れなかったコトは容易に想像できる。彼女だけじゃない。2020年入社組の全社会人に同じコトが言える。そんな彼らが、何かのキッカケで心身のバランスを崩したとしても不思議じゃない。
2011年、国連人権理事会において「国連ビジネスと人権指導原則」が全会一致で承認された。それを機に、企業がライツホルダーの国際的に認められた人権を尊重する責任を果たすべく、近年、企業不祥事における第三者委員会の存在感が増している。当委員会の報告書でも、随所に“人権”に関する記述が見られ、その数は実に728箇所に上る。
その反面――同報告書では原則匿名表記の中、中居正広サンを例外的に実名表記し、彼を一方的に“性暴力”者と認定した。更に一社員の編成幹部をやや過剰に、“個人的に”追及する箇所が随所に見られた。
本当に、人権は守られたのだろうか。