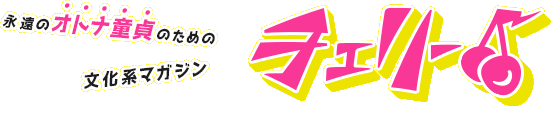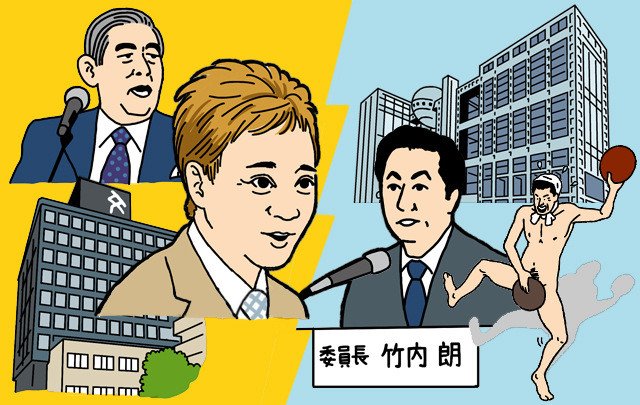初めに断っておくが、これはコラムである。
先の5月中旬、『少しクールダウンして、フジテレビ&中居正広さん案件を改めて考える』と題して、かなり長めの文章を書かせてもらってから、早やふた月あまり――。もう、この案件に触れるコトはないと思ってたけど、その後も様々なコトが報じられ、また、前回書き足らなかったコトもいくつか生じたので――今回、改めて一連の問題を冷静に、シンプルに整理して、その先の“ゴール”を見据える【完結編】と題したコラムを書かせてもらいました。
現状、先の6月25日のフジ・メディア・ホールディングス(以下、FMH)の株主総会で会社提案の取締役11人が全員選任され、そして7月6日には『検証 フジテレビ問題 ~反省と再生・改革~』と題した検証番組を放映し――まぁ、フジとしては、ひとまず懸案だった2つのヤマ場を乗り越えたというトコロでしょう。とはいえ、未だナショナルクライアントが完全復帰するメドは見えず、また敗れたとはいえ、アクティビスト(物言う株主)のダルトン・インベストメンツの次の一手や、筆頭株主として存在感を増す野村絢氏(あの村上世彰氏の娘である)の今後の動きも気になるトコロ――。
なので、本コラムは、この一連の案件の何が一番重要で、フジテレビや中居正広サンはどこへ向かおう(ゴール)としているのか――を極力シンプルに、分かりやすく解きほぐしたいと思います。
まず、一連のフジテレビ&中居正広サン案件の全体像を俯瞰して眺めると、意外に論点はシンプルなコトに気付きます。要するに――
①フジテレビが一番大切にしているコト
②中居正広サンが一番大切にしているコト
③フジテレビが今後、目指すべきコト
――ざっくり言えば、本案件が抱える諸問題は、この3つに集約されると思います。順を追って説明しましょう。
フジテレビが一番大切にしているコト
まず1つめ、フジテレビが一番大切にしているコト。これはシンプルに“ナショナルクライアントに戻ってきてもらう”――この一点に尽きます。ナショナルクライアントとは、日本を代表する大手企業のコト。1つの指標として「日本アドバタイザーズ協会」、かつての“主協”(ぬしきょう)に加盟する200数十社を指すとも言われます。

思えば、日本で民間放送が始まったのが1953年。ソコから今日まで民放テレビ局は、彼らナショナルクライアントと二人三脚で、世界最大(アメリカの4大ネットワークを上回る5大ネットワーク)の民放テレビ文化を築き上げました。そんな中、キー局の1つが半年以上に渡って、ナショナルクライアントから一斉にCM差し止めを食らうなんて、前代未聞。コレ、掛け値なしに、日本の民放史における“超・非常事態”なんです。
つまり、コレはもはやフジテレビ一社の問題じゃないと。盤石に見えた日本の“民放のビジネスモデル”が、意外に脆弱(ぜいじゃく)だったと露呈したのが本案件。フジとしては、他局に迷惑をかけない意味でも、何を置いても、この局面を変えないといけない。ゆえに、あの3月31日の第三者委員会の報告からココまで、同社の行動はすべて、“ナショナルクライアントの復帰”に向けて突き進んできたと言っても過言じゃない。以下、時系列で同社の動きを記します。
4月3日
総務省がフジテレビの清水賢治社長とFMHの金光修社長(当時)を呼び出し、「放送に対する国民の信頼を失墜させた」と、厳重注意。人権尊重や法令順守に関する強化策の具体化と、その実施状況を逐次報告するよう要請。4月30日
フジの清水社長とFMHの金光社長が総務省を訪れ、前述の再発防止策「フジテレビの再生・改革に向けた8つの具体的強化策」を提出。その中身は、人権ファーストの徹底、アナウンス室の編成・制作部門からの独立、女性管理職の比率UP、若手リーダーの積極登用、そしてフジテレビを長く牽引してきたスローガン「楽しくなければテレビじゃない」からの脱却――等々。5月16日
FMHが新取締役候補者11人を決定。そのココロは――①清水賢治次期社長以外の取締役を一新(前体制の払しょく)、②取締役のスリム化(22人→11人)、③過半数を社外取締役に(透明性・客観性の確保)、④女性比率を3割以上に(45.5%)、⑤平均年齢の引き下げ(10歳以上若返り)――等々。5月30日
フジの清水社長とFMHの金光社長が総務省を訪れ、先の4月30日に提出した「再生・改革の8つの具体的強化策」の進捗状況を報告。「全社員の対面グループ研修を実施し、1000人以上が出席(全社員数1160人)」、「女性管理職を3割以上にUP」など、強化策8つのうち6つで“概ね実行済み”。6月3日
林芳正内閣官房長官が定例会見で、読売新聞記者の質問に答えるカタチで、政府のフジテレビに対する広告出稿を「今後は各府省で広告の趣旨、効果などを勘案し、適切に判断して対応する」と、再開する方針を表明。6月5日
フジテレビが一連の問題に関して、当時の編成幹部に4段階降職と一ヶ月の懲戒休職を課すなど、関係社員らの処分を発表。また、問題発生時に代表取締役社長だった港浩一氏と専務取締役だった大多亮氏の法的責任を追及することを同社監査役が決め、訴訟の準備に入ったと表明。6月9日
それまで経営陣と対立していたフジテレビ労働組合が、経営陣が提示した再生・改革プランに賛同の意を表明。6月10日
アメリカの大手議決権助言会社のインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)が、FMH側の候補全員に賛成を、ダルトン側の候補全員に反対を推奨すると表明。6月19日
フジの清水社長が被害女性に対面で謝罪。両者は、被害女性を誹謗中傷から守る措置を講じるように努めること、今回の事案で被った経済的・精神的損害に対する補償を行うことなどで合意。6月25日
FMHの株主総会が開催され、清水賢治新社長ら会社提案の11人の取締役が選任。全員、賛成率が80%を超える一方、ダルトン側の12人は、いずれも賛成率が30%未満と惨敗。6月27日
サントリーと大和ハウス工業が、先の結果を受け、7月からフジへのCM出稿を再開すると表明。30日にはロッテと大東建託も追随。7月6日
フジテレビが一連の事案について『検証 フジテレビ問題 ~反省と再生・改革~』と題した検証番組を放映。
――とまぁ、この3ヶ月間、フジの清水社長はFMHの金光社長(当時)と共に、ひたすら平身低頭に、ナショナルクライアントに戻ってきてもらうよう、その一点に集中して、ぬかりなくモノゴトを進めてきたのがお分かり頂けると思う。
意外にヤリ手だった清水賢治新社長
清水社長、パッと見はごく平凡なサラリーマン社長に見える。しかし、次々に有効な手札を切ってきたあたり、ある種の胆力すら感じる。中でも驚いたのが――そう、前任者2人の法的責任を問う訴訟の準備に入ったという表明。正直、その非情な措置に複雑な感情を抱くフジテレビ関係者や業界関係者も少なくないけど(僕もその一人だ)、ナショナルクライアントに戻ってきてもらうためには、先の株主総会を“完勝”に近いカタチで乗り切る必要があり、「肉を切らせて骨を断つ」じゃないけど、ソレくらいフジテレビは本気だと周囲に見せる必要があったのは確か――。

ただ、その非情な措置について、実は僕はもう一つ、別の見方もしていて――。ソレについては後段の《フジテレビが今後、目指すべきコト》のブロックで、改めて語りたいと思います。
さて、そんな風に株主総会を全力で“取り”に来たフジに対して、片や惨敗したダルトンだけど、正直――彼らの仕事が終始杜撰だった感は否めない。外国人が取締役に入ると「放送持株会社」の認定を取り消されると知って、慌てて候補者を日本人に差し替えたり、「監査等委員」を取締役候補(12人)の中に入れ忘れたり、スリム化・多様化したフジの取締役に対して、その人数も女性比率も遠く及ばなかったり――。
そもそも先陣を切って会見したSBIホールディングスの北尾吉孝会長からして大誤算だった。横柄な態度、その経営ビジョンは20年古く、何より“テレビ愛”が微塵も感じられなかった。こんな人にフジテレビを任せられないと、多くの株主がネガティブな反応を示したのは事実である。ぶっちゃけ、勝負は最初から見えていたとも――。
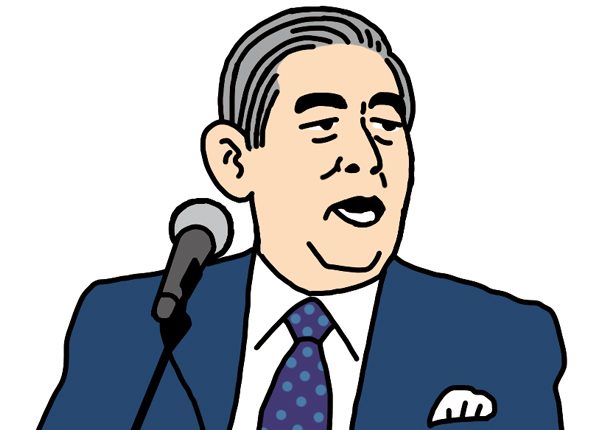
ナショナルクライアント復帰のカギは“空気”
とはいえ、肝心のナショナルクライアントはいつ全面復帰するのか――。その話題になると、当のフジテレビを始め、誰も答えられないのが実情である。なぜなら、ソレを阻んでいる一番の要因が、世間の“空気”だから。この3ヶ月間、フジテレビが万全のカードを切ってきたコトは、先の株主総会の圧勝を見れば明らか。ただ、CM復帰となると、世間の空気が元に戻るしかなく、これが一番読めない。
ちなみに、先の5月30日、フジテレビが総務省を訪れ、「再生・改革プラン」の進捗状況を報告した際に、取引先のスポンサー200社に聴いた“CM再開”へのアンケート結果も公表した。それによると、3割の企業が“フジの改革次第で”と、再開に前向きな意向を示した一方、7割はソレでも保留を表明したという。問題はその理由。「他社の動向や世論の動きを見て判断する」――要は“世間の空気を読んで、横に倣います”と。結局、この話はソコに行きつくんです(ヤレヤレ)。
一応、フジの清水社長の腹づもりとしては、先の6月10日の東洋経済のインタビュー記事によると、「(ナショナルクライアントの)CMが回復し始めてくるのは(株主総会を終えた)7月以降ではないか。第4四半期(来年の1~3月)くらいに例年並みに戻り、来期以降、本格的に戻ってくれればありがたいと考えている」とのコト。さて、どうなるか。
まぁ、1つ救いがあるとすれば、現在、フジテレビの社内は、かつてないほど社員が一つになっているという。先の株主総会の当日、ワイドショーの『ゴゴスマ』(TBS系)に出演した元フジテレビの内田恭子サンも、件の話を振られ、「一連のこの騒動の中で、フジテレビの社員の方と話していても、やっぱりみんなあの騒動の後、もう一致団結している空気がすごく会社内にあって。みんなで前を向いて行こうという気持ちにすごくなっている」と答えている。
フジの“類似事案”を冷静に考える
ただ――うーん……コレを言うと怒られるかもしれないけど、そもそもフジテレビはソコまで断罪(日本の民間放送史上類を見ない、ナショナルクライアントから半年以上にも渡ってCM差し止め)されるほど、極悪非道なコトをしたのだろうか。第三者委員会の報告書には、中居正広サンと被害女性のトラブルのほかに、全社員を対象に行われた“類似事案”に関するアンケート結果も結構な分量で記されている。ソコには取引先(出演者、芸能プロダクション、制作会社、スポンサー、広告代理店など)との会合(懇親会、食事会)において、社員らが関わった様々なセクハラ・パワハラのエピソードが赤裸々に綴られている。以下、例を挙げる。
〇部長クラスの社員が、若手女性社員を喜び組と呼び、芸能プロダクションのトップとの会合に、喜び組でも呼んどけ、と言っていた。
〇CX 社員から広告代理店の女性社員へのセクハラ的言動が散見される
〇広告代理店から CX 女性社員へのセクハラ的言動が散見される。
〇広告代理店との会合は毎回セクハラまみれの会と聞いた。
〇女性アナウンサーにスポンサーが喜ぶから会食に参加してほしい旨の依頼があったと聞いた。
〇役員に誘われた会合にいた出演者が下ネタばかり話した。
〇役員自らが下ネタを振ってきた。
〇取材先から身体に関する情報を教えたら情報を渡すと言われた。
〇政治部や社会部では、女性アナウンサーや若手の女性社員やスタッフを「勉強になる」「人脈作り」等として、取材先の会合に連れ回すこともあった。
〇取材相手とともに毎日ナイトクラブに行き、深夜まで酒を飲み、スキンシップを求められた。
〇有力な番組出演者との個室での飲み会において、若手男性社員と若手男性出演者が全裸になり、どちらが面白く酒をつぐことができるかを競い合うということが行われていた。その場に女性社員も同席していた。
――とまぁ、コレは一部だけど、なかなか眉をひそめたくなる惨状ではある。ただ、注意してほしいのは、同調査は過去10年について調べたものであり、申告された事例の多くはコロナ禍前の2010年代――つまり平成の話だろう。僕の知る限り、コロナ禍の令和以降、フジに限らずメディア業界全体の飲み会が激減し、特に二次会は壊滅した。そして、先の惨状の多くは特段、フジに限ったハナシじゃないとも。実際、食事会に“花”を添えようと、若手の女性社員が呼ばれたり、彼女らが得意先へのお酌を強要されたり、望んでもいない下ネタを聴かされたり――といった悪習は、フジテレビに限ったハナシだろうか。あなたの会社は過去10年、その種の案件が一度もなかったと言い切れるだろうか。
フジテレビの社風が高じたセクハラ
一方で、こちらはフジテレビに昔からはびこる悪習というか、社風が高じて、セクハラやパワハラに発展したケースもある。例えば、“喜び組でも呼んどけ”――なる発言。コレ、誤解なきよう、本当に女性社員らをそう見ていたワケじゃなく、同社特有の“何か面白いコトを言わなくちゃいけない”社風が高じてのもの。女性社員も参加した個室の飲み会で、若手男性社員と若手男性タレントが全裸になってお酌のパフォーマンスに興じた一件もその類いである。
実際、フジの社風をよく知る人物のハナシとして、先の4月中旬、YouTubeで配信された『真相深入り!虎ノ門ニュース』の中で、MCの生明辰也サンが、ゲストの北村晴男弁護士から同話題を振られ、こんな風に答えている。彼はフジテレビ系列の山形県のさくらんぼテレビ出身のフリーアナ。同局の上層部には元フジの社員が多数在籍し(天下りである)、身をもってその社風に接してきたという。
「風潮として、ソレ(自ら全裸になるコト)が面白い番組を作るために必要なんだ……くらいに考えてると思うんです。“喜び組”発言に関しても、こういう風に例えたら面白いだろ?……くらいの感覚ですね」
ソレともう一つ――これはフジに限らず、テレビ局や大手広告代理店などマスコミ業界全体にも言えるコトだけど、俗に「年次の壁は海よりも深い」と言われるように、昔から同業界は部署にもよるけど“体育会系”気質が強い。なので、宴席の場で若手男性社員が自ら率先して、裸踊りに興じるケースも珍しくない。ぶっちゃけ、コロナ禍前まで大手商社や老舗の家電メーカー、大手ビール会社などにもそういう風潮はあった。分かりやすく言うと、有名大学のラグビー部出身の社員が多い会社なんてそう。その源流は、英国のエリート養成機関、パブリックスクールにあったり――。伊藤忠なんて、若手男性社員の裸踊りが伝統芸能化して、今や貴重な見せ物として、微笑ましく報じられるほど。要は、メディアを始め、その種のメディアと関わりのある業界全体が長らく共犯関係にあったんです。
そう言えば、漫画『課長 島耕作』にも同種のシーンがある。ある年の暮れ、社用カレンダーの欠陥が発覚し、大阪の販社に謝罪するために中沢部長と島耕作が先方の宴席へ出向く。そこで島は「裸踊り」を強要され、『冗談じゃない』と内心、気色ばむ。すると――横から中沢部長が「裸踊り? それ私の得意芸ですわ」とおどけるフリをして、両手にお盆を持って“かっぽれ踊り”を披露したエピソードである。
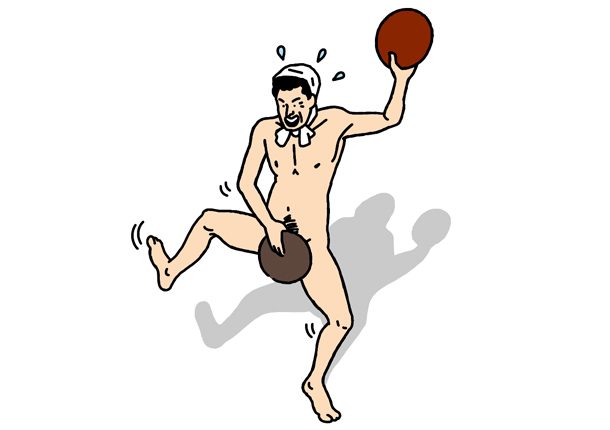
フジに限らず、社会全体に向けられた警鐘
まぁ、そんな風に、大企業に古くから伝わる裸踊り(伝統芸能)は、源流である英国のパブリックスクールの“男子校文化”を受け継ぎ、昭和の男性社会ゆえに成立した文化とも。ソレが1986年の男女雇用機会均等法から女性が総合職で採用されるようになり、平成以降、普通に彼女たちも宴席の場に呼ばれるようになると――その時初めて、男性陣は女性からの指摘で“裸踊り”がハラスメントであるコトに気付かされたと。そうして次第に伝統は衰退し、消えていく中、マスコミを始めとする一部の体育会系企業のみ2010年代の平成の終わりまで悪習が残っていた――ソレが報告書にも記された類似事案の正体だ。
――つまり、あの報告書の後半部分については、フジテレビ一社に限ったハナシではなく、コロナ禍前までのマスコミ界隈始め、日本の大企業に蔓延した古き悪習を可視化したもの。つまり、世のすべての男性に向けた警鐘だと思う。ライバル局やナショナルクライアントの人たちは、アレを“他人事”とは思わず、自らも改める糧にした方が建設的だと思います、ハイ。
それと、一見矛盾するような話だけど、報告書にはこれら一連の記述の最後に、フジテレビの女性社員の総意として、次の一文で締められている。――「女性社員が飲み会に参加できないような結果にはなってほしくない」。
そう、こういうコトがあると、臭いものに蓋じゃないけど、全部禁止にしてしまえと極論に走りがちだけど――そうじゃないと。正すべきは、飲み会(懇親会、食事会)をなくすコトでも、男女をゾーニングするコトでもなく――仕事を進める潤滑油として、その必要性を正しく認識した上で、男女問わず、“個人の意思”で自由に参加を決められるコトである。
おっと、1つ目の「フジテレビが一番大切にしてるコト」に思いのほかページを割いてしまった。安心してほしい。ココから先はそれほど長くない(……と思う)。
中居正広サンが一番大切にしてるコト
さて、冒頭で記した本案件の2つ目の論点「中居正広サンが一番大切にしてるコト」に移ります。周知の通り、中居サンの新弁護団がフジテレビの第三者委員会に対して、報告書の“性暴力認定”に公開書面で反論したのが、先の5月12日。曰く「中居氏から詳細な事情聴取を行い、関連資料を精査した結果、本件には『性暴力』という日本語から一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されませんでした」――。
その後、第三者委員会は、一度は回答に応じたものの、旗色が悪くなったのか、6月3日に「今後のやりとりを差し控える」と一方的に打ち切り――。さすがに、それはないんじゃないの?――と思っていたら、7月5日に中居サンの弁護団から改めて「ヒアリング中の中居氏へのパワハラ疑惑」や新たに発覚した「報告書の取り扱いに関する疑惑」等が発せられると、その2日後には第三者委員会が慌てて疑惑を打ち消すコメントを発表――と、何のかんので、やり取りは続いている。
ところで、なぜ3月31日の第三者委員会の報告からひと月半も経って、中居サンは突如反論したのか。新たに弁護団を組み直して、内容を精査したり、新たに調査や資料集めなどをしていたら、ソレくらいはかかると言われるものの――僕はもう一つ、別の理由があったのでは?と推測する。
中居サンの性格を思えば、既に引退した身であり、単に自身の名誉回復のためにソコまでやるというのは、ちょっと考えにくい(分かる方には分かると思います)。その一方、今もSNSでは「中居ヅラ」と呼ばれるファンの人たちの変わらぬ思いが散見される。あるいは、そんな書き込みを見て、中居サンが立ち上がったのかもしれない。自分が世間からどう見られようと構わない。ただ、ファンの人たちまで「性暴力者のファン」と後ろ指を指されるのは耐え難い――と。
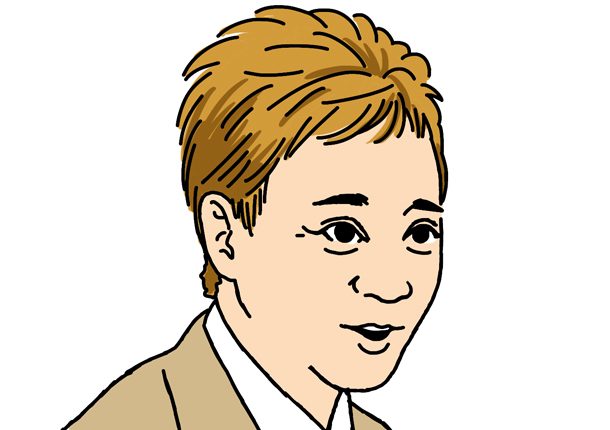
故・河島英五サンの『時代おくれ』には、“自分のことは後にする”という歌詞がある。思えば、中居サンも昔からそんな気質の人だった。例えば、普段の自分の食事はカップ麺等で軽く済ませつつも、座長を務める番組の共演者やスタッフには、定期的に高級寿司折や叙々苑の焼肉弁当などを150人から200人分、さりげなく差し入れるなど(総額100万円ほど!)――その気遣いと男前っぷりは業界でも評判だった。となれば、件の報告書から反論までタイムラグがあったのも、ファンの思いに心を動かされて……と思えば、不自然じゃない。
そう、「中居正広サンが一番大切にしてるコト」――ソレは、ファンの人たちが後ろ指を指されないよう、自身に向けられた“性暴力者”なるレッテルを払拭するコト。それ以上でも以下でもなく。むろん、自身の芸能界への復帰などは微塵も考えていないだろう。そういう人だ。
橋下徹氏が指摘した第三者委員会の3つの誤り
では――中居サンの弁護団は今後、どんな戦略をとってくるのだろうか。引き続き公開質問状を発信し続けるのか、どこかで第三者委員会と話し合いの場を設けるのか、あるいは裁判に訴えるのか――。正直、ソレは分からないけど、落としどころのカギとして、同じく弁護士である橋下徹サンが先の5月22日に、自らのXに投稿したポストに色々ヒントがありそうだ。
ソコには、遡ること一週間前に、橋下サンが関西テレビの『旬感LIVEとれたてっ!』に出演した際に発したコメントについて、週刊文春から受けた質問に答えるカタチで自身の見解が綴られている。かなりの長文だが、ざっくり言うと、橋下サンは以下の3点で、件の第三者委員会にダメ出しをしている。
① フジテレビ第三者委員会は、フジテレビの依頼に基づいて、同社の組織的な問題の解明とその対策を提言することが職務。それ以外の第三者の行為について断罪し、制裁を加える権限を全く持たない。
② 仮に第三者委員会が中居氏の行為を法的に評価し、断罪するのであれば、中居氏の主張をしっかりと聞くだけでなく、関係資料や相手方女性・関係者の証言について、中居氏の反対尋問権・防御権をしっかりと確保することが必要不可欠。
③ そもそも第三者委員会が中居氏の行為について、一般読者・視聴者の普通の注意と読み方を基準(最高裁昭和31年7月20日判決)としたときに、あたかも刑事法に触れるかのような表現である「性暴力」との表現を用いて断罪したことは完全に越権行為。
――このうち、①と②は中居サンの弁護団も再三指摘しているので、いわゆる法曹界の共通認識と見ていいだろう。実際、第三者委員会がその回答を拒み続けている様子から、彼らにとってかなり「分が悪い」案件と推察される。また①については、先の橋下サンが出演した関西テレビの『旬感LIVEとれたてっ!』の中で、司会の青木源太キャスターと、性被害問題に詳しい上谷さくら弁護士との間で、実に興味深いやりとりが交された。以下、引用させてもらう。
青木「今回の第三者委員会が問題を調査するにあたって、中居氏の性暴力という認定をすることも含めて必要だったというお考えですか?」
上谷「そうですね、そこに性暴力がないと、いわゆる男女の仲たがいという類であれば、そもそもこの第三者委員会が必要であったのかということにもなると思います。ここの事実認定は、必須だっただろうと思っています」
――これ、上谷弁護士はサラッと言ってるけど、“男女の仲たがい”という類なら、そもそも第三者委員会は必要ではなかったと。裏を返せば、第三者委員会の存在を正当化するために、わざわざWHO(世界保健機構)の定義を持ち出してまで、中居サンに「性暴力」の汚名を着せたという見方もできる(コレ、結構大事な話です)。
更に言えば、②に挙げた、中居サンに十分な反論の機会が与えられなかった問題。コレも、3月31日というお尻のスケジュール(年度末で区切りをつけたかったフジの意向でしょう)ありきが原因だとしたら、結構ヤバい話になる。実際、中居サンへのヒアリングが行われたのは3月9日と、時間的に追加ヒアリング(反論の機会)が困難な時期。であれば、なおさら中居サンを「性暴力」と、安易に認定すべきではなかった(コレも大事な話です)。
カギを握る最高裁判所の判例
そして――僕がこの中居サン案件の落としドコロのカギと見ているのが、③である。ここで橋下サンが提示した“一般読者・視聴者の普通の注意と読み方を基準(最高裁昭和31年7月20日判決)”とは、法曹界やジャーナリストを志す学生たちには有名な判例で、ざっくり言えば、こういう意味なんですね。――“新聞記事を精読すれば、(懸念される)誤解は避けられるとしても、大事なのは一般読者が普通に読んで抱く印象のほう。それが事実に反して当該人物の名誉を傷つけるとしたら、その記事はアウト”――であると。
これを第三者委員会の報告書に当てはめると――“「中居サンが性暴力を犯した」とする同報告書は、WHOの「性暴力」の定義に基づいたもの。それは、広く「同意のない性的な行為」を指し、男女間のトラブル(非犯罪行為)なども含まれる。ただ、多くの読み手は「性暴力」の言葉の強さから、何か暴力的または強制的な性的行為が行われたと見るだろう。であれば、過去の最高裁の判例に照らせば、中居サンへの名誉棄損になりかねず、第三者委員会による「性暴力」表記はアウト”――というコトになる。

日本は判例主義の国だから、仮に裁判になって③の線で争うコトになれば――おそらく第三者委員会にとって、かなり分が悪い結果になるのではないか。
1つ、興味深いコトがある。中居サンの弁護団が第三者委員会に一連の反論を始めて以降――ソレまで本案件は、「中居正広氏の女性への性暴力を発端とする~」と各種メディアで報じられてきたのに、いつからか「中居正広氏と女性とのトラブルを発端とする~」に変わってきたコト。先のフジテレビの検証番組でも、「性暴力」という言葉は用いられず、「タレントだった中居正広氏が女性アナウンサーAさんの人権を侵害する事案」などの表現に終始した。おそらく、メディアの側で、本案件に関して何らかの“判断”が働いた結果ではないだろうか――。
現状、判明している3つの状況証拠
あの日、2人の間に何があったのか。それは守秘義務があり、双方が解除しない限り、その内容が明かされるコトはない。ただ、1つだけ確かな“事実”がある。先の1月9日――中居正広サンが、自身の公式サイト(当時)で発表したお詫びコメント内の「このトラブルにおいて、一部報道にあるような手を上げる等の暴力は一切ございません」なる文言。この声明文、公開にあたり“守秘義務”に関わるので、事前に被害女性側の弁護士に確認を取り、了承を得た上で公開されている。両者合意のもとに公開された守秘義務に関わる事実は、コレ一点のみである(←ココ大事です)。
なので、それ以外――週刊誌や第三者委員会の報告書に載った“リーク”の類いは、どちらか片方の発言しかなかったり、知人らによる“キリトリ”後のもの。当たり前だけど、証拠にならない。第三者委員会は公的な捜査機関でもなんでもなく、私的な弁護士チームである。
ちなみに、先の中居サンのお詫びコメントで、よく批判される「なお、示談が成立したことにより、今後の芸能活動についても支障なく続けられることになりました」も、中居サンの弁護団によると、“相手女性代理人からの修正要求によって、中居氏本人の本来の意図が伝わらず、誤解を招きかねない文章になってしまった”――とのコト。これは僕の推測だけど、当初の文案はこんな感じだったのではないだろうか。
「なお、示談が成立したことにより、今後の芸能活動についても相手さまのご了承をいただいております」
では――あの夜、2023年6月2日、2人の間で何があったのかを客観的な状況のみから整理したい。現状、守秘義務から内容は分からないが、状況証拠から得られる情報は、以下の3点である。
① 当時の2人の立ち位置は、キー局の女性アナウンサーとフリーの男性有名タレント。
② 2人の関係性は、特番などで数回、共演経験あり。その他、大人数での食事会も数回。
③ 2人の間で、暴力や強制力を伴わない、(第三者委員会によると)“同意のない性的な行為”が行われたと推察される。
不同意性交等罪を成立させる8要件
ココから先は、しばらく一般論になる。
2023年7月13日、「不同意性交等罪」なる性犯罪の法律が施行された。従来の強制・準強制性交等罪では、被害者の強い抵抗の有無が重視されたのに対し、本改正では被害者側の「ノー」の意思表示が難しい状況でも、それに乗じた行為は犯罪だと明示した点が画期的だった。
実は、この性犯罪の法改正の動きは、日本に限らず、2010年代半ば以降、欧米各国でも見られたもの。キッカケは、2014年に発効したイスタンブール条約(女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅に関する欧州評議会条約)で、同条約は「同意に基づかない性的行為を処罰する規定」を設けるよう、締約国に要請。そして欧米各国が法改正を進める中――そのトレンドに日本も追随したのが、先の「不同意性交等罪」である。
――なので、その内容は基本、欧米各国に準じている。同罪の成立には以下の8つの要件が類型化されている。
① 暴行・脅迫
② 被害者に心身の障害がある
③ アルコール・薬物を摂取させて正常な判断が不能に
④ 睡眠状態
⑤ 不意に襲われる
⑥ 恐怖(フリーズ)
⑦ 虐待
⑧ 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる(上司と部下など)
ワインスタイン事件の構造
――で、大事なのはココから。このうち、よく話題にされるのが、⑧の要件である。有名なのは、ハリウッドの超大物プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインの性暴力事件。2017年、彼は長年に渡り、自身の作品に出演する女優らに対して性的暴行を働いていたことが発覚。翌年逮捕され、ニューヨーク州バッファローの刑務所に収監された。
ワインスタインは、『パルプ・フィクション』や『イングリッシュ・ペイシェント』、『恋におちたシェイクスピア』など数々のヒット作で知られる超大物プロデューサー。一方、被害女性は彼の作品に出演した女優たち。そこには、圧倒的な主従関係があり、彼女たちは声を挙げると、自身も著しく不利益を被ることを憂慮し、長年に渡り沈黙を強いられたという。日本でも、著名な映画監督と出演女優の間で同種の案件が、いくつか告発されている。
そう、安定した給料が保証される会社員等と違い、俳優は1回1回の映画やドラマのオーディションに人生を賭ける。彼らにとって、自身を起用した(キャリアをもたらした)監督やプロデューサーを告発するのは容易なことではない。ゆえに、 こういった案件は長年に渡り、発覚しないことが多い。宗教における教祖と信者、スポーツにおける指導者と選手、組織における人事権を持つ上司と部下といったケースも同様。そんな被害者たちに救いの手を差し伸べたのが、先の「不同意性交等罪」だった。
思考実験としての1つの解
翻って、本案件である。もちろん、「不同意性交等罪」が施行される前に起きた事案であり、憲法第39条の遡及処罰の禁止により、適用されるコトはない。なので、あくまで1つの「思考実験」として考察する。本案件は、キー局の正社員とフリーの有名タレントの間で起きたトラブルである。2人の関係性は、特番等での共演経験はあるものの、関係性としてはそこまで強くない。よって、食事に誘われ、同じ業界の年長者への敬意と、数度の共演で培われた親しみから、それに応じるコトは特段珍しくない。
ただ――食事を共にするのと、その先の行為に及ぶのとでは、全く別次元の話になる。そこへ至るのに暴力や強制がなく、2人の間に強い主従関係もないとなれば――そこで起きたと推察される“同意のない性的な行為”は、現状「男女のトラブル」としか表現のしようがない。これが、現在判明している状況証拠から導かれる、思考実験の1つの「解」である 。
一般論だけど、男女の間でごく自然に行為に発展するも、事後に両者の間で何らかの行き違いが生じ、片方が内心“本意でなかった”と、心情を翻すケースは珍しくない。誤解を恐れずに言えば、その割合は、不同意性交等罪が疑われるサンプルの数十倍から数百倍に上るのではないか。
――なので、これは世界各国の“同罪”に対する共通認識だけど――いちいち男女間のトラブルに司法が介入するのを防ぐために(全てに応じていたら裁判所が回らない)、慎重に冤罪対策が講じられている。まず、基本的に被害者の“内心の訴え”だけで犯罪になるコトはない。求められるのは、客観的な証拠――心身いずれかに対する強制力の有無である。例えば、2人の関係性や前後の流れ、場所などの状況から、同意がなかった、何らかの強制力が働いたと客観的に言えるような明確な証拠がある場合――初めて、同罪が適用される。
興味深いのは、「アムール(愛)の国フランス」のケース。基本的に、大人の男女のトラブルに国家は介入しないというスタンスである。同国は伝統的に、恋愛を成就させるために行われる男女間の駆け引きや、ある種の計略を不問にする文化がある。また、男女平等を掲げるジェンダー先進国ゆえに、ことさら女性を“弱い存在”に見立てない風潮がある。もちろん、明確な“不同意性交等”の客観的証拠があれば、その限りではないが。
中居正広氏が引退した理由
ここからはSNSの話を。よく、中居正広サンの弁護団が第三者委員会に反論の声を上げる度に、その界隈では「だったら、どうして引退したんだよ」という心ない声が上がる。これは、当時のデキゴトを時系列で眺めるといいけど、少なくともお詫びコメントを発した1月9日の時点では、中居サンにその気はなかったと文面から伝わる。心境に変化が生じたのは、1月17日に日本生命とトヨタがフジテレビへのCM出稿を差し止めてからではないか。
そう、中居サンが引退を表明した理由は、時系列から推察するに――フジテレビへのナショナルクライアントの“一斉CM差し止め”の責任を感じて(あるいは、少しでもその波が止まるように)――という理由以外にあり得ない。以下、例のお詫びコメントから、引退発表までの彼の動きを時系列で記してみる。
2025年
1月9日 中居氏が自身の公式サイトでお詫びコメント。「示談が成立したことにより、今後の芸能活動についても支障なく続けられることになりました」
1月15日 日本テレビが『ザ!世界仰天ニュース』の中居氏降板を発表
1月17日 日本生命とトヨタがフジテレビへのCM差し止め。以後、雪崩を打つように同月末にかけて、他のナショナルクライアントも同調
1月20日 TBSが『THE MC3』の中居氏降板、『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』の終了を発表
1月21日 ニッポン放送が『中居正広ON&ON AIR』の終了を発表
1月22日 テレビ朝日が『中居正広の土曜日な会』の終了を発表。同日、フジテレビも『だれかtoなかい』の終了を発表
1月23日 中居氏が芸能活動からの引退を発表
――ちなみに、中居サンの冠番組の終了は、彼が自ら局に働きかけて、早々に実現させたと聞く。レギュラー出演者の1人に過ぎない『世界仰天ニュース』の降板と異なり、普通、自身がMCを務める冠番組の終了ともなれば、スポンサーとの調整や、テレビ局内を始め、関係する芸能事務所との行政面の手打ちなど、一筋縄ではいかない。だが、今回の場合、“座長”自らが積極的に動いて、“終了”させている。そのくらい、ナショナルクライアントによるフジへの“一斉CM差し止め”のインパクトは大きかった。自らも数々のCMに出演してきた中居サンだけに、民放にとってのスポンサーの重要度が痛いほど分かるのだろう。
解決金が「9000万円」である理由
SNSネタをもう一つ――「示談の解決金9000万円」について。これも、よく「ソレだけ払ったのだから、とんでもないコトをしたに違いない」という暴論が定期的にSNSで流れる。まず、中居サンが何をしたのかは、先にも記した通り「暴力や強制力を伴わない、(第三者委員会によると)“同意のない性的な行為”が行われたと推察される」としか言えない。なので、ここでは9000万円の妥当性や積算基準について、お節介ながら推理したいと思う。また、コレも先に書いた通り、中居サンは他人のためにお金を使う人である。ソレも世間の相場と関係なく。となれば、被害女性に対しても、彼なりに最大限の誠意を見せたのではないだろうか。
まず――大前提として、本案件によって被害女性が志半ばで退職に至ったのは、事実である。学生時代から憧れた職業に就いた早々、折からのコロナ禍でリモート研修を強いられ、その後も社内外のコミュニケーションもままならないまま会社員生活を送り、ようやくコロナが2類から5類に移行した4年目の初夏、これから仕事もプライベートも充実した人生が送れると思った矢先の2023年6月初旬――件の案件に遭遇する。そしてPTSDを発症し、翌年の8月に4年5ヶ月務めた会社を退職した。
中居サンなら、彼女にどんなケアをするだろうか。これは、僕の完全な想像だけど――例えば、被害女性が本案件に遭遇せず、そのまま仕事を続けていた場合――同局の女性アナの平均勤続年数「10年」を基準とすると、4年目以降だと、あと7年務める計算になる。フジの若手社員の平均給与を1000万円と推定すると、7年で7000万円。それプラス入院代その他の経費を含めたお見舞金が1000万円。ソコに先方の弁護士の手数料を足せば――大体9000万円になる。まっ、あくまで僕の勝手な想像ですが。違ったら、ごめんなさい。
――おっと、「中居正広サンが一番大切にしているコト」にも大分ページを割いてしまった。今度こそ、ここから先は長くない。最後のブロック「フジテレビが今後、目指すべきコト」に移ります。
フジテレビの歴史を見つめなおす
まず――よく“日枝(久)体制からの脱却”と言われる。でも、カリスマ的リーダーがトップに君臨し続けたキー局の例は、何もフジテレビに限らない。日本テレビだって氏家齊一郎サンが1992年に社長に就いてから亡くなる2011年まで20年間トップに君臨したし、テレビ朝日だって、『ニュースステーション』の生みの親の早河洋サンが2009年に社長に就任して、今もトップである(現在の肩書は代表取締役会長)。そして、ますますお元気だ(何よりです)。
3人に共通するのは、在任中に自局の視聴率を民放トップに押し上げ、業績を上げたコト(視聴率とCM料金は連動するのでそうなります)。実績あるリーダーが長くトップを続けるのは、資本主義の社会ではよくあるコト。僕はむしろ、今回の案件は、日枝サンが2017年限りで代表権のない取締役相談役に退き、経営から距離を置いたコトが遠因になったのでは?――とも見ている(日枝サンに案件を上げなかったのはそういうコトでしょう)。
加えて、こちらもよく言われる、長くフジを象徴するスローガンだった「楽しくなければテレビじゃない」からの脱却――。既に、「フジテレビの再生・改革に向けた8つの具体的強化策」でも示されているけど、同スローガンは少々誤解されていて、“楽しくなければ”は、作り手でなく、視聴者の心情を代弁してるんですね。それ以前――テレビは、作り手が作りたいものを作る場所だった。フジはそこにマーケティングの視点を取り入れ、お茶の間が見たい番組を追求したのである。ソコで生まれたのが、例えば――テレビ局の都合ではなく、芸能人自ら友人に電話をかけ、翌日のゲストをキャスティングする『笑っていいとも!』であり、それまで教育的側面が強かった動物ドキュメンタリーにバラエティの要素を入れ、お茶の間の目線を下げた『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』だった。
更に、その手法はニュース番組にも生かされる。1984年10月にスタートした、逸見政孝アナと幸田シャーミンさんの『FNN スーパータイム』がそう。当時、ニュースと言えば、アナウンサーが原稿を読むオーソドックスなスタイルだったのに対し、同番組は、2人のキャスターが時に会話しつつ、ニュースを視聴者に寄り添いながら伝えた。スポーツニュースにも力を入れ、体操のロス五輪金メダリストの森末慎二サンをキャスターに起用し、バラエティ的構成で伝えた。そして翌年、同番組をモチーフにした新しい大型ニュース番組が他局で誕生する。――『ニュースステーション』(テレビ朝日系)である。
今日、フジテレビを批判する際、この「楽しくなければテレビじゃない」をやり玉に挙げる識者が少なからずいる。しかし、今日テレビ界で当たり前になっている――マーケティングの視点を取り入れ、視聴者に寄り添う番組作りは、80年代にフジが始めたもの。ソレは90年代以降、他局にも波及し、今やNHKと全民放が“フジテレビ化”したのを忘れてはならない。
そう、何が言いたいのかというと――これまでのフジテレビの歴史は、決して否定 されるべきものじゃないってコト。70年代以前のスローガン「母と子のフジテレビ」にしても、その視点は、お茶の間のチャンネル権を持つお父さんではなく、母と子に向けられたもの。要は、マイノリティにやさしいテレビ局――それがフジテレビだった。そして生まれた番組枠が、大ヒットメロドラマ『日日の背信』に代表される主婦向けの“昼ドラ”であり、『ママとあそぼう!ピンポンパン』や『ひらけ!ポンキッキ』などの子ども番組だった。
温故知新――過去から学ぶ
そこで1つ提案。ナショナルクライアントがいない、この状況を逆に利用するといったらアレだけど、フジの過去の番組の中から、選りすぐりのドラマやバラエティを『温故知新』と題して、ゴールデンタイムに堂々と“再放送”したらどうだろう。それも、オリジナルを尊重する姿勢から、今ではコンプライアンス上、オンエアが難しいとされる表現等を一切、排除せず――。
実際、今年の2月24日、フジが放送した『国民が選ぶ!志村けんの爆笑ベストコント30』は、過去に同局でオンエアされた志村サン絡みの番組の中からベスト30を紹介する企画だったけど、番組冒頭《志村さんの歴史の集大成を視聴者の皆様と振り返るという趣旨で制作しており、当時の映像をそのまま使用しております》とのテロップが流れ、今や不適切とされる表現や、地上波でなかなかお目にかかれない、田代まさしサンの映像も普通に流れ、SNSでは、珍しくフジを褒める書き込みであふれたのである。
そう、本番組が60分枠なら、本編は一切編集せず、当時のままにオンエアする。ただ、それだけじゃ芸がないので、番宣も含めて一切のCM枠を排除し、余った10数分を、当時の作り手たちを招いて話を聞くのもどうだろう。聴き手はフジのエンタメの生き字引である軽部真一アナ。そして、昭和の映画番組の解説役のように、彼がアタマとお尻に登場し、ゲストであるフジのOBやOGに、当時の舞台裏を聞くフォーマットである。
例えば――諸般の事情から長らく再放送が封印されている木村拓哉主演の『ギフト』を、当時のプロデューサーの山口雅俊サン(現・株式会社ヒント代表)を招いて、撮影の裏話を伺ったり、伝説の深夜バラエティ『夢で逢えたら』の苦労話を、当時ディレクターを務めた吉田正樹サン(現・ワタナベエンターテインメント代表取締役)に吐露してもらったり、あるいは、まだまだお元気な倉本聰サンをゲストに、あの『北の国から』が生まれた経緯を語ってもらったり、はたまた「FNS27時間テレビ」の伝説の第1回『FNSスーパースペシャルテレビ夢列島』の舞台裏を三宅恵介サン(現・千代田企画社長)にぶっちゃけてもらったり――。
フジテレビが今後、目指すべきコト
いよいよ、このコラムも終局が見えてきた。ここまで長々と綴ってきたが、ここからはフジテレビが復活するために一番大切なコトを語りたいと思う。ソレは昔も今も、そして未来もきっと変わらない、たった1つのコト――そう、“ヒット番組”を作るコトに他ならない。本案件の前、フジテレビの視聴率はずっと低迷していた。そもそも順風満帆じゃなかった。ならば、スポンサーが離れた今、もはや何も怖いものはない。もう一度、フジテレビの原点に戻り(お茶の間に寄り添い)、人々が見たくなるヒット番組を作るしかない。
1つのヒントがある。今や世界に冠たる日本の「マンガ」文化である。ソレを生み出す少年ジャンプ(集英社)を始めとする、いわゆる“マンガ編集部”のビジネスモデルを模倣したらどうだろう。その強さの源泉は、常に新人の門戸を開放し(持ち込み、新人賞など)、一人の作家に担当編集者がついて、細かくアドバイスをして読み切りデビューを果たし、次に連載デビューを果たし、連載中は毎週、読者の人気投票でランキングが発表され、人気低迷の作品は連載が打ち切られ、その空いた枠に新人が起用される――。そう、常に新陳代謝し続ける、あのビジネスモデルである。
あの手法をテレビ界に取り入れたらどうだろう。ドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー、アニメ――それぞれの作家や演出家の卵たちに、常に門戸を開く一方――テレビ局内にディレクターや演出家は置かず、局員は全員、プロデューサー(黒子)に徹する。
局内にスターを置かない、作らない
思うんだけど、テレビ局員が作り手(演出家)になると、失敗しても責任の所在が曖昧となり、成功したらモンスター(権力)化して――いずれにしても周囲が意見しづらく、あまりいいコトがない。テレビ局内にスターを置かない、作らない――これこそ、週刊ジャンプに代表されるマンガ編集部のスタンスである。スターは外に置いて、その代わり、毎週熾烈な競争にさらされ、新陳代謝が進む。一方、プロデューサーは黒子に徹し、多くの新人作家を育てる。あるいは苦戦するベテラン作家に再チャレンジの機会を与え、復活させる。実はコレ、フジテレビの編成部時代の石原隆サンがまんまやってたコトなんですね。ちなみに、彼が黒子となり、ブレイクに導いた作家たちが――例えば、『警部補・古畑任三郎』の三谷幸喜サンであり、『踊る大捜査線』の本広克行監督であり、『HERO』の脚本家・福田靖サンである。
更に、ソレに加えて――この際、局アナウンサーを廃止したらどうだろう。これも、局内にスターを置かない、作らない…というコト。かつて、映画会社も専属のスターを持っていたけど、やがて彼らは自由な仕事を求め、外に飛び出した。同様に、優秀なアナウンサーも外部のプロダクションに所属させて、局を超えて活躍した方がいいとも。それと、局内にスターがいると…また何か、ややこしいコトが起きかねない。もちろん、反発もあるだろう。ただ、ナショナルクライアントに対して、「局アナウンサーを廃止しました」というメッセージは、それなりに強く響くと思う。
週刊文春を許していいのか
最後に――本案件をずーっと観察してきて、やはり許せないと思うのは、悪質なミスリードを繰り返してきた「週刊文春」である。中でも、「編成幹部が被害女性を誘い、中居正広サンに上納した」とする“初動”の誤報(およそ一ヶ月間、訂正記事を出さなかった)と、その誤報に端を発する、ありもしない「(性)上納文化」をでっち上げた――これら2つの“世紀の大誤報”は、フジテレビに大きな損害をもたらした。
そこで、本コラムの前段部分――《フジテレビが一番大切にしてるコト》でも触れた、清水賢治社長が前任者2人(港浩一前社長・大多亮元専務)への訴訟準備を進めている一件に戻ります。思うに――そのウラには、先の「週刊文春」の世紀の大誤報をけん制する意味合いもあるのではないか。
どういうコトか。仮に、前任者2人が出廷するコトになれば――当然、証人として、CMを差し止めた当事者であるナショナルクライアント側の見解も聞かれる。となると――これは僕の前号のコラム『少しクールダウンして、フジテレビ&中居正広さん案件を改めて考える』でも書いたけど、あのナショナルクライアントの“一斉CM差し止め”の本当の原因が語られる。つまり、例の港浩一社長(当時)の会見前には、ほぼ差し止めが決まっていたコトが露呈する(※そもそも火ぶたを切ったトヨタと日本生命のCM差し止めも、港社長の会見前である)。
そう、誰がナショナルクライアントを動かしたのか?
こうなると、週刊文春にとって、かなりマズい展開になる。当時のSNSを紐解くと、丁度そのタイミングでバズった記事が、同誌の「(性)上納」報道である。フジテレビが長年に渡り、組織的・常習的に、自社の女性アナをタレントや芸能事務所幹部に“上納”していたというトンデモ記事だ。ちなみに、「上納」を広辞苑で紐解くと、“官府に金銭や物品を納めること”とある。つまり、自社の女性アナを先方に“納めていた”――と。いやいや、いくら週刊誌だからって、何を書いてもいいワケじゃないでしょう。もはや誤報を通り越して、これはフジテレビや同社の女性アナたちへの人権侵害である。
当然、国内メディアはこの下品極まりないゴシップ記事をスルーした。しかし、米ABCなど海外の有力メディアは、文春の記事を引用するカタチで“フジテレビに(性)上納文化が存在する”趣旨の記事を報じたのである。当然、そのコトは今や海外で広く仕事をするナショナルクライアントにも伝わった。彼らのフジテレビへの一斉CM差し止めが始まるのは、それから間もなくである。
もちろん、後の第三者委員会の報告書で、文春のソレらの記事は誤報だったと判明する(当たり前でしょう)。中居正広サンが被害女性を誘った一件にフジの編成幹部は関与しておらず、“常習的”と報じた「スイートルームの飲み会」も1度しか開かれておらず、それもコロナ禍で店が利用できない事情があってのコト。タレントによる2件のセクハラ事案も、フジの編成幹部に道義的責任はあれど、彼が計画的に関与した事実はなかった。港社長の「港会」に至っては、参加した女性アナが全員、「不快な思いはしていない」と回答。そして多くのフジの社員が、文春の報じた“(性)上納文化”を強く否定した。
断っておくが、女性社員を会食の場に同席させて、先方を“もてなす”行為と、“上納する(差し上げる)”では、天と地ほどの開きがある。もちろん、昨今のジェンダー規範に照らせば、前者も許されるコトじゃない。しかし、後者は紛うことなく“人身売買”の性犯罪だ。だが――その極めて幼稚な誤報が、SNSではさも既成事実かのように拡散されたのである。
仮に裁判が開かれ、週刊文春の報じた「フジの編成幹部が被害女性を誘い、中居正広サンに上納した」とする初動の誤報と、それに端を発する「(性)上納報道」が、ナショナルクライアントの一斉CM差し止めに深く関与したコトが立証されたら――半年で数百億円ともされる被害額を、同誌はどう責任を取るのだろう。いや、コトはもはや一週刊誌の問題じゃない。株式会社文藝春秋として、どう落とし前を付けるのか。1つ興味深いコトがある。先の6月5日に清水社長が件の訴訟の準備を表明して以降、週刊文春は自分に火の粉が降りかかるのを恐れてか、その後3週に渡り、フジテレビ関連の記事をタダの1行も載せなかったのである。個人的には「文春さん、ビビってんのかなー」と思ってしまった。

民放の灯を守るため
今回の週刊文春の教訓は、例え下世話な週刊誌のでっち上げ記事でも、ひとたびSNSで火が着けば――いとも簡単に、民放キー局の1つが半年以上もナショナルクライアントから“一斉CM差し止め”を食らう危険が露呈したことである。
そう、コトはフジテレビ一社の問題じゃない。図らずも民放テレビ局のビジネスモデルの“脆弱性”が露呈したのだ。収入の6割を広告収入に頼る民放テレビは、CMを差し止められたら最後、全面降伏して白旗を上げるしかない。それでも、未だ全面復帰できるメドが見えないのが、今のフジテレビである。
日本には公共放送のNHKと、5つの民間放送のキー局とそのネットワーク、それに独立放送局や衛星放送、ケーブルテレビなどがある。このうち、国が予算を承認するNHKと対抗できるのは、民放の5大ネットワークしかない。仮にNHKが予算を国会の人質に取られ、“国営放送”紛いのコトをやり始めたら、広く、迅速に、国民に選択肢を提供できるのは、民放の5大ネットワークしかない。そして、その命綱が“広告”である。
日本は、アメリカの4大ネットワークを凌ぐ、民間放送の5大ネットワークを持つ、世界一の民放大国である。それ即ち、国民の選択肢の“幅”を表しており、その数は多ければ多いほどいい。戦後80年――日本が戦争をせずに済んでいる要因の1つに、僕は本気で民放テレビ局の存在があると思っている。スイッチ1つで広く迅速に、安定した電波で、無料で見られる民放テレビ。それは広告のお陰である。そして広告とは、自由と平和の象徴である。
だから、民放テレビの灯を消してはいけない。そのためにも、人々がSNSで二度と同じ過ちを繰り返さないよう、週刊文春――いや、株式会社文藝春秋は今回の件で、何らかのペナルティを受けるべきである。
天国で、菊池寛が泣いている。
了