連載『指南役のTVコンシェルジュ』今回は特別編。
指南役さんの最新刊『「朝ドラ」一人勝ちの法則』 (光文社新書)発売記念!ドラマのヒットの法則を分析したこの最新刊と連動し、肝となる内容の一部を特別大公開!
もちろん書籍そのままではなく『TVコンシェルジュ』用に加筆・編集された特別バージョンでお届けします。
【朝ドラ編】前編はこちら
【朝ドラ編】後編はこちら
【連ドラ編】前編はこちら
今日――2017年11月21日は、映画『私をスキーに連れてって』の公開からちょうど30周年である。
思えば、かの映画の登場は衝撃的だった。80年代、邦画は角川映画を除けば暗黒の時代で、スピルバーグやルーカスなど娯楽志向のハリウッドに比べて、総じて暗かった。主人公は内省的で、四畳半のアパート暮らしで、ストーリーも面倒くさかった。救いと言えば、女優が脱いでくれることくらいだった。
だが、『私スキ』は違った。
スキー場を舞台にしたボーイ・ミーツ・ガールの物語。音楽はユーミンで、流行りのアイテムも劇中にたくさん登場する。登場人物たちもどこかオシャレ。何より、話が抜群に面白かった。
時に、バブル華やかりしころ。同映画はたちまち時代のアイコンになった。
億単位の決済を20代にやらせた80年代のフジテレビ
なぜ、『私をスキーに連れてって』はそれまでの邦画の潮流に捉われず、突き抜けて明るい娯楽映画にできたのか。
若さである。
同映画の企画を馬場康夫監督がフジテレビに持ち込んだ時、フジ側のスタッフは小牧次郎サンと石原隆サン。共に20代半ばだった。馬場監督の話すストーリーに2人は興味を示し、なんと億単位の決済を下したのだ。当時のフジは入社3~4年目の若手社員にそんな大金を任せていたのである。
時に、フジのトップはジュニアこと鹿内春雄議長。まさに「楽しくなければテレビじゃない」を地で行く社風である。そんな“若気の至り”で生まれた映画が、面白くないわけがない。
平均年齢26歳が作った映画
思えば、同映画の企画に携わった人々は皆、一様に若かった。前述の2人に加え、脚本家の一色伸幸サン、フジのプロデューサー(当時)の河井真也サン、小学館のプロデューサー(当時)の倉持太一サン――etc.皆20代だった。一番年長の馬場監督ですら30歳そこそこ。
いつしか周囲の人たちは、そんな若者たちが企画に没頭する同映画を評して、「平均年齢26歳が作った映画」と呼ぶようになった。
ちなみに、同映画で原田貴和子演ずる真理子が「オンナ26、いろいろあるわ」と明るく吐き捨てる名シーンがあるが、三上博史演ずる主人公ら劇中の幼馴染み5人組もまた、26歳の設定である。
同時上映のB面だった
意外に思われるかもしれないが、映画『私をスキーに連れてって』は、同時上映の『永遠の1/2』のB面扱いだった。
『永遠の1/2』は直木賞作家・佐藤正午を原作に、根岸吉太郎監督と時任三郎・大竹しのぶ主演という盤石の布陣で作られた文芸作品。当然、A面扱いだ。クランクイン直前まで日立製作所のサラリーマンで、劇場公開映画を初めて手掛ける馬場監督が太刀打ちできる相手じゃない。
だが、この“2本立て同時上映”というシステムがあったからこそ、『私スキ』は世に出ることができたのである。
新人監督がデビューできるチャンス
かつてのレコードにもA面とB面があった。A面はヒット狙いで大御所の作曲家・作詞家陣を起用するのに対し、B面は時に新人の作家陣を起用した。いわゆるお試し枠である。
映画の同時上映も同じだった。1本は大御所の監督を起用してヒット狙いで臨むが、もう1本は新人監督などのお試し枠。そのシステムが、新人が世に出る機会を提供し、新陳代謝を生み出したのだ。
しかし――シネコンが普及した現在、劇場客は入れ替わり制になり、1日の上映の回転数を上げることが優先されるようになり、2本立て同時上映は激減した。21世紀の映画界は、新人監督が世に出るチャンスがめっきり減ったのである。
それはヒットの定石の宝庫だった
平均年齢26歳の若者たちによる企画の立ち上げ、2本立て同時上映による新人監督のデビュー――だが、それだけで映画はヒットしない。
実は、『私をスキーに連れてって』は、映画がヒットする定石に沿って作られたものだった。それゆえ、若者たちのハートを掴み、時代のアイコンになり得たのだ。少々前置きが長くなったが、今回のテーマは映画やドラマがヒットするための“定石”である。

『私スキ』に込められた16の定石
では、早速、『私スキ』に込められたヒットの定石を見ていこう。都合、それは16個ほど見受けられる。おっと、この先はネタバレも含まれるので、もし映画を未見の方は、見られてから読まれることをお勧めする。
1 映画は静かに始まる
基本、映画は静かに始まるもの。映画とは2時間の疑似体験。その世界に観客を引き込むには、現実世界から静かに入るのが鉄則である。テーマパークのアトラクションのようにいきなりフルスロットルで来られても、せいぜい持って4~5分。静かに入り、気がつけば映画の中に入っていたというのが理想だ。
『私スキ』の場合、三上博史演ずる主人公・矢野の日常のオフィスシーンから始まる。定石通りだ。
2 指針となるプロローグ
そして、大抵の映画は、プロローグにその映画の指針となる1エピソードが来る。同映画の場合、矢野が自宅ガレージでスキーに出かける準備に費やす一連のシークエンスがこれに該当する。ほぼ1カット長回しで、この間、彼はひと言も発しない。愛車のタイヤをスタッドレスに履き替え、ラゲッジにスキーブーツやストックを積み込み、そしてルーフキャリアに板をセットする――そこへ浮かび上がるタイトル「私をスキーに連れてって」。この演出はゾクゾクするほどカッコいい。要は、「この映画は道具に凝ってまっせ!」という監督からのメッセージである。
3 オープニングスイッチ
そして、主題歌である。ここで観客のスイッチが入る。『私スキ』の場合、クルマに乗り込んだ矢野がカセットテープをセットすると、その瞬間、ユーミンの『サーフ天国、スキー天国』が始まる。リトラクタブルヘッドライト(懐かしいですナ)が上がり、いざスキー場へ向けて走り出す。
続いて、原田知世と鳥越マリが西武のスキーバスに乗り込むシーン。もう、ここで観客の心もスキー場へ向かっている。途中、矢野の運転するカローラⅡとスキーバスが関越自動車道の途中で並走するシーンがあるが、並走しているのは彼らだけじゃない。僕ら観客もだ。
4 ヌケ
『私をスキーに連れてって』の撮影期間中、馬場監督は毎日スーツを着て、現場に臨んだ。それは彼なりの映画へのリスペクトを表した美学だったが、直近まで日立製作所に勤めていたサラリーマン上がりの監督に、映画の現場の人々は厳しかった。無理もない。彼らは叩き上げでここまで来た職人たち。突然、外の世界からやってきた広告代理店みたいな男に従う筋はない。
しかし、その時、1人だけ馬場監督の味方になってくれた人がいた。それが今年6月に亡くなられた名カメラマン、長谷川元吉氏である。そして長谷川サンの手により、この映画に圧倒的なゲレンデの世界観がもたらされたのだ。
俗に、日本映画の父と言われる牧野省三が残した映画作りの鉄則に、「1.スジ、2.ヌケ、3.ドウサ」がある。スジは脚本、ヌケは映像、ドウサは役者の演技である。『私スキ』の場合、まさに2の「ヌケ」が圧倒的だった。極端な話、ストーリーを脇に置いても、ゲレンデを主人公たちが華麗に滑走する姿や、セリカGT-FOURがゲレンデをかっ飛ばす(!)シーンでお腹いっぱいである。長谷川元吉サン、ありがとう!
5 ボーイ・ミーツ・ガール
古今東西、映画といえば「ボーイ・ミーツ・ガール」――男女が出会い、恋に落ちる物語が定番である。『私スキ』はまさに、この王道を行ったもの。しかし、それは日本映画が久しく忘れていたものでもあった。いつしか日本映画は、作り手の自己満足に過ぎない、屈折した世界観ばかり描くようになっていたからである。
しかし、映画は観客あってのもの。月並みと言われようとも、「ボーイ・ミーツ・ガール」の原点を忘れちゃいけないのである。
6 繰り返しの台詞
優れた映画に付き物の要素に、繰り返しの台詞がある。同映画の場合、次の3つの台詞が劇中、繰り返し登場する。
〇沖田浩之サン演ずる小杉がカメラ撮影するときの台詞「とりあえず」
〇原田知世サン演ずる優が矢野に対して指鉄砲するときの台詞「バーン」
〇矢野が優のスキーの癖を指摘するときの台詞「内足持ち上げる癖~」
繰り返しの台詞のいいところは、キャラクターを立たせたり、ユーモアが生まれることにある。特に小杉の「とりあえず」は、同映画のいわば緩衝材として、様々な場面で機能する。
7 偶然は1度だけ
しばしばエンタテインメントの命題に上がるテーマである。映画やドラマ作りにおいて、偶然は何度まで許されるか。――答えは「1度」きりである。大抵、それは主人公とヒロインの再会シーンだが、ありえない偶然で2人は再会する。但し、2人が神様からもらえるボーナスはその1度だけ。あとは双方の努力で恋を前に進めなければならない。
『私スキ』の場合、矢野と優はスキー場で運命の出会いを果たすが、矢野に恋人がいると誤解した優は、彼に嘘の電話番号を教える。東京に戻った矢野は優に連絡を取ろうとするが、もちろん電話はつながらない。万事休す――と思われたその時、偶然、会社の中で優と再会する。なんと彼女は同じ会社の秘書課の社員だったのだ――。「なんてアホな!」とツッコみたくなるが、いえいえ、エンタテインメントの世界では、それがたった1度だけ許されるのだ。そう、切札は1枚しか切れないから、切札なのである。

8 「I love you」と言わずして愛を伝える
その昔、夏目漱石が「I love you」を「月がきれいですね」と訳したとされる有名な逸話があるが、直接的な言葉で告白するよりも、その方がずっと情緒があるし、物語的である。
すぐれた映画やドラマも同様、いかに「I love you」と言わずして、愛を伝えるかが勝負になる。例えば、かの木村拓哉を一躍有名にしたドラマ『あすなろ白書』に、キムタク演ずる取手クンが石田ひかり演ずるなるみを後ろから抱いて(いわゆる“あすなろ抱き”)「俺じゃダメか?」と告げるシーンがある。ここで、敢えて「君が好きだ」と言わないところが取手の切なさを表し、同シーンを屈指の名場面に至らしめたのである。
さて、『私スキ』の場合、最大の告白の山場は、大晦日の夜、万座から5時間かけてクルマで志賀へやって来た矢野と誤解の解けた優が再会するシーンだ。この時、矢野は優に間違った電話番号を教えられたことを「やっぱり、間違いじゃなかった(意図的だった)のかな?」と諦めたように語り、立ち去ろうとする。それを「あの」と呼び止める優。この瞬間、夜空に新年を告げる花火が打ち上がる。そのあとの優の台詞がいい。「明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」――そして笑顔。
普通なら、それは単なる新年の挨拶だ。深い意味はない。だが、このシチュエーションだと、それは矢野へのOKのサインになる。「私もあなたが好き」と言うより、彼女の奥ゆかしさも表現され、何十倍も洗練された返事に聞こえる。馬場監督曰く、このシーンは一色伸幸サンのオリジナルのアイデアだとか。さすがは名脚本家である。
9 リスペクト
よく言われることだが、映画における優れた作り手とは、過去のヒット作をどれだけ知っているかと同義語である。そして映画作りにおけるクリエイティブとは、0を1にすることではなく、1を3や5にブラッシュアップする作業とも――。
それ即ち、「リスペクト」である。例えば、ルーカスやスピルバーグなどのハリウッドの巨匠たちで、黒澤明監督をリスペクトしている者は少なくない。かの『スター・ウォーズ』が、黒澤監督の『隠し砦の三悪人』をオマージュして作られたのは有名な話であるように。
さて、『私スキ』の場合、作品のベースにあるのは、馬場監督が愛してやまない「若大将シリーズ」と「007シリーズ」である。特に同じスキー映画ということで、『アルプスの若大将』と『女王陛下の007』へのリスペクトは外せない。
そこで、馬場監督が両作品への思いをどう表現したかというと、「007」に対しては、映画ポスターのデザインで伝え(あの原田知世サンを中央にした構図は、初期の007シリーズのポスターをオマージュしたもの)、「若大将」に対しては、かつて青大将を演じた田中邦衛サンのキャスティングだ。『私スキ』において邦衛サンの役どころは、W杯6位の実績を持つ往年の競技スキーヤーという設定。役名は田山雄一郎。言うまでもなく、それは若大将で加山雄三サンが演じた「田沼雄一」から来ている。もちろん、邦衛サンは配役のトメにクレジットされる。
10 マジックナンバー・エイト
優れた映画の鉄則に、主要な登場人物が「8人」以内に収まるというのがある。主人公の男女一組を中心に、周囲にその友人たち。そして敵役がいて、ベテランが締める。これ、かのアメリカのNASAが唱える組織学的にも、人間が一度に把握できる最適人数は「8人」であり、意外に理にかなっているのだ。いわゆる「マジックナンバー・エイト」である。
これを『私スキ』に当てはめると――まず矢野と優の主人公コンビがいて、泉・小杉・ヒロコ・真理子の友人4人。そして竹中直人サン演じる敵役の所崎がいて、ベテラン・田中邦衛サン演じる田山雄一郎が締めるという具合。
見事、8人に収まっている。
11 伏線
そして、映画になくてはならない「伏線」である。優れた映画はこの見せ方がうまい。『私スキ』の場合、映画の終盤でブレイクスルーの鍵となる「志賀―万座直線2キロ」の事実。これを映画の中盤、矢野が万座周辺エリアのジオラマ(立体地図)を見るシーンでさりげなく匂わせている。
この時、上田耕一サン演じるロッジのオーナーの一連の台詞が、物語終盤の重要なシーンをことごとく説明しているのが面白い。こんな具合に。
「ああ、志賀―万座ルートね。いいツアーコースですよぉ」
「夜は無理ですよ、夜は。それにあのコース、春までは滑走禁止なんですよ。相当な難所ですからねぇ、冬に滑るのは自殺行為です」
「直線2キロなのにねぇ。車だと菅平回っていくから5時間近くもかかるんですよぉ。変な話ですよねぇ」――ほら。
12 ユーモア
言わずもがな、「ユーモア」の要素も優れた映画には欠かせない。
同映画の場合、愛すべき矢野の仲間たちが主にこの役割を担う。例えば、矢野とゆり江がくっつくかどうかで泉と小杉が賭けをしたりと、劇中、彼らはことあるごとに賭けをする。曰く「馬券買わないで競馬見たって、ただの家畜のかけっこだからな」(@小杉)。
同映画のコメディリリーフは布施博演ずる泉だが、彼の真骨頂は、優にフラれた矢野を癒そうと、聖心の女子大生を紹介するために電話で呼び出すシーン。しかし、矢野は「そんな気分じゃないよ」と断る。カメラ引くと、外科医の泉は手術前。「相当、堪えてんなぁ」とつぶやき、マスクを上げてメスを受け取る。遊びのためには、1秒も無駄にしない感じが出ていて、かなり面白い。
そして同映画で、最も有名なユーモアのシーンと言えば、サロットの誤配送が発覚して、志賀から万座までウェアを大至急届けなければならないシーン。その任を請け負ったのは、高橋ひとみ演ずるヒロコと原田貴和子演ずる真理子。早速、愛車のセリカGT-FOURに乗り込むが、出発前に2人はドアを開けて雪を掴んでひと言「凍ってるね」――そして微笑む。一世一代の大ピンチなのに、楽しむ余裕も忘れない。これぞ映画の醍醐味である。
13 2つのルート
映画は、いよいよクライマックスへと突き進む。ヒロコと真理子を見送った後、優は偶然、ロビーにある地図を見て、志賀と万座の直線2キロの事実に気が付く。そして意を決して、自らスキーを操り、禁断の――冬場は滑走禁止の――ツアーコースに挑む。一方、セリカチームは4WDの強みを生かして、ゲレンデをガンガンすっ飛ばす。このシーンは同映画最大の見せ場でもある。
やがて、ゲレンデから戻ってきた矢野はロッカーに貼られた優からの伝言を受け取る。そして急いで優の後を追いかける。ここからはタイムレースだ。優と、それを追う矢野のスキーチームが間に合うか、それともセリカチームが間に合うか。クライマックスに向けて2つのルートが並行して進む。そう、観客に2つの視点を与える――これも優れた映画のクライマックスに付きものの鉄則である。
14 すべてのアイテム、シーンには意味がある
ようやく優に追いついた矢野。そこから2人で万座へと急ぐが、なんとコースを外れてしまう。気がつけば夜。そもそも冬場は滑走禁止なのに、夜ともなれば動くと命取りだ。仕方なく2人はビバークの準備に入る。
この時、矢野が「せめて、食べるものでも持ってくればよかったな」とつぶやいたのに対して、優はポケットからチョコレートを取り出す。そう、バレンタインのチョコレートだ。優は食料のつもりで矢野に見せるが、このシーンはあらためて2人の愛の確認になる。
そう、優れた映画というのは、アイテム1つとっても、無駄な見せ方はしないのである。
15 忘れさせる
スキーチームとセリカチーム、2つのルートでクライマックスに向かって進むが、セリカチームが思わぬ横転。やむなくリタイアとなる。残るはスキー組のみだ。こちらはビバークしていたところに、頼りになる仲間たち――泉と小杉がやって来て、いろいろあって、4人で万座へ向かう。
だが、ようやく辿り着いて、サロットの発表会場に走るも、既に記者発表は終わったあと。万事休す――と思われたその時、屋外のステージが賑わっているのに気がつく。見ると、ヒロコと真理子がファッションモデルばりにポージングしている。脇にはボロボロになったセリカ。なんと、間に合ったのだ。誰かに助けてもらったのだろう。横転した時点で観客に忘れさせておいて、最後の最後に復活させる。これぞクライマックスの王道である。
16 最高のアイデアを捨てる勇気
なぜ、観客はセリカチームを忘れたのだろうか――。
それは、主人公の2人が辿るルートこそが「勝つ」と信じたからである。そもそも、その「志賀―万座直線2キロ」という珠玉のアイデアを見つけたからこそ、『私をスキーに連れてって』の企画が生まれのだ。そんな経緯もあり、映画の中に登場するアイデアの重要度で言えば、間違いなくトップに来る。
しかし、だからこそ、最後の最後で捨てる(それをゴールにしない)勇気が試されるのだ。優れた映画とは、自らが見つけた最高のアイデアを土壇場で捨てられるか、それにかかっていると言っても過言じゃない。
そんな勇気が予定調和ではない、珠玉のエンタテインメントを生むのである。
結局、大事なのはタイミングとリアリティ
――以上、映画『私をスキーに連れてって』を題材に、ヒット映画にありがちな定石を16ほど紹介したが、それらはテクニック論であって、実はこれから述べる2つの要素が、優れた映画を作る上で、最も重要な鍵となる。
1つはタイミングである。よく誤解されがちだが、『私スキ』が空前のスキーブームを生み出したワケじゃない。ユーミンが『サーフ天国、スキー天国』を含むアルバム『SURF&SNOW』をリリースしたのは1980年。その辺りから徐々にスキー熱が盛り上がり始め、プリンスホテルを持つ西武がそれをバックアップしたり、ウェアや板も劇的に進化した。さらに85年に関越が全線開通したり、上越新幹線が上野に乗り入れたりして、格段にアクセスもよくなり、日帰りスキーツアーも可能になった。
そうした総合的な背景を見た馬場監督が、「これならスキーブームに便乗できる!」と、映画の企画を思いついたのだ。それは最高のタイミングだった。まず、これが1つ。
もう1つは、そもそもホイチョイ・プロダクションズのメンバーたち自身が重度のスキーフリークで、毎年大晦日から正月にかけて皆でスキーへ出かけるのが恒例行事で、仲間同士で連絡を取り合うためにアマチュア無線(ハム)の資格を取ったり、スキー場を舞台に8ミリ映画を撮ったりと、粋な遊びに明け暮れていた。
そう、映画の中の登場人物たちは、ホイチョイ自身を投影したものだったのだ。つまり「本物」だ。本物は強い。同映画のスキー遊びのシーンに妙なリアリティがあるのは、馬場監督をはじめ、ホイチョイのメンバーたちのリアルな実体験がベースにあるからである。
『私スキ』から生まれたトレンディドラマ
かくして、映画『私をスキーに連れてって』はヒットし、たちまち時代のアイコンになった。多くの若者たちが劇場に押し寄せ、既に熱を帯び始めていたスキーブームはさらに盛り上がった。
そんな観客の中に、一人の男がいた。フジテレビのドラマ班の大多亮サンだ。彼は『私スキ』を見て、大変驚いたという。それまでフジのドラマといえば、80年代の邦画同様、どこか屈折していて、野暮ったく、若者たちから見放されていたからだ。それに対して、『私スキ』は見事に若者たちの心を捉え、とにかくオシャレだった。
「よし、こんなドラマを作ろう!」
――かくして翌88年1月、フジテレビ月9枠でトレンディドラマ第一号となる『君の瞳をタイホする!』が始まった。メインのキャスト陣の一人に三上博史がいたことが、『私スキ』の影響を物語る。
そして、現代の連ドラ事情
それを機に、テレビ界はトレンディドラマの一大ブームが巻き起こり、若者たちをテレビへ惹きつけることに成功する。さらに90年代に入ると、『東京ラブストーリー』を機に、純愛路線が開花。その余波は他局へも波及し、空前の連ドラ黄金時代が幕開ける。
しかし、90年代末ごろから芸能プロダクションが力を持ち始め、連ドラの世界は“バーター”により出演者が増え、やがて“多牌”に。それを解決するために、出演者を増やせる医療ドラマや刑事ドラマなどのお仕事ドラマ(群像劇)が主流となり、かつて恋愛ドラマにハマっていた若者たちは連ドラから離れていった。
そして――気がつけば、視聴率一桁が頻発する連ドラ冬の時代に。
かつて脚本家の時代があった
実は、連ドラが冬の時代を迎えたのは、今回が初めてじゃない。1980年代後半にも1度あった。
そして、その前――1970年代半ばから80年代前半にかけて、ドラマ界は「脚本家の時代」と呼ばれた。それは、映画の真似事から始まったテレビドラマの歴史が、1つの成熟期を迎えたことを意味した。映画とは別の、ドラマならではの作家性が評価されたのだ。
次に示すのが、主に「脚本家の時代」に活躍した脚本家である。
彼らは――『傷だらけの天使』(日本テレビ系)の市川森一、『前略おふくろ様』(日本テレビ系)の倉本聰、『岸辺のアルバム』(TBS系)の山田太一、『阿修羅のごとく』(NHK)の向田邦子、『おんな太閤記』(NHK)の橋田壽賀子、『金曜日の妻たちへ』(TBS系)の鎌田敏夫――等々である。

だが、彼らの時代は長く続かない。
83年に、『積木くずし』(TBS系)が連ドラ最高視聴率45.3%を記録し、さらに堀ちえみ主演の『スチュワーデス物語』(TBS系)などの独特の作風の大映ドラマが話題になると、連ドラ界はターゲットの低年齢化が一気に進み、大味な演出や過激な描写が増え、アイドルの起用が目立つようになった。それは図らずも、ドラマの作家性を後退させることも意味した。
そして80年代後半、連ドラ界は「冬の時代」に突入する。
だが――そんな連ドラの惨状を救ったのも、また脚本家たちだった。
若き脚本家を生んだフジテレビの2つの登竜門
そう、連ドラ冬の時代を救った脚本家たち。彼らを生み、育んだのは、フジテレビの2つの登竜門である。
1つは、1987年に創設された「フジテレビヤングシナリオ大賞」だ。第1回の大賞が坂元裕二で、第2回が野島伸司。同賞の何が画期的だったかと言うと、受賞者を即戦力として起用したこと。間もなく2人は、『東京ラブストーリー』と『101回目のプロポーズ』という大ヒット作を生み出す。
そして、これ以降も、『白線流し』の信本敬子、『ラブジェネレーション』の浅野妙子、『結婚できない男』の尾崎将也、『ROOKIES』のいずみ吉紘ら、綺羅星のごとき精鋭たちが巣立っていった。
そして、フジテレビの生んだもう1つの登竜門が『世にも奇妙な物語』である。
それは、前身番組『奇妙な出来事』も含めて、小牧次郎・石原隆といったフジの歴代“深夜の編成部長”の肝入りで始まった短編オムニバスのドラマ枠だ。こちらも数多くの若手脚本家の卵を世に送り出した。
一例を挙げると、君塚良一、三谷幸喜、飯田譲治、北川悦吏子、岡田惠和、戸田山雅司、江頭美智留、田辺満、野依美幸、水橋文美江、中園ミホ――そうそうたる顔ぶれである。同ドラマが「ドラマ界のトキワ荘」と呼ばれる所以である。
脚本家の全盛期は10年
ここで奇妙な事実に気が付く。
2度の脚本家の時代――1度目は70年代半ばから80年代前半にかけて。2度目が90年代全般である。2つの時代を見比べて気づくのは、それぞれの時代に活躍した脚本家たちが、見事に入れ替わっている点である。
ここで、1つの仮説を発表したいと思う。それは、「連ドラの脚本家の全盛期は10年間」とする説である。
かの宮崎駿監督が映画『風立ちぬ』の中で、偉大なる設計家カプローニに、ゼロ戦の開発者堀越二郎に向かってこんな台詞を吐かせている。
「創造的な人生の持ち時間は10年だ。設計家も芸術家も同じだ。君の10年を、力を尽くして生きなさい」

――創造的な人生の持ち時間は10年。なかなか示唆に富んだ言葉である。恐らくこれは、宮崎監督自身から若きクリエイターたちへのメッセージだろう。これを脚本家に当てはめると、奇妙なくらいに符合する。
【第1次脚本家ブーム】
〇向田邦子/『時間ですよ』(71年)~『あ・うん』(80年)/10年間
〇倉本聰/『2丁目3番地』(71年)~『北の国から』(81年)/11年間
〇山田太一/『知らない同志』(72年)~『ふぞろいの林檎たち』(83年)/12年間
〇鎌田敏夫/『金曜日の妻たちへ』(83年)~『29歳のクリスマス』(94年)/12年間【第2次脚本家ブーム】
〇三谷幸喜/『やっぱり猫が好き』(88年)~『ラヂオの時間』(映画/97年)/10年間
〇野島伸司/『君が嘘をついた』(88年)~『世紀末の詩』(98年)/11年間
〇北川悦吏子/『素顔のままで』(92年)~『ビューティフルライフ』(00年)/9年間
〇君塚良一/『ずっとあなたが好きだった』(92年)~『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(映画/03年)/12年間
連ドラは時代の鏡
――いかがだろう。連ドラというのは時代の鏡であり、局のプライムタイムの看板枠で、毎週のように高い視聴率を求められる、テレビドラマの中でも最も難しい仕事である。その第一線でヒットを飛ばし続けられるのは、10年前後が目安なんだと思う。いわゆる「時代と並走できる」期間は10年間ということ。
それを過ぎると、魔法が解けるように視聴率から見放される。もちろん、それは脚本家の腕が落ちたワケではない。単に時代とリンクしなくなっただけである。それだけ連ドラというのは、時代と並走する高い感性が求められるのだ。
ヒントは野木亜希子にあり
つまり――何が言いたいのかというと、3度目の「脚本家の時代」を呼び起こすには、何より新しい脚本家じゃないといけないということ。そのヒントは、『逃げ恥』の野木亜紀子サンにある。
実は彼女、かのフジの「ヤングシナリオ大賞」の出身である。しかし、デビューからしばらくは、月9のセカンドライターや同局の深夜枠でくすぶっていた。そんな彼女に「日曜9時」というメジャーな枠を与え、メインライターとして起用したのは、他ならぬTBSだった。そして彼女は見事にその期待に応え、『空飛ぶ広報室』をヒットさせたのである。その後は、『掟上今日子の備忘録』(日本テレビ系)に『重版出来!』(TBS系)、そして先の『逃げ恥』と、ヒット街道をまい進しているのは承知の通りである。
つまり――才能ある脚本家の卵には、積極的に大きめの服を買い与えること。かつてのフジなら、野木サンをいきなりメジャー枠のメインライターに起用しただろうが、それができなかったところに、近年の同局の不振が重なって見える。
物語のパターンは36通り
さて、そうと分かったら、積極的に才能ある若い脚本家を起用するしかない。
しかし、やみくもに何を書いてもいいというワケじゃない。
これまでにも再三述べてきたように、ドラマや映画がヒットする鍵は「温故知新」。世の物語には限られたパターンがあり、古今東西のヒット作の多くは旧作の焼き直しだ。かの劇作家ウィリアム・シェークスピアは物語のパターンを36通りに分類したとされ、それを具体的に体系化したのが、フランスの批評家ジョルジュ・ポルティの「物語の36局面」である。
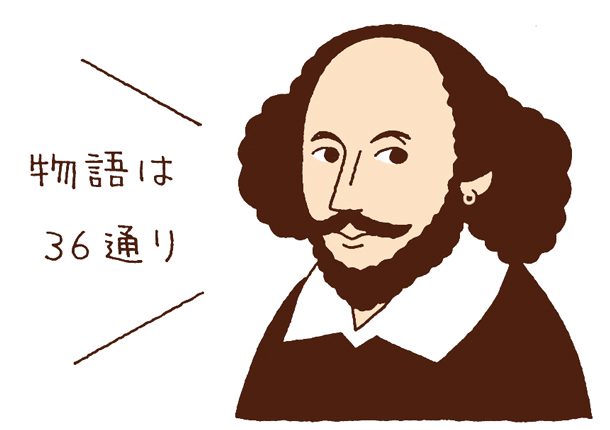
それは、以下のように分類される。
1 哀願・嘆願
2 救助・救済
3 復讐・復讐に追われる罪
4 近親間の復讐
5 逃走・追跡
6 苦難・災害
7 残酷な、又は不幸な渦に巻きこまれる
8 反抗・謀反
9 戦い・不敵な争い・大胆な企図
10 誘拐
11 不審な人物・問題・謎
12 目的への努力・獲得
13 近親間の憎悪
14 近親間の争い
15 姦通から生じる残虐・殺人的な姦通
16 精神錯乱
17 運命的な手ぬかり・浅慮
18 知らずに犯す愛慾の罪
19 知らずに犯す近親者の殺傷
20 理想のための自己犠牲
21 近親者のための自己犠牲
22 情熱のための犠牲
23 愛する者を犠牲にする
24 三角関係・優者と劣者との対立
25 姦通
26 不倫な恋愛関係
27 愛する者の不名誉を発見
28 愛人との間に横たわる障害
29 敵を愛する場合
30 大望・野心
31 神に叛く争い
32 誤った嫉妬
33 誤った判断
34 悔恨
35 失われた者の探索と発見
36 愛する者の喪失
――もちろん、これら1つ1つが単純に物語になるわけじゃない。いくつかが組み合わさったり、アレンジされたりして、物語が完成する。
要するに、ここで言いたいのは、ゼロから新しい物語を作るのは時間の無駄だってこと。そんな苦労をしても面白いドラマになる保証はどこにもないし、古今東西のヒット作の多くは、旧作をアレンジして生まれたものだ。
おっと、誤解なきよう。旧作をオマージュして、設定を似せる行為は、どんな名監督でもやっていること。それ自体は悪いことではない。いや、むしろクリエイティブを継承していく意味で褒められるべき行為である。なぜなら、映画の世界では、しばしばこんな風に“クリエイティブ”が語られるからだ。
「映画作りにおけるクリエイティブとは、どれだけ過去作品を知っているかと同義語である」
古畑任三郎は100%のクリエイティブ
つまり、「温故知新」とは、旧作をオマージュしつつも、それに現代的要素を加味したり、舞台設定に基づいて内容をアレンジしたり、役者に合わせて当て書きしたりと、バージョンアップすることが肝要なのだ。それらの一連の作業が「クリエイティブ」となる。
例えば、『古畑任三郎』は『刑事コロンボ』へのリスペクトから生まれたものである。しかし、三谷幸喜サンは風采の上がらない刑事を主役に当てるような安易なオマージュの道を選ばず、コロンボが理詰めで犯人を追い詰める「倒叙法」の推理劇の要素の方を重視した。つまり、コロンボの頭脳をオマージュしたのだ。古畑自身は田村正和が演じるだけあって、オシャレに仕立てた。結果、『古畑』は『コロンボ』にひけを取らぬ大傑作となった。

結論――連ドラを面白くする2つの処方箋。
1つは、新人脚本家をメジャーな枠で、メインライターとして起用すること。そして2つ目は、ゼロから新作を生み出す邪念を捨て、優れた旧作をオマージュして、現代風にアレンジすること。そして、その一連の作業をクリエイティブと認識すること。
この2つの処方箋を忠実に服用すれば、必ずや連ドラは復活する。
脚本の9割は既に完成している
最後に、ある高名な脚本家が発した、こんな言葉を紹介したいと思う。
「ドラマを書くにあたって、大まかな設定と主要なキャラクターを決めた時点で、既に脚本の9割以上は完成しています。つまり、自分がアイデアを付加できる部分は1割もないんです」
――これ、どういうことか分かります?
先の話の続きで言えば、まず連ドラを書くにあたって、元ネタとなるオマージュ作品を決める。そして、これを現代風にアレンジして、主要なキャラクターを決める。先生曰く、この時点で既に脚本の9割は完成しているという。まだ1行も書いていないのに、だ。
その脚本家はこう続ける。
「脚本の9割はセオリーなんです。脚本の神様が決めた設計図に従って、こちらはただキーボードを叩くだけ」
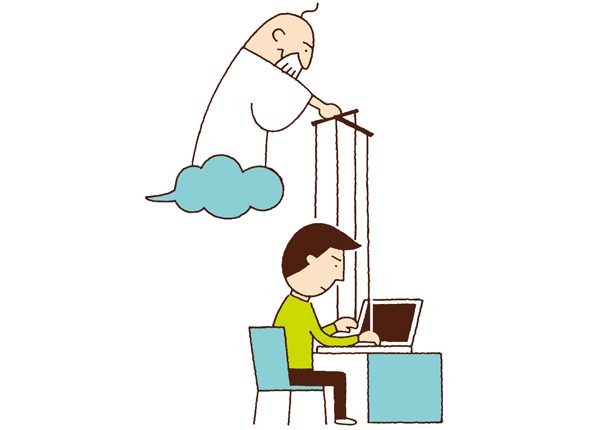
そう、セオリー。連ドラの脚本の9割は既に設計図があって、脚本家はそれに従って、書き進めればいいと。言われてみれば、時々、脚本家の武勇伝などで、こんな発言を聞く。
「もう、キャラクターが勝手に動いて、勝手に喋り出すんです」
世に言う“ドラマツルギー”である。俗に「物語が降りてくる」とも言うが、それはアイデアが降臨するワケではない。物語の構造上、既に決められたストーリーがあって、脚本家はそれを模写しているに過ぎないのだ。
『逃げ恥』にも見られるドラマツルギー
例えば、かの『逃げ恥』にも、いくつかのドラマツルギーが見られる。
〇ヒットする連ドラの鍵は「ニコハチ」
大抵の連ドラは10話から11話で構成されるが、ヒットする連ドラに共通するのが「ニコハチ」の法則である。これ、連ドラにとって2話と5話と8話が重要になる法則で、1話は登場人物の紹介がメインとなるから、最初の平常運転の2話、次に主人公とヒロインが一度恋仲になる5話(その後また離れる)、そして主人公の内面が明かされ、最終回への起点となる8話。この3回がちゃんと描かれているドラマは間違いなくヒットする。『逃げ恥』はまさにこの法則に沿って作られている。
〇ラブストーリーなら1クール中、必ずどこかで温泉に行く
連ドラというのは、不思議と中盤あたりになると、決まって美術の予算とスケジュールが切迫してくる。ここで、ロケ回が1回入ると、随分とラクになる。そのため、大抵の連ドラは中盤あたりで温泉に行くエピソードが作られる。視聴者にとっては絵変わりして新鮮だし、出演者にとっても気分転換になる。ちなみに、『逃げ恥』は6話で温泉に行っている。
――と、これらは数多あるドラマツルギーのほんの一例。
もっと知りたい方は、拙著『「朝ドラ」一人勝ちの法則』をお読みください。
『逃げ恥』は他のキャストでも数字が取れた
優れた連ドラは大抵、パクリである。でも、それは悪いことではない。温故知新――エンタテインメントにおけるクリエイティブとは、旧作を現代風にアレンジする作業のこと。それ即ち、オマージュであり、リスペクト。0を1にするのではなく、1を2や5や10にするのが、連ドラのクリエイティブなのだ。
かの『逃げ恥』が成功したのも、古今東西のヒット作をオマージュした結果である。仮に、主役の2人が別の俳優であっても(例えば、みくり役が波瑠、平匡役が高橋一生であっても)、やはり同ドラマはヒットしたと思う。

繰り返すが、ドラマがヒットする際に最も重要なのは、脚本である。『逃げ恥』のヒットの要因を「脚本のおかげ」と正当に評価する姿勢こそ、これから先の日本の連ドラを復活させる最も重要なカギとなるのだ。
そう、第2、第3の野木亜希子は――あなたです。
(文:指南役 イラスト:高田真弓)
指南役さんの最新刊『「朝ドラ」一人勝ちの法則』 (光文社新書)
は好評発売中!





