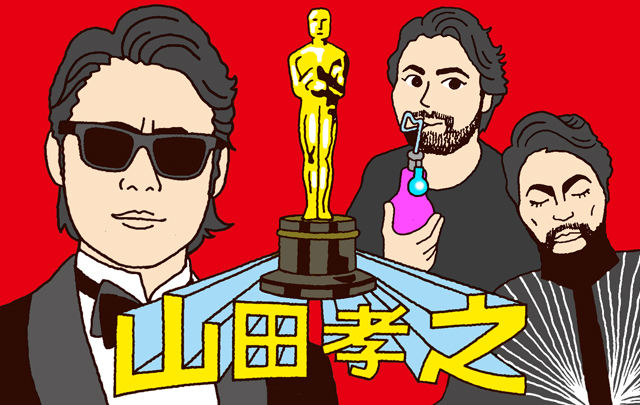ちょっと前の話になるが、先月――11月6日に放送された『しゃべくり007』(日本テレビ系)にゲスト出演したマツコ・デラックスさんが、こんなことを言っていた。
「こないだ見た? 生放送のヤツ。ユリ・ゲラーみたいになっているのよ。山田君が。山田孝之が日本を元気にする力がありますっていう生放送」
そしてひとしきり番組の感想を述べた後、最後にこう締めくくった。
「これは……私がやりたかったって、ちょっと悔しくなっちゃって」
今やテレビ界イチの売れっ子タレントのマツコさんをして「悔しい」と言わしめる山田孝之という男――。
今回は、このTVコンシェルジュが独自に制定する「2017テレビマン・オブ・ザ・イヤー」に輝いた俳優・山田孝之について、今年彼が起こした2つの奇跡と、何ゆえ彼が選ばれたのか、その理由について語りたいと思います。
マツコ・デラックスも悔しがった番組
件の番組は、去る10月6日深夜にテレビ東京系で放送された『緊急生放送!山田孝之の元気を送るテレビ』である。MCはいとうせいこうサン。山田孝之サンがスタジオから、電波に乗せて日本中に“元気”を送るという趣旨。基本、真剣モードだが、怪しさプンプンである。
実は当初、同番組は別の企画で進んでいたという。それが諸事情あって、件のタイトルになったとか。番組の公式サイトには、こんなお詫び文が載っている。
「テレビ東京では、10月6日(金)深夜0時12分より『山田孝之の演技入門』と題し、役者・山田孝之が役作りの基本から、俳優のあり方まで説く番組をお送りする予定でしたが、急遽内容を変更し、『緊急生放送!山田孝之の元気を送るテレビ』を放送致します」
急きょ、差し替えられた企画という前フリ
山田孝之の演技入門――そんなクソ面白くない番組がそもそも深夜に放映されるワケもなく――(笑)。
ちなみに、内容変更の理由は「いとうせいこうが水面下で進めていた取材により、山田孝之の周辺で科学的に説明できない不思議な現象が次々と起きていることが明らかになりました。当番組では、いとうせいこうが旗振り役となり、取材を通して不思議な現象を解明し、山田孝之自らが生放送のスタジオで前代未聞の壮大な実験を行います」――とある。ますます怪しい。
そして、その謝罪文は次の一文で終わる。
「また、『山田孝之の演技入門』のゲストとしてお呼びしていた小池栄子、松岡茉優、紀里谷監督にもご出演いただきます」
企画が180度変わったのに、ゲストは同じ――(んなアホな!)。
かくして、番組はオンエア日を迎えたのである。
異様な緊張感に包まれるスタジオ
「時刻は0時15分を回りました。今夜は『山田孝之の演技入門』をお送りする予定でしたが、大幅に内容を変更してお送りします」
水原恵理アナの進行で始まった同番組。スタジオは異様な緊張感に包まれている。水原アナの横には、いとうせいこうサン。2人とも神妙な顔つきである。彼らの後ろには番組タイトル。しかし、紙に乱雑な手書きである。看板の作成も間に合わないほどの緊急の内容変更だったのだろうか――(んなアホな!)。
司会の2人の横にゲストの3人――紀里谷和明監督、小池栄子サン、松岡茉優サンが座っている。3人とも一様に戸惑った表情を浮かべている。
座して目をつぶり、元気を送る山田孝之
ここで、カメラはスタジオの中央にいる人物を映し出す。椅子に座り、黒装束に身を包み、目をつぶって両手を広げている男――山田孝之その人である。

水原アナ「あちらでは、山田さんが精神を集中されているように見えるんですけど……何をされているんでしょうか?」
いとう「もう既に、日本に“元気”を送っていると思います」
水原アナ「“元気”を送るとは?」
いとう「テレビをご覧の皆さんは、既に身の回りで不思議なことや、良いことが起きているかもしれません。番組ではそれを募集します。その時々で紹介したいと思います」
かくして、番組ではTwitter(#山田孝之元気)とメールで、視聴者からの奇跡の報告が呼びかけられた。ここに、伝説の番組が切って落とされたのである。
3人のゲストたち
いとうせいこうサンが3人のゲストに語り掛ける。
「紀里谷監督はわざわざアメリカからお越しいただいたワケですが、番組の趣旨は変わりましたが、監督はむしろ……」
紀里谷「来て、大正解でしたね。山田孝之という男は日本最高峰の俳優だと思いますが、彼がなぜそこまで人を惹きつけるのか。それを見届けたいと思います」
一方、小池栄子サンは戸惑いを隠せない。
小池「正直、山田クンのファンですけど……元気を送るというのは抽象的過ぎて……」
松岡茉優サンは比較的フラットなスタンスである。
松岡「きっと今日は奇跡の体験ができるだろうし、俳優としての山田サンの新しいステージを見たいなぁと……」
三者三様だが、注目すべきは彼らが映画監督及び役者という点である。つまり、「演じる」という点において彼らはプロなのだ。
そう、この番組にとって、彼らはゲストなどという生易しいものではない。欠かすことのできない共演者なのである。それは番組が進むに従い、次第に明らかになる。
未公開テープに映っていた奇跡
「山田孝之は……元気ですっ!」
いとうせいこうサンの決め顔とポージングでVTRが始まる。なぜ、この番組が企画されたのか、その趣旨説明である。
その中で、いとうサンは1本の未公開テープに出会う。それは、山田孝之サンがかつて出演した番組『山田孝之のカンヌ映画祭』(テレビ東京系)の最終回で、山田サンが故郷・鹿児島に帰った際に映されたテープである。
――とある森の中。山田サンが池のほとりにたたずんでいる。その時だった。何気に山田サンが池に手を浸すと、数秒後、十数匹の魚たちが一斉に水面を飛び跳ね始めたのだ。続いて、上空では鳥の大群がけたたましい鳴き声を響かせる。単なる偶然とも言えなくもないが、ディレクター曰く、魚と鳥の声がシーンに似つかわしくなく、カットしたという(普通の理由だ)。
しかし、これを見て、いとうせいこうサンは驚愕する。
「山田孝之には、何か不思議な力があるのだろうか?」
金魚に“元気”を送る
スタジオに、水槽が1つ用意される。中には金魚が数匹泳いでいる。今から山田サンが金魚に“元気”を送るという。未公開テープと同じ現象が再び起きるとしたら、金魚が水槽から飛び跳ねることになる。VTRを見た後なので、ゲストたちもいささか興奮している。
小池「もしかしたら、ものすごい瞬間に立ち会えるのかも……」
紀里谷「絶対、何か起きますよ。信じてます」
不意に椅子から立ち上がる山田サン。水槽の前まで来て、おもむろに人差し指を水の中に入れる。
次の瞬間、金魚たちは動揺したような仕草を見せ(そりゃ指が突然入ってきたら驚くだろう)、そして動きを止めた。
松岡「(興奮して)固まってる!」
それから金魚たちは、今度は指から離れるように逆向きに泳ぎ始めた(単純に怖がっているのだろう)。
いとう「(興奮して)金魚が遠のいていく……遠のいていきますね!」
リアル笑ってはいけないショー
――ハイ、もうお分かりですね。これは、ある意味「リアル笑ってはいけないショー」。目の前で起きている茶番に、いとうサンはじめ、3人のゲストたちが真剣に付き合っている構図である。絶対に笑ってはいけない。クスリとでもしたら、番組が台無しである。その意味では、本家の「笑ってはいけない」より数段厳しい。もっとも、当の山田サンが一番大変だ。何せ、これは生放送なのだ。
ゲストたちも、段々乗ってきたのか、次々にサービス発言が飛び出す。
松岡「金魚たちのツヤが……さっきよりも強くなったと思います!」
紀里谷「プロだから分かるんですが、発色が全然違いますね」
小池「私まで……なんだか背中が熱くなってきました」
視聴者参加の大喜利ショー
実は、オンエアの途中から、画面の下には視聴者からの“奇跡”の報告が続々と寄せられていた。
一例を挙げると、以下のような報告である。
○録画予約を忘れていたのに、勝手に番組が録画されていました。
○今、ふと思って財布の中身を確認したら、所持金が777円でした。
○片目だけ二重になりました。
○カレーの味にコクが出ました。
○母が急にご飯を作り始めました。
○ケータイの充電がいつもより早く完了しました。
○ハイボールがいい感じの濃さで作れました。
○飼い犬がいつもと違う向きで寝ています。
○飲み会の後、普段はキャバクラに寄る旦那がまっすぐ帰ってきました。
○シラスの中にカニが入っていました。
○iPhoneのホームボタンが直りました。
○シャワーの出がよくなりました。
○LとRの発音がよくなりました。
○母が起きだして、爪を切り始めました。
○衣替えが終わりました。
○切れかかった蛍光灯が復活しました。
○ギターのFが押さえられるようになりました。
○15年前のミニスカートが断捨離できました。
○いい下の句が浮かびました。
――いかがだろう。もはやこれは大喜利である。スタジオのノリと同様、お茶の間もこの番組の空気感に付き合い、大真面目にボケてくれているのだ。
これぞ、番組とお茶の間の“共犯関係”である。
スタジオ生ライブに踊るゲストたち
番組のラストは、「山田孝之が元気を送るライブ」と称して、プロのミュージシャンとダンサーたちによるスタジオ生ライブが行われた。彼らは全員、動物の被り物をしている。その前で一心に“元気”を送り続ける山田孝之――。
スタジオは段々とグルーブ感に包まれていく。動物たちが演奏し、踊る姿は、まるで太古の神々の祈りを連想させた。
気がつけば、紀里谷監督がカメラを持ち出し、一心不乱に山田サンを撮影している。小池サンと松岡サンの2人の女優は立ち上がって踊り狂っている。
そんな混濁と狂乱の中――番組は終わった。
ひと言も喋らなかった山田孝之
結局、70分間の生放送中、スタジオの山田孝之サンはひと言も喋らなかった。ただのひと言も、である。
ただ目をつぶり、両手を広げ、ひたすら“元気”を送り続けた。
恐らく、この番組を見終えた人たちは、同じ感想を抱いただろう。「この番組は一体、なんだったんだ?」って。
でも――考えたら、テレビとは本来、「今この瞬間、視聴者が求めるものを伝える」装置だ。ニュースやドラマ、バラエティといったジャンル分けは後付けでしかない。要は、この番組は、山田孝之という男をどう使ったら一番面白く、お茶の間が喜ぶかを考え、企画されたのだ。
バラエティの可能性の扉を開いた山田孝之
ここで、僕らはふと気がつく。この番組に係わった人たち――いとうせいこうサンをはじめ、大真面目に茶番に付き合った3人のゲストたち、そして大喜利を通して共犯関係となったお茶の間――結果的に、僕らは大いに番組を楽しんだのは間違いない。もしかしたら、山田孝之サンが送り続けた“元気”の正体は、これだったのではないか。
バラエティというジャンルに一石を投じ、新たな可能性の扉を開けた『緊急生放送!山田孝之の元気を送るテレビ』――その中心人物である山田孝之サンはある意味、奇跡の男と言って間違いない。
それはドキュメントなのか? ドラマなのか?
振り返れば、2017年の山田孝之サンは、年の初めの1月から異次元の動きを見せていた。そう――お茶の間はもとより、テレビ業界人たちの間でも「あれは一体なんなんだ?」と話題となった『山田孝之のカンヌ映画祭』である。
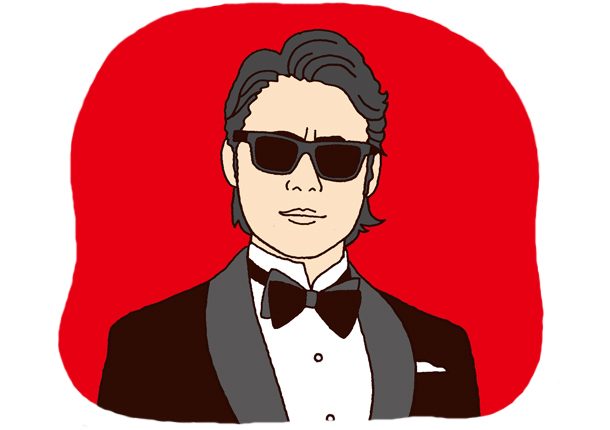
ご覧になられた方なら分かると思うけど、それは不思議な番組だった。ドキュメンタリーっぽいけど、ドラマのようでもあり、1クール全12話で終わった。
種を明かせば、それはフェイクドキュメンタリーだった。要は、ドキュメンタリーを装ったドラマである。ただ、ちゃんとした台本があるわけではなく、おおよその流れを決め、それに沿ってドキュメンタリーっぽく作られるのだ。
2年前の挑戦
実は、2年前にも一度、山田孝之サンはフェイクドキュメンタリーを仕掛けている。それが、『山田孝之の東京都北区赤羽』(テレビ東京系)だった。
物語は、ある日、自分の演技に疑問を抱いた山田サンが心機一転、赤羽に引っ越し、そこに暮らす人たちと交わりながら、役者として再生する話である。
だが、仕掛けは面白かったものの、正直僕は今一つ乗り切れなかった。ドキュメンタリーの要素が強すぎて、ドラマに昇華していない感じがしたのだ。
目標はカンヌの一等賞
その点、この『~カンヌ映画祭』は違った。ストーリーが抜群に面白かったのだ。「カンヌ映画祭でパルムドールが欲しい」――そこを起点に物語が転がる。ゼロから映画の企画を考え、役者を揃え、スポンサーを集め、撮影する。そんな映画作りのハウ・トゥが描かれたのだ。
最初は無謀と思われる夢に挑戦し、試行錯誤を重ねる中で、次第に夢が現実味を帯びてくる――それはサクセスストーリーとして、ドラマや映画の定番のフォーマットである。しかし、これはフェイクドキュメンタリーだ。あくまで現実とリンクしている体なので、本当にカンヌが取れるのか、お茶の間は続きが気になり、つい見てしまう。よく出来た構造である。
呼び出された山下敦弘監督
物語は、以前『~東京都北区赤羽』でも組んだ山下敦弘監督(映画『リンダ リンダ リンダ』や『天然コケッコー』を撮った結構すごい監督です)が山田孝之サンに呼び出されるところから始まる。
山田サンはこう告げる。「賞が欲しい。それも映画界の最高峰のカンヌの賞が」
そう、カンヌ国際映画祭。ベルリン国際映画祭やヴェネツィア国際映画祭と並ぶ世界三大映画祭の1つであり、その最高峰。そのレッドカーペットを歩くのは、全ての映画人の憧れである。
既に“圧”が強い山田孝之
この部分の山田サンと山下監督の会話が面白い。
「カンヌ行ったことありますか?」と問いかける山田サンに、「カンヌはないけど、ナント(三大陸映画祭)やロッテルダム(国際映画祭)は招待されたことはある」
山田「そんなハンパなやつではなく、取るならトップのやつを……」
山下「ハンパではないんだけど……カンヌとは違う」
山田「行きたいですよね? カンヌ。取りたいですよね? 賞」
山下「正直、あんまり考えたことなかった」
山田「だからでしょう。これまで意識してなかったから取れなかった。ここから本気出せば取れますよ」
山下「本気……そういうことなのかなぁ?」
それなりに実績のある山下監督に対して、かなり失礼な物言いだけど、既にこの時点で山田サンの“圧”が強い。撮りたい映画があるのではなく、まずカンヌの賞が欲しいと言ってる時点で、かなり嫌なタイプのプロデューサーである。
だが、このキャラクターなくして、このフェイクドキュメンタリーは成り立たないのだ。
前のめりの山田プロデューサー
そして始まったカンヌプロジェクト。
同ドラマは終始、前のめりの山田プロデューサーと、それに翻弄され、付き合わされる山下監督の姿を追っていく。ある意味、真の主人公は山下監督である。
まず、山田Pは横浜に事務所を借り、さらに「合同会社カンヌ」という会社まで立ち上げ、早々に名刺まで作る。いっぱしの“形”から先行するスタイルに、このプロデューサーの性格が表れている。
そんな山田Pに戸惑いながらも、映画の企画内容を尋ねる山下監督。すると、題材は決まっているという。かつて実在した身長2メートルの連続殺人鬼、エド・ケンパーという男の話を作りたいと。テーマは「親殺し」である。
暴走する山田機関車
かなりリスキーな題材に、殺人鬼を演じる俳優選びに苦労するのでは?と尋ねる山下監督。だが、山田プロデューサーは既にアタリはつけてあるという。
山下「もう決まってるの? 誰なの?」
山田「楽しみにしててください」
早速、主演俳優に会いにいく2人。しかし、待ち合わせ場所に現れたのは、ランドセルを背負った芦田愛菜サンだった。
「え? ちょっと待って」戸惑う山下監督と、どや顔の山田P。
――こんな感じで、そのフェイクドキュメンタリーは動き出す。
前代未聞の出資要請
この後、同プロジェクトは、日本映画大学に行ってカンヌの傾向と対策の授業を受けたり、プロットを作る前からパイロットフィルムを作ったり、それを元に出資者を集めたり――と、山田Pの暴走機関車は留まるところを知らない。プロットがないのにパイロットフィルムを作るなど狂気の沙汰だが、既存の映画作りにこだわりたくないというのが、山田Pのポリシーらしい。
笑ったのは、出資を要請しに、山田Pと山下監督、芦田愛菜サンの3人で東宝を訪れた時のこと。山田Pが制作費1億円を提示したところ、「やはり脚本がないと……」と困惑する東宝担当者。それを受け、山田Pはこれまで自分が出演した東宝作品の興行収入を積算して「大体500億円ですね」と大人げないリアクションを見せたのだ。クズである。
結局、東宝をはじめ、大手から断られた山田Pは奥の手として、Twitterで自分のフォロワーであるガールズバーの経営者と接触し、出資を要請する。この辺りの切羽詰まって段々とアンダーグラウンドな世界に足を踏みいれるくだりは、妙なリアリティがある。
カンヌを下見する
ある日、山田Pは急に「カンヌに行きません?」と切り出す。山下監督が「もう映画祭は終わってるけど」と返すと、山田P曰く、現地の空気を感じることが大事だと。
芦田愛菜サンも誘うが、彼女は夏休みのラジオ体操を理由に断る。「友だちと皆勤賞を狙ってて、判子をもらわないと……」「どんな判子? 判子ならこっちで作りますよ」と、とんでもないことを言いだす山田Pに、「やっぱりズルは……」と苦笑いの芦田サン。この辺りのやりとりは相当おかしい。山田Pがどんどんクズになっていく。
結局、カンヌへは山田Pと山下監督の2人で向かうことになり、2人は授賞式の会場を下見したり、タキシードを借りて記念撮影したりと、単なる観光客と化す。
フランスの映画人たちのアドバイス
とはいえ、さすがにそれで日本に帰るわけにもいかず、2人は複数のフランスの映画関係者と会い、パイロットフィルムを見てもらい、カンヌの傾向と対策をリサーチする。ここでのアドバイスは結構、ちゃんとしており、それなりに使えそうである。
「一風変わった作品なので、カンヌよりロカルノ(国際映画祭)の方がいいわ」
「カメラは是枝組の山崎裕さんなのですね。有能なスタッフが関わっているのはそれだけでプラスだと思います」
「包丁はもっと切れ味がよく見えるように強調したほうがいい」
「アジア映画については、新しい手法が求められています」
「最も大事なのは撮りたい場所を1つと、撮りたい俳優を1人見つけることです。場所と俳優が見つかれば、映画ができたも同然です」
その後、余った時間で、2人はプロットを練る。映画のタイトルは『穢の森』(けがれのもり)である。そう、明らかにあの作品を意識している。2007年にカンヌでパルムドールに次ぐ「グランプリ」を受賞した河瀨直美監督の『殯の森』(もがりのもり)だ。
そして、帰国した2人に芦田愛菜サンを加えた3人は、その女性監督に会いに行く。だが、ここで山田Pはとんでもない返り討ちに遭う。
容赦ない河瀨直美監督
河瀨直美監督は高校時代にバスケットボール部キャプテンとして国体出場経験を持つほど、体育会系で男前の性格である。彼女は山田Pにも容赦しない。「そもそも、なんで俳優なのに、プロデューサーしようと思ってんの?」
「中に入って……ものを作っている実感が欲しくて」と答える山田P。が、それに対して河瀨監督は痛烈なカウンターを繰り出す。
「それやったら、カンヌとかどうでもいいんじゃない?」
カンヌをよく知る女性監督の容赦ない問いかけに、答えに窮する山田P――。
クズ化する山田プロデューサー
ここから、加速度的に山田Pがクズ化していく。
まず、脚本を作らず、シーンごとのイメージの絵を発注する(コンテとは違う)。この絵をもとにイマジネーションで映画を撮るという。
次に、劇中に登場する前科持ちの役を、リアルにこだわる余り、実際に前科持ちの人たちを集めて、オーディションで選びたいと言い出す。
さらには、父親役に起用した村上淳サンに、首つりシーンを吹替えではなくリアルでいきたいと、過酷な練習を強いる。しかし、後日、ふとした気まぐれから森の木の役へと変更し、挙句の果てに歌がもう一つと降板させる。
ここまでで十分クズだが、極めつけのエピソードがこの後に来る。母親役のキャスティングである。
長澤まさみを脱がそうとする
山田Pが温めていた母親役のキャスティングが明らかになる。なんと、長澤まさみサンである。
とはいえ、この母親役が難役なのだ。濡れ場はあるは、全裸で逃げるシーンはあるは、狂い死ぬシーンはあるは――要は脱がないといけない。
「昔はヌードもいいかなと思ってましたが、大人になって、見え方とか気になって……」
戸惑いを隠せない長澤サン。当たり前である。何せ脚本すらないのだ。
後日、山田Pと山下監督、長澤サンの3人だけで話し合いの場が持たれた。全力で脱がしにかかる2人に、言葉を選びつつ、返答する長澤サン。
長澤「もし、全裸が出演条件の一番なら、お断りしようかな、と……」
山田「全裸が抵抗あるなら、チラッ、チラッと……片方だけとか」
長澤「片方?」
――クズである(笑)。この翌日、長澤サンから正式に降板が申し入れられる。
クランクインの日、山下監督降板。そして……!
迎えたクランクインの日、結局、母親役は巨大なオブジェで代用される。
しかし、これを見た山田Pは迫力が足りないと、この3倍の大きさで作り直してくれと言いだす。しかし、作り直すと3週間もかかり、予算もオーバーする。何より、クランクインのために集まってくれたスタッフをバラさないといけない。それは山下監督としては避けたかった。
プロデューサーと監督の間で話し合いが持たれた。しかし、平行線。遂には山田Pから山下監督へ決定的なひと言が発せられる。
山田「帰っていいっすよ」
山下「これで終わりなの?」
――走り出す山下監督。そして、監督の手によりオブジェが爆破される。
「撮影は延期になりますが、監督は僕がやりますので」
スタッフに延期を告げる山田Pに、珍しく厳しい表情の芦田愛菜サンが言葉を発する。
「山田さん、何がやりたいんですか」
その瞬間、言葉を失う山田P――。
強烈なアンチテーゼ
物語は事実上、この11話で終わりである。翌週の最終回は山田Pが故郷である鹿児島へ戻り、自分の過ちに気づいて原点に立ち返る話だが、要はエピローグだ。
一体、この一連の物語――フェイクドキュメンタリーは何を伝えたかったのだろうか。
恐らく――それは、山田孝之サンの考える理想の映画作りへの強烈なアンチテーゼである。映画作りのハウ・トゥを描きつつ、暴走するプロデューサーを自身が演じることで、その“反面教師”を伝えたかったのだ。
「まず、カンヌありき」
「知名度優先の役者起用」
「脚本軽視」
「形から入る」
「女優は脱がせる」
――そういった映画界の悪しき作法を浮き上がらせることで、その逆を説きたかったと推察する。
ドラマ界の可能性の扉を開いた山田孝之
かくして、フェイクドキュメンタリーという手法で、2年前の初挑戦『山田孝之の東京都北区赤羽』からさらに進化した形でお茶の間を楽しませてくれた山田孝之――。
普段の彼は心優しき青年で、およそ劇中の“クズ”プロデューサーとは180度キャラクターが違う。もちろん、山下監督とは今も変わらず朋友で、執拗に脱がそうとした長澤まさみサンとも互いにリスペクトし合う仲である。何より、この物語のナレーションを途中降板した彼女が務めているのが、その証左。芦田愛菜サンが最後に山田プロデューサーに発した“突き刺さる”ひと言も含めて、全ては“フェイク”なのだ。
ここでも、ドラマの可能性の扉を開いた奇跡の男――山田孝之である。
フェイクではない、リアルなプロデュース映画
ここから先の話はあまり長くない。
2018年、1本の映画が公開される。山田孝之サンが初めて完全裏方に徹してプロデュースする映画『デイアンドナイト』である。彼は資金繰りからロケ地への挨拶、オーディションから脚本会議まで、全てのプロデュース業務を完璧にこなしたという。そう、まさにそれは、『~カンヌ映画祭』を反面教師にした作品なのだ。
主演は同じ事務所で、親友の阿部進之介サン。監督は、映画『オー!ファーザー』や『光と血』などの藤井道人監督。フェイクでない証拠に、同映画は脚本をことさら重視し、山田孝之サンも度々脚本会議に参加し、その改稿は実に数十回に及んだという。脚本を作らなかった『~カンヌ映画祭』と真逆である。
『72時間ホンネテレビ』への参戦
映画『デイアンドナイト』――栄えあるクランクインは、先の11月3日に行われた。そう、その日といえば、前回の連載でもお伝えした通り、あの「新しい地図」の3人が挑んだAbemaTVの『72時間ホンネテレビ』に、山田孝之サンが秋田から急きょ駆けつけた日だ。

その日の午前中、秋田県三種町にて映画のクランクインを見届けた彼は、あとは現場を監督に任せ、藤田晋社長のプライベートジェットに乗り、帰京したのは周知のとおりである。
現場に余計な口出しをせず、むしろ現場から離れ、プロデューサーの本分である映画の宣伝を皆が注目する『72時間ホンネテレビ』内でさりげなく行う――ここでも『~カンヌ映画祭』の教訓が活かされている。
新しいテレビのそばに山田孝之あり
――以上、「2017テレビマン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた山田孝之サンの選考理由でした。
自身が主役として深く関わった2つの番組でバラエティとドラマの可能性の扉を開く一方、新しいテレビと話題のAbemaTVの『72時間ホンネテレビ』にも顔を出す――しかも、その日は自身がプロデュースする映画のクランクイン日という最高の宣伝。
新しいテレビのそばに山田孝之あり、である。
(文:指南役 イラスト:高田真弓)

“永遠のオトナ童貞のための文化系マガジン・チェリー”では、『山田孝之のカンヌ映画祭』放送終了後のタイミングで松江哲明監督と山下敦弘監督にインタビューをおこなっています! そちらもあわせてどうぞ!
「ものづくりはブーメラン」松江哲明&山下敦弘が“山田孝之というジャンル”を通して見えたこと