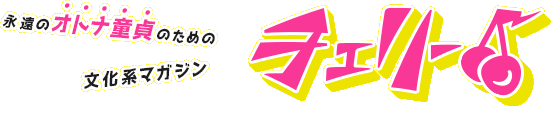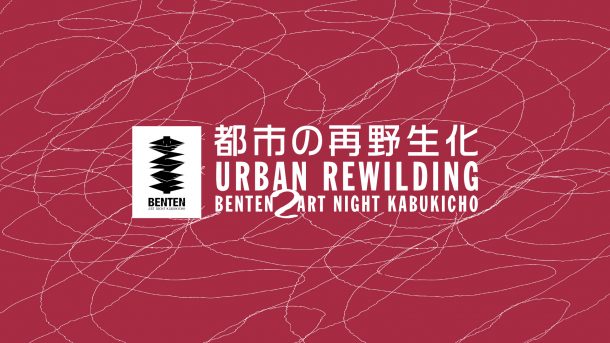2005年の結成から、今年で20周年を迎える6人組のアーティストコレクティブ・Chim↑Pom。(2022年よりChim↑Pom from Smappa!Group。以下、Chim↑Pom)
東京で増殖するネズミを捕獲して剥製にする『スーパーラット』や、広島の原爆ドーム上空に飛行機雲で「ピカッ」と書く『ヒロシマの空をピカッとさせる』、岡本太郎の壁画『明日の神話』の右下にある隙間に福島第一原発事故を描いた絵をゲリラ設置した『Level 7 feat.明日の神話』など……その他にも現代社会に介入した多くのプロジェクトを通して世界各地の展覧会に参加している。一方で、近年では歌舞伎町を中心にさまざまな自主企画を展開している。
永遠のオトナ童貞のための文化系WEBマガジン・チェリーでは、Chim↑Pomメンバーで2018年までリーダーを務めた卯城竜太さんにインタビュー。取材時はちょうど「都市の再野生化」を掲げ、Chim↑Pomがキュレーターを務める『BENTEN 2 Art Night Kabukicho』の準備の真っ最中。舞台となる歌舞伎町との関わりや、その変遷など、チェリーに合わせて「◯◯童貞」(※特定の領域での経験が少ない/ないことを俗にこう言う)といった言葉を使いながら語ってくれた――。
いつも“◯◯童貞”でやってきた
――いきなり恐縮なのですが、40代後半とは思えない若さを感じます。
卯城:それでいつも舐められがちなんですよ…(笑)まあ、会社に行って年相応のポジションについたりする人生ではないので、そういう振る舞いがない分、それが影響しているんですかね。ただ、Chim↑Pomのメンバーを含めて、僕の周りって年の割に若い人が多いんですよ。ポジティブに捉えてみればでしょうか……、ひょっとしてアートってアンチエイジングにいいのかもしれないですね。僕自身、あまり年齢のことを考えずに来てしまったので雑な返事ですが……。
――すみません、もちろん舐めずに純粋に褒めてます!(笑)ということで、永遠のオトナ童貞のための文化系WEBマガジン・チェリーと申します。よろしくお願いします!
卯城:いいですね。僕も童貞には強い思い入れがあります。僕自身、今も昔も何をやっても素人というか、アマチュアリズムで生きてきた感が強いんですね。今は2歳半の育児をしているのですが、まだ全然慣れなくて、“育児童貞”です(笑)。アートも、何をやってもいいからこそ、飽きずにやれている部分があって。例えば『また明日も観てくれるかな』や『にんげんレストラン』などではビルの自体に穴を開けましたし、多くのパフォーマーたちと協働しました。その都度初めてのことばかりです。森美術館のときも、「美術館で見たこともないものをやろう」と考えていた時点で、“美術館童貞”みたいなもんですよね(笑)。だから、童貞のまま色々初めてのことをやれるっていう時点で、アートは自分にとってはいいんだと思うんですよね。一個のことを極める場合もありますが、新しいことに挑戦できなかったりしたら、僕は飽きてしまうというかダメなタイプなので。
――色々なことに童貞のままだったからこそ、20年やってこられたわけですね。
卯城:はい、やっていることはいつも“◯◯童貞”なんです。ただアート全体ということに関しては、さすがに“アート童貞”とも言えなくなってきていると言いますか……。最近、自分が何をやってもアートになっちゃう感じに困っている部分もあって。何をやってもアートとして見られてしまうといいますか。自分でもそういう振る舞いを身につけてしまってきていて、つまらなさもあるし、でもありがたさもあるしで、そこはせめぎ合っている部分がありますね。
エクストリームなことをするのに向いている街
――Chim↑Pomのみなさんがキュレーションを務められる『BENTEN 2 Art Night Kabukicho(以下、BENTEN )』が始まります。先ほどお話に出た『ナラッキー』や2018年の『にんげんレストラン』など、歌舞伎町でも多くのプロジェクトを開催されていますが、そもそもみなさんが歌舞伎町と深く関わるようになったきっかけは何だったんでしょうか?
卯城:2014年にエリイが手塚マキさん(歌舞伎町のホストクラブなどを経営するSmappa!Group会長)と結婚したときに、路上を使って、結婚式のデモって言ってるんですけど、パレードのようなものをしたんですね。

それから多くのプロジェクトをやってきましたが、とにかく全部が全部、やりたいことを120%にしてできる街なんですね。安易に通報するような文化もないから自粛も必要ないし、そもそも「迷惑」みたいなことの次元が他の街とは違うところにある。エクストリームなことをするには向いている街だな、と思ったんですよね。2016年に解体が予定されていた歌舞伎町振興組合ビルで、『また明日も観てくれるかな?』っていう展覧会をやったあたりからは、オリンピックに向けての再開発みたいなののムーブメントの中にそのビルの解体工事があったので、自ずと都市論のようなものに関わるようになっていったのですが、その視点からも特異な街だなと常々思わされてきました。

都市論的な俯瞰した視点をもってからは、自分たちの表現だけではプロジェクトが収まらなくなってきたというのもありますね。例えば結婚式は個が公共に介入するみたいな感じのイメージでしたが、今度は自分たちが公共性を持って都市を体現したいと考えるようになって。そうすると、単に自分たちの展示をするだけじゃなくて、エクストリームな表現者たちに来てもらって、その容れ物になって来たというか。そういう意味で、自らの作家性が歌舞伎町的な公共性に強く影響を受けてきたという感じです。
若い人が増えたことの嬉しさと怖さ
――それが今回のキュレーションという役割にも結びついているわけですね。その後、この10年ほどの歌舞伎町の変異で感じることはありますか?
卯城:2018年の『にんげんレストラン』の会期2週間ほどの間に、会場となったビルから半径100メートルほどの範囲内で飛び降り自殺が相次いでしまったんですね。それは、あるジャーナリストの当時の視点では、どうやら若い人たちが警戒心のないままどんどん街の中に入ってきている状況とリンクしているのではないかと。
その後、2020年のコロナの頃には夜の街なんて言われてバッシングされていましたし、東横キッズなんて言葉も騒がれるようになってきました。ただ、歌舞伎町は彼らにとってもアーティストにとっても、逃げ込んでくる人や流れ着く人たちにとっては、居場所になってきたんです。コロナで自粛モードになって、他の地域の色んなアートスペースが閉鎖していく時期に、歌舞伎町では今回のBENTENの会場にもなるようなアートスペースやギャラリーなんかが次々とオープンしていきました。フリーズしていたアートシーンにとっては真に代替的な街であったし、つまりその時からはオルタナティブなプラットフォームになった感じがします。
――2023年の『ナラッキー』に行ったときに、その客層の若さにとても驚きました。それは、今おっしゃった歌舞伎町に若い人たちが警戒心なく入ってくる流れとリンクするものなのでしょうか? 前年の森美術館での『Chim↑Pom展:ハッピースプリング』も若者が多かった印象なのでChim↑Pom自体の力もあるのかもしれませんが……
卯城:リンクはしていると思います。『ナラッキー』のときはTikTokを見て来たみたいな若い子がたくさん来ましたが、それだけでは説明出来ないような客層の方々がとにかく来ていて、僕らも驚かされました。もちろん作品を観て考えてもいるのですが、単に、展示として設置したカラオケをしに来てるだけなのではみたいなノリもありました(笑)。読み解けば難しい展覧会でもありましたが、一方で、僕らの中にもそういうものを楽しむノリはあるので。歌舞伎町が持っている、非・予定調和な空気感を僕らも好きですしね。会期も延長するほどで大成功ではあったんですが、その一方で、僕らを入口に歌舞伎町に来て、危ない目にあってしまう人もいないとは言い切れないので、そこは複雑な気持ちではありました。
再野生化する歌舞伎町の中で生き残るために
――ナラッキーと同じ2023年には、東急歌舞伎町タワーができるなど、歌舞伎町も再開発が進んでいます。2019年に発売された卯城さんと松田修さんの対談本『公の時代』では、渋谷の再開発などを例に挙げて、「公」と言いつつもマジョリティの人々にしか開かれていないことへの疑義を呈していらっしゃいました。2025年現在の、一種の逃げ場としても成立している歌舞伎町は、その意味ではマジョリティ以外にも開かれた街になっているということでしょうか?
卯城:そうですね。渋谷の再開発によって秩序ができる感じとは違って、歌舞伎町は独自の変化を遂げていますよね。いわゆる秩序からはそもそも逸脱している活動が多い時点で、トップダウンにコントロールするのは難しい街です。歌舞伎町って戦後の文脈で言えば、闇市とかから始まっているので、ルールありきで人が集まっているのではなく、人が集まってルールができた街だと思うんです。そもそも善悪が二項対立していない街というか。
歌舞伎町タワーができても、あの辺には今も、コンカフェ嬢の方もいれば、路上飲みし続けているオジサンたちもいる。むしろ、再開発で少し安全に見えるようになったことで、より色んな人が来るようになって、カオティックになっている印象すらあります。
そういった現状を、僕らは歌舞伎町の再野生化と呼んでいます。街自体が再野生化しているなら、野生の生態系の中でペットが生き残れないように、街にくる自分たちも再野生化するしかないですよね。今回のBENTENは、先ほどのアートに触れられる場所が増えてきたという話も含めて、点を線で結びつけてみると、歌舞伎町界隈の文化の生態系みたいなのが見えやすくなってきたので、整理して提示してみようという感じです。
Chim↑Pomという名前が負った“業”
――最後の質問です。20年以上にわたって活動を広げられているChim↑Pomさんですが、名前のニュアンスで正当に評価されないと感じることはありますか? 僕らは媒体名にもろに「童貞」という言葉が入っているのでナメられることも多いのですが……。
卯城:名前の由来はもっと感覚的だったのですが、かつては何か意図があるようにそこだけピックアップする人もいました(笑)。まあ、パチンコって名付けた人とたぶん同じ気持ちだと思います。もはや受け取る側もパチンコって名前を気にすることはないじゃないですか。活動を続けているうちに自分たちもそうなってきたように思っています。
<取材・文>霜田明寛
<撮影>
卯城竜太:みなみあさみ
LOVE IS OVER:篠山紀信
BLACK OF DEATH:森田兼次
【『BENTEN 2 Art Night Kabukicho』開催概要】
■会期
2025年11月1日(土)15:00-5:00/11月2日(日)15:00-5:00/11月3日(月・祝)15:00-23:00
※会場によって開場時間が異なります。公式WEBサイトやSNS等によりご確認ください。■会場
歌舞伎町地区一帯(王城ビル/歌舞伎町能舞台/デカメロン/WHITEHOUSE /東京砂漠(旧芸術公民館) /THE FOUR-EYED /ユニカビジョン)
■公式ウェブサイト http://benten-kabukicho.com