俗に、連ドラの世界には、こんな格言がある。
「ドラマの9割は脚本」――。
この「9割」は、人によって「8割」だったり、「7割」の時もある。また、同種の格言に「映画は監督、舞台は役者、ドラマは脚本」というのもある。いずれにせよ――ドラマにとって脚本が重要な役割を担うことには違いない。
そこで、今回は脚本家の話である。それも、現時点において、この人が書いている作品なら見ておいて損はないという、実力派の脚本家の話だ。今回は6人を挙げさせてもらう。言うなれば、6人の脚本家の聖人たち――略して、6人の“脚聖”だ。
一人目は、先の7月クールで驚異の右肩上がりの視聴率を見せた“ギボムス”こと『義母と娘のブルース』(TBS系)を書いた森下佳子サンである。
伏線と回収の森下マジック
森下サンと言えば、先のギボムスでも見せてくれた「伏線と回収」に定評がある。大抵の脚本家は風呂敷を広げるだけ広げて、畳まない人が多いが――森下サンは違う。ちゃんと先々を見据えて風呂敷を広げ、ドラマの終盤、見事に畳んでみせる。通称、森下マジック。
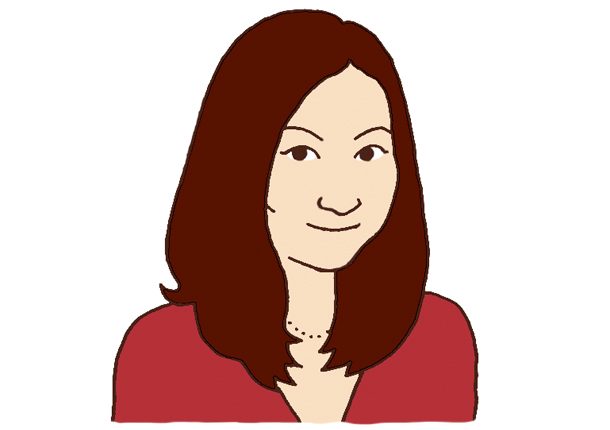
例えば、ギボムスでは、前半パート、佐藤健演じる麦田の職業が毎回異なり(バイク便→花屋→タクシードライバー→リサイクルショップ→葬儀屋)、その度に彼がきっかけで、亜希子(綾瀬はるか)の周りで小さな奇跡が起きた。良一(竹野内豊)曰く「奇跡って、割とよく起きるじゃないですか」――なんて。
それが後半パートになると、麦田はパン屋を営み、亜希子はそこで働き始め、2人は急接近する。そして、とうとう9話で麦田の過去の仕事の変遷が亜希子の知るところとなり、かつての奇跡が麦田のお陰だったと気づく。「店長は私にとって、小さな奇跡ということです」――なんと最終回の1つ前に至り、前半パートの麦田の転職の伏線が、“ロングパス”で回収されたのである。
それを受け、麦田が亜希子に告白。さて、2人の恋の展開は?――と同ドラマのボルテージも最高潮に。伏線を回収した上に、最大のクライマックスも演出する。これが森下マジックである。
連ドラのクライマックスは最終回の1つ前
そうそう、同ドラマ、この9話の盛り上がりに比べ、最終回がちょっと物足りなかったという声も聞かれたけど、大体、連ドラというのは最終回の1つ手前の回が一番盛り上がるようにできているんです。何せ連ドラにとって一番大事な要素は、お茶の間に「次、どうなるのか?」とカタルシスを抱かせることだから。
例えば、あの『踊る大捜査線』にしたって、全11話の一番のクライマックスは、真下(ユースケ・サンタマリア)が凶弾に倒れ、湾岸署の刑事たちに拳銃携帯命令が発令された、最終回の1つ前だった。『東京ラブストーリー』も、消えたリカ(鈴木保奈美)を探しにカンチ(織田裕二)が郷里の愛媛に戻り、母校の小学校の柱に新しく彫られたばかりのカンチとリカの名前を見つけるシーンがクライマックス。あれも最終回の1つ前だった。『ロンバケ』も同じく、一番盛り上がったシーンは、瀬名(木村拓哉)と南(山口智子)が初めて屋上でキスを交わした、最終回の1つ前のラストだった。
日テレからTBSに移り、ブレイク
ここで、森下サンの経歴をざっと紹介すると――東大文学部(!)を卒業して、一旦就職するも、脚本家を志してシナセン(シナリオセンター)に通い、遊川和彦サン主宰のコンペに応募して合格。晴れて遊川サン企画の『平成夫婦茶碗~ドケチの花道~』(日テレ系)にて脚本家デビューする。
その後、日テレで数本連ドラを書くも、本格的にブレイクしたのは、TBSの『世界の中心で、愛をさけぶ』から。まぁ、日テレの作品は、どちらかと言えばバラエティ色の強い企画案件。それより彼女には作品主導型のTBSの水のほうが合っていたということだ。
その後の活躍はご承知の通り。『白夜行』、『JIN-仁-』、『とんび』、『天皇の料理番』、そして直近の『義母と娘のブルース』と、着実にTBSでヒットを重ねる一方、朝ドラ『ごちそうさん』や大河ドラマ『おんな城主 直虎』など、NHKの伝統枠でも高い評価を得てきた。
もっとも、『~直虎』は題材がマイナーすぎて視聴率的には苦戦するも、内容面では、井伊直虎(柴咲コウ)と筆頭家老・小野政次(高橋一生)の数奇な運命を中盤過ぎまで巧みに描き、最終回で井伊家の跡取りの万千代(菅田将暉)が、家康から井伊の通り字である「直」、小野の通り字である「政」を取って「直政」の名を授かるという“大ロングパス”を決め、お茶の間は拍手喝采。何かと「スイーツ大河」と言われる近年の大河において、久々にお茶の間の読後感はよかったと思う。
キャリア19年――。森下サンは、今なお第一線で高いクオリティの脚本を生み続ける“脚聖”と称しても過言でないことが、お分かりいただけただろうか。
今最も旬な脚本家・野木亜紀子
続いては、『逃げ恥』や『アンナチュラル』でもお馴染みの野木亜紀子サンである。もう説明するまでもないですね。今最も脂が乗っていると言われる脚本家だ。

まずはそのプロフィールから振り返ってみたい。
脚本家デビューは、フジテレビのヤングシナリオ大賞である。同賞からは、坂元裕二サン、野島伸司サン、尾崎将也サン、橋部敦子サン、浅野妙子サン、いずみ吉紘サン、金子茂樹サン、古家和尚サン等々――佳作も含めて、これまでにヒットメーカーを数多く輩出している。新人脚本家の登竜門は数あれど、ここまで出身者が活躍している賞は他にない。それはひとえに、フジテレビが早くから入賞者にチャンスを与え、局を上げて新人脚本家を育てるからである。
ところが――どういうワケか、野木亜紀子サンという大魚を逃してしまった。近年、彼女が書いているのはTBSと日テレばかりである。もちろん、フジも野木サンの受賞から2年後には、月9のセカンドライターや、土曜夜11時台のドラマというチャンスを与えている。でも、今ひとつ芽が出ず、彼女がブレイクするのはその翌年、TBSの日曜劇場『空飛ぶ広報室』をピンで書いてからである。
フジとTBSの脚本家の育て方の違い
フジとTBSで何が違った?
一見すると、新人脚本家にキャリアを積ませようと、月9という看板枠でセカンドライターのチャンスを与えたり、若者向けの深夜ドラマを書かせたフジは正しいように見える。
一方、TBSは、最初から野木サンを一人前の脚本家として扱い、日曜劇場という大役をピンで任せた。人間、大き目の服を与えられた方が成長する――彼女はその期待に全力で応え、見事に成功させたのである。
あくまで新人脚本家として上から目線で接したフジに対し、一人前の脚本家として扱ってくれたTBS。そこに両局の差があった。
その後、野木サンは、『掟上今日子の備忘録』(日テレ系)、『重版出来!』(TBS系)、『逃げるは恥だが役に立つ』(TBS系)、『アンナチュラル』(TBS系)――と、ヒット作を連発。そして、この10月から日テレ系の新ドラマ『獣になれない私たち』を書いている。主演は、野木脚本4度目のガッキーと、松田龍平のコンビ。何より画期的なのは、同ドラマは野木サンにとって初のオリジナルのラブストーリーなのだ。
そう、初のオリジナルのラブストーリー――ここに野木亜紀子という稀代の脚本家を解く鍵がある。
ストーリーテリングの名手
意外に思われるかもしれないが、野木サンがメインで書いた連ドラで、オリジナル作品は、前作の『アンナチュラル』が初めてだった。それまでは全て原作ありきの作品である。
一般に、脚本家を志すような人は作家志向が強く、原作のある作品を脚色するよりは、オリジナルを書きたがる。ところが――野木サンは、脚色の仕事も喜んで引き受けたんですね。そして特筆すべきは、そのクオリティが原作を生かしつつ、連ドラとしても最高に面白いという“神業”だったこと。
これは、前回のコラム「7月クールドラマ中間決算」でも述べたが、原作を映画化したり、ドラマ化する場合、原作とは別ものと考えるのがスジである。だって、原作は映画やドラマの“脚本”じゃないのだから――つまり、映画やドラマとして最高に面白くしないと意味がない。
ラブの要素を入れて成功した『掟上今日子』
その点、野木亜紀子サンは、ぬかりない。例えば『掟上今日子の備忘録』では、ガッキー演ずる主人公・掟上今日子が1日寝たら全ての記憶を失う“忘却探偵”である原作の設定を最大限に生かしつつ、連ドラでは原作にはない相棒の隠舘厄介(岡田将生)との淡いラブの要素も取り入れた。
これが連ドラにハマった。基本、厄介の片想いに過ぎないが、恋が進展しそうになると、決まって翌日、今日子から「はじめまして」と言われる、切ない展開が繰り返される。ところが最終回――遂に2人は両想いになる。だが、眠れば最後、今日子の記憶は失われる。睡魔に襲われる中、「私……忘れたくない」と涙ぐむ今日子。このシーンは切なかった。
そう、原作の謎解きの面白さは生かしつつ、“ラブ”の要素も取り入れ、連ドラとして一味違った最高の作品に仕上げる――これが野木サンの“脚色”の優れているところだ。ちなみに、最終回のラスト、及川光博演ずる所長に「経験や感情を身体が覚えていて、いつの日か恋が結実するかもしれないネ」と言わせて、お茶の間に淡い期待を抱かせることも野木サンは忘れない。
野木亜紀子、初のオリジナルラブストーリー
そして、この10月から始まる『獣になれない私たち』である。野木サンにとって日テレの連ドラは、先の『掟上~』以来となる。そして今度は、オリジナル脚本である。
基本、今の連ドラ界は、オリジナルが書きにくい環境にある。90年代の連ドラ全盛期と違い、ドラマの視聴率は低迷し、テレビ局は保険の意味で、人気小説やコミックのドラマ化、あるいは外国でヒットしたドラマのリメイクに走りがちだ。オリジナルが書けるのは、大御所の脚本家先生くらいである。
つまり、野木サンですら、自分を高く売るには、地道に脚色で実績を重ねるしかなかった。そして、ようやく前作の『アンナチュラル』で、初めてオリジナルドラマを書くチャンスを得たのである。とはいえ、いきなりラブストーリーというワケにはいかず、ここでも固定客の見込める医療ドラマと刑事ドラマ(謎解き)の要素を入れざるを得なかった。結果は――視聴率も内容も上々の出来。年間ギャラクシー賞まで受賞し、野木サンは見事、試験にパスしたのである。
そして今回、オリジナルのラブストーリーという、今の連ドラ界で最もハードルの高い(視聴率の取りにくい)ジャンルを書かせてもらえるお許しを得たのである。これは期待せずにはおられない。
野木亜紀子、一世一代の晴れ舞台である。
古沢良太という天才
今年に入って、フジテレビのドラマが持ち直しつつある。
先の7月クールは、月9と木10の2大伝統枠が共に平均二桁の視聴率を獲得。これは実に、2014年の10月クール以来の快挙だった。
復活の理由は何か。
僕は、フジのドラマが“脚本重視”の姿勢に変わったのが一番だと思う。そして、その転機となったのが――4月クールの月9ドラマ『コンフィデンスマンJP』であり、そのキーマンこそ、脚本家の古沢良太サンだった。
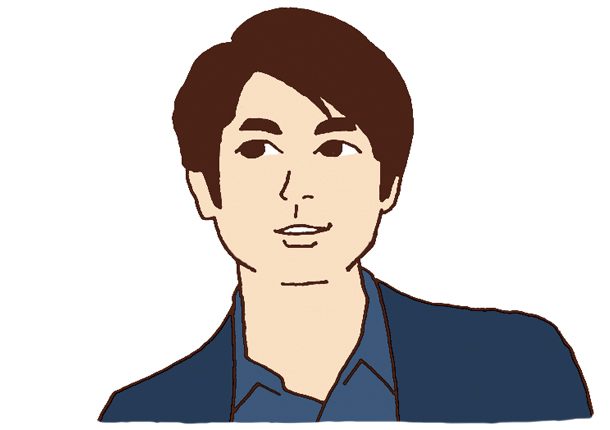
そう、古沢良太――。ひと言で言えば、天才脚本家である。
世の中の時流とか、ドラマのセオリーとかをことごとく覆して、それでも面白い脚本に仕上げられるのは、古沢サンにしかできない芸当だ。
例えば、『リーガル・ハイ』の敏腕弁護士・古美門研介(堺雅人)の台詞は、勧善懲悪とか、弱きを助け強きをくじくといった旧来型のドラマ・セオリーとは一線を画する。
例えば――
「うぬぼれるな。われわれは神ではない。ただの弁護士だ。真実が何かなんてわかるはずがない」
「この国では世間様に嫌われたら有罪なんです。法治国家でもなければ、先進国でもない。魔女を火あぶりにして喜んでいる中世の暗黒時代そのものだ!」
「何を基準にして人を好きになるかは個人の自由であり、そこに優劣はない。熊井健吾の場合は顔がきれいかどうか。どんなに性格が悪くても顔がきれいな人がいい。立派なポリシーだ。それを不謹慎だと言う君たちの方が歪んでいる」
――いやはや、痛快だ(笑)。一見暴論だけど、古美門が口にすると、なぜか僕らは納得してしまう。その強烈なキャラクターが違和感なく見えてしまう――そう、そこに古沢脚本の秘密が隠されている。
ファンはキャラクターにつく
よく、『週刊少年ジャンプ』あたりの編集者が、持ち込みの漫画家のタマゴに向かって吐く定番のフレーズがある。それは――「ファンはキャラクターにつく」。
得てして、新人漫画家はストーリーさえ面白ければと、練りに練った物語を作りがちだ。でも、肝心の読者は物語よりキャラクターに惹かれる。だから、まずは魅力的なキャラクターを作り上げろという意味である。
実は、古沢サンは、かつて漫画家を志したことがある。そのせいだろうか、古沢サンの書くドラマは、どれも主人公のキャラが強烈だ。『リーガル・ハイ』の古美門、『デート~恋とはどんなものかしら~』の依子(杏)と巧(長谷川博己)、『コンフィデンスマンJP』のダー子(長澤まさみ)――。
そして――実は、古沢サンが凄いのはここから。それら破天荒なキャラが、最終的にはすんなりとお茶の間に受け入れてもらえるよう、盤石の物語を構築するのである。そのテクニックが神業なのだ。
そう、先のジャンプの編集者が言いたかったことも同じこと。まずは、読者に好かれるキャラクターを作り、その上で彼らが魅力的に見える、珠玉のストーリーを構築せよと。
男主人公がハマる古沢脚本
ただ、古くからの古沢ファンには、直近の『コンフィデンスマンJP』は少々物足りなかったようで――やはり『リーガル・ハイ』や『デート』のほうがしっくりくるという。
実際、視聴率は正直なもので、『コンフィデンス~』が最後まで二桁に届かなかったのは、何かしらの原因があるのだろう。僕は――それは男主人公の有無だと思う。
多分、古沢サンは男主人公のほうが、より魅力的なキャラクターが描けるのだ。『リーガル・ハイ』の古美門、『デート』の巧、もっと言えば『鈴木先生』の鈴木(長谷川博己)――いずれも超個性的で、多面的な性格の持ち主で、人間的にも面白い。それに対して、『コンフィデンス~』のダー子は、ちょっとキャラが一元的過ぎる嫌いがあった。もちろん長澤まさみサンは魅力的に演じていたのだけど――。
ただ、『コンフィデンス~』は嬉しい誤算というか、相棒のボクちゃん(東出昌大)が抜群に面白かった。東出サンの芸風をあんな風に生かせるのは、古沢サンならでは。さらに、リチャード(小日向文世)は安定してうまく、五十嵐(小手伸也)という飛び道具もあった。――となると、次なる楽しみは、番組内で告知された“劇場版”の公開になる。
今のところ、詐欺ではなく、ちゃんと進んでいるようなので、安心してほしい(笑)。もっとも、フジテレビ的には『劇場版コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』が絶好調で、興行収入が90億円を突破して今年の1位がほぼ確定なので、この流れをうまく生かしてほしいところ。
空気を作る天才・奥寺佐渡子
映画の話が出たついでに、あのアニメ映画の話も――。
細田守監督の『未来のミライ』である。『バケモノの子』から3年ぶりのオリジナル作品。前作が58億円の興行収入を記録したことから期待されるも――今のところ興収27億円と半分以下である。何よりヤフーの映画サイトのレビューの点数が目も当てられない。中には冷やかし半分の投稿もあるかもしれないけど、やはり作品のクオリティが今ひとつである感は否めない。
なぜ、こんなことになったのか?
思うに――奥寺佐渡子サンが脚本を書いていないからじゃないだろうか。

そう、奥寺佐渡子サン。ちなみに、彼女が脚本を担当した細田作品は、『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』、『バケモノの子』(※脚本協力)の4本。そして今回の『未来のミライ』には一切タッチしていない。これはもう、そこに原因があると考えるのが自然じゃないだろうか。
正直、前の4作は面白かった。
奥寺佐渡子サンの持ち味と言えば、いわゆる作品の“空気感”である。それを作らせたら、この人の右に出る脚本家はいない。彼女の作品を冒頭から2分も見ていると、気づいたら僕らはスッと物語の中に入っているもの。
例えば、『時をかける少女』もそうだった。冒頭、いきなり真琴と千昭と功介の3人が校庭で野球をしているが、このわずか1分ちょっとのシークエンスで、真琴が活発な女の子であること、3人が恋人関係ではなく友人同士であること――などが自然と伝わってくる。
そう、それが最も生きたのが、彼女が手掛けた一連のTBS金ドラのシリーズだ。
女だらけの鉄板スクエア
『夜行観覧車』、『Nのために』、『リバース』――この3タイトルを見て、すぐにピンときたら、あなたはドラマ通である。
そう、これらは主要なスタッフィングが全て女性たちという座組で作られたTBS金曜ドラマの一連のシリーズだ。原作・湊かなえ、プロデュース・新井順子、チーフ演出・塚原あゆ子、そして脚本・奥寺佐渡子――通称、女だらけの鉄板のスクエア。
よく連ドラには「記録よりも記憶に残る」と言われる作品があるが、まさにこの3作品がそう。取り立てて視聴率がよかったワケではない。しかし、不思議と印象に残り、テレビドラマの各賞を受賞し(つまり審査員ウケもいい)、何よりお茶の間、特に女性視聴者からの反響が高かった。その意味では、先のスクエアに1つ足して、女だらけの鉄板のペンタゴンとも――。
3作品に共通するのは、独特の空気感である。これこそが奥寺佐渡子サンの真骨頂。物語はミステリーベースながら、そこに人間ドラマが深く関わり、特に女性の心理描写が鍵となる。そして独特の読後感――。
3作品は登場人物もストーリーも全く別物である。それでも“シリーズ”と呼ばれるのは、作り手たちの思いが作品を通してダイレクトに伝わり、それをお茶の間が共有するから。そこには、古き良きテレビの送り手と受け手の信頼関係がある。
間違いなく――奥寺佐渡子サンは映画、ドラマ界に欠かせない逸材である。細田監督、次回作はぜひ再考を。
2人のベテラン脚本家
ここから先の話はあまり長くない。
6人の脚聖――残る2人は、これからNHKの2つの伝統枠に挑む、2人のベテラン脚本家である。福田靖サンと宮藤官九郎サン――奇しくも、福田サンは大河ドラマ『龍馬伝』を書いたものの、朝ドラは初挑戦。宮藤サンは朝ドラ『あまちゃん』を書いたものの、大河は初挑戦である。
まず福田靖サン。脚本家としてデビュー後しばらくはテレビ朝日の仕事が続いたが、一大転機となったのは2001年――フジテレビで『HERO』を書いてからである。
ご存知、木村拓哉主演の検事ドラマ。1stシーズンは全話視聴率30%超えの偉業を達成し、これは日本の民放ドラマ史上、今もって唯一の快挙である。

石原隆プロデューサーとの出会い
実は福田サン、『HERO』はピンチヒッターで呼ばれて、途中から参加したんですね。というのも、当初このドラマはフジのヤングシナリオ大賞を受賞した新人の大竹研サンが書くはずだったんだけど、1話を書いている途中で、度重なる直しに耐え切れず、降板。そこで急遽呼ばれたのが――『救命病棟24時』のセカンドライターながら、クオリティの高い脚本が評価され、同ドラマの最終回を任された福田靖サンだった。
福田サンにとってラッキーだったのは、ここでプロデューサーの石原隆サンから、それこそ脚本作りのノウハウを徹底的に仕込まれたこと。プロット作りから、伏線と回収、ドラマツルギー、コメディリリーフ、ゲームチェンジ、ロングパス、そしてカタルシス――etc.
石原サンといえば、『古畑任三郎』や『踊る大捜査線』の生みの親でもあり、古今東西の映画に精通している日本一のプロデューサーである。彼としても、メインの脚本家に降りられた手前、絶対に失敗は許されないし、何せ主演は当時全盛期のキムタクである。そこで自身の持つあらゆるノウハウを惜しみなく福田サンに注いだ。そして福田サンも貪欲にそれらを吸収した。
朝ドラ『まんぷく』への期待
かくして――「群像劇の名手」と呼ばれる福田靖サンが誕生した。以後の活躍はご承知の通り。フジテレビの『救命病棟』、『海猿』、『ガリレオ』シリーズをはじめ、テレビ朝日の『DOCTORS~最強の名医~』シリーズ――いずれも群像劇で、軒並み高視聴率を獲得した。
そして――この10月から始まったNHK朝ドラ『まんぷく』である。朝ドラと言えば、それこそ究極の群像劇。半年間にもわたる長丁場で、登場人物は限りなく多い。綿密なキャラ付け、プロットが求められ、福田靖サンの得意とするところだ。これは期待せずにはおられない。
加えて、今作は朝ドラ定番の実話ベースの物語で、舞台は戦前・戦中・戦後とノスタルジー感も満載。演出も、大阪らしい明るいタッチが期待できる。ヒロインに安藤サクラ、相手役に長谷川博己と、メインの2人も芸達者揃い――これはひょっとすると、凄いドラマになりそうだ。
33年ぶりの近現代路線
一方、宮藤官九郎――クドカンは来年の大河ドラマである。もはや彼については、プロフィールの紹介はいらないだろう。

タイトルは、『いだてん〜東京オリムピック噺〜』である。1912年の日本のオリンピック初参加から、40年の幻の東京オリンピックを挟み、64年の悲願達成までの半世紀にわたる歴史を、「日本のマラソンの父」金栗四三と、東京オリンピック招致に尽力した田畑政治(日本水泳連盟元会長)の2人の主人公で、リレー形式で見せるという。
大河の近現代路線は、1986年の『いのち』(脚本・橋田壽賀子)以来である。実に33年ぶり。正直、当時イマイチの評判だった大河の近現代路線の復活に、クドカンという民放で活躍するコメディ脚本家の起用――古くからの大河ファンの中には不安視する向きもあると思う。
だが、心配ご無用。ここに面白いデータがある。
初舞台で実力を発揮するクドカン
確かにクドカンの得意とするドラマは小ネタ満載のコメディベース。それも現代の若者ドラマが対象だ。大河に求められる脚本とは180度真逆のイメージがある。
しかし――その一方で、「初舞台に強い」クドカン伝説というものがある。彼は、初めての舞台や、初めて組む相手とは、不思議とバランスの取れたいい仕事をするのだ。しかも視聴率もいい。以下がそうである。
『池袋ウエストゲートパーク』(TBS系)平均視聴率14.9%
【初めてのフジテレビ】
『ロケット・ボーイ』平均視聴率18.8%
【初めての東野圭吾原作】
『流星の絆』(TBS系)平均視聴率16.6%
【初めてのNHK朝ドラ】
『あまちゃん』平均視聴率20.6%
――いかがだろう。見事に高視聴率が並んでいる。
初めての連ドラの『池袋~』は、演出が堤幸彦監督。恐らくクドカンはガチガチに緊張しながら脚本の打ち合わせに参加したと思うし、TBS育ちのクドカンにとって初めてのフジテレビは、演出が河毛俊作サンで、主演が織田裕二。これもコワモテ相手に相当緊張したはずだ。
そして、初めての東野圭吾原作――これは、文壇の大御所とのタッグという、相手も立てないといけない慣れない仕事だったろうし、初めてのNHK朝ドラは文字通り他流試合である。謙虚に打ち合わせに臨んだと思われる。
そう、今度のドラマはクドカンにとって、「初めてのNHK大河」である。成功する鍵は、いかにクドカンに緊張させ、大河の空気を取り入れつつ、彼にバランスの取れた脚本を書かせるかにかかっている。
それが叶えば、同ドラマの成功は見えている。何せ脚本家としての実力はピカ一。あとは、いかにその才能を引き出すか。個人的には、こちらも大河初演出となる大根仁監督との化学反応が楽しみだ。
――以上、駆け足だが、現時点における脚本界の「6人の“脚聖”」を紹介してきた。何はともあれ、彼らの最新作――野木亜紀子サンの『獣になれない私たち』(日テレ系)と福田靖サンの『まんぷく』(NHK朝ドラ)、来年のクドカンの『いだてん〜東京オリムピック噺〜』(NHK大河)は、見て損はないと思う。これらの感想等については、また本コラムで追ってフォローしたいと思います。
最後に――今回は6人に絞ったけど、もちろん優れた脚本家はまだまだ大勢いる。『カーネーション』の渡辺あやサンに、『結婚できない男』の尾崎将也サン、晴れて100作記念のNHK朝ドラ『なつぞら』の脚本を担当する名人・大森寿美男サン――etc.
ドラマは時代の鏡であり、脚本家も常に時代とリンクする感覚が求められる。新人脚本家も次々に登場している。
一年後の「6人の“脚聖”」は、ガラリとメンバーが変わっているかもしれない。
(文:指南役 イラスト:高田真弓)




